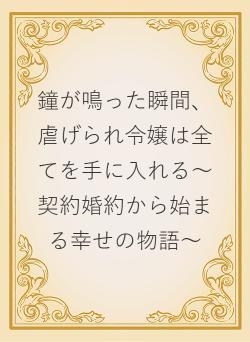「そういえば、クリフにシオドーラの件を話してくれたんですか?」
私の妊娠発覚で、あやふやになっていた話題を持ち出した。
「話はしたが、詳細はクリフ本人から聞いてくれ」
「何故ですか?」
「帰って来てから、クリフと話していないだろう。寂しがっていたぞ」
「えっ! 本当ですか? こないだ、弟離れをしろと言われたので、ちょっと遠慮していたんですが」
急に態度を改めたから、驚いたのかもしれない。それとも、考えを変えたのかしら。やっぱり私の心のオアシスは可愛らしいわ。
ふふふっ、と思わず口元を緩ませると、アリスター様の不機嫌な声が飛んできた。
「……甘やかすのもほどほどにしてくれよ」
「クリフは私の心のオアシスなので、無理です」
「俺は?」
「旦那様は旦那様です」
それ以外でもそれ以上でもない。私だけの旦那様だ。しかし、眉間の皺が消えない。
私はアリスター様の袖を引っ張った。
「どうして不機嫌になるんですか?」
「……それ以外の称号が、特別が欲しい」
「十分、特別ですよ。こないだの巡回で思い知らされました。傍にいてほしくて堪らなかったんです」
見送った途端に会いたくて仕方がなかった。本来ならば、ガーラナウム城でどっしりと構えて、アリスター様の帰りを待つべきなのに……私にはまだそれができなかった。
アリスター様が安心して城を空けられるようにするのが、女主人の役目だというのに。
そんな私の弱音を聞いて、どう思っただろうか。アリスター様は気の強い女性が好きだ。
失望しただろうか。
すると突然、ふわりと体が浮いた。と思った時にはすでに、アリスター様の膝の上に。
「何でこんな時に、そんな可愛いことを言うんだろうな、俺の奥様は」
「っ! だ、だって旦那様が……」
「少しだけ、いやだいぶクリフが羨ましかったんだ。俺もあれくらい、メイベルに甘やかされたくてな」
え? 羨ましい? それってつまりクリフ相手に嫉妬したの?
「ふふふっ。クリフは弟なんですよ。甘やかすのは当然です。もう、これでは子どもが生まれたらどうするんですか? 子どもにまで嫉妬をする、とはさすがに言いませんよね?」
「どうだろうな。断言することはできない」
「え? これは、いつもの冗談ですよね?」
可愛がるどころか嫉妬だなんて……。
私はアリスター様の頬を撫でた。すると、オデコとオデコを軽くぶつけられ、思わず目を閉じる。それを待っていたかのように触れる唇。
「子どもに嫉妬させたくなかったら、俺を蔑ろにしないでくれよ」
「何を言っているんですか? それは逆ですよ。旦那様が甘えに来てください。いつも通りに」
「俺が? いいのか?」
「勿論です。でも、仕事を疎かにすることだけはしないでくださいね。私がダリルに怒られるんですから」
嬉しそうな顔から一転、渋い顔になるアリスター様。
こうした喜怒哀楽を見られるのは、妻の特権、とばかりにいじわるをしたくなった。偏屈なアリスター様に似てしまったのかしら。
ふふふっ、と笑うと苦笑いに変わる。それさえも愛おしかった。
***
クリフと話せたのはその二時間後。
アリスター様はクリフを呼びに行くと言いながら「エルバートと今後について話してくる」と、クリフと入れ違いに、そのまま出て行ってしまった。
実際、出産まで、いや出産後もブレイズ公爵邸にいることになるかもしれないため、お兄様と話すのは理解できる。
けれど、自分からクリフを呼びに行くというのは、少しだけ不思議に思った。
それも同席しないなんて……。
「今更のような気もするけど、お帰りなさい。姉様」
「ただいま、クリフ」
私はそう言うと、両手を広げた。案の定、眉を顰めるクリフ。
「何?」
「抱き締めてあげたいけど無理だから」
そう、いつもどちらかが帰宅した時など、挨拶のようにしていた抱擁。私の一方的だったそれを、思い切ってクリフに要求したのだ。
理由は簡単。アリスター様が「寂しがっていたぞ」と教えてくれたからだ。家族ですら、感情があまり読めないというのに、接点があまりないアリスター様からの進言。
余程のことだと思うのは当然のことだった。
けれど一向に来る気配がない。アリスター様が読み間違えるとも思えず、私はベッドから降りてクリフのところへ行こうとした。が、立ち上がる直前に肩を掴まれてしまう。
「……そういえば、何か物足りないと思ったら、姉様からの抱擁がなかったからだったんだね」
溜め息と呆れた声が頭上から降ってくる。けれど、私の背中に置かれた手は、まるで壊れ物を扱うかのような手つきだった。
確かにまだ成人していないクリフからしたら、妊婦は未知の生物かもしれないけれど……初めてなのだ。クリフからの抱擁は。
嬉しいけれど、家にいた時もしてほしかったな、と思わず言いたくなった。が、お小言を言って機嫌を悪くされるのはマズい。
アリスター様からはただ、話をした、としか聞いていないのだ。ちゃんと引き受けてくれたのか、それとも断られたのか……。
今のクリフを見ただけでは判別できなかった。
そんな私の心配を他所に、クリフは隣にゆっくりと腰掛ける。
「会ってもいいってことは、具合は良くなったってこと?」
「ん? お母様に禁止でもされたの?」
「だって、追い出されたから……」
あぁ、そうか。妊娠を知ったあの時、クリフも私の部屋にいたことを思い出した。
うるさいからってお母様に締め出されたのを、まだ気にしているなんて。
「ごめんね。私が騒がしくしたから、クリフまでとばっちりを受けてしまって」
「僕はいいんだ。姉様は気にしないで。聖女の件も、僕が上手く処理しておくから」
しょ、処理!?
たった二文字の言葉に私は慌てた。
私の妊娠発覚で、あやふやになっていた話題を持ち出した。
「話はしたが、詳細はクリフ本人から聞いてくれ」
「何故ですか?」
「帰って来てから、クリフと話していないだろう。寂しがっていたぞ」
「えっ! 本当ですか? こないだ、弟離れをしろと言われたので、ちょっと遠慮していたんですが」
急に態度を改めたから、驚いたのかもしれない。それとも、考えを変えたのかしら。やっぱり私の心のオアシスは可愛らしいわ。
ふふふっ、と思わず口元を緩ませると、アリスター様の不機嫌な声が飛んできた。
「……甘やかすのもほどほどにしてくれよ」
「クリフは私の心のオアシスなので、無理です」
「俺は?」
「旦那様は旦那様です」
それ以外でもそれ以上でもない。私だけの旦那様だ。しかし、眉間の皺が消えない。
私はアリスター様の袖を引っ張った。
「どうして不機嫌になるんですか?」
「……それ以外の称号が、特別が欲しい」
「十分、特別ですよ。こないだの巡回で思い知らされました。傍にいてほしくて堪らなかったんです」
見送った途端に会いたくて仕方がなかった。本来ならば、ガーラナウム城でどっしりと構えて、アリスター様の帰りを待つべきなのに……私にはまだそれができなかった。
アリスター様が安心して城を空けられるようにするのが、女主人の役目だというのに。
そんな私の弱音を聞いて、どう思っただろうか。アリスター様は気の強い女性が好きだ。
失望しただろうか。
すると突然、ふわりと体が浮いた。と思った時にはすでに、アリスター様の膝の上に。
「何でこんな時に、そんな可愛いことを言うんだろうな、俺の奥様は」
「っ! だ、だって旦那様が……」
「少しだけ、いやだいぶクリフが羨ましかったんだ。俺もあれくらい、メイベルに甘やかされたくてな」
え? 羨ましい? それってつまりクリフ相手に嫉妬したの?
「ふふふっ。クリフは弟なんですよ。甘やかすのは当然です。もう、これでは子どもが生まれたらどうするんですか? 子どもにまで嫉妬をする、とはさすがに言いませんよね?」
「どうだろうな。断言することはできない」
「え? これは、いつもの冗談ですよね?」
可愛がるどころか嫉妬だなんて……。
私はアリスター様の頬を撫でた。すると、オデコとオデコを軽くぶつけられ、思わず目を閉じる。それを待っていたかのように触れる唇。
「子どもに嫉妬させたくなかったら、俺を蔑ろにしないでくれよ」
「何を言っているんですか? それは逆ですよ。旦那様が甘えに来てください。いつも通りに」
「俺が? いいのか?」
「勿論です。でも、仕事を疎かにすることだけはしないでくださいね。私がダリルに怒られるんですから」
嬉しそうな顔から一転、渋い顔になるアリスター様。
こうした喜怒哀楽を見られるのは、妻の特権、とばかりにいじわるをしたくなった。偏屈なアリスター様に似てしまったのかしら。
ふふふっ、と笑うと苦笑いに変わる。それさえも愛おしかった。
***
クリフと話せたのはその二時間後。
アリスター様はクリフを呼びに行くと言いながら「エルバートと今後について話してくる」と、クリフと入れ違いに、そのまま出て行ってしまった。
実際、出産まで、いや出産後もブレイズ公爵邸にいることになるかもしれないため、お兄様と話すのは理解できる。
けれど、自分からクリフを呼びに行くというのは、少しだけ不思議に思った。
それも同席しないなんて……。
「今更のような気もするけど、お帰りなさい。姉様」
「ただいま、クリフ」
私はそう言うと、両手を広げた。案の定、眉を顰めるクリフ。
「何?」
「抱き締めてあげたいけど無理だから」
そう、いつもどちらかが帰宅した時など、挨拶のようにしていた抱擁。私の一方的だったそれを、思い切ってクリフに要求したのだ。
理由は簡単。アリスター様が「寂しがっていたぞ」と教えてくれたからだ。家族ですら、感情があまり読めないというのに、接点があまりないアリスター様からの進言。
余程のことだと思うのは当然のことだった。
けれど一向に来る気配がない。アリスター様が読み間違えるとも思えず、私はベッドから降りてクリフのところへ行こうとした。が、立ち上がる直前に肩を掴まれてしまう。
「……そういえば、何か物足りないと思ったら、姉様からの抱擁がなかったからだったんだね」
溜め息と呆れた声が頭上から降ってくる。けれど、私の背中に置かれた手は、まるで壊れ物を扱うかのような手つきだった。
確かにまだ成人していないクリフからしたら、妊婦は未知の生物かもしれないけれど……初めてなのだ。クリフからの抱擁は。
嬉しいけれど、家にいた時もしてほしかったな、と思わず言いたくなった。が、お小言を言って機嫌を悪くされるのはマズい。
アリスター様からはただ、話をした、としか聞いていないのだ。ちゃんと引き受けてくれたのか、それとも断られたのか……。
今のクリフを見ただけでは判別できなかった。
そんな私の心配を他所に、クリフは隣にゆっくりと腰掛ける。
「会ってもいいってことは、具合は良くなったってこと?」
「ん? お母様に禁止でもされたの?」
「だって、追い出されたから……」
あぁ、そうか。妊娠を知ったあの時、クリフも私の部屋にいたことを思い出した。
うるさいからってお母様に締め出されたのを、まだ気にしているなんて。
「ごめんね。私が騒がしくしたから、クリフまでとばっちりを受けてしまって」
「僕はいいんだ。姉様は気にしないで。聖女の件も、僕が上手く処理しておくから」
しょ、処理!?
たった二文字の言葉に私は慌てた。