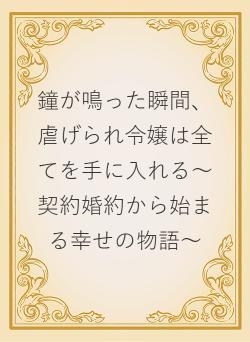首都に戻る。つまり、私にとってはホームグラウンドへの帰還を意味する。
別に辺境伯領が嫌だったわけじゃない。ホームシックになったわけでもない。けれど、逸る気持ちを抑え切れなかった。
それを代弁するかのように私室のカーテンを全開にして、窓の外を見る。
本当は窓を開けて、思いっ切り空気を吸い込みたかったのだが、冬の朝にそれをするのは自殺行為に等しい。今は同じ部屋に、アリスター様がいるから特に。
「メイベル。首都に帰る前に一つ、相談したいことがあるんだがいいか?」
「はい」
後ろからアリスター様が、神妙な声で話しかけてきた。逆に私は明るい声で返事をする。
今の私は良いことも悪いことでも、何でも受け入れられる。それくらい気分が高揚していた。アリスター様は私の浮かれ具合を察したのか、すぐに話を切り出さなかった。
「旦那様?」
「すまない。何だか、水を差すような気分になってな」
「大丈夫です。逆に今なら、何だって聞ける体勢ですから、むしろチャンスと思ってもらえると有り難いです」
「そうか」
アリスター様は再び「そうか」と言い、ご自分に納得させているかのようだった。しかし、なかなか切り出してくれない。
「旦那様?」
今度は顔を覗き込むように言うと、しどろもどろだったが、ようやく話す気になってくれたようだった。
「あ、あぁ。その、なんだ。シオドーラの件なんだが」
「はい」
「まだ処罰が決まっていないくてな。このまま追放でもいいんだが……」
「追放……」
私はアリスター様の言葉を反芻しながら、ソファーに座った。顎に手を当てて考えていると、その様子を見ながら、アリスター様もゆっくりと隣に腰かける。
「う~ん」
仮に追放したとしても、シオドーラは聖女だ。いざとなれば、どこかの貴族に保護してもらってのし上がることだって可能だ。しかし、問題があった。
「私の悪い噂を流したことがある人物です。追放した後、また同じことをしないとは言い切れません」
「あぁ。だが、聖女としての力を失っても、国中に知れ渡っている人物だ。それだけに――……」
「ま、待ってください。力を失ったって、どういうことですか?」
思わずアリスター様に詰め寄った。
いくら聖女でも、私を襲ったくらいで力を失う? そんなやわな力ではないでしょう? あれだけ領民の支持を受けているんだから。
けれど私の驚きとは裏腹に、アリスター様は落ち着いた口調で、シオドーラに襲われた一連の出来事を教えてくれた。
私に罪悪感を抱かせないためなのかと思っていたが、そうではなかったらしい。奇しくも、私の悩みとシオドーラの悩みが同じだったから……。
「下手に力がある分、暴走してしまったんですね」
「そんな悠長に言うが、殺されかけたんだぞ」
「すみません」
何せ憶えていないせいか、どこか他人事のように感じてしまう。その態度がいけなかったらしい。アリスター様の怒りに再び火をつけた。
「俺が駆けつけた時には……っ!」
険しい表情になり、まるで掴みかかってくるほどの勢いだった。
けれどその時のことを思い出したのか、一瞬グッと堪え、目を閉じる。再び目を開けた時は、何故か悲しそうに私を見た。
「切り傷が酷くてな。それはもう、痛々しくて……今はこうして綺麗に消えたから、どれほどだったかも想像できないと思うが。それに服だって、シオドーラにやられたもの以外にも。メイベル」
「は、はいっ!」
静かだったが、怒気を孕んだ声に、思わず勢いよく返事をした。
「いくら動き易さを重視したからといっても、アレは切り過ぎだ。抱き上げる時、どれだけ大変だったか。向きを変えても、太ももが見えて……あの場にいた男どもを追い出したくて仕方がなかったんだぞ!」
「申し訳ありません」
どれくらいスカートを切ったのか憶えていないのに、後ろめたさでいっぱいになった。それと同時に、嬉しさが募る。
嫉妬してくれたから?
怒ってくれたから?
違う。ちょっとした独占欲に可愛いと思ってしまったのだ。
私は、ブレイズ公爵家が所有する騎士団に交じって訓練をしていたから、あまり気にならない。訓練着は体のラインが見えるパンツスタイルだからだ。
もしかして、それもダメ、とか言わないわよね。
「メイベル、聞いているのか」
「は、はい! 聞いています」
「とにかく、そのくらい酷い目に遭ったことは自覚してくれ」
「分かりました」
私は返事をしつつ、次にくる説教に身構えた。が、返ってきたのは、怒りではなく神妙な声だった。
「そんなメイベルには悪いが、シオドーラの処分について考えてくれないか。俺だと処刑する以外の選択肢がない」
「え?」
処刑? いくらなんでもやり過ぎ、という言葉が脳裏を過ったが、グッと呑み込んだ。お小言は一度でいい。いや、二度と聞きたくない。
「そうですね。聖女としての力を失った、といっても、白い蝶が黒い蝶に変わっただけで、力そのものは変化したわけではないんですよね」
「いや、治療はできなくなったと聞いている。結界は……まだ使えるそうだが」
「力の本質は?」
「さぁな。確認はしていないが神聖力が魔力になるとは思えん」
確かに。相反する力だ。
そもそも聖女の力とは? 簡単に失えるものなの? 文献レベルの存在だから、情報が足りない。首都に戻ったら調べてみるかな。
ん? 首都? そうだ。
「では、こうするのはどうでしょうか。シオドーラも一緒に、首都に行くのは」
「何故だ?」
怪訝な表情を隠しもせずに尋ねてくるアリスター様。すぐに反対の意見を唱えるわけではないのが、救いだった。
「考えても見てください。そもそもシオドーラがこうなったのは誰のせいですか?」
「……皇后、いや教会か?」
「教会と言いたいところですが、ここは敢えて両方にしましょうか。だから皇后様にお願いするんです。教会に圧力をかけて、再びシオドーラを引き取らせることを」
「どうやって……あっ」
どうやら私の考えを、いや誰かの顔を思い浮かべたのだろう。
「私がシオドーラに襲われた件などを話せば、穏便に事を運んでくれると思うんですよ」
「……まぁ、辺境伯領で迷惑をかけた聖女をどうにかしてくれ、というより説得力はあるが。穏便に、とは思えんのだが……」
さっき、処刑と言った人物とは思えない反応だった。
「ふふふっ。旦那様は知らないでしょうが、平和主義者なんですよ、クリフは」
だからこそ、私の心のオアシスなのだから。心外とばかりの声音で返事をした。
別に辺境伯領が嫌だったわけじゃない。ホームシックになったわけでもない。けれど、逸る気持ちを抑え切れなかった。
それを代弁するかのように私室のカーテンを全開にして、窓の外を見る。
本当は窓を開けて、思いっ切り空気を吸い込みたかったのだが、冬の朝にそれをするのは自殺行為に等しい。今は同じ部屋に、アリスター様がいるから特に。
「メイベル。首都に帰る前に一つ、相談したいことがあるんだがいいか?」
「はい」
後ろからアリスター様が、神妙な声で話しかけてきた。逆に私は明るい声で返事をする。
今の私は良いことも悪いことでも、何でも受け入れられる。それくらい気分が高揚していた。アリスター様は私の浮かれ具合を察したのか、すぐに話を切り出さなかった。
「旦那様?」
「すまない。何だか、水を差すような気分になってな」
「大丈夫です。逆に今なら、何だって聞ける体勢ですから、むしろチャンスと思ってもらえると有り難いです」
「そうか」
アリスター様は再び「そうか」と言い、ご自分に納得させているかのようだった。しかし、なかなか切り出してくれない。
「旦那様?」
今度は顔を覗き込むように言うと、しどろもどろだったが、ようやく話す気になってくれたようだった。
「あ、あぁ。その、なんだ。シオドーラの件なんだが」
「はい」
「まだ処罰が決まっていないくてな。このまま追放でもいいんだが……」
「追放……」
私はアリスター様の言葉を反芻しながら、ソファーに座った。顎に手を当てて考えていると、その様子を見ながら、アリスター様もゆっくりと隣に腰かける。
「う~ん」
仮に追放したとしても、シオドーラは聖女だ。いざとなれば、どこかの貴族に保護してもらってのし上がることだって可能だ。しかし、問題があった。
「私の悪い噂を流したことがある人物です。追放した後、また同じことをしないとは言い切れません」
「あぁ。だが、聖女としての力を失っても、国中に知れ渡っている人物だ。それだけに――……」
「ま、待ってください。力を失ったって、どういうことですか?」
思わずアリスター様に詰め寄った。
いくら聖女でも、私を襲ったくらいで力を失う? そんなやわな力ではないでしょう? あれだけ領民の支持を受けているんだから。
けれど私の驚きとは裏腹に、アリスター様は落ち着いた口調で、シオドーラに襲われた一連の出来事を教えてくれた。
私に罪悪感を抱かせないためなのかと思っていたが、そうではなかったらしい。奇しくも、私の悩みとシオドーラの悩みが同じだったから……。
「下手に力がある分、暴走してしまったんですね」
「そんな悠長に言うが、殺されかけたんだぞ」
「すみません」
何せ憶えていないせいか、どこか他人事のように感じてしまう。その態度がいけなかったらしい。アリスター様の怒りに再び火をつけた。
「俺が駆けつけた時には……っ!」
険しい表情になり、まるで掴みかかってくるほどの勢いだった。
けれどその時のことを思い出したのか、一瞬グッと堪え、目を閉じる。再び目を開けた時は、何故か悲しそうに私を見た。
「切り傷が酷くてな。それはもう、痛々しくて……今はこうして綺麗に消えたから、どれほどだったかも想像できないと思うが。それに服だって、シオドーラにやられたもの以外にも。メイベル」
「は、はいっ!」
静かだったが、怒気を孕んだ声に、思わず勢いよく返事をした。
「いくら動き易さを重視したからといっても、アレは切り過ぎだ。抱き上げる時、どれだけ大変だったか。向きを変えても、太ももが見えて……あの場にいた男どもを追い出したくて仕方がなかったんだぞ!」
「申し訳ありません」
どれくらいスカートを切ったのか憶えていないのに、後ろめたさでいっぱいになった。それと同時に、嬉しさが募る。
嫉妬してくれたから?
怒ってくれたから?
違う。ちょっとした独占欲に可愛いと思ってしまったのだ。
私は、ブレイズ公爵家が所有する騎士団に交じって訓練をしていたから、あまり気にならない。訓練着は体のラインが見えるパンツスタイルだからだ。
もしかして、それもダメ、とか言わないわよね。
「メイベル、聞いているのか」
「は、はい! 聞いています」
「とにかく、そのくらい酷い目に遭ったことは自覚してくれ」
「分かりました」
私は返事をしつつ、次にくる説教に身構えた。が、返ってきたのは、怒りではなく神妙な声だった。
「そんなメイベルには悪いが、シオドーラの処分について考えてくれないか。俺だと処刑する以外の選択肢がない」
「え?」
処刑? いくらなんでもやり過ぎ、という言葉が脳裏を過ったが、グッと呑み込んだ。お小言は一度でいい。いや、二度と聞きたくない。
「そうですね。聖女としての力を失った、といっても、白い蝶が黒い蝶に変わっただけで、力そのものは変化したわけではないんですよね」
「いや、治療はできなくなったと聞いている。結界は……まだ使えるそうだが」
「力の本質は?」
「さぁな。確認はしていないが神聖力が魔力になるとは思えん」
確かに。相反する力だ。
そもそも聖女の力とは? 簡単に失えるものなの? 文献レベルの存在だから、情報が足りない。首都に戻ったら調べてみるかな。
ん? 首都? そうだ。
「では、こうするのはどうでしょうか。シオドーラも一緒に、首都に行くのは」
「何故だ?」
怪訝な表情を隠しもせずに尋ねてくるアリスター様。すぐに反対の意見を唱えるわけではないのが、救いだった。
「考えても見てください。そもそもシオドーラがこうなったのは誰のせいですか?」
「……皇后、いや教会か?」
「教会と言いたいところですが、ここは敢えて両方にしましょうか。だから皇后様にお願いするんです。教会に圧力をかけて、再びシオドーラを引き取らせることを」
「どうやって……あっ」
どうやら私の考えを、いや誰かの顔を思い浮かべたのだろう。
「私がシオドーラに襲われた件などを話せば、穏便に事を運んでくれると思うんですよ」
「……まぁ、辺境伯領で迷惑をかけた聖女をどうにかしてくれ、というより説得力はあるが。穏便に、とは思えんのだが……」
さっき、処刑と言った人物とは思えない反応だった。
「ふふふっ。旦那様は知らないでしょうが、平和主義者なんですよ、クリフは」
だからこそ、私の心のオアシスなのだから。心外とばかりの声音で返事をした。