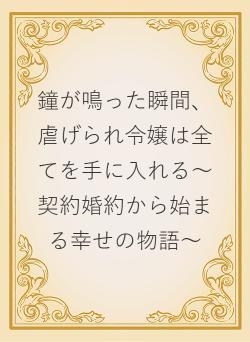翌日。
最初から私の見送りなど期待していなかった、かのようにお母様たちは首都へ帰って行った。
私がその報告を聞いたのは、お昼頃のこと。
「まだ寝ていても、大丈夫だぞ」
ベッドの上で朝食という名の昼食を食べていると、アリスター様が心配そうに声をかけてきた。
どうやら、昨夜のことを反省しているらしい。私は気にしていないのに、と同じことを何度、言ったことだろう。
全く聞き入れてくれないので、諦めることにした。それが多分、正しい対応だと思うから。
ちょうどお兄様たちが滞在している影響なのか、それを真に受けて、過保護になっているような気がしたのもあって。
大切に扱ってくれるのは嬉しいけれど、こちらの言い分も聞いてほしい。
けれどお兄様やお母様たちと違って心地良く感じるのは、偏にアリスター様を愛している、からだと思う。
「どうかしたのか?」
「あっ、いえ。まさか、こんな風になるなんて、昨日までは思わなかったので、驚いたような……嬉しいような。不思議な感じがして」
それもまた、言葉が違うような気がした。けれど、他の言葉が出てこない。
「そもそも契約結婚だったから」というのも、さらに言い辛くて。いや、蒸し返すようで言えなかったのだ。
もう私たちの間にはない。そう、信じたくて仕方がなかったからだ。
けれどそんな不安を抱えているのは私だけ、だとも言いたいのか、アリスター様は平然とした態度で言い放った。
「どうかな。俺はこうなると思っていたぞ」
「……負け惜しみで言っています?」
「この状況で、誰に対して言うんだ」
「何となく、そう思っただけです」
逆に私の方が負けたような気分になった。それもまた、何に対してだかは分からない。
私は不貞腐れたように、トレイの上にあるパンを一口サイズに千切った。途端、その手をアリスター様に掴まれる。
「何をす――……」
るんですか、と言おうとした時にはすでに、私の手から千切ったパンが無くなっていた。
どこにって、アリスター様の口の中に。それもご丁寧に私の指も嘗めている。昨夜の方がもっと刺激が強過ぎたのに、免疫というのはすぐにつくものではないらしい。
アワアワしている隙に、口を塞がれた。アリスター様の唇によって。しかも……。
「んん~」
千切ったパンが口の中に!!
思わず、アリスター様の顔が離れたのと同時に、口を手で覆った。勢いでそのまま飲み込んでしまい、私はさらに顔を真っ赤にさせた。
「婚約した時から、いやその前からこうしたかったからだ」
「え?」
再び同じ疑問が浮かんだが、すぐに先ほどの質問の回答だと気がつく。
「言葉で言ってください。突然、態度で示されたらビックリします」
「それでは意味がない。瞬発的な態度ほど、本心が分からないからな」
「つまり、私の気持ちを確かめているってことですか? 初めて会った時から」
「……初対面でした覚えはないが」
「したじゃないですか。契約結婚を持ちかけたり、おちょくったり」
季節を一つ越しただけなのに、もう忘れてしまったの!?
いや、そもそも取り引きした時の状況を忘れるなんてあり得ない!
けれど私の憤りは、すぐに収まってしまった。何故なら……。
「……やっぱり覚えていないか」
寂びしそうな顔で頭を撫でられてしまったからだ。その姿を前に「何を?」とは、さすがに聞けなかった。
一体、私は何を忘れているのだろう。アリスター様との思い出は、あの牢屋からのものしかないのに。
***
アリスター様は、結婚式の翌日でも、私のようにのんびりしていられない。ここは国境に面している、エヴァレット辺境伯領だ。
この浮かれている隙が、一番危ない。
だから、終始一緒にいられないのは分かるんだけど。と寂しげに語ってみるが、実際には私よりも、アリスター様の方が酷かった。
私たちの寝室と、アリスター様の執務室の距離は、あまり離れていない。夜遅くまで仕事をしている時があるため、すぐに休めるようになっているのだ。
それもあってか、アリスター様は一時間置きに私の様子を見に来ていた。
「あの……私はけして、病気ではないので、大丈夫ですよ?」
何でも、執務室と寝室が近いのは、アリスター様のお母様の為だという。
元々、虚弱体質の方で、アリスター様を生んでからは、さらにお体を悪くされたんだそうだ。アリスター様が気の強い女性を好むのは、前辺境伯夫人の影響らしい。
「分かってはいるんだが、こう距離が近いと気になってな」
「では、ダリルに頼んでみましょうか? アリスター様が仕事に集中できないようなので――……」
「待った。呼び方が戻っているぞ」
「え? あれは周りに対してではなかったのですか?」
主に、シオドーラを牽制するために、「旦那様」呼びを強要したのだとばかり思っていた。
「……すまない。昨夜のことが夢だったのではないか、と思うと、な」
私は目をパチクリさせた。
夢……だって? 私が好き好んで、未だベッドにいるとでも言うの? それに、お昼頃と言っていることが違うじゃない! 何でまた……。
「実感したいんだ。結婚のことも含めて」
「昨日、騎士団の団員たちが賑やかに祝ってくれたのも、夢だったというんですか?」
「違う」
「……私が、憶えていないからですか?」
お昼の時は、私の体を気遣いながらも、自信満々だった。それなのに、この表情と態度。豹変させた原因は一つしか思い浮かばなかった。
「いや、あれは忘れてくれ。憶えていないのなら、それでいいんだ」
「よくありません! 私だって……」
「メイベル」
「っ! 私だって、旦那様との記憶を共有したいって気持ちくらいあるんですからっ!」
そのくらい分かれ、とばかりに、私は枕を投げつけた。勿論、アリスター様は軽々と受け止める。どこかの皇子と違って。
「すまない。エルバートが変な置き土産でもしたのではないか、と心配になったんだ」
「憶えていないのに、置き土産なんか、あるとでも思うんですか?」
「……そうだな。変なことを言った。それでも、しばらくは旦那様と呼んで欲しい」
「分かりました。夫の我が儘を時折聞くのも良妻だと、お母様から聞きましたので」
実際は、お父様の我が儘どころか、意見さえ無視しているようなお母様だけど。私にはそう言っていた。
自分のようにはならないように、という助言なのだろうか。
「夫、か」
アリスター様は、私のたった一言を噛み締めるように呟く。
それだけで喜んでくれるなんて……可愛い。思わず八歳差というのも忘れてしまうくらい。
だからこそ、一体何があったのか、気になって仕方がなかった。
最初から私の見送りなど期待していなかった、かのようにお母様たちは首都へ帰って行った。
私がその報告を聞いたのは、お昼頃のこと。
「まだ寝ていても、大丈夫だぞ」
ベッドの上で朝食という名の昼食を食べていると、アリスター様が心配そうに声をかけてきた。
どうやら、昨夜のことを反省しているらしい。私は気にしていないのに、と同じことを何度、言ったことだろう。
全く聞き入れてくれないので、諦めることにした。それが多分、正しい対応だと思うから。
ちょうどお兄様たちが滞在している影響なのか、それを真に受けて、過保護になっているような気がしたのもあって。
大切に扱ってくれるのは嬉しいけれど、こちらの言い分も聞いてほしい。
けれどお兄様やお母様たちと違って心地良く感じるのは、偏にアリスター様を愛している、からだと思う。
「どうかしたのか?」
「あっ、いえ。まさか、こんな風になるなんて、昨日までは思わなかったので、驚いたような……嬉しいような。不思議な感じがして」
それもまた、言葉が違うような気がした。けれど、他の言葉が出てこない。
「そもそも契約結婚だったから」というのも、さらに言い辛くて。いや、蒸し返すようで言えなかったのだ。
もう私たちの間にはない。そう、信じたくて仕方がなかったからだ。
けれどそんな不安を抱えているのは私だけ、だとも言いたいのか、アリスター様は平然とした態度で言い放った。
「どうかな。俺はこうなると思っていたぞ」
「……負け惜しみで言っています?」
「この状況で、誰に対して言うんだ」
「何となく、そう思っただけです」
逆に私の方が負けたような気分になった。それもまた、何に対してだかは分からない。
私は不貞腐れたように、トレイの上にあるパンを一口サイズに千切った。途端、その手をアリスター様に掴まれる。
「何をす――……」
るんですか、と言おうとした時にはすでに、私の手から千切ったパンが無くなっていた。
どこにって、アリスター様の口の中に。それもご丁寧に私の指も嘗めている。昨夜の方がもっと刺激が強過ぎたのに、免疫というのはすぐにつくものではないらしい。
アワアワしている隙に、口を塞がれた。アリスター様の唇によって。しかも……。
「んん~」
千切ったパンが口の中に!!
思わず、アリスター様の顔が離れたのと同時に、口を手で覆った。勢いでそのまま飲み込んでしまい、私はさらに顔を真っ赤にさせた。
「婚約した時から、いやその前からこうしたかったからだ」
「え?」
再び同じ疑問が浮かんだが、すぐに先ほどの質問の回答だと気がつく。
「言葉で言ってください。突然、態度で示されたらビックリします」
「それでは意味がない。瞬発的な態度ほど、本心が分からないからな」
「つまり、私の気持ちを確かめているってことですか? 初めて会った時から」
「……初対面でした覚えはないが」
「したじゃないですか。契約結婚を持ちかけたり、おちょくったり」
季節を一つ越しただけなのに、もう忘れてしまったの!?
いや、そもそも取り引きした時の状況を忘れるなんてあり得ない!
けれど私の憤りは、すぐに収まってしまった。何故なら……。
「……やっぱり覚えていないか」
寂びしそうな顔で頭を撫でられてしまったからだ。その姿を前に「何を?」とは、さすがに聞けなかった。
一体、私は何を忘れているのだろう。アリスター様との思い出は、あの牢屋からのものしかないのに。
***
アリスター様は、結婚式の翌日でも、私のようにのんびりしていられない。ここは国境に面している、エヴァレット辺境伯領だ。
この浮かれている隙が、一番危ない。
だから、終始一緒にいられないのは分かるんだけど。と寂しげに語ってみるが、実際には私よりも、アリスター様の方が酷かった。
私たちの寝室と、アリスター様の執務室の距離は、あまり離れていない。夜遅くまで仕事をしている時があるため、すぐに休めるようになっているのだ。
それもあってか、アリスター様は一時間置きに私の様子を見に来ていた。
「あの……私はけして、病気ではないので、大丈夫ですよ?」
何でも、執務室と寝室が近いのは、アリスター様のお母様の為だという。
元々、虚弱体質の方で、アリスター様を生んでからは、さらにお体を悪くされたんだそうだ。アリスター様が気の強い女性を好むのは、前辺境伯夫人の影響らしい。
「分かってはいるんだが、こう距離が近いと気になってな」
「では、ダリルに頼んでみましょうか? アリスター様が仕事に集中できないようなので――……」
「待った。呼び方が戻っているぞ」
「え? あれは周りに対してではなかったのですか?」
主に、シオドーラを牽制するために、「旦那様」呼びを強要したのだとばかり思っていた。
「……すまない。昨夜のことが夢だったのではないか、と思うと、な」
私は目をパチクリさせた。
夢……だって? 私が好き好んで、未だベッドにいるとでも言うの? それに、お昼頃と言っていることが違うじゃない! 何でまた……。
「実感したいんだ。結婚のことも含めて」
「昨日、騎士団の団員たちが賑やかに祝ってくれたのも、夢だったというんですか?」
「違う」
「……私が、憶えていないからですか?」
お昼の時は、私の体を気遣いながらも、自信満々だった。それなのに、この表情と態度。豹変させた原因は一つしか思い浮かばなかった。
「いや、あれは忘れてくれ。憶えていないのなら、それでいいんだ」
「よくありません! 私だって……」
「メイベル」
「っ! 私だって、旦那様との記憶を共有したいって気持ちくらいあるんですからっ!」
そのくらい分かれ、とばかりに、私は枕を投げつけた。勿論、アリスター様は軽々と受け止める。どこかの皇子と違って。
「すまない。エルバートが変な置き土産でもしたのではないか、と心配になったんだ」
「憶えていないのに、置き土産なんか、あるとでも思うんですか?」
「……そうだな。変なことを言った。それでも、しばらくは旦那様と呼んで欲しい」
「分かりました。夫の我が儘を時折聞くのも良妻だと、お母様から聞きましたので」
実際は、お父様の我が儘どころか、意見さえ無視しているようなお母様だけど。私にはそう言っていた。
自分のようにはならないように、という助言なのだろうか。
「夫、か」
アリスター様は、私のたった一言を噛み締めるように呟く。
それだけで喜んでくれるなんて……可愛い。思わず八歳差というのも忘れてしまうくらい。
だからこそ、一体何があったのか、気になって仕方がなかった。