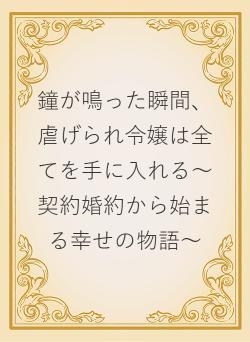季節は夏から秋へ。
暑さも落ち着いた頃。気持ちにも余裕が出て、穏やかに結婚式を迎えることができた……はずだった。
「これは……祝ってもらえているんですよね」
目の前で繰り広げられている光景に、私は唖然としながらアリスター様に尋ねた。何せ、騎士たちが暴れ……いや、お酒を飲んで楽しんでいるのだ。
ダリルの妻、ハリエットからガーラナウム城は男所帯だと聞いていなかったら、さらに驚いていたことだろう。
お母様は予め知っていたのか、この状況になる前に、お父様たちと一緒に退場されていた。私の親族で残っているのは、お兄様のみ。それも一緒になって楽しんでいる。
「そうか。メイベル嬢は、いやメイベルは騎士団の内情を知らなかったんだな」
「っ! そんなことはありません。一緒に訓練などしていたのですから、内情くらい……」
「いや、そっちの内情とは別の話だ。壮行会や激励会、打ち上げなどには参加したことが……違うな。させてもらったことはないのだろう?」
確かに。でもそれはまだ、私が子どもで、お酒を嗜む年齢ではなかったからだと思っていた。けれど、お兄様たちがダメだと言っていた理由が、これだとしたら……。
「お母様たちは知っていて、早々に席を外されたということですか?」
「あぁ。あいつらにとっては、いいガス抜きにもなるし、メイベルに対しても悪い印象を与えなくて済む。だから、何も言わずに出て行ったんだ。さらに言うと、酒や食事のメニューはブレイズ公爵夫人が指示したものなんだぞ。騎士団員たちの席には、酒と肴しか用意されていない」
嘘っ、と身を乗り出して確かめた。
すると腕を掴まれて、座るように促される。花嫁がいきなり立ち上がれば、何があったのかと、皆が心配するのに。
「どうした、メイベル。お前もお母様たちと一緒に、部屋へ戻るか?」
案の定、その筆頭ともいえるお兄様が席に近づく。顔にはしっかり、俺もそろそろ戻りたい、と書いてあった。
「そうですね。今朝から慌ただしくしていたので、私もこの辺で。よろしいですよね、アリスター様」
「……旦那様と呼んでくれたら、構わんよ」
「えっ!?」
ここで!? いや、そもそもこんな大勢のいる席で言うことじゃない。
「さっき誓いを立てたのに、もう破る気か?」
「そんなつもりはありませんが……」
「なら、言えるだろう?」
何で突然、そんな意地悪なことを言うの? 正直、さっきの呼び方だって、できれば二人きりの時にしたかったのに。
けれどアリスター様は関係ない、とばかりに腕を掴んで離さない。
「無理強いはいけませんわ、エヴァレット辺境伯様。いくら式を挙げたからといっても、すぐに切り替えられるものではないのですから」
すると、何故かシオドーラが現れて、私を援護するような言い方をしてきた。が、見方を変えれば、私をバカにしているのと同じこと。私はシオドーラを凝視した。
あの時は、顔を見ることは出来なかったが、美しい金髪に、草木を思わせる素朴な瞳。親しみ易さを兼ね備えた、まさに聖女という称号が相応しい女性だった。
けれどアリスター様は、そんな美女を目の前にしても視線すら向けない。
「……聖女様はてっきり、役目を終えたから帰ったのだとばかり思っていたが」
「騎士団の皆さんが楽しそうにしているので、雰囲気だけでも味合わせてもらっているんです」
「そうか。ならばダリル。聖女様を騎士団の席にお連れしろ」
「え、エヴァレット辺境伯様? 私はそういう意味で言ったのでは……!」
シオドーラはそう言いながらも、ダリルに引っ張られていってしまった。さすがは元騎士。容赦がない。
「さて、興が冷めた。俺も戻るとするかな。エルバート、すまないが交代してもらうぞ」
「いいけど、あまりメイベルをいじめるなよ」
「ちょっと待ってください。今の流れで戻るって私とですか?」
「他に誰がいる。旦那様呼びだって、まだ聞いていない」
先ほどのお兄様の忠告なんて何処へやら。
「あまり急かさないでください」
そう返事をするだけで精一杯だった。
だって、私たちが同時に席を外すということは、その、つまり……初夜の準備に入ることを意味していたからだ。
周りの囃し立てる声と音に、私の顔はますます赤くなっていった。
***
準備が整い、寝室に入る。そう、初めて入る夫婦の寝室だ。
一応アリスター様からはこの後、別々の寝室になることを告げられている。それが、この契約結婚の内容だったからだ。
今更ながら、寂しいと感じてしまう。だからといって、私から言うのも恥ずかしい。これから迎える初夜は、特に……!
けれど、アリスター様は違うようだった。
寝室に入ると、すでにソファーに座り込み、何やら深刻そうな顔をしていた。
さっきは私に旦那様呼びを強要していたのに!? 何で?
「アリスター様……いえ、あの、だ、旦那様?」
思わず、そう言い直すとバッと顔を向けられた。驚いたような、嬉しそうな。そんな顔で。
「その、さっきは大勢の前だったので……」
「だからこそ、言ってほしかったんだけどな」
そう言うと、アリスター様は隣を叩いた。
座れってことで、いいんだよね。あっ、そっか。初夜をどうするのか、話し合う必要があるから。
「私たちの仲を示すためですか?」
「……あぁ。見ての通り、シオドーラが……聖女があぁだからな」
やはり、気づいていらっしゃったから、あのような態度を……。
すると、牢屋の中で契約結婚を持ち出された時の光景が脳裏に浮かんだ。
『まぁ、なんだ。それは……アレだ。周りが結婚しろと煩いからで……』
あれはあながち間違いではなかったってこと?
「それほどまでに、シオドーラが煩いんですか? 結婚してほしいとか」
会話が噛み合っていないのは、偏に気持ちが一方通行しているからだ。辺境伯領に着くまで、何度も体験したから分かる。
つまり、アリスター様はシオドーラに気はない。聖女であっても。
それは嬉しい事実だけど、別の現実を叩きつけられた気分だった。
「あからさまではないにしても、皆、気づいている。俺も含めて、な」
「シオドーラが聖女だから、周りも賛成しているんですか? だからその風よけにするために私と契約結婚を?」
「結果的には、な。メイベル嬢には不快な思いをさせた」
「メイベルです」
首を傾げるアリスター様に、私はもう一度言った。
「今日から私は旦那様の妻です。人妻です。もう令嬢じゃないんです!」
「そ、そうだったな」
「ですから、もう寝ます!」
信じられない! あれだけ私を揶揄っておいて、風よけだなんて。それも他の令嬢ならいざ知らず、聖女に対してだなんて。
泣きたいのを通り越して、怒りが込み上げてきた。
私はそれを示すように、ズカズカとベッドへ向かって行った。
暑さも落ち着いた頃。気持ちにも余裕が出て、穏やかに結婚式を迎えることができた……はずだった。
「これは……祝ってもらえているんですよね」
目の前で繰り広げられている光景に、私は唖然としながらアリスター様に尋ねた。何せ、騎士たちが暴れ……いや、お酒を飲んで楽しんでいるのだ。
ダリルの妻、ハリエットからガーラナウム城は男所帯だと聞いていなかったら、さらに驚いていたことだろう。
お母様は予め知っていたのか、この状況になる前に、お父様たちと一緒に退場されていた。私の親族で残っているのは、お兄様のみ。それも一緒になって楽しんでいる。
「そうか。メイベル嬢は、いやメイベルは騎士団の内情を知らなかったんだな」
「っ! そんなことはありません。一緒に訓練などしていたのですから、内情くらい……」
「いや、そっちの内情とは別の話だ。壮行会や激励会、打ち上げなどには参加したことが……違うな。させてもらったことはないのだろう?」
確かに。でもそれはまだ、私が子どもで、お酒を嗜む年齢ではなかったからだと思っていた。けれど、お兄様たちがダメだと言っていた理由が、これだとしたら……。
「お母様たちは知っていて、早々に席を外されたということですか?」
「あぁ。あいつらにとっては、いいガス抜きにもなるし、メイベルに対しても悪い印象を与えなくて済む。だから、何も言わずに出て行ったんだ。さらに言うと、酒や食事のメニューはブレイズ公爵夫人が指示したものなんだぞ。騎士団員たちの席には、酒と肴しか用意されていない」
嘘っ、と身を乗り出して確かめた。
すると腕を掴まれて、座るように促される。花嫁がいきなり立ち上がれば、何があったのかと、皆が心配するのに。
「どうした、メイベル。お前もお母様たちと一緒に、部屋へ戻るか?」
案の定、その筆頭ともいえるお兄様が席に近づく。顔にはしっかり、俺もそろそろ戻りたい、と書いてあった。
「そうですね。今朝から慌ただしくしていたので、私もこの辺で。よろしいですよね、アリスター様」
「……旦那様と呼んでくれたら、構わんよ」
「えっ!?」
ここで!? いや、そもそもこんな大勢のいる席で言うことじゃない。
「さっき誓いを立てたのに、もう破る気か?」
「そんなつもりはありませんが……」
「なら、言えるだろう?」
何で突然、そんな意地悪なことを言うの? 正直、さっきの呼び方だって、できれば二人きりの時にしたかったのに。
けれどアリスター様は関係ない、とばかりに腕を掴んで離さない。
「無理強いはいけませんわ、エヴァレット辺境伯様。いくら式を挙げたからといっても、すぐに切り替えられるものではないのですから」
すると、何故かシオドーラが現れて、私を援護するような言い方をしてきた。が、見方を変えれば、私をバカにしているのと同じこと。私はシオドーラを凝視した。
あの時は、顔を見ることは出来なかったが、美しい金髪に、草木を思わせる素朴な瞳。親しみ易さを兼ね備えた、まさに聖女という称号が相応しい女性だった。
けれどアリスター様は、そんな美女を目の前にしても視線すら向けない。
「……聖女様はてっきり、役目を終えたから帰ったのだとばかり思っていたが」
「騎士団の皆さんが楽しそうにしているので、雰囲気だけでも味合わせてもらっているんです」
「そうか。ならばダリル。聖女様を騎士団の席にお連れしろ」
「え、エヴァレット辺境伯様? 私はそういう意味で言ったのでは……!」
シオドーラはそう言いながらも、ダリルに引っ張られていってしまった。さすがは元騎士。容赦がない。
「さて、興が冷めた。俺も戻るとするかな。エルバート、すまないが交代してもらうぞ」
「いいけど、あまりメイベルをいじめるなよ」
「ちょっと待ってください。今の流れで戻るって私とですか?」
「他に誰がいる。旦那様呼びだって、まだ聞いていない」
先ほどのお兄様の忠告なんて何処へやら。
「あまり急かさないでください」
そう返事をするだけで精一杯だった。
だって、私たちが同時に席を外すということは、その、つまり……初夜の準備に入ることを意味していたからだ。
周りの囃し立てる声と音に、私の顔はますます赤くなっていった。
***
準備が整い、寝室に入る。そう、初めて入る夫婦の寝室だ。
一応アリスター様からはこの後、別々の寝室になることを告げられている。それが、この契約結婚の内容だったからだ。
今更ながら、寂しいと感じてしまう。だからといって、私から言うのも恥ずかしい。これから迎える初夜は、特に……!
けれど、アリスター様は違うようだった。
寝室に入ると、すでにソファーに座り込み、何やら深刻そうな顔をしていた。
さっきは私に旦那様呼びを強要していたのに!? 何で?
「アリスター様……いえ、あの、だ、旦那様?」
思わず、そう言い直すとバッと顔を向けられた。驚いたような、嬉しそうな。そんな顔で。
「その、さっきは大勢の前だったので……」
「だからこそ、言ってほしかったんだけどな」
そう言うと、アリスター様は隣を叩いた。
座れってことで、いいんだよね。あっ、そっか。初夜をどうするのか、話し合う必要があるから。
「私たちの仲を示すためですか?」
「……あぁ。見ての通り、シオドーラが……聖女があぁだからな」
やはり、気づいていらっしゃったから、あのような態度を……。
すると、牢屋の中で契約結婚を持ち出された時の光景が脳裏に浮かんだ。
『まぁ、なんだ。それは……アレだ。周りが結婚しろと煩いからで……』
あれはあながち間違いではなかったってこと?
「それほどまでに、シオドーラが煩いんですか? 結婚してほしいとか」
会話が噛み合っていないのは、偏に気持ちが一方通行しているからだ。辺境伯領に着くまで、何度も体験したから分かる。
つまり、アリスター様はシオドーラに気はない。聖女であっても。
それは嬉しい事実だけど、別の現実を叩きつけられた気分だった。
「あからさまではないにしても、皆、気づいている。俺も含めて、な」
「シオドーラが聖女だから、周りも賛成しているんですか? だからその風よけにするために私と契約結婚を?」
「結果的には、な。メイベル嬢には不快な思いをさせた」
「メイベルです」
首を傾げるアリスター様に、私はもう一度言った。
「今日から私は旦那様の妻です。人妻です。もう令嬢じゃないんです!」
「そ、そうだったな」
「ですから、もう寝ます!」
信じられない! あれだけ私を揶揄っておいて、風よけだなんて。それも他の令嬢ならいざ知らず、聖女に対してだなんて。
泣きたいのを通り越して、怒りが込み上げてきた。
私はそれを示すように、ズカズカとベッドへ向かって行った。