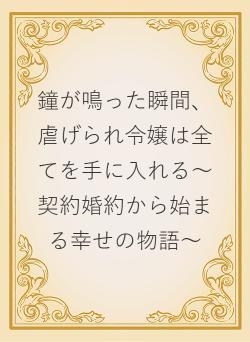アリスター様の命令を、素直に聞き入れたのか、シオドーラとはあれから一度も会っていない。
それが意図的なのかどうか、敢えて私も言及しなかった。何故なら、重要な行事を控えていたからだ。
そう、私とアリスター様の結婚式。
「早いものですね。エヴァレット辺境伯領に来て、もう三週間です。あと一週間後には奥様たちがいらっしゃるなんて、まだまだ信じられません」
「ふふふっ。ここに来て、サミーが一番忙しくしていたからね。誰よりも早く感じるのは当然だわ」
「お嬢様のためなら、このサミー。いくらだって頑張れますよ! 下心のある者を一歩たりとも近づけはしませんからっ!」
ということは、やっぱりいたのね。それもたくさん。
胸を張って言うサミーには悪いけれど、その態度でおおよそのことは想像がついた。
私に気に入られれば、エヴァレット辺境伯領だけでなく、首都のタウンハウスへ行く機会だってできる。
そして、子爵か男爵でもいい。貴族と結婚して華やかな人生を送りたい! と考えている女性は、何も辺境だからいるってわけじゃない。首都にいる者たちだって同じだった。
お父様の浮気相手がいい例。お母様という強敵を前に、戦うこともなく逃げていったけれど。
そんな怪物たちがどこに潜んでいるのかも分からない世界に、好き好んで入ろうだなんて……。
もしかして、シオドーラがエヴァレット辺境伯領にいるのは、そのため……? 何となくだけど、違うような気がする。
アリスター様に気があるような……そんな感じがするのだ。だから、あの場所にいたのが、その証拠。
一日に一度は展望台に行く、と公言するくらいだから、周りの人間たちだって勿論、知っているのだろう。
つまりあの場所にいれば、必ずアリスター様に会える。ガーラナウム城への立ち入りを禁止されているのに、シオドーラがやってきた理由は、それしかない。
いつ現れるかも分からないアリスター様を待っていたのだ。
けれどアリスター様はシオドーラを邪険に扱っている。何の力もない私より、聖女の方が辺境伯領には必要なのに。
私を……。
「如何されましたか? そんな可笑しなことを言ったでしょうか」
「えっ!? あっ、違うの。えっと、お母様が一週間後にやって来ると思ったら、ちょっと憂鬱になっちゃって……。でも、お兄様たちも来るでしょう。それは楽しみなの。だから、ちょっと複雑な気分になっちゃって」
「そうですね。お坊ちゃま方は寂しそうにされていると思うので、きっとお喜びになられますわ。けれど奥様は……この現状を見たら、お怒りになるかもしれません。急いで首都を出ざるを得なかったとはいえ、準備不足は否めませんから」
しまった!
シオドーラのことを気にしていたとはいえ、サミーを落ち込ませてしまうなんて……!
「大丈夫よ。それは皆、納得した上のことなんだから、いくらお母様でも怒ることはないと思うの」
「しかし……」
「仮にしたとしても、矛先はきっと別のところに行くはずだから。サミーは安心していいんだからね」
そこまで言うと、さすがのサミーでも、私の言葉の真意に気がついたようだった。
確かにお母様はご自分にも他人にも厳しい方だけど、その分、愛情も大きい。けれど、一度敵意を向けた相手には、とことん厳しかった。
***
「この状態で結婚式を挙げるなんて、本気で言っているの?」
性格が似ているから、尚のこと、お母様の行動は読み易い。着いて早々、準備が半分も出来ていない惨状に、抗議の声を上げた。
勿論相手は……。
「落ち着いてください、ブレイズ公爵夫人。それを見越して、これだけの大所帯で、辺境伯領に押し寄せたのではないのですか?」
そう、アリスター様の言う通り、お母様はまるで、こちらの状況を知っていたのかと思うくらい、多くの物資と人を連れてきた。
「念のために、よ。これ以上、メイベルが恥をかかないように万全を期しただけ。さぁ、メイベル。貴女はドレスの仕上げに向かいなさい」
「ですが……」
大丈夫なのですか? とアリスター様の方に顔を向ける。
いくらここがアリスター様の領地であり、お母様が部外者ともいえる立場であったとしても。この状態を放置して去るのは気まずかった。
とはいえ、私に何か出来るわけじゃないんだけど。
「時間がないことくらい、分かるでしょう。メイベルにしかできないものが、まだまだ山のようにあるのよ。のんびりしていたツケを、あとで払う方がどれだけ大変か。身をもって知りたいのならいいけれど?」
「……いいえ」
お母様たちの滞在日数は決まっている。無限ではないのだ。私は渋々、客間へ向かって行った。
その後、ガーラナウム城の使用人たちが、あわあわするほどの攻防が繰り広げられていたとも知らずに。
***
けれど結婚式までの騒動は、これだけではなかった。
長いこと女主人がいなかった、ということもあり、お母様の目につく案件が山のように出てきてしまったのだ。
たとえば、結婚式の招待状から設営に至るまで。
ガーラナウム城では戦勝パーティーなどはするが、舞踏会などの近隣の貴族を招く催しは、近年、開催すらされていなかったらしい。呼べるような時勢でもなかったのも相まって。
そのため、ダリルがお母様に頼んだのだ。
どの道、口を出されるのなら一層のこと、任せた方がいいと思ったのだろう。それが問題の一因だったことにも気づかずに。
そのお陰で私は今、お母様の指示のもと、招待客をチェックし、招待状をダリルの妻、ハリエットと共に作成していた。
「何だかお母様が迷惑をかけているみたいで、ごめんね」
「そんなっ! 本当なら私かメイド長がするところをやっていただいていますので、とても助かっています。何分、ガーラナウム城は男所帯ですから、私たちが何を言っても聞いてくれないことが多いんです」
「確かに。そんな感じがするわ。でもお母様は相手が男だろうが、女だろうが関係ない。刃向かってくれば正論で捲し立てるし、護身術も身につけていらっしゃるから大丈夫だと思うの」
一応、常に護衛を配置しているから、万が一、ということもないだろう。
「噂には聞いていましたが、やはり凄い方なのですね」
「まぁ、うん。……そうね」
どんな噂が出回っているのか、敢えて聞かずにおいた。だいたいは公爵邸でのものと変わらないだろうから。
私はハハハッと愛想笑いをして、その場をやり過ごした。
そして一カ月後、無事(?)に結婚式が行われる運びとなったのだ。
それが意図的なのかどうか、敢えて私も言及しなかった。何故なら、重要な行事を控えていたからだ。
そう、私とアリスター様の結婚式。
「早いものですね。エヴァレット辺境伯領に来て、もう三週間です。あと一週間後には奥様たちがいらっしゃるなんて、まだまだ信じられません」
「ふふふっ。ここに来て、サミーが一番忙しくしていたからね。誰よりも早く感じるのは当然だわ」
「お嬢様のためなら、このサミー。いくらだって頑張れますよ! 下心のある者を一歩たりとも近づけはしませんからっ!」
ということは、やっぱりいたのね。それもたくさん。
胸を張って言うサミーには悪いけれど、その態度でおおよそのことは想像がついた。
私に気に入られれば、エヴァレット辺境伯領だけでなく、首都のタウンハウスへ行く機会だってできる。
そして、子爵か男爵でもいい。貴族と結婚して華やかな人生を送りたい! と考えている女性は、何も辺境だからいるってわけじゃない。首都にいる者たちだって同じだった。
お父様の浮気相手がいい例。お母様という強敵を前に、戦うこともなく逃げていったけれど。
そんな怪物たちがどこに潜んでいるのかも分からない世界に、好き好んで入ろうだなんて……。
もしかして、シオドーラがエヴァレット辺境伯領にいるのは、そのため……? 何となくだけど、違うような気がする。
アリスター様に気があるような……そんな感じがするのだ。だから、あの場所にいたのが、その証拠。
一日に一度は展望台に行く、と公言するくらいだから、周りの人間たちだって勿論、知っているのだろう。
つまりあの場所にいれば、必ずアリスター様に会える。ガーラナウム城への立ち入りを禁止されているのに、シオドーラがやってきた理由は、それしかない。
いつ現れるかも分からないアリスター様を待っていたのだ。
けれどアリスター様はシオドーラを邪険に扱っている。何の力もない私より、聖女の方が辺境伯領には必要なのに。
私を……。
「如何されましたか? そんな可笑しなことを言ったでしょうか」
「えっ!? あっ、違うの。えっと、お母様が一週間後にやって来ると思ったら、ちょっと憂鬱になっちゃって……。でも、お兄様たちも来るでしょう。それは楽しみなの。だから、ちょっと複雑な気分になっちゃって」
「そうですね。お坊ちゃま方は寂しそうにされていると思うので、きっとお喜びになられますわ。けれど奥様は……この現状を見たら、お怒りになるかもしれません。急いで首都を出ざるを得なかったとはいえ、準備不足は否めませんから」
しまった!
シオドーラのことを気にしていたとはいえ、サミーを落ち込ませてしまうなんて……!
「大丈夫よ。それは皆、納得した上のことなんだから、いくらお母様でも怒ることはないと思うの」
「しかし……」
「仮にしたとしても、矛先はきっと別のところに行くはずだから。サミーは安心していいんだからね」
そこまで言うと、さすがのサミーでも、私の言葉の真意に気がついたようだった。
確かにお母様はご自分にも他人にも厳しい方だけど、その分、愛情も大きい。けれど、一度敵意を向けた相手には、とことん厳しかった。
***
「この状態で結婚式を挙げるなんて、本気で言っているの?」
性格が似ているから、尚のこと、お母様の行動は読み易い。着いて早々、準備が半分も出来ていない惨状に、抗議の声を上げた。
勿論相手は……。
「落ち着いてください、ブレイズ公爵夫人。それを見越して、これだけの大所帯で、辺境伯領に押し寄せたのではないのですか?」
そう、アリスター様の言う通り、お母様はまるで、こちらの状況を知っていたのかと思うくらい、多くの物資と人を連れてきた。
「念のために、よ。これ以上、メイベルが恥をかかないように万全を期しただけ。さぁ、メイベル。貴女はドレスの仕上げに向かいなさい」
「ですが……」
大丈夫なのですか? とアリスター様の方に顔を向ける。
いくらここがアリスター様の領地であり、お母様が部外者ともいえる立場であったとしても。この状態を放置して去るのは気まずかった。
とはいえ、私に何か出来るわけじゃないんだけど。
「時間がないことくらい、分かるでしょう。メイベルにしかできないものが、まだまだ山のようにあるのよ。のんびりしていたツケを、あとで払う方がどれだけ大変か。身をもって知りたいのならいいけれど?」
「……いいえ」
お母様たちの滞在日数は決まっている。無限ではないのだ。私は渋々、客間へ向かって行った。
その後、ガーラナウム城の使用人たちが、あわあわするほどの攻防が繰り広げられていたとも知らずに。
***
けれど結婚式までの騒動は、これだけではなかった。
長いこと女主人がいなかった、ということもあり、お母様の目につく案件が山のように出てきてしまったのだ。
たとえば、結婚式の招待状から設営に至るまで。
ガーラナウム城では戦勝パーティーなどはするが、舞踏会などの近隣の貴族を招く催しは、近年、開催すらされていなかったらしい。呼べるような時勢でもなかったのも相まって。
そのため、ダリルがお母様に頼んだのだ。
どの道、口を出されるのなら一層のこと、任せた方がいいと思ったのだろう。それが問題の一因だったことにも気づかずに。
そのお陰で私は今、お母様の指示のもと、招待客をチェックし、招待状をダリルの妻、ハリエットと共に作成していた。
「何だかお母様が迷惑をかけているみたいで、ごめんね」
「そんなっ! 本当なら私かメイド長がするところをやっていただいていますので、とても助かっています。何分、ガーラナウム城は男所帯ですから、私たちが何を言っても聞いてくれないことが多いんです」
「確かに。そんな感じがするわ。でもお母様は相手が男だろうが、女だろうが関係ない。刃向かってくれば正論で捲し立てるし、護身術も身につけていらっしゃるから大丈夫だと思うの」
一応、常に護衛を配置しているから、万が一、ということもないだろう。
「噂には聞いていましたが、やはり凄い方なのですね」
「まぁ、うん。……そうね」
どんな噂が出回っているのか、敢えて聞かずにおいた。だいたいは公爵邸でのものと変わらないだろうから。
私はハハハッと愛想笑いをして、その場をやり過ごした。
そして一カ月後、無事(?)に結婚式が行われる運びとなったのだ。