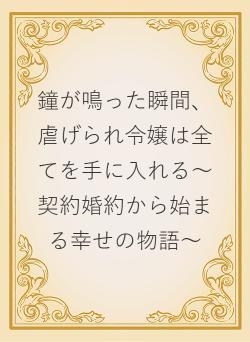お詫びに行く、というのはこちらの都合で、本当は呼び出されたらしい。
皇城にあるバードランド皇子の執務室に入ると、まるで待っていたかのような態度だった。
恐らく、早朝にブレイズ公爵家に訪れたというのに、用事の一つもこなせなかったどころか、恥をかかされた、と思い込んでいるのかもしれない。
バードランド皇子とはそういう男なのだ。だから、私は好きになれなかった。
「メイベル嬢。私にまず言うことがあるんじゃないか」
執務室に入っても何も言わない私に対して、高圧的な態度を取るバードランド皇子。
「そうですね。頭は大丈夫ですか? 打ったとお聞きしましたが」
私が投げた枕が、勢いよく頭に直撃したらしい。
そこまで重みのある枕ではなかったのだが、反動で後ろに倒れた挙げ句、頭から地面に……。いい音がしたらしいが、私は再びベッドの中に入ってしまったため、知らなかったのだ。
「っ! どうやら反省していないようだな」
「気に触ったのならお詫び致します。けれど何分、寝起きのことだったので、記憶にないんです」
私とバードランド皇子のやり取りに、執務室にいる側近は青ざめ、使用人たちは顔を赤らめた。
別段、甘い会話をしているわけではないのだが、やはり婚約者という立場が、拍車をかけるのだろう。
ブレイズ公爵家に生まれた、というだけで決められた婚約だというのに。それはバードランド皇子も同じだった。
「だったら再び言うだけだ。私はメイベル嬢との婚約破棄を望んでいる」
「……望めば破棄できるんですか?」
この婚約は皇帝が、いや皇后がバードランド皇子のためにしたもの。破棄することは、双方を無下にするのに等しかった。
私はその、皇后と同じ赤い髪と、皇帝から受け継いだ皇族の証でもある、金色の瞳を見つめた。
「それだけならば苦労はしない」
「でしたらどうするんですか? 良い案でも?」
「……メイベル嬢は相変わらず揚げ足を取るのが好きだな」
そんなつもりはないんだけど……取られる方が悪いとは思わないのかしら。
「だがそれもこれまでだ。今朝の件を不敬罪とし、婚約破棄を免罪符にする」
「……悪い案ではありませんが、私だけ損をしていませんか?」
「物事を成し遂げるためには犠牲はつきものだ。よってすまないが、一時、牢に入ってもらう」
「え?」
反論さえも許してくれないのか、側近たちに取り押さえられた。一応、公爵令嬢という肩書があるせいか、両腕を掴まれただけに過ぎない。
それでも、男二人に抵抗する力を持ち合わせていない私には到底、太刀打ちできなかった。
「大丈夫。すぐに助けが来るはずだから」
「な、何を根拠に! それにいきなりこのようなことをして、横暴過ぎだとは思わないのですか?」
「しかしメイベル嬢も、破棄自体には反対しなかったではないか」
「それは……」
恋愛感情もない相手にどうしろというの? 私だって好きな人と結婚したいというのに。
けれどそんなことを言えば、火に油を注ぐのと同じ結果しか生まないのは分かっている。幼い時から知っているだけに、厄介な相手だった。
「しばらくの我慢だ。正式に婚約が破棄されれば解放する」
「こんな状況で、それを信じろというのですか?」
「すまない。しかし、今の私にはそれしか言えないんだ」
「っ!」
こんなことなら、枕じゃなくて壺でも投げればよかった。
両脇にいるバードランド皇子の側近に引かれながら、私は執務室の外へ連れ出される。
憤りに満ちていた私は、その二人の表情が憐れんでいることなど、一切気づくことはなかった。
***
その感情は、側近が騎士に、私を引き渡した後も煮えたぎっていた。さらに牢へ入れられた時は、最高潮といっても過言ではない。
そもそも一時っていつまで?
「助けなんて、誰が来るというのかしら」
今日の登城だって、お母様の説教の末、お父様に命じられたのだ。牢に入れられたと知られれば、謝罪に失敗したと思われた挙げ句、恥さらしだと思われる可能性が大きかった。
それだけ、ベルリカーク国唯一の公爵家というのは、プライドが高いのだ。特にお母様のような、嫁いできた身としては。
しかも寝起きが悪いのが原因で牢屋に入るなんて、顔向けできない!
「ということは、期待してもいいのだろうか」
両手で顔を覆い、羞恥と絶望に苛まれている最中。誰かに声をかけられるとは思わなかった私は、間抜けにも辺りを見渡した。
「こっちだ。メイベル・ブレイズ公爵令嬢」
名前を呼ばれて、ようやく鉄格子の方へ視線を向ける。が、そこに立っていたのは、見覚えのない男性だった。
「誰?」
明らかに看守ではないと分かる身なり。紺色の上着はシックに見えるが、使われている生地には光沢があり、肌触りが良さそうだった。明らかに安物だとは思えない代物。
さらに容貌もキリッとしていて、どこか理知的にも見える。銀色の髪も手入れが行き届いているのか艶があり、サラサラしていた。
どこかの令息? ううん。私よりもかなり年上に見えるから、爵位を賜っている方のかもしれない。
「アリスター・エヴァレットだ」
「エヴァ、レット?」
聞いたことのある家名を前に、私の頭がフル動員して、脳の中にある貴族名鑑を捲った。
妃教育を受けていた賜物なのか、そういう癖がついていたのだ。お陰で、結果を導き出すのに、そう時間はかからなかった。
「っ! 辺境伯、様?」
私は思わずその名を口にした。アリスター様の口角が上がっていることに気づかないほど、驚きの声を上げながら。
皇城にあるバードランド皇子の執務室に入ると、まるで待っていたかのような態度だった。
恐らく、早朝にブレイズ公爵家に訪れたというのに、用事の一つもこなせなかったどころか、恥をかかされた、と思い込んでいるのかもしれない。
バードランド皇子とはそういう男なのだ。だから、私は好きになれなかった。
「メイベル嬢。私にまず言うことがあるんじゃないか」
執務室に入っても何も言わない私に対して、高圧的な態度を取るバードランド皇子。
「そうですね。頭は大丈夫ですか? 打ったとお聞きしましたが」
私が投げた枕が、勢いよく頭に直撃したらしい。
そこまで重みのある枕ではなかったのだが、反動で後ろに倒れた挙げ句、頭から地面に……。いい音がしたらしいが、私は再びベッドの中に入ってしまったため、知らなかったのだ。
「っ! どうやら反省していないようだな」
「気に触ったのならお詫び致します。けれど何分、寝起きのことだったので、記憶にないんです」
私とバードランド皇子のやり取りに、執務室にいる側近は青ざめ、使用人たちは顔を赤らめた。
別段、甘い会話をしているわけではないのだが、やはり婚約者という立場が、拍車をかけるのだろう。
ブレイズ公爵家に生まれた、というだけで決められた婚約だというのに。それはバードランド皇子も同じだった。
「だったら再び言うだけだ。私はメイベル嬢との婚約破棄を望んでいる」
「……望めば破棄できるんですか?」
この婚約は皇帝が、いや皇后がバードランド皇子のためにしたもの。破棄することは、双方を無下にするのに等しかった。
私はその、皇后と同じ赤い髪と、皇帝から受け継いだ皇族の証でもある、金色の瞳を見つめた。
「それだけならば苦労はしない」
「でしたらどうするんですか? 良い案でも?」
「……メイベル嬢は相変わらず揚げ足を取るのが好きだな」
そんなつもりはないんだけど……取られる方が悪いとは思わないのかしら。
「だがそれもこれまでだ。今朝の件を不敬罪とし、婚約破棄を免罪符にする」
「……悪い案ではありませんが、私だけ損をしていませんか?」
「物事を成し遂げるためには犠牲はつきものだ。よってすまないが、一時、牢に入ってもらう」
「え?」
反論さえも許してくれないのか、側近たちに取り押さえられた。一応、公爵令嬢という肩書があるせいか、両腕を掴まれただけに過ぎない。
それでも、男二人に抵抗する力を持ち合わせていない私には到底、太刀打ちできなかった。
「大丈夫。すぐに助けが来るはずだから」
「な、何を根拠に! それにいきなりこのようなことをして、横暴過ぎだとは思わないのですか?」
「しかしメイベル嬢も、破棄自体には反対しなかったではないか」
「それは……」
恋愛感情もない相手にどうしろというの? 私だって好きな人と結婚したいというのに。
けれどそんなことを言えば、火に油を注ぐのと同じ結果しか生まないのは分かっている。幼い時から知っているだけに、厄介な相手だった。
「しばらくの我慢だ。正式に婚約が破棄されれば解放する」
「こんな状況で、それを信じろというのですか?」
「すまない。しかし、今の私にはそれしか言えないんだ」
「っ!」
こんなことなら、枕じゃなくて壺でも投げればよかった。
両脇にいるバードランド皇子の側近に引かれながら、私は執務室の外へ連れ出される。
憤りに満ちていた私は、その二人の表情が憐れんでいることなど、一切気づくことはなかった。
***
その感情は、側近が騎士に、私を引き渡した後も煮えたぎっていた。さらに牢へ入れられた時は、最高潮といっても過言ではない。
そもそも一時っていつまで?
「助けなんて、誰が来るというのかしら」
今日の登城だって、お母様の説教の末、お父様に命じられたのだ。牢に入れられたと知られれば、謝罪に失敗したと思われた挙げ句、恥さらしだと思われる可能性が大きかった。
それだけ、ベルリカーク国唯一の公爵家というのは、プライドが高いのだ。特にお母様のような、嫁いできた身としては。
しかも寝起きが悪いのが原因で牢屋に入るなんて、顔向けできない!
「ということは、期待してもいいのだろうか」
両手で顔を覆い、羞恥と絶望に苛まれている最中。誰かに声をかけられるとは思わなかった私は、間抜けにも辺りを見渡した。
「こっちだ。メイベル・ブレイズ公爵令嬢」
名前を呼ばれて、ようやく鉄格子の方へ視線を向ける。が、そこに立っていたのは、見覚えのない男性だった。
「誰?」
明らかに看守ではないと分かる身なり。紺色の上着はシックに見えるが、使われている生地には光沢があり、肌触りが良さそうだった。明らかに安物だとは思えない代物。
さらに容貌もキリッとしていて、どこか理知的にも見える。銀色の髪も手入れが行き届いているのか艶があり、サラサラしていた。
どこかの令息? ううん。私よりもかなり年上に見えるから、爵位を賜っている方のかもしれない。
「アリスター・エヴァレットだ」
「エヴァ、レット?」
聞いたことのある家名を前に、私の頭がフル動員して、脳の中にある貴族名鑑を捲った。
妃教育を受けていた賜物なのか、そういう癖がついていたのだ。お陰で、結果を導き出すのに、そう時間はかからなかった。
「っ! 辺境伯、様?」
私は思わずその名を口にした。アリスター様の口角が上がっていることに気づかないほど、驚きの声を上げながら。