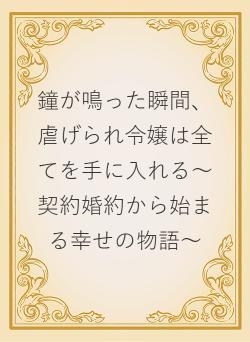「キャッ!」
いつ寝てしまったのか。さらに何故、こんな体勢で寝ていたのか。それらに驚く暇もないまま、私は馬車の中だということも忘れて飛び起きた。
途端、すぐさまアリスター様に腕を掴まれて、抱き寄せられる。
抵抗しようにも、長い溜め息のようなものが髪の毛にかかり、それもできなかった。
「っ!」
「本当に飛び起きるとは、な。予測していても、心臓に悪い」
「……あっ、すみません」
ガタガタッとリズミカルな揺れを感じる。アリスター様の言うように、いかに危険な行為をしたのか、思い知らされた。
下手をしたら、頭や背中、お尻まで打撲するところだったのだ。けれど、今の体勢は……。
さっきのも恥ずかしかったけれど。こ、これはもっと……!
何せ私は今、座っているアリスター様に抱き締められているのだ。それも、揺れる馬車の中、立っているため、ほぼ支えられていると言っても過言ではない。
「以後、気をつけますので、放してください」
「ダメだ」
「何故ですか!?」
「俺の膝が頑張ったんだ。褒美くらいは必要だろう?」
「意味が分かりません!」
膝が痺れたのであれば、逆に体を引き離した方が楽なのではないだろうか。体を前に倒している状態よりも、後ろの背もたれに預けている方が、何倍もいいと思う。
けれどアリスター様は、支離滅裂なことを平然と言う。
「ならば、暴れられないようにしているから、と答えれば満足か?」
「答え、いえ、質問の意図が分かりません。満足も何も、放してくれれば解決する話です。何を仰っているんですか?」
そう問いかけても、アリスター様の腕は一向に緩む気配はなかった。しかし、私の体は気持ちとは裏腹に、変な方に主張をし始めた。
ぐ~~~~~~。
「っ!」
「なるほど。俺が悪かった。考えてみればすぐに分かるというのに、配慮が足りなかったようだ」
「あ、その……違うんです。だから、お気遣いなく!」
とはいえ、この空腹をどうにかできる手段を私は持ち合わせていない。アタフタしている隙にアリスター様は、私を隣に座らせた。
逆にご自身は席を立つ。馬車はまだ動いているというのに。
「アリスター様っ!?」
「大丈夫だ。それよりも、サミーがメイベル嬢にと持ってきた食事だ。先ほどのは恐らく、この匂いにつられたのだろう。気にすることはない」
「あ、ありがとうございます……」
反対側の座席に置いてあったバスケットを手渡される。中には、包みが二つ。
これは私だけではなく、アリスター様の分も用意してくれたのかしら。そうなると、考えられることは一つしかない。
「もしかして、私のせいで食事を取られなかったのですか?」
「何故だ?」
「バスケットの中に、包みが二つあるからです。これは、私とアリスター様の分ではないのですか?」
すると、私の膝に置いてあるバスケットを覗き込む。本当なのかどうか、確かめるのはごく自然な行為だというのに、また距離が縮まってしまった。
「なるほどな。俺は腹が減っていないが、貰おうか」
「無理しないでください。私が食べますから」
「もうすぐ宿に着く。それまでに食べきれるのか。この量を、一人で」
「っ! 平気です!」
体感としては、そこまでお腹は空いていないけれど、食べ出した瞬間、それは錯覚だったことが何度もあった。特に長時間寝た後は特に。
だからサミーも、それを見越したに違いない。
私は包みを取り出して、中にあったサンドイッチを口に入れた。すでに時間が経っていたため、パンに挟まっていたレタスにシャキシャキ感はない。
けれど、ハムやチーズはそのままでも十分美味しかった。これなら、もう一食分は食べられそうだと、ふと顔を上げた瞬間、サミーの意図を履き違えていたことに気がついた。
「あの、やっぱり少しだけ手伝ってもらえませんか?」
そう、一人で食べている気まずさだ。しかも、ずっとこちらを向いている。物欲しそうな顔をしていなくても、差し出したくなってしまう。
だからもう一食分、用意してくれたのね。一人で食事をする時は、サミーも一緒に食べるように言っていたから。
「……最初から素直に言えばいいものの」
「そうですね。今回は反省しています。サミーの好意を無下にしてしまうところでしたから」
「何?」
「私は一人で食べるのが苦手なんです。憶えておいてもらえますか?」
「勿論」
アリスター様はそういうと、私の手首を掴み、そのままサンドイッチに齧り付いた。
「ふふふっ。そういうところも含めて、お兄様と同じなんですね。アリスター様の方が豪快ですが」
「エルバートもするのか?」
「クリフもしますよ。二人とも、食事の用意まで待てないらしくて」
「……多分、違うと思うぞ」
「え?」
私が驚いている間に、サンドイッチは半分以上無くなっていた。さすがは辺境伯様。どんな場面にも対応できるように、普段から心掛けているのだろう。
そろそろ手を離すところかな、と様子を窺っていると、アリスター様からとんでもない発言が飛び出した。
「残りは食べていいからな」
残りって、アリスター様。
私は、自分の手よりも小さくなったサンドイッチの残骸を見た。
「ご自分で最後まで食べてください!」
今度は私が、アリスター様の手首を掴む。このへそ曲がりめ、とばかりの勢いで。
いつ寝てしまったのか。さらに何故、こんな体勢で寝ていたのか。それらに驚く暇もないまま、私は馬車の中だということも忘れて飛び起きた。
途端、すぐさまアリスター様に腕を掴まれて、抱き寄せられる。
抵抗しようにも、長い溜め息のようなものが髪の毛にかかり、それもできなかった。
「っ!」
「本当に飛び起きるとは、な。予測していても、心臓に悪い」
「……あっ、すみません」
ガタガタッとリズミカルな揺れを感じる。アリスター様の言うように、いかに危険な行為をしたのか、思い知らされた。
下手をしたら、頭や背中、お尻まで打撲するところだったのだ。けれど、今の体勢は……。
さっきのも恥ずかしかったけれど。こ、これはもっと……!
何せ私は今、座っているアリスター様に抱き締められているのだ。それも、揺れる馬車の中、立っているため、ほぼ支えられていると言っても過言ではない。
「以後、気をつけますので、放してください」
「ダメだ」
「何故ですか!?」
「俺の膝が頑張ったんだ。褒美くらいは必要だろう?」
「意味が分かりません!」
膝が痺れたのであれば、逆に体を引き離した方が楽なのではないだろうか。体を前に倒している状態よりも、後ろの背もたれに預けている方が、何倍もいいと思う。
けれどアリスター様は、支離滅裂なことを平然と言う。
「ならば、暴れられないようにしているから、と答えれば満足か?」
「答え、いえ、質問の意図が分かりません。満足も何も、放してくれれば解決する話です。何を仰っているんですか?」
そう問いかけても、アリスター様の腕は一向に緩む気配はなかった。しかし、私の体は気持ちとは裏腹に、変な方に主張をし始めた。
ぐ~~~~~~。
「っ!」
「なるほど。俺が悪かった。考えてみればすぐに分かるというのに、配慮が足りなかったようだ」
「あ、その……違うんです。だから、お気遣いなく!」
とはいえ、この空腹をどうにかできる手段を私は持ち合わせていない。アタフタしている隙にアリスター様は、私を隣に座らせた。
逆にご自身は席を立つ。馬車はまだ動いているというのに。
「アリスター様っ!?」
「大丈夫だ。それよりも、サミーがメイベル嬢にと持ってきた食事だ。先ほどのは恐らく、この匂いにつられたのだろう。気にすることはない」
「あ、ありがとうございます……」
反対側の座席に置いてあったバスケットを手渡される。中には、包みが二つ。
これは私だけではなく、アリスター様の分も用意してくれたのかしら。そうなると、考えられることは一つしかない。
「もしかして、私のせいで食事を取られなかったのですか?」
「何故だ?」
「バスケットの中に、包みが二つあるからです。これは、私とアリスター様の分ではないのですか?」
すると、私の膝に置いてあるバスケットを覗き込む。本当なのかどうか、確かめるのはごく自然な行為だというのに、また距離が縮まってしまった。
「なるほどな。俺は腹が減っていないが、貰おうか」
「無理しないでください。私が食べますから」
「もうすぐ宿に着く。それまでに食べきれるのか。この量を、一人で」
「っ! 平気です!」
体感としては、そこまでお腹は空いていないけれど、食べ出した瞬間、それは錯覚だったことが何度もあった。特に長時間寝た後は特に。
だからサミーも、それを見越したに違いない。
私は包みを取り出して、中にあったサンドイッチを口に入れた。すでに時間が経っていたため、パンに挟まっていたレタスにシャキシャキ感はない。
けれど、ハムやチーズはそのままでも十分美味しかった。これなら、もう一食分は食べられそうだと、ふと顔を上げた瞬間、サミーの意図を履き違えていたことに気がついた。
「あの、やっぱり少しだけ手伝ってもらえませんか?」
そう、一人で食べている気まずさだ。しかも、ずっとこちらを向いている。物欲しそうな顔をしていなくても、差し出したくなってしまう。
だからもう一食分、用意してくれたのね。一人で食事をする時は、サミーも一緒に食べるように言っていたから。
「……最初から素直に言えばいいものの」
「そうですね。今回は反省しています。サミーの好意を無下にしてしまうところでしたから」
「何?」
「私は一人で食べるのが苦手なんです。憶えておいてもらえますか?」
「勿論」
アリスター様はそういうと、私の手首を掴み、そのままサンドイッチに齧り付いた。
「ふふふっ。そういうところも含めて、お兄様と同じなんですね。アリスター様の方が豪快ですが」
「エルバートもするのか?」
「クリフもしますよ。二人とも、食事の用意まで待てないらしくて」
「……多分、違うと思うぞ」
「え?」
私が驚いている間に、サンドイッチは半分以上無くなっていた。さすがは辺境伯様。どんな場面にも対応できるように、普段から心掛けているのだろう。
そろそろ手を離すところかな、と様子を窺っていると、アリスター様からとんでもない発言が飛び出した。
「残りは食べていいからな」
残りって、アリスター様。
私は、自分の手よりも小さくなったサンドイッチの残骸を見た。
「ご自分で最後まで食べてください!」
今度は私が、アリスター様の手首を掴む。このへそ曲がりめ、とばかりの勢いで。