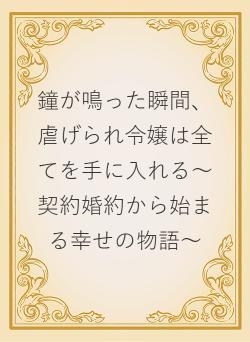黒を基調とした清潔感のある客室。同じ屋敷に住みながら馴染のない部屋に、思わず辺りを見渡した。
まず目を引いたのは、隅に置かれた背の高い観葉植物。緑は目に優しく、癒しの効果もあると聞くから、客室に相応しかった。黒い部屋の中で、いいアクセントにもなっている。
また、飾られている絵画は何代か前のブレイズ公爵の功績を讃えたものだ。
正確な数字は覚えていないけれど、他の部屋にも似たような絵画が飾られているから、これくらいは分かる。
そういう面ではお兄様の言う通り、同じ騎士団を抱えている家門が迎えるに相応しい部屋だと思った。
意外にも、ちゃんと考えて割り振られていたのね。いや、公爵家のプライドというやつかしら。
お母様の考えに染まってしまったのか、我が家の使用人たちは、誇りを大事にする者が多かった。また、サミーのような過保護になってしまう使用人も。
「ここに入るのは初めてか?」
後ろから聞こえてくるアリスター様の声音は、普段と変わらなかった。が、責められているわけではないと分かりつつも、その余韻に俯いてしまう。
『自分の家なのに?』
そう非難されているように感じたのだ。
「まぁ俺も、領地にある邸宅もそうだが、首都のタウンハウスも把握しきれていない身だ」
「そう、なんですか?」
「あぁ。邸宅を仕切っている家令の方が、俺なんかよりも詳しく知っている。自信を持って言えるぞ。それに幾つも抱えていると、どうしてもな。だからいい機会だと思って、存分に見て行け」
これは……もしかして、励まされている? 言葉は自傷も交じった乱暴なものだったけれど。
思わず私はアリスター様に近づいた。
「何を仰っているんですか? ここは私の家ですよ。存分に見るのは当たり前ではありませんか」
したり顔で言いながらも、内心は本当、私も素直じゃない、と思ってしまう。
「自分の家だというのなら、どうして正規の方法で来なかった?」
「え?」
「簡単なことだ。ブレイズ公爵夫人が許可を出すはずがない。メイベル嬢とバードランド皇子の婚約破棄の裏話を知っているだけに、俺への当たりは強いからだ。そんなところに――……」
「だからです!」
私は声を張り上げた。が、次に出てきたのは小さな声だった。
「だから……心配になったんです」
「なるほど。だから、さっきのメイドが……」
「サミーです。お母様の目を掻い潜れる方法で、ここまで連れてきてもらいました」
さすがに隠し通路のことは口に出せなかった。いくら婚約者になったからといえども、公爵邸の秘密を言うわけにはいかないのだ。
「どんな方法か、はおおよそ想像できる。が、危険を掻い潜ってまで来る必要はあったか? これでも辺境の地で心身ともに鍛えているんだ。魔物や隣国相手にも戦っている。しかし、頼りなく見えてしまうのなら仕方がないがな」
「いいえ。そんなことはありません」
頼りない人物だったら、いくら釈放する条件とはいえ、契約結婚など受け入れてはいなかっただろう。
この人なら大丈夫だと思ったから。そう、思えたから承諾したのだ。
「本当か?」
「はい。しかし、ここは公爵邸で、私の家なんです。お母様の意に染まった使用人も多いため、何かあったら、と心配するのは当たり前ではありませんか。アリスター様がここの家人、または使用人たちを傷つけることはしない、と思っているので、余計に」
現にお母様に対して、横柄な態度を取っていなかった。だからこそ、やられっぱなしになるのでは、と思ってしまったのだ。
「婚約破棄されて、行く手のない私を憐れに思って引き受けてくださった、というのなら話は別ですが……」
「それは違うと言ったではないか」
「……ですが、お兄様とお知り合い、いえ親しいようでしたので、やっぱりと思ってしまったんです。バードランド皇子では、お母様相手に対応できないから頼まれたのではありませんか? 昼間の様子から、全く問題ないように見えました」
「何を聞いたのか知らないが、それもまた違う」
ここまで言ったのにもかかわらず、やはり何も語ってはくれない。契約結婚の話を持ちかけられた時のように。
もしかして、アリスター様もすぐに知られるのは恥ずかしいのかしら。私がその立場だったら……確かに恥ずかしいし気まずいかもしれない。
どの道、アリスター様とは長い付き合いになるのだ。最低でも一年は。
それは考えれば、すぐに分かることだった。
朝寝坊はし放題。辺境伯夫人の仕事は最低限でいいと言っても、嫁ぐ場所は慣れない辺境の地。
望めば首都のタウンハウスにいてもいいらしいが、そこだって我が家のようになるまで、どのくらいかかるか分からない。
さらにいうと、他に好きな方など、すぐにできるとは思えないことも一因だった。
なにせ、バードランド皇子の婚約者になった後も、様々な殿方に会ったが、特にいいと思える人はいなかったからだ。
辺境伯領に行けば、また違うのかもしれないけれど……。
私は頭を振った。
「ともあれ、私の取り越し苦労でご迷惑をおかけしました。今後は気をつけます」
「そうしてもらえると助かる。いくら婚約者になったばかりといえど……それが名ばかりであったとしても、俺も男だ。こんな時間にそんな格好で来られるのは困る」
格好? あぁ、寝間着のことかな。でも、カーディガンを羽織っているから問題はないと思うけれど。ここに来る前に、大丈夫かどうか、サミーに確認してもらったんだから。
けれど、男性と女性とでは主観が違うのかもしれない。私は恐る恐る尋ねた。
「……困るほど、変な格好……ですか?」
「いや、そうじゃない。そうじゃなくて、だな。……危険だと言っているんだ」
「え?」
何が、と思っている間に一歩、近づくアリスター様。私も反射的に一歩、下がる。すると、また距離を縮められてしまう。
アリスター様の顔も、どこか怒っているのか眉間に皺を寄せ、口も一文字に結んでいる。確かに身の危険を感じた。
故に私は後退せざるを得なかったのだ。その方向も、無意識に扉へと。まるで引っ張られるように、向かって行った。
「多少は、俺の言った意味が分かったか?」
扉に背中が当たった瞬間、低い声で問いかけてくるアリスター様。
さらに顔を近づけられて、思わず目を瞑った。途端、影が差し、アリスター様が言った『危険』という言葉がさらに脳裏に浮かぶ。
「っ! す、すまない」
私の体が小刻みに震え出したのと同時に、アリスター様の気配が遠ざかる。けれど、震えは止まらなかった。すると、背もたれにしている扉から、小さなノック音がした。
「お嬢様?」
サミーの声に目を開ける。震えも止まり、私は息をゆっくりと吐いた。いくらお母様譲りの性格といっても、周りにいつも助けられてきた。
今はサミーに。牢屋の中ではアリスター様に。
そうだ。私は助けてもらったんだった、アリスター様に。公爵邸に帰る時だって、慰めてくれた。それなのに私は、怯えるなんて失礼なことを……!
謝らないと、と思って顔を上げた瞬間、さっきまで残っていた恐怖心が一気になくなった。
だって、あんなに怖かったアリスター様の顔が……ふふふっ。
眉を寄せているところは同じだが、八の字になり、口は何かを言いたいのか、開いたり閉じたりして忙しい。
そう、見たことがないほど狼狽えていたのだ。
まず目を引いたのは、隅に置かれた背の高い観葉植物。緑は目に優しく、癒しの効果もあると聞くから、客室に相応しかった。黒い部屋の中で、いいアクセントにもなっている。
また、飾られている絵画は何代か前のブレイズ公爵の功績を讃えたものだ。
正確な数字は覚えていないけれど、他の部屋にも似たような絵画が飾られているから、これくらいは分かる。
そういう面ではお兄様の言う通り、同じ騎士団を抱えている家門が迎えるに相応しい部屋だと思った。
意外にも、ちゃんと考えて割り振られていたのね。いや、公爵家のプライドというやつかしら。
お母様の考えに染まってしまったのか、我が家の使用人たちは、誇りを大事にする者が多かった。また、サミーのような過保護になってしまう使用人も。
「ここに入るのは初めてか?」
後ろから聞こえてくるアリスター様の声音は、普段と変わらなかった。が、責められているわけではないと分かりつつも、その余韻に俯いてしまう。
『自分の家なのに?』
そう非難されているように感じたのだ。
「まぁ俺も、領地にある邸宅もそうだが、首都のタウンハウスも把握しきれていない身だ」
「そう、なんですか?」
「あぁ。邸宅を仕切っている家令の方が、俺なんかよりも詳しく知っている。自信を持って言えるぞ。それに幾つも抱えていると、どうしてもな。だからいい機会だと思って、存分に見て行け」
これは……もしかして、励まされている? 言葉は自傷も交じった乱暴なものだったけれど。
思わず私はアリスター様に近づいた。
「何を仰っているんですか? ここは私の家ですよ。存分に見るのは当たり前ではありませんか」
したり顔で言いながらも、内心は本当、私も素直じゃない、と思ってしまう。
「自分の家だというのなら、どうして正規の方法で来なかった?」
「え?」
「簡単なことだ。ブレイズ公爵夫人が許可を出すはずがない。メイベル嬢とバードランド皇子の婚約破棄の裏話を知っているだけに、俺への当たりは強いからだ。そんなところに――……」
「だからです!」
私は声を張り上げた。が、次に出てきたのは小さな声だった。
「だから……心配になったんです」
「なるほど。だから、さっきのメイドが……」
「サミーです。お母様の目を掻い潜れる方法で、ここまで連れてきてもらいました」
さすがに隠し通路のことは口に出せなかった。いくら婚約者になったからといえども、公爵邸の秘密を言うわけにはいかないのだ。
「どんな方法か、はおおよそ想像できる。が、危険を掻い潜ってまで来る必要はあったか? これでも辺境の地で心身ともに鍛えているんだ。魔物や隣国相手にも戦っている。しかし、頼りなく見えてしまうのなら仕方がないがな」
「いいえ。そんなことはありません」
頼りない人物だったら、いくら釈放する条件とはいえ、契約結婚など受け入れてはいなかっただろう。
この人なら大丈夫だと思ったから。そう、思えたから承諾したのだ。
「本当か?」
「はい。しかし、ここは公爵邸で、私の家なんです。お母様の意に染まった使用人も多いため、何かあったら、と心配するのは当たり前ではありませんか。アリスター様がここの家人、または使用人たちを傷つけることはしない、と思っているので、余計に」
現にお母様に対して、横柄な態度を取っていなかった。だからこそ、やられっぱなしになるのでは、と思ってしまったのだ。
「婚約破棄されて、行く手のない私を憐れに思って引き受けてくださった、というのなら話は別ですが……」
「それは違うと言ったではないか」
「……ですが、お兄様とお知り合い、いえ親しいようでしたので、やっぱりと思ってしまったんです。バードランド皇子では、お母様相手に対応できないから頼まれたのではありませんか? 昼間の様子から、全く問題ないように見えました」
「何を聞いたのか知らないが、それもまた違う」
ここまで言ったのにもかかわらず、やはり何も語ってはくれない。契約結婚の話を持ちかけられた時のように。
もしかして、アリスター様もすぐに知られるのは恥ずかしいのかしら。私がその立場だったら……確かに恥ずかしいし気まずいかもしれない。
どの道、アリスター様とは長い付き合いになるのだ。最低でも一年は。
それは考えれば、すぐに分かることだった。
朝寝坊はし放題。辺境伯夫人の仕事は最低限でいいと言っても、嫁ぐ場所は慣れない辺境の地。
望めば首都のタウンハウスにいてもいいらしいが、そこだって我が家のようになるまで、どのくらいかかるか分からない。
さらにいうと、他に好きな方など、すぐにできるとは思えないことも一因だった。
なにせ、バードランド皇子の婚約者になった後も、様々な殿方に会ったが、特にいいと思える人はいなかったからだ。
辺境伯領に行けば、また違うのかもしれないけれど……。
私は頭を振った。
「ともあれ、私の取り越し苦労でご迷惑をおかけしました。今後は気をつけます」
「そうしてもらえると助かる。いくら婚約者になったばかりといえど……それが名ばかりであったとしても、俺も男だ。こんな時間にそんな格好で来られるのは困る」
格好? あぁ、寝間着のことかな。でも、カーディガンを羽織っているから問題はないと思うけれど。ここに来る前に、大丈夫かどうか、サミーに確認してもらったんだから。
けれど、男性と女性とでは主観が違うのかもしれない。私は恐る恐る尋ねた。
「……困るほど、変な格好……ですか?」
「いや、そうじゃない。そうじゃなくて、だな。……危険だと言っているんだ」
「え?」
何が、と思っている間に一歩、近づくアリスター様。私も反射的に一歩、下がる。すると、また距離を縮められてしまう。
アリスター様の顔も、どこか怒っているのか眉間に皺を寄せ、口も一文字に結んでいる。確かに身の危険を感じた。
故に私は後退せざるを得なかったのだ。その方向も、無意識に扉へと。まるで引っ張られるように、向かって行った。
「多少は、俺の言った意味が分かったか?」
扉に背中が当たった瞬間、低い声で問いかけてくるアリスター様。
さらに顔を近づけられて、思わず目を瞑った。途端、影が差し、アリスター様が言った『危険』という言葉がさらに脳裏に浮かぶ。
「っ! す、すまない」
私の体が小刻みに震え出したのと同時に、アリスター様の気配が遠ざかる。けれど、震えは止まらなかった。すると、背もたれにしている扉から、小さなノック音がした。
「お嬢様?」
サミーの声に目を開ける。震えも止まり、私は息をゆっくりと吐いた。いくらお母様譲りの性格といっても、周りにいつも助けられてきた。
今はサミーに。牢屋の中ではアリスター様に。
そうだ。私は助けてもらったんだった、アリスター様に。公爵邸に帰る時だって、慰めてくれた。それなのに私は、怯えるなんて失礼なことを……!
謝らないと、と思って顔を上げた瞬間、さっきまで残っていた恐怖心が一気になくなった。
だって、あんなに怖かったアリスター様の顔が……ふふふっ。
眉を寄せているところは同じだが、八の字になり、口は何かを言いたいのか、開いたり閉じたりして忙しい。
そう、見たことがないほど狼狽えていたのだ。