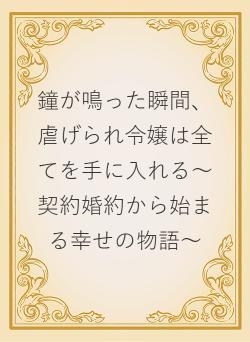ベルリカーク帝国唯一の公爵家と謳っているだけあって、我が家の屋敷も古い。
建てられた当時は最新の技術が用いられていたのだろうが、建国する前からあったとされるブレイズ公爵家。今では歴史的建造物に該当するほどだった。
けれど私は、それを疎ましく思ったことはない。誇らしいものだと教えられてきたからだ。とはいえ、真に受けることはしなかった。
『古き伝統を守るのが、貴族の責務です』
聞いた時は内心笑ったものだ。新しさを入れなければ、いつまでも発展しない。頭でっかちになる。けれど今なら実感する。その有り難みを。
「お嬢様、足元にお気をつけください」
狭く薄暗い中、手燭を持ったサミーが振り返った。黄色い蝋燭の光が私の方にも届く。サミーの顔を、柔らかな光が照らしてくれるお陰で、私の気持ちもいくらか和らいだ。
何せここは、ブレイズ公爵邸に張り巡らされている隠し通路なのだ。
初めて通る道なだけに、私はサミーの服を掴みながら歩いていた。サミーもまた、その方が安心できる、と言ってくれたお陰でもある。
「大丈夫。言われた通り、サミーと同じところを歩いているから」
「壁もなるべく触らないようにお願いしますね。仕掛けはないと聞いていますが、分からないので」
確かに。いつ、この通路が作られて、使用されなくなったのか、すら分からないという。さらに、仕掛けがあるのかないのかも不明らしい。……記録があまりにも無さ過ぎて。
あるのは、使用人たちの間で口伝のように語り継がれていたことだけ、だという。故に家人である私は知らなかったのだ。
サミーは家族で仕えてくれている、数少ない古参の分類に位置するメイドの一人。
男兄弟しかいない私にとって、姉のような親友のような存在なのだ。だからこそ、サミーの言葉は絶対だった。
今のように、お母様の裏をかくことも厭わない、その心意気。エヴァレット辺境伯領まで一緒に来てほしい。勿論、サミーとアリスター様の許可が取れれば、だけど。
「う、うん。それであと、どれくらいで着くの?」
「えーと、お嬢様のお部屋が南側で、エヴァレット辺境伯様がいる客室は西側にあるので……。さっき家紋が見えたから、大丈夫です。あと少しで着きます」
「……サミー。サミーとなら、ここで迷っても平気だからね」
頼りにはしているが、それでも思わず口に出た。
「そこはご安心してください。抜け道はたくさんありますから、いざとなったらそこから外に出ましょう」
「っ! 一生、着いていくからね!」
「ありがとうございます。でも、声は小さくお願いしますよ。隠し通路とはいえ、壁を隔てた先のお部屋に聞こえてしまっては元も子もありませんから」
私は咄嗟に口元を手で隠し、頷いた。するとサミーは優しく微笑み、再び前を向いて歩き出す。
うん。絶対にアリスター様にお願いしよう。サミーと離れるのは嫌だから。
それからどのくらい歩いただろうか。長くないとは思いつつ、変わらない景色に、私も飽き始めてしまった。
サミーが言うほど、仕掛けのようなものが発動されなかったからだ。だんだん、緊張感が薄れていく。
もしかしたら、ないのかもしれない。
そんな安易な想像も、徐々に薄まる原因の一つだった。しかしそれは私だけだったらしい。
再び振り向くサミーの表情は不安気だった。
「お嬢様。やはり一度、通路の外に出ますね。多分、ここで合っていると思うんですが、私も確信が持てないので」
「大丈夫よ。むしろずっと使っていなかったんだから」
本当に蝋燭の黄色い光は温かみがあっていい。安堵するサミーの表情が際立って、私まで嬉しくなった。
サミーは手燭を壁に近づけて、ゼラニウムの絵が彫られた石を押す。ゼラニウムの花言葉は確か、「真の友情」や「尊敬」があった。
その意味を持つ花ならば客室、または客間か応接間に繋がっている可能性が高い。
なるほど、と感心をしている暇もなく、開け放たれる扉。石を押したのと同時に開くのだから、こちらにも驚かされた。
「どういうカラクリをしているの?」
「さぁ。私もただ、こうすると開くことくらいにしか聞いていないので、何とも言えません」
「そうよね。逆にそこまで知っていたらビックリするわ」
いくら口伝でも限界はある。
私は気にせずに辺りを見渡した。
「ここは……廊下ね。しかも……」
壁に掛けられている燭台の光のお陰で、窓の外が見えた。我が家の庭師が丹精込めた庭園が。
「サミー、あれを見て。庭園がこの角度にあるってことは」
「はい。ここを真っ直ぐ行けば、客室です。なので、もうすぐですよ、お嬢様。どの部屋をお使いになられているのかは、把握しておりますので、そちらも問題ありません」
「わぁ、ありがとう、サミー!」
ようやく見えたゴールに、私たちは周りを気にする余裕もなくはしゃいだ。深夜ではないとはいえ、廊下に響き渡っているとも知らずに。
建てられた当時は最新の技術が用いられていたのだろうが、建国する前からあったとされるブレイズ公爵家。今では歴史的建造物に該当するほどだった。
けれど私は、それを疎ましく思ったことはない。誇らしいものだと教えられてきたからだ。とはいえ、真に受けることはしなかった。
『古き伝統を守るのが、貴族の責務です』
聞いた時は内心笑ったものだ。新しさを入れなければ、いつまでも発展しない。頭でっかちになる。けれど今なら実感する。その有り難みを。
「お嬢様、足元にお気をつけください」
狭く薄暗い中、手燭を持ったサミーが振り返った。黄色い蝋燭の光が私の方にも届く。サミーの顔を、柔らかな光が照らしてくれるお陰で、私の気持ちもいくらか和らいだ。
何せここは、ブレイズ公爵邸に張り巡らされている隠し通路なのだ。
初めて通る道なだけに、私はサミーの服を掴みながら歩いていた。サミーもまた、その方が安心できる、と言ってくれたお陰でもある。
「大丈夫。言われた通り、サミーと同じところを歩いているから」
「壁もなるべく触らないようにお願いしますね。仕掛けはないと聞いていますが、分からないので」
確かに。いつ、この通路が作られて、使用されなくなったのか、すら分からないという。さらに、仕掛けがあるのかないのかも不明らしい。……記録があまりにも無さ過ぎて。
あるのは、使用人たちの間で口伝のように語り継がれていたことだけ、だという。故に家人である私は知らなかったのだ。
サミーは家族で仕えてくれている、数少ない古参の分類に位置するメイドの一人。
男兄弟しかいない私にとって、姉のような親友のような存在なのだ。だからこそ、サミーの言葉は絶対だった。
今のように、お母様の裏をかくことも厭わない、その心意気。エヴァレット辺境伯領まで一緒に来てほしい。勿論、サミーとアリスター様の許可が取れれば、だけど。
「う、うん。それであと、どれくらいで着くの?」
「えーと、お嬢様のお部屋が南側で、エヴァレット辺境伯様がいる客室は西側にあるので……。さっき家紋が見えたから、大丈夫です。あと少しで着きます」
「……サミー。サミーとなら、ここで迷っても平気だからね」
頼りにはしているが、それでも思わず口に出た。
「そこはご安心してください。抜け道はたくさんありますから、いざとなったらそこから外に出ましょう」
「っ! 一生、着いていくからね!」
「ありがとうございます。でも、声は小さくお願いしますよ。隠し通路とはいえ、壁を隔てた先のお部屋に聞こえてしまっては元も子もありませんから」
私は咄嗟に口元を手で隠し、頷いた。するとサミーは優しく微笑み、再び前を向いて歩き出す。
うん。絶対にアリスター様にお願いしよう。サミーと離れるのは嫌だから。
それからどのくらい歩いただろうか。長くないとは思いつつ、変わらない景色に、私も飽き始めてしまった。
サミーが言うほど、仕掛けのようなものが発動されなかったからだ。だんだん、緊張感が薄れていく。
もしかしたら、ないのかもしれない。
そんな安易な想像も、徐々に薄まる原因の一つだった。しかしそれは私だけだったらしい。
再び振り向くサミーの表情は不安気だった。
「お嬢様。やはり一度、通路の外に出ますね。多分、ここで合っていると思うんですが、私も確信が持てないので」
「大丈夫よ。むしろずっと使っていなかったんだから」
本当に蝋燭の黄色い光は温かみがあっていい。安堵するサミーの表情が際立って、私まで嬉しくなった。
サミーは手燭を壁に近づけて、ゼラニウムの絵が彫られた石を押す。ゼラニウムの花言葉は確か、「真の友情」や「尊敬」があった。
その意味を持つ花ならば客室、または客間か応接間に繋がっている可能性が高い。
なるほど、と感心をしている暇もなく、開け放たれる扉。石を押したのと同時に開くのだから、こちらにも驚かされた。
「どういうカラクリをしているの?」
「さぁ。私もただ、こうすると開くことくらいにしか聞いていないので、何とも言えません」
「そうよね。逆にそこまで知っていたらビックリするわ」
いくら口伝でも限界はある。
私は気にせずに辺りを見渡した。
「ここは……廊下ね。しかも……」
壁に掛けられている燭台の光のお陰で、窓の外が見えた。我が家の庭師が丹精込めた庭園が。
「サミー、あれを見て。庭園がこの角度にあるってことは」
「はい。ここを真っ直ぐ行けば、客室です。なので、もうすぐですよ、お嬢様。どの部屋をお使いになられているのかは、把握しておりますので、そちらも問題ありません」
「わぁ、ありがとう、サミー!」
ようやく見えたゴールに、私たちは周りを気にする余裕もなくはしゃいだ。深夜ではないとはいえ、廊下に響き渡っているとも知らずに。