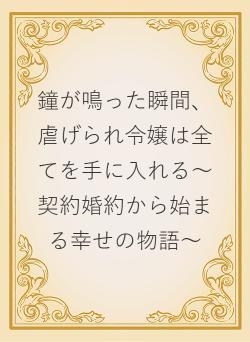ゴホゴホ。
「お父様。無理をなさらず横になってください」
咳き込むお父様の背中を摩り、休むよう促した。
私が無理に起こしてしまった手前、罪悪感が大きかった。
体調が悪いのに、責めるようなことを言ってしまった。ずっとベッドにいたのだから、無理は禁物だってことくらい、見て分かるじゃない。
やはり無理をしていたのか、お父様は布団の中に入ると、ふーっと息を吐いた。
「エリアス。マリアンヌを部屋に連れて行ってくれるかい」
「はい、旦那様」
真後ろから聞こえた声に、私は息を吞んだ。
いつの間に? ううん。部屋に入って来たのさえ、気がつかなかった。
肩を掴まれた瞬間、私はふり払い、掛け布団を握った。
「マリアンヌ。ここは旦那様の言うことを……」
「嫌っ! お願いです、お父様。邪魔はしないので、ここにいさせてください」
「旦那様はこれからお休みになられるんだ。我儘を言うのは……」
「分かっているわ。でも――……」
ずっと内緒にされてきたんだから、多少の我儘を聞いてくれてもいいじゃない!
声に出せなかった抗議を、目で訴えた。内緒にするよう命じたお父様の手前、心労をかけたくなかったからだ。
いや、そう思うのなら、部屋を出るべきなんだろうけど。気持ちが追いつかなかった。
まだここにいたい。お父様の傍に。
「頼むから、言うことを聞いてくれ」
再び掴まれる肩。今度はふり払えないように、強く掴まれた。
「嫌っ!」
私も掛け布団を掴む手に力が入る。けれど、エリアスの力に敵うはずもなく、私は引き離された。
「エリアス。お嬢様を放しなさい」
そこを助けてくれたのは、お父様ではない。この部屋に一緒に入ったポールだった。
エリアスの腕を掴み、私から引き離してくれた。
「俺は旦那様の指示に従っているんだ。邪魔をしないでくれ」
「もうすでに伯爵気取りか? いくら仕事を任されているからと言っても、使用人の立場であることを忘れるな!」
「ポール。助けてくれたのは有り難いけど、言い過ぎよ」
「いいえ、示しは必要です。勘違いしたままでは、お嬢様が困ることになるんですよ、いずれ」
ポールの言い分は最もだと思ったが、なぜだろう。同意するのが怖かった。
そうだ。これはリュカの時に似ている。でも、それよりも圧を感じる怖さだった。
「お嬢様にはもう一つ、知ってもらいたいことがあります」
「な、何を?」
「旦那様の容態についてです」
「っ! 教えて、ポール!」
一番肝心なことを忘れていた。どうしてお父様はベッドに伏せているの? その疑問に。
「一カ月前から伏せっていると言いましたが、その前から体調を崩されていました」
「仕事が忙しくて?」
「それもありますが、お医者様がいうには、毒に侵されているようなのです」
「毒!?」
聞いた途端、二年前に飲んだ毒を思い出し、私は胸を押さえた。
苦しくて、血を吐いた。あの経験を。
左手が自然と口元へ行く。
「以前、お嬢様が飲んだようなものではありません。徐々に衰えて、まるで病気を装うかのように蝕む毒なのです」
「……一体誰が? いえ、それよりも、今もお父様は毒に侵されているの?」
「分かりません。しかし、誰というのは判明しています」
確信に満ちた表情をするポール。
分かっているのなら、なぜ捕まえないの? なぜここで言うの? お父様がいるこの部屋で。
それでも聞かずにはいられなかった。
「誰がそんなことをしたの?」
「エリアスです」
「あ、あり得ないわ!」
思わず立ち上がってエリアスを見る。
「そうでしょう、エリアス」
「勿論、俺は旦那様に毒なんて盛っていない」
「ではなぜ、一カ月前から毎晩、邸宅の外に出ている。毒を持ち込んでいる証拠じゃないか」
「ちまちまと毎晩、毒を持ち込むわけがないだろう」
それはそうだ。毒は一液でも効果を発するものがある。小瓶一つで事足りる。毎晩、外出しているからといっても、それはおかしな考えだ。
むしろ、一カ月前から毎晩、ケヴィンのところに行っていた事実の方に、私は驚いた。
「しかし、帰ってくると必ず厨房へ行っているらしいじゃないか」
「帰ってくれば、腹が減るだろう。外でメシを食えるほど、懐が温かいわけじゃないんだ」
「昨日、ニナと旦那様について言っていたことはどうだ? お嬢様よりも旦那様を心配した方がいいと言っていたらしいな」
「旦那様が伏せっていたんだから、おかしな発言じゃないだろう」
「どうかな。毎日、急いでお嬢様の部屋に行くほどだ。制限をかけた旦那様を疎ましく思っていてもおかしくはないだろう。すでに、伯爵になる準備は出来ている。あとはお嬢様と婚約するだけ。旦那様がいなくなって得をするのは、エリアス。お前しかいない」
ポールの言い分からしたら、私も該当しそうだと思った。が、お父様によって除け者扱いされていた私が、犯人というのは無理がある。
でも、エリアスがそんなことをするはずがない。ないのよ!
「エリアス……」
「違う。俺は旦那様に毒なんて盛っていない」
「分かっているわ。エリアスはそんなことをしていないって」
けれど、何も準備をしていない、知らされていなかった私では力不足だった。
考えるのよ。エリアスが犯人ではないと言える材料を。
「お嬢様。エリアスを庇いたいのは分かりますが、状況は揃っています」
状況ですって! そうだ。
「揃ってなんかいないわ。エリアスが毒を持っている証拠が!」
「いいえ。先ほど、エリアスの部屋から見つかりました。これが証拠です」
ポールは懐から茶色い小瓶を取り出した。
「勝手に俺の部屋に入ったのか」
「抜き打ちのチェックは時々しているだろう。そこまで過敏に反応することは、やはり犯人だと言わざるを得ないな」
「でたらめなことを言いやがって」
「それはどうかな。詳しいことは治安隊が来てからにしようか」
それを合図に、使用人たちが部屋に入ってきて、エリアスを拘束した。私がそれを止める手段はなかった。
「お父様。無理をなさらず横になってください」
咳き込むお父様の背中を摩り、休むよう促した。
私が無理に起こしてしまった手前、罪悪感が大きかった。
体調が悪いのに、責めるようなことを言ってしまった。ずっとベッドにいたのだから、無理は禁物だってことくらい、見て分かるじゃない。
やはり無理をしていたのか、お父様は布団の中に入ると、ふーっと息を吐いた。
「エリアス。マリアンヌを部屋に連れて行ってくれるかい」
「はい、旦那様」
真後ろから聞こえた声に、私は息を吞んだ。
いつの間に? ううん。部屋に入って来たのさえ、気がつかなかった。
肩を掴まれた瞬間、私はふり払い、掛け布団を握った。
「マリアンヌ。ここは旦那様の言うことを……」
「嫌っ! お願いです、お父様。邪魔はしないので、ここにいさせてください」
「旦那様はこれからお休みになられるんだ。我儘を言うのは……」
「分かっているわ。でも――……」
ずっと内緒にされてきたんだから、多少の我儘を聞いてくれてもいいじゃない!
声に出せなかった抗議を、目で訴えた。内緒にするよう命じたお父様の手前、心労をかけたくなかったからだ。
いや、そう思うのなら、部屋を出るべきなんだろうけど。気持ちが追いつかなかった。
まだここにいたい。お父様の傍に。
「頼むから、言うことを聞いてくれ」
再び掴まれる肩。今度はふり払えないように、強く掴まれた。
「嫌っ!」
私も掛け布団を掴む手に力が入る。けれど、エリアスの力に敵うはずもなく、私は引き離された。
「エリアス。お嬢様を放しなさい」
そこを助けてくれたのは、お父様ではない。この部屋に一緒に入ったポールだった。
エリアスの腕を掴み、私から引き離してくれた。
「俺は旦那様の指示に従っているんだ。邪魔をしないでくれ」
「もうすでに伯爵気取りか? いくら仕事を任されているからと言っても、使用人の立場であることを忘れるな!」
「ポール。助けてくれたのは有り難いけど、言い過ぎよ」
「いいえ、示しは必要です。勘違いしたままでは、お嬢様が困ることになるんですよ、いずれ」
ポールの言い分は最もだと思ったが、なぜだろう。同意するのが怖かった。
そうだ。これはリュカの時に似ている。でも、それよりも圧を感じる怖さだった。
「お嬢様にはもう一つ、知ってもらいたいことがあります」
「な、何を?」
「旦那様の容態についてです」
「っ! 教えて、ポール!」
一番肝心なことを忘れていた。どうしてお父様はベッドに伏せているの? その疑問に。
「一カ月前から伏せっていると言いましたが、その前から体調を崩されていました」
「仕事が忙しくて?」
「それもありますが、お医者様がいうには、毒に侵されているようなのです」
「毒!?」
聞いた途端、二年前に飲んだ毒を思い出し、私は胸を押さえた。
苦しくて、血を吐いた。あの経験を。
左手が自然と口元へ行く。
「以前、お嬢様が飲んだようなものではありません。徐々に衰えて、まるで病気を装うかのように蝕む毒なのです」
「……一体誰が? いえ、それよりも、今もお父様は毒に侵されているの?」
「分かりません。しかし、誰というのは判明しています」
確信に満ちた表情をするポール。
分かっているのなら、なぜ捕まえないの? なぜここで言うの? お父様がいるこの部屋で。
それでも聞かずにはいられなかった。
「誰がそんなことをしたの?」
「エリアスです」
「あ、あり得ないわ!」
思わず立ち上がってエリアスを見る。
「そうでしょう、エリアス」
「勿論、俺は旦那様に毒なんて盛っていない」
「ではなぜ、一カ月前から毎晩、邸宅の外に出ている。毒を持ち込んでいる証拠じゃないか」
「ちまちまと毎晩、毒を持ち込むわけがないだろう」
それはそうだ。毒は一液でも効果を発するものがある。小瓶一つで事足りる。毎晩、外出しているからといっても、それはおかしな考えだ。
むしろ、一カ月前から毎晩、ケヴィンのところに行っていた事実の方に、私は驚いた。
「しかし、帰ってくると必ず厨房へ行っているらしいじゃないか」
「帰ってくれば、腹が減るだろう。外でメシを食えるほど、懐が温かいわけじゃないんだ」
「昨日、ニナと旦那様について言っていたことはどうだ? お嬢様よりも旦那様を心配した方がいいと言っていたらしいな」
「旦那様が伏せっていたんだから、おかしな発言じゃないだろう」
「どうかな。毎日、急いでお嬢様の部屋に行くほどだ。制限をかけた旦那様を疎ましく思っていてもおかしくはないだろう。すでに、伯爵になる準備は出来ている。あとはお嬢様と婚約するだけ。旦那様がいなくなって得をするのは、エリアス。お前しかいない」
ポールの言い分からしたら、私も該当しそうだと思った。が、お父様によって除け者扱いされていた私が、犯人というのは無理がある。
でも、エリアスがそんなことをするはずがない。ないのよ!
「エリアス……」
「違う。俺は旦那様に毒なんて盛っていない」
「分かっているわ。エリアスはそんなことをしていないって」
けれど、何も準備をしていない、知らされていなかった私では力不足だった。
考えるのよ。エリアスが犯人ではないと言える材料を。
「お嬢様。エリアスを庇いたいのは分かりますが、状況は揃っています」
状況ですって! そうだ。
「揃ってなんかいないわ。エリアスが毒を持っている証拠が!」
「いいえ。先ほど、エリアスの部屋から見つかりました。これが証拠です」
ポールは懐から茶色い小瓶を取り出した。
「勝手に俺の部屋に入ったのか」
「抜き打ちのチェックは時々しているだろう。そこまで過敏に反応することは、やはり犯人だと言わざるを得ないな」
「でたらめなことを言いやがって」
「それはどうかな。詳しいことは治安隊が来てからにしようか」
それを合図に、使用人たちが部屋に入ってきて、エリアスを拘束した。私がそれを止める手段はなかった。