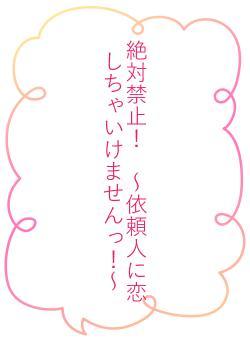「すげーいいニオイ」
ビニール袋の中に積み上げられたフライドチキンのパックのうちの一つを取り出すと、奏がさっそく鼻をひくつかせる。
「でも、そんなにもらってどうするの? 一人じゃさすがに食べきれないでしょ」
「残ったら、冷凍でもしとこっかなって。いつかの非常食用に」
「そっかあ。なんか奏、ちゃんと一人で生活してるんだね」
わたしがしみじみと言うと、
「ま、バンドの稼ぎなんて、ほとんどないに等しいからさ。このバイトに、だいぶ助けられてるよ」
そんなことを言いながらパックを開けると、さっそくひとつ目のチキンに手を伸ばす。
「お、まだあったかいぞ、これ」
奏が、目を輝かせながら、大きな骨付きチキンにかぶりつく。
「ほら、栞も冷めないうちに、早く食えって」
「うん。いただきます。……あ、これ、おいしい!」
「へへっ、だろ?」
奏がドヤ顔をする。
「そのへんのファストフード店のにだって負けてないよな」
「うん、負けてない、負けてない。じゃあ、こっちも食べよ。奏、昔よく言ってたよね。ワンホール全部一人で食べたいって」
「いやー、あの頃は若かったなー」
「ちょっと、おじいちゃんみたいなこと言わないでよっ! ……って、そうだ、フォークないじゃん」
「あー……チキンは素手でいけても、ケーキはさすがにキツいよな」
「だよねー。どうしよう」
「ま、家に帰ってから食えば?」
「こんなにあるのに!? 一人じゃ食べきれないよ」
仮に食べきれたとしても、しばらく怖くて体重計に乗れなくなっちゃうよ。
ビニール袋の中に積み上げられたフライドチキンのパックのうちの一つを取り出すと、奏がさっそく鼻をひくつかせる。
「でも、そんなにもらってどうするの? 一人じゃさすがに食べきれないでしょ」
「残ったら、冷凍でもしとこっかなって。いつかの非常食用に」
「そっかあ。なんか奏、ちゃんと一人で生活してるんだね」
わたしがしみじみと言うと、
「ま、バンドの稼ぎなんて、ほとんどないに等しいからさ。このバイトに、だいぶ助けられてるよ」
そんなことを言いながらパックを開けると、さっそくひとつ目のチキンに手を伸ばす。
「お、まだあったかいぞ、これ」
奏が、目を輝かせながら、大きな骨付きチキンにかぶりつく。
「ほら、栞も冷めないうちに、早く食えって」
「うん。いただきます。……あ、これ、おいしい!」
「へへっ、だろ?」
奏がドヤ顔をする。
「そのへんのファストフード店のにだって負けてないよな」
「うん、負けてない、負けてない。じゃあ、こっちも食べよ。奏、昔よく言ってたよね。ワンホール全部一人で食べたいって」
「いやー、あの頃は若かったなー」
「ちょっと、おじいちゃんみたいなこと言わないでよっ! ……って、そうだ、フォークないじゃん」
「あー……チキンは素手でいけても、ケーキはさすがにキツいよな」
「だよねー。どうしよう」
「ま、家に帰ってから食えば?」
「こんなにあるのに!? 一人じゃ食べきれないよ」
仮に食べきれたとしても、しばらく怖くて体重計に乗れなくなっちゃうよ。