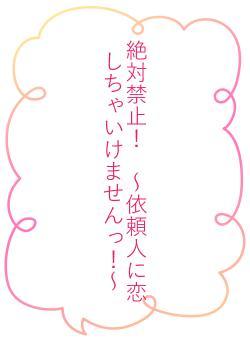わたしの声に、隣に立った男子が反射的にわたしを見下ろす。
「え、マジで栞!? は? ここで働いてたの? っていうか、いつから東京にいたんだよ。だっておまえ、地元の大学に受かったって言ってたよな!?」
……なんて言おう。
正直、気まずさしかない。
あれだけ「東京なんか行かない」って散々言っておきながら、結局こんなところでこんな形で再会しちゃうなんて。
「あー……うん。あっちは一年でやめて、東京の大学受け直した」
「マジかー。……そっか、そっか」
噛みしめるように、奏が何度もうなずいた。
奏は昔から優しいから。
直球は投げられないよね?
『やっぱり歌手の夢、諦めてなかったんだな』なんて。
わたしが一番触れてほしくないところだって、奏が多分一番知ってるから。
奏は、高校卒業と同時にギター一本背負って東京へ出た。
もちろん、なんのツテもコネもないままに。
その後、どこかのインディーズバンドのギタリストとして活動してるっていうウワサくらいは耳にしていたけど、それ以上のことはなにも知らなかった。
夏休みも、年末年始も、一度も家に帰ってこないって、奏のお母さんがしょっちゅうわたしの母にぼやいてたくらいだ。
「え、マジで栞!? は? ここで働いてたの? っていうか、いつから東京にいたんだよ。だっておまえ、地元の大学に受かったって言ってたよな!?」
……なんて言おう。
正直、気まずさしかない。
あれだけ「東京なんか行かない」って散々言っておきながら、結局こんなところでこんな形で再会しちゃうなんて。
「あー……うん。あっちは一年でやめて、東京の大学受け直した」
「マジかー。……そっか、そっか」
噛みしめるように、奏が何度もうなずいた。
奏は昔から優しいから。
直球は投げられないよね?
『やっぱり歌手の夢、諦めてなかったんだな』なんて。
わたしが一番触れてほしくないところだって、奏が多分一番知ってるから。
奏は、高校卒業と同時にギター一本背負って東京へ出た。
もちろん、なんのツテもコネもないままに。
その後、どこかのインディーズバンドのギタリストとして活動してるっていうウワサくらいは耳にしていたけど、それ以上のことはなにも知らなかった。
夏休みも、年末年始も、一度も家に帰ってこないって、奏のお母さんがしょっちゅうわたしの母にぼやいてたくらいだ。