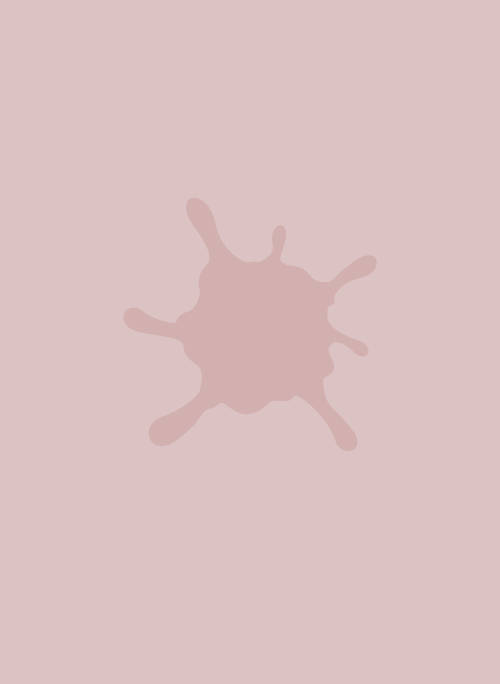死体を、単なる肉体の器と見立て。
その器に、本人の魂を宿すことによって、その人を蘇らせた訳だ。
二十音に邪神の魂を降ろして、二十音の肉体ごと邪神を滅ぼした…あの方法と似てるね。
成程、いかにも私が考えそうな方法だ。
しかも、それが成功してるんだから…さすがはイーニシュフェルトの「聖賢者様」と言ったところか。
本人の死体を用意するのは困難だけど、他人の死体なら比較的簡単に手に入るもんね。
家族にお金を払って買ったのか、研究に協力してくれている人に提供してもらったのか…。
とにかく、若くて新鮮で、出来るだけ損傷の少ない死体を用意し。
その中に、蘇らせたい人物の魂を宿らせる。
そうすることで私は、里の族長を生き返らせた。
正気の沙汰とは思えないが、私はこの世界で、見事その偉業を成し遂げたのだ。
…一体、何の為に?
偉業を成し遂げることで誰かに褒められたかったのか、それとも偉業を成し遂げた自分の自尊心を満足させる為か。
いずれにしても、この世界の私は本当の私ではない。それは確かだ。
本当の私が、このような「善人」であるはずがないのだから。
「族長様、聖賢者様がいらっしゃいました」
珠蓮君は、生き返った族長が住んでいる家の扉を開けた。
その家は、かつて族長が住んでいた家と全く同じ外装だった。
そして、中にいる人物も。
「おぉ…。シルナ・エインリー、来たのか」
家の中には、大きなベッドが置かれ。
そこに、見知らぬ若い男性が横たわっていた。
知らない顔をしているのは当然だ。…全く関係のない、他人の死体を使っているのだから。
だけど、肉体の器などどうでも良い。
肝心なのは、中身だ。
全く知らない人の顔をしているけど、その中身は私のよく知る人物のもの。
イーニシュフェルトの里の族長…そして、ヴァルシーナちゃんの実の祖父。
名を、ヴァストラーナ・クルスという。
感動の再会…と言ったところか。
もう二度と…会うことはないし、合わせる顔もないと思ってたんだけどね。
まさか、幻覚の世界で再会する羽目になるとは。
…いや、これは現実じゃないのだから、正確には再会したとは言えないのだろうか?
その器に、本人の魂を宿すことによって、その人を蘇らせた訳だ。
二十音に邪神の魂を降ろして、二十音の肉体ごと邪神を滅ぼした…あの方法と似てるね。
成程、いかにも私が考えそうな方法だ。
しかも、それが成功してるんだから…さすがはイーニシュフェルトの「聖賢者様」と言ったところか。
本人の死体を用意するのは困難だけど、他人の死体なら比較的簡単に手に入るもんね。
家族にお金を払って買ったのか、研究に協力してくれている人に提供してもらったのか…。
とにかく、若くて新鮮で、出来るだけ損傷の少ない死体を用意し。
その中に、蘇らせたい人物の魂を宿らせる。
そうすることで私は、里の族長を生き返らせた。
正気の沙汰とは思えないが、私はこの世界で、見事その偉業を成し遂げたのだ。
…一体、何の為に?
偉業を成し遂げることで誰かに褒められたかったのか、それとも偉業を成し遂げた自分の自尊心を満足させる為か。
いずれにしても、この世界の私は本当の私ではない。それは確かだ。
本当の私が、このような「善人」であるはずがないのだから。
「族長様、聖賢者様がいらっしゃいました」
珠蓮君は、生き返った族長が住んでいる家の扉を開けた。
その家は、かつて族長が住んでいた家と全く同じ外装だった。
そして、中にいる人物も。
「おぉ…。シルナ・エインリー、来たのか」
家の中には、大きなベッドが置かれ。
そこに、見知らぬ若い男性が横たわっていた。
知らない顔をしているのは当然だ。…全く関係のない、他人の死体を使っているのだから。
だけど、肉体の器などどうでも良い。
肝心なのは、中身だ。
全く知らない人の顔をしているけど、その中身は私のよく知る人物のもの。
イーニシュフェルトの里の族長…そして、ヴァルシーナちゃんの実の祖父。
名を、ヴァストラーナ・クルスという。
感動の再会…と言ったところか。
もう二度と…会うことはないし、合わせる顔もないと思ってたんだけどね。
まさか、幻覚の世界で再会する羽目になるとは。
…いや、これは現実じゃないのだから、正確には再会したとは言えないのだろうか?
私の内心の葛藤をよそに、ヴァストラーナ族長は嬉しそうに、私の訪問を歓迎した。
「よく来たな、シルナ・エインリー…。いや、今はイーニシュフェルトの聖賢者と呼んだ方が良いか」
「…」
「あの小さかった若造が、よくもまぁこれほど立派になったものよ。…そうなるだろうとは思っていたがな。昔から、お前には天性の才覚があった。この世の救世主となり得る器がな」
…死体とは思えないくらい、饒舌に喋るんだね。
しかも、私のことをべた褒め。
あの族長が、だよ。
私のやることなすこと、一度として認めてくれなかったような人が。
あの族長が私を褒めるなんて、とても信じられなくて。
見た目だけじゃなくて、やっぱり中身も別人なんじゃないかと疑うほどだ。
だけど…昔の私を知ってるってことは、この族長には過去の記憶があるのだ。
じゃあやっぱりこの人は、ヴァストラーナ族長のそっくりさん…とかではなく。
本物の、ヴァストラーナ族長の魂を宿しているのだ。
魔導科学では、その人の本質は肉体ではなく、魂だと考えられている。
いくら肉体が別人のものだろうと、中身がその人のものなら、それはその人本人だと考える。
実際ヴァルシーナちゃんも、この人を「お祖父様」と呼んでいた訳だし。
珠蓮君も他の皆も、この人を族長だと思っている。
だけど、私はどうしても…この人がヴァストラーナ族長だとは思えなかった。
ただの死体だ。
死体が喋ってるに過ぎない。
「見事邪神を討ち滅ぼし、我ら一族の悲願を果たしたそうだな」
その死体が、なおも私に話しかけ続けた。
あぁ。
そうらしいね。この世界では。
「全て、ヴァルシーナから聞いた。邪神を滅ぼした後、国を造って魔導師を養成する学院を開き、この里を再建したと」
「…はい」
そうみたいだね。
私は全く記憶がないけど。
「よくぞ使命をやり遂げた。ここに至るまで、数多くの労苦があっただろう」
「…」
「だが、お前はやり遂げたのだ。己の使命を果たし、イーニシュフェルトの聖賢者の二つ名に恥じない働きをした。シルナ・エインリー。お前は我ら一族の誇りだ」
…誇り、誇りだって。
…それは皮肉か。
カンニングで百点満点を取ったテストを、褒められているようなもどかしさ。
決して私の功績じゃないのに、何故私が褒められているのか。
私は決して、族長の思っているような人間ではない。
「よく来たな、シルナ・エインリー…。いや、今はイーニシュフェルトの聖賢者と呼んだ方が良いか」
「…」
「あの小さかった若造が、よくもまぁこれほど立派になったものよ。…そうなるだろうとは思っていたがな。昔から、お前には天性の才覚があった。この世の救世主となり得る器がな」
…死体とは思えないくらい、饒舌に喋るんだね。
しかも、私のことをべた褒め。
あの族長が、だよ。
私のやることなすこと、一度として認めてくれなかったような人が。
あの族長が私を褒めるなんて、とても信じられなくて。
見た目だけじゃなくて、やっぱり中身も別人なんじゃないかと疑うほどだ。
だけど…昔の私を知ってるってことは、この族長には過去の記憶があるのだ。
じゃあやっぱりこの人は、ヴァストラーナ族長のそっくりさん…とかではなく。
本物の、ヴァストラーナ族長の魂を宿しているのだ。
魔導科学では、その人の本質は肉体ではなく、魂だと考えられている。
いくら肉体が別人のものだろうと、中身がその人のものなら、それはその人本人だと考える。
実際ヴァルシーナちゃんも、この人を「お祖父様」と呼んでいた訳だし。
珠蓮君も他の皆も、この人を族長だと思っている。
だけど、私はどうしても…この人がヴァストラーナ族長だとは思えなかった。
ただの死体だ。
死体が喋ってるに過ぎない。
「見事邪神を討ち滅ぼし、我ら一族の悲願を果たしたそうだな」
その死体が、なおも私に話しかけ続けた。
あぁ。
そうらしいね。この世界では。
「全て、ヴァルシーナから聞いた。邪神を滅ぼした後、国を造って魔導師を養成する学院を開き、この里を再建したと」
「…はい」
そうみたいだね。
私は全く記憶がないけど。
「よくぞ使命をやり遂げた。ここに至るまで、数多くの労苦があっただろう」
「…」
「だが、お前はやり遂げたのだ。己の使命を果たし、イーニシュフェルトの聖賢者の二つ名に恥じない働きをした。シルナ・エインリー。お前は我ら一族の誇りだ」
…誇り、誇りだって。
…それは皮肉か。
カンニングで百点満点を取ったテストを、褒められているようなもどかしさ。
決して私の功績じゃないのに、何故私が褒められているのか。
私は決して、族長の思っているような人間ではない。
あの族長が、私に対してべた褒めとは。
本当にあのヴァストラーナ族長なのかと、疑いたくなる。
実際、この人はヴァストラーナ族長ではない。
だってここは幻の世界であって、本物の族長は、今もイーニシュフェルト魔導学院の土の下に眠っているのだ。
思い出してみると良い。
ルディシア君が土の下から掘り起こした、本物の族長の死体と相対したとき。
あのとき、鋭い眼光で私を睨んでいた…族長の憎しみに燃える目を。
あれが、あれこそが本物だ。
今目の前にいる族長は、ハクロとコクロが私に見せている幻。
…そんなことは分かっている。
分かってるけど…考えずにはいられない。
私は、こんな風に褒めてもらえることを、心の何処かで期待していたのだろうか。
よくやった、よくぞ使命を果たしたと。
そう言ってもらって、皆に聖賢者だと持て囃されて、褒められて期待されて。
あなたは素晴らしい人だと、そう認めて欲しかったのだろうか。
その欲望が、この世界を作り出しているのだろうか。
二十音をこの手で殺した代償が、これなのか。
…満たされない。
これじゃ満たされないよ。私は。
「それから…これもヴァルシーナから聞いたのだが」
「…はい?」
「お前は、再建されたこのイーニシュフェルトの里を、外の世界に開かれた場所にしたいと考えているそうだな」
…そうなの?
でも…確かに、私ならそう思ってもおかしくないかもしれない。
私は昔、元のイーニシュフェルトの里にいた頃から。
閉じられた里の世界を、もっと外に広げようと考えていた。
里の人間は決して、外の世界と交流してはならない。
長老達が考える、このような古めかしい価値観を変えようとしていた。
里にいた頃は、私がいくら意見を述べても、若造の言うことだと聞き入れてもらえなかった。
しかし、今は。
私のような若造の意見に反対する長老達は、族長を除いて一人もいない。
そして、墓から蘇った族長自身でさえも。
「ヴァルシーナや、ここにいる珠蓮を通じて、外の世界と交流すると良い。若者の方が受け入れられやすいだろう」
里が外の世界と交流するなんて許さない、ではなかった。
「もう少し里の再建が進んだら、外の人間を招き、外との交流を深めよう。少しずつな」
私は、思わず耳を疑った。
あの族長が、外の世界と交流することに対して、これほど前向きな発言をするなんて。
「…どうしてですか?」
幻と会話をしても仕方ないと分かっているのに、私はそう聞き返していた。
「里が外と交流することを…あれほど反対されていたのに…」
「…そうだな。以前は、お前の意見には耳を貸さなかった。今でも我は、個人的には外の世界と関わりを持つのは反対だ」
やっぱり。
でも、族長は反対しているのに…何故私の意見を優先させようとするのだろう?
本当にあのヴァストラーナ族長なのかと、疑いたくなる。
実際、この人はヴァストラーナ族長ではない。
だってここは幻の世界であって、本物の族長は、今もイーニシュフェルト魔導学院の土の下に眠っているのだ。
思い出してみると良い。
ルディシア君が土の下から掘り起こした、本物の族長の死体と相対したとき。
あのとき、鋭い眼光で私を睨んでいた…族長の憎しみに燃える目を。
あれが、あれこそが本物だ。
今目の前にいる族長は、ハクロとコクロが私に見せている幻。
…そんなことは分かっている。
分かってるけど…考えずにはいられない。
私は、こんな風に褒めてもらえることを、心の何処かで期待していたのだろうか。
よくやった、よくぞ使命を果たしたと。
そう言ってもらって、皆に聖賢者だと持て囃されて、褒められて期待されて。
あなたは素晴らしい人だと、そう認めて欲しかったのだろうか。
その欲望が、この世界を作り出しているのだろうか。
二十音をこの手で殺した代償が、これなのか。
…満たされない。
これじゃ満たされないよ。私は。
「それから…これもヴァルシーナから聞いたのだが」
「…はい?」
「お前は、再建されたこのイーニシュフェルトの里を、外の世界に開かれた場所にしたいと考えているそうだな」
…そうなの?
でも…確かに、私ならそう思ってもおかしくないかもしれない。
私は昔、元のイーニシュフェルトの里にいた頃から。
閉じられた里の世界を、もっと外に広げようと考えていた。
里の人間は決して、外の世界と交流してはならない。
長老達が考える、このような古めかしい価値観を変えようとしていた。
里にいた頃は、私がいくら意見を述べても、若造の言うことだと聞き入れてもらえなかった。
しかし、今は。
私のような若造の意見に反対する長老達は、族長を除いて一人もいない。
そして、墓から蘇った族長自身でさえも。
「ヴァルシーナや、ここにいる珠蓮を通じて、外の世界と交流すると良い。若者の方が受け入れられやすいだろう」
里が外の世界と交流するなんて許さない、ではなかった。
「もう少し里の再建が進んだら、外の人間を招き、外との交流を深めよう。少しずつな」
私は、思わず耳を疑った。
あの族長が、外の世界と交流することに対して、これほど前向きな発言をするなんて。
「…どうしてですか?」
幻と会話をしても仕方ないと分かっているのに、私はそう聞き返していた。
「里が外と交流することを…あれほど反対されていたのに…」
「…そうだな。以前は、お前の意見には耳を貸さなかった。今でも我は、個人的には外の世界と関わりを持つのは反対だ」
やっぱり。
でも、族長は反対しているのに…何故私の意見を優先させようとするのだろう?
「だが、この新たなイーニシュフェルトの里は、お前が再建させたものだ。そして我は、一度は死んだ身。墓の下から蘇ったに過ぎん」
…自分がゾンビだっていう自覚はあるんだ。一応。
おまけに、私に蘇らせてもらったという負い目と言うか…恩くらいは感じているらしい。
殊勝なことだ。
「里のこれからの方針は、お前やヴァルシーナや…若者が決めるべきだ。この老人の役目は、お前達若者が困ったときに横から口を挟むことくらいよ」
「…」
「何より、立派に役目を果たしたお前だ。この里の未来を託すに相応しい。思うように、存分に腕を振るうが良い。きっとお前なら、世界を救ったように、このイーニシュフェルトの里をも、大きく発展させることが出来よう」
…族長からの、全幅の信頼。
初めて見る、族長の微笑み。
こんなものが…私の欲しかったものなのか。
二十音をこの手で殺してまで、手に入れたかったものなのか?
これで、二十音を失った私の欠落を埋めようと?
…そんな馬鹿な話があるものか。
「…分かりました。期待に添えるよう精進致します」
私は機械的に口を動かして、思ってもいないことを族長に伝えた。
…そして。
「ですが…一つ、お尋ねしたいことがあります」
「何だ?」
「もしも…もしも、ですよ。私が役目を果たせず、邪神を討ち滅ぼすことも、あなたを蘇らせることもせず、あまつさえ…邪神を守る為に正義から背を向けていたとしたら」
元の世界の私がしたことを、今のあなたが知ったら。
その時、果たして。
「あなたは…私に何と言っていたでしょう?」
「何を世迷い言を。お前としたことが…。さては、自信をなくしたか?」
「…どうかお答えください」
「そんなものは決まっている」
と、ヴァストラーナ族長は鼻を鳴らし、吐き捨てるようにこう言った。
「己の役目を果たせぬ人間に、生きる価値などない」
…予想して通りの言葉ではあった。
図らずもそれは、アーリヤット皇王の口癖と同じだった。
その言葉が、私の心に突き刺さった。
…自分がゾンビだっていう自覚はあるんだ。一応。
おまけに、私に蘇らせてもらったという負い目と言うか…恩くらいは感じているらしい。
殊勝なことだ。
「里のこれからの方針は、お前やヴァルシーナや…若者が決めるべきだ。この老人の役目は、お前達若者が困ったときに横から口を挟むことくらいよ」
「…」
「何より、立派に役目を果たしたお前だ。この里の未来を託すに相応しい。思うように、存分に腕を振るうが良い。きっとお前なら、世界を救ったように、このイーニシュフェルトの里をも、大きく発展させることが出来よう」
…族長からの、全幅の信頼。
初めて見る、族長の微笑み。
こんなものが…私の欲しかったものなのか。
二十音をこの手で殺してまで、手に入れたかったものなのか?
これで、二十音を失った私の欠落を埋めようと?
…そんな馬鹿な話があるものか。
「…分かりました。期待に添えるよう精進致します」
私は機械的に口を動かして、思ってもいないことを族長に伝えた。
…そして。
「ですが…一つ、お尋ねしたいことがあります」
「何だ?」
「もしも…もしも、ですよ。私が役目を果たせず、邪神を討ち滅ぼすことも、あなたを蘇らせることもせず、あまつさえ…邪神を守る為に正義から背を向けていたとしたら」
元の世界の私がしたことを、今のあなたが知ったら。
その時、果たして。
「あなたは…私に何と言っていたでしょう?」
「何を世迷い言を。お前としたことが…。さては、自信をなくしたか?」
「…どうかお答えください」
「そんなものは決まっている」
と、ヴァストラーナ族長は鼻を鳴らし、吐き捨てるようにこう言った。
「己の役目を果たせぬ人間に、生きる価値などない」
…予想して通りの言葉ではあった。
図らずもそれは、アーリヤット皇王の口癖と同じだった。
その言葉が、私の心に突き刺さった。
族長の家を後にしてから。
私は珠蓮君に頼んで、再建されたイーニシュフェルトの里を案内してもらった。
細部に細かな違いがあれど、里の景色は、私の記憶にあるものと同じだった。
やっぱり、わざと里の風景を再現しているのだろう。
懐かしさは、やっぱりなくて。
それよりも、先程族長から言われた言葉が、頭の中をぐるぐると回っていた。
生きている価値などない…か。
そんなの分かっている。自分が一番良く分かっている。
だけど、私は他に…どうすれば良かったというのだ?
己の孤独や苦しみを無視して、己の役目を忠実に果たすべきだったと?
二十音を邪神ごと、この手で殺せば良かったと?
私の孤独を埋めてくれた、唯一の存在を?
そして、その結果手に入れたものは何だ?
二十音は既に、この世界には存在していない。私が殺したから。
その代わり、私は世界を救った英雄として誰からも褒め称えられ。
聖賢者様と呼ばれ、救世主として扱われ。
ヴァルシーナちゃんに慕われ、ヴァストラーナ族長の誇りになった。
これが、私の求めていたもの?
これが、二十音の代わりに手に入れたもの?
なんと空虚で薄っぺらで、虚しいものだろう。
名声も名誉も要らない。私の隣にはただ、あの子が居れば良い。
他には何も要らない…。
この世界に二十音がいないのに、それこそ私が生きている理由なんて…。
そんなことをぼんやりと考えながら、私は珠蓮君に付き添われて歩いていた。
「あの…聖賢者様。大丈夫ですか?」
珠蓮君が、心配そうな顔で尋ねた。
「…え?」
「いえ、その…。先程からずっと、暗い顔をされているので…。族長様と何かありましたか?」
「…」
私があまりに浮かない顔をしているから、気になったらしい。
…だろうね。
酷い顔してると思うよ。今は…。
「お疲れですか?良かったら、今日は王都には帰らず、里にお泊りになって…。明日になってからお戻りになっては?」
「別に…何でもないよ。ちょっと気分が、」
「…?聖賢者様、どうされました?」
…その人物を見て、私は思わず足を止めてしまった。
自分の見たものが信じられなかった。
私の目の前を、ぬいぐるみを抱いた小さな子供が駆けていった。
その顔は、私の記憶にあるものと同じ。
「…二十音…!?」
あの日、座敷牢に閉じ込められていた二十音と全く同じ顔の子供が、私の目の前を走っていったのだ。
私は珠蓮君に頼んで、再建されたイーニシュフェルトの里を案内してもらった。
細部に細かな違いがあれど、里の景色は、私の記憶にあるものと同じだった。
やっぱり、わざと里の風景を再現しているのだろう。
懐かしさは、やっぱりなくて。
それよりも、先程族長から言われた言葉が、頭の中をぐるぐると回っていた。
生きている価値などない…か。
そんなの分かっている。自分が一番良く分かっている。
だけど、私は他に…どうすれば良かったというのだ?
己の孤独や苦しみを無視して、己の役目を忠実に果たすべきだったと?
二十音を邪神ごと、この手で殺せば良かったと?
私の孤独を埋めてくれた、唯一の存在を?
そして、その結果手に入れたものは何だ?
二十音は既に、この世界には存在していない。私が殺したから。
その代わり、私は世界を救った英雄として誰からも褒め称えられ。
聖賢者様と呼ばれ、救世主として扱われ。
ヴァルシーナちゃんに慕われ、ヴァストラーナ族長の誇りになった。
これが、私の求めていたもの?
これが、二十音の代わりに手に入れたもの?
なんと空虚で薄っぺらで、虚しいものだろう。
名声も名誉も要らない。私の隣にはただ、あの子が居れば良い。
他には何も要らない…。
この世界に二十音がいないのに、それこそ私が生きている理由なんて…。
そんなことをぼんやりと考えながら、私は珠蓮君に付き添われて歩いていた。
「あの…聖賢者様。大丈夫ですか?」
珠蓮君が、心配そうな顔で尋ねた。
「…え?」
「いえ、その…。先程からずっと、暗い顔をされているので…。族長様と何かありましたか?」
「…」
私があまりに浮かない顔をしているから、気になったらしい。
…だろうね。
酷い顔してると思うよ。今は…。
「お疲れですか?良かったら、今日は王都には帰らず、里にお泊りになって…。明日になってからお戻りになっては?」
「別に…何でもないよ。ちょっと気分が、」
「…?聖賢者様、どうされました?」
…その人物を見て、私は思わず足を止めてしまった。
自分の見たものが信じられなかった。
私の目の前を、ぬいぐるみを抱いた小さな子供が駆けていった。
その顔は、私の記憶にあるものと同じ。
「…二十音…!?」
あの日、座敷牢に閉じ込められていた二十音と全く同じ顔の子供が、私の目の前を走っていったのだ。
あまりにびっくりして、私は固まってしまったが。
小さな二十音は、私には全く目もくれず。
幼い子供らしく、無邪気な顔で駆けていった。
「あぁほら、そんなに走っちゃ駄目よ」
その二十音の後ろから、母親らしき女性が追いかけてきた。
追いかけてきたその母親にも、見覚えがあった。
二十音を座敷牢に閉じ込め、この化け物を引き取ってくれと私に頼んだ…。
あのときの、二十音の母親と同じ顔。
その母親が、無邪気にはしゃぐ二十音を抱き留めた。
「ご迷惑になってるじゃない。…ごめんなさい」
二十音を抱き上げて、母親はこちらに会釈した。
どうやら、私が聖賢者であることには気づいていないようだ。
二十音は無邪気な笑顔で、母親にしがみつき。
母親もまた、柔らかな笑顔を小さな二十音に向けた。
「さぁ、おうちに帰りましょうね」
そう言って、母親は二十音を抱いたまま歩き出した。
私は身動きもせず、ただ雷に打たれたように固まっていた。
…二十音。
あれは、確かに二十音だった。
この私が見間違うはずがない。
二十音が…何で、このイーニシュフェルトの里に。
しかも子供の姿で、母親と一緒に…外に出て。
「…聖賢者様?どうされました?」
珠蓮君が尋ねた。
私は、震える声で珠蓮君に聞き返した。
「い、今の…親子は?」
「?里が再建されたとき、新たに里の住民として移住した親子ですが…。…聖賢者様が移住の許可を出されたんですよね?」
…知らないよ、そんなこと。
何で二十音が…母親と一緒に…。
いや、何であの子が生きてるんだ?
しかも、あんな幼い子供の姿で…。
この世界の二十音は、私が邪神と一緒に殺したんじゃ…。
「確かあの親子は、魔導適性を持たないんですよね。魔導適性がない者でも、イーニシュフェルトの里に住む権利がある…。新たな里の在り方を示すモデルケースとして、あのように魔導適性のない家族を積極的に受け入れたと、そう聞いています」
と、珠蓮君が教えてくれた。
魔導適性がない…二十音。
私が近くにいたのに、私には目もくれなかった。
私を知らない、私の知らない二十音。
そのとき、私の中に一つの可能性が思い浮かんだ。
…転生。
そう、転生だ。
そういうこと。…そういうことなんだ。
あの子は二十音じゃない。死んだ二十音の…生まれ変わり。
愛されずに生まれ、望まれずに生かされていた二十音は。
邪神をその身に宿され、私に滅ぼされて死んだ後。
ようやく、自分を愛してくれる両親のもとに生まれ変わった…。
…そういう、ことだったんだ。
小さな二十音は、私には全く目もくれず。
幼い子供らしく、無邪気な顔で駆けていった。
「あぁほら、そんなに走っちゃ駄目よ」
その二十音の後ろから、母親らしき女性が追いかけてきた。
追いかけてきたその母親にも、見覚えがあった。
二十音を座敷牢に閉じ込め、この化け物を引き取ってくれと私に頼んだ…。
あのときの、二十音の母親と同じ顔。
その母親が、無邪気にはしゃぐ二十音を抱き留めた。
「ご迷惑になってるじゃない。…ごめんなさい」
二十音を抱き上げて、母親はこちらに会釈した。
どうやら、私が聖賢者であることには気づいていないようだ。
二十音は無邪気な笑顔で、母親にしがみつき。
母親もまた、柔らかな笑顔を小さな二十音に向けた。
「さぁ、おうちに帰りましょうね」
そう言って、母親は二十音を抱いたまま歩き出した。
私は身動きもせず、ただ雷に打たれたように固まっていた。
…二十音。
あれは、確かに二十音だった。
この私が見間違うはずがない。
二十音が…何で、このイーニシュフェルトの里に。
しかも子供の姿で、母親と一緒に…外に出て。
「…聖賢者様?どうされました?」
珠蓮君が尋ねた。
私は、震える声で珠蓮君に聞き返した。
「い、今の…親子は?」
「?里が再建されたとき、新たに里の住民として移住した親子ですが…。…聖賢者様が移住の許可を出されたんですよね?」
…知らないよ、そんなこと。
何で二十音が…母親と一緒に…。
いや、何であの子が生きてるんだ?
しかも、あんな幼い子供の姿で…。
この世界の二十音は、私が邪神と一緒に殺したんじゃ…。
「確かあの親子は、魔導適性を持たないんですよね。魔導適性がない者でも、イーニシュフェルトの里に住む権利がある…。新たな里の在り方を示すモデルケースとして、あのように魔導適性のない家族を積極的に受け入れたと、そう聞いています」
と、珠蓮君が教えてくれた。
魔導適性がない…二十音。
私が近くにいたのに、私には目もくれなかった。
私を知らない、私の知らない二十音。
そのとき、私の中に一つの可能性が思い浮かんだ。
…転生。
そう、転生だ。
そういうこと。…そういうことなんだ。
あの子は二十音じゃない。死んだ二十音の…生まれ変わり。
愛されずに生まれ、望まれずに生かされていた二十音は。
邪神をその身に宿され、私に滅ぼされて死んだ後。
ようやく、自分を愛してくれる両親のもとに生まれ変わった…。
…そういう、ことだったんだ。
確証がある訳じゃない。
これはあくまで、私の仮説に過ぎない。
単なる他人の空似である可能性も、充分にある。
大体、ここはハクロとコクロが見せている、幻の世界なのだ。
幻なんだから、何でもアリだろう。
でも…何でもアリってことは、あの子が本当に私の推察した通り、二十音の生まれ変わりである可能性もあるってことだ。
…そう、そうだったんだね。
「…あはは…」
私は両手で顔を押さえ、タガが外れたように笑い出した。
だって、笑わずにいられる?こんなの。
「せ、聖賢者様…!?突然どうされたんですか?」
驚いた珠蓮君が、慌てて私に駆け寄ってきたけど。
そんなことは、私にはどうでも良かった。
笑えるよ。喜劇だよね、こんなの。
母親に抱かれて、無邪気に笑っていた二十音の顔を見た?
私のことなんて、まるで眼中になかった。
当たり前だ。さっき見た転生した二十音は、母親に愛されて育てられているのだから。
私に殺された二十音は、生まれ変わって、幸せな子供として、魔導適性も持たず。
特別な力なんて何も持たず、ただの平凡な子供として。
座敷牢に閉じ込められることも、家族に死を望まれることもなく。
今度こそ、幸せな子供として生きているのだ。
…私が、いなくても。
あの子はちゃんと、幸せになれたんだ。
それなのに私は、元の世界で二十音を…自分の隣に縛り付けている。
死ねば開放されるだろうに。生まれ変わって、あんなに幸せに暮らすことが出来たのに。
その可能性を、私がこの手で全部潰した。
何の為に?
私の為だ。
私の自分勝手な独りよがり。ただ私が一人になりたくないから。
それだけの理由で。
二十音に依存し、二十音に依存させ、神の器としての役目を押し付け。
私の罪に付き合わせ、私の身勝手の為にあの子を縛り付け…。
…私がちゃんと正しい道を選べていたら、二十音はこうして、幸せに生きられただろうに。
その可能性を、私は自分の身勝手のせいで潰してしまったのだ。
…これをどうして、笑わずにいられるだろう?
これはあくまで、私の仮説に過ぎない。
単なる他人の空似である可能性も、充分にある。
大体、ここはハクロとコクロが見せている、幻の世界なのだ。
幻なんだから、何でもアリだろう。
でも…何でもアリってことは、あの子が本当に私の推察した通り、二十音の生まれ変わりである可能性もあるってことだ。
…そう、そうだったんだね。
「…あはは…」
私は両手で顔を押さえ、タガが外れたように笑い出した。
だって、笑わずにいられる?こんなの。
「せ、聖賢者様…!?突然どうされたんですか?」
驚いた珠蓮君が、慌てて私に駆け寄ってきたけど。
そんなことは、私にはどうでも良かった。
笑えるよ。喜劇だよね、こんなの。
母親に抱かれて、無邪気に笑っていた二十音の顔を見た?
私のことなんて、まるで眼中になかった。
当たり前だ。さっき見た転生した二十音は、母親に愛されて育てられているのだから。
私に殺された二十音は、生まれ変わって、幸せな子供として、魔導適性も持たず。
特別な力なんて何も持たず、ただの平凡な子供として。
座敷牢に閉じ込められることも、家族に死を望まれることもなく。
今度こそ、幸せな子供として生きているのだ。
…私が、いなくても。
あの子はちゃんと、幸せになれたんだ。
それなのに私は、元の世界で二十音を…自分の隣に縛り付けている。
死ねば開放されるだろうに。生まれ変わって、あんなに幸せに暮らすことが出来たのに。
その可能性を、私がこの手で全部潰した。
何の為に?
私の為だ。
私の自分勝手な独りよがり。ただ私が一人になりたくないから。
それだけの理由で。
二十音に依存し、二十音に依存させ、神の器としての役目を押し付け。
私の罪に付き合わせ、私の身勝手の為にあの子を縛り付け…。
…私がちゃんと正しい道を選べていたら、二十音はこうして、幸せに生きられただろうに。
その可能性を、私は自分の身勝手のせいで潰してしまったのだ。
…これをどうして、笑わずにいられるだろう?
…ねぇ、二十音。私はどうしたら良い?
こんな幻の世界、何の価値もないと思っていたのに。
生まれ変わった、小さな君の姿を見て…私の心は酷く揺れ動いた。
ここは確かに、私にとっては虚しい世界だ。
でも、正しい世界だ。
誰にとっても、正しい世界。
本来元の世界も、こうであるべきだった。
私は己の役目を果たし、二十音は死ぬ。
でも生まれ変わって、私を知らない二十音になって、今度こそ愛してくれる母親のもとで、幸せに暮らしている。
二十音だけじゃない。
私が役目を果たしたお陰で、救われた人が大勢いる。
イレースちゃんも天音君もナジュ君も、令月君もすぐり君もマシュリ君も。
あのヴァルシーナちゃんでさえ、私の右腕として、私を慕い、支えてくれている。
そして、ヴァストラーナ族長も…。
皆私が正しい選択をしたことに喜び、そのお陰で救われている。
私が…自分の苦しみを押し殺して、ちゃんと正しい選択をしていれば。
きっと元の世界も、こんな風に誰もが幸せな世界だっただろうに。
今からでも遅くないって、そう言っているのだろうか。
今からでも遅くないから、お前は罪の十字架を背負って、この正しい世界で生きていけと。
例え幻でも、この正しい世界で。
私が犯した罪の、責任を取れと。
「…二十音」
こんなにも私は、君を一番大切に思っているのに。
世界にとって一番大切なことは、私の大切なこととは違うんだ。
ねぇ。二十音…私、どうしたら良いと思う?
こんな幻の世界、何の価値もないと思っていたのに。
生まれ変わった、小さな君の姿を見て…私の心は酷く揺れ動いた。
ここは確かに、私にとっては虚しい世界だ。
でも、正しい世界だ。
誰にとっても、正しい世界。
本来元の世界も、こうであるべきだった。
私は己の役目を果たし、二十音は死ぬ。
でも生まれ変わって、私を知らない二十音になって、今度こそ愛してくれる母親のもとで、幸せに暮らしている。
二十音だけじゃない。
私が役目を果たしたお陰で、救われた人が大勢いる。
イレースちゃんも天音君もナジュ君も、令月君もすぐり君もマシュリ君も。
あのヴァルシーナちゃんでさえ、私の右腕として、私を慕い、支えてくれている。
そして、ヴァストラーナ族長も…。
皆私が正しい選択をしたことに喜び、そのお陰で救われている。
私が…自分の苦しみを押し殺して、ちゃんと正しい選択をしていれば。
きっと元の世界も、こんな風に誰もが幸せな世界だっただろうに。
今からでも遅くないって、そう言っているのだろうか。
今からでも遅くないから、お前は罪の十字架を背負って、この正しい世界で生きていけと。
例え幻でも、この正しい世界で。
私が犯した罪の、責任を取れと。
「…二十音」
こんなにも私は、君を一番大切に思っているのに。
世界にとって一番大切なことは、私の大切なこととは違うんだ。
ねぇ。二十音…私、どうしたら良いと思う?
――――――…ハクロとコクロが見せる、幻の世界にやって来て。
…シルナの存在しない、偽りの世界にやって来て、およそ一週間が経過した。
とはいえ、それはこちらの世界の時間であり。
元の世界で、どれくらい時間が経過しているのかは分からない。
もしかしたら、1分とか、一時間くらいしか経ってないのかもしれないし。
あるいは…一ヶ月、一年くらい経っているのかもしれない。
もしそれくらい経ってるんだとしたら、もう決闘終わってんな。
果たしてどうなってるんだろう。
元の世界のことも気になるが、俺はこの一週間で、この世界のことをより詳しく調べた。
…と言っても、大したことは分かっていない。
ただ、この世界にはシルナが存在していないから。
シルナの存在しないことによって、果たしてどんな風に、この国の歴史が変わっているのかを確認しただけだ。
もっと詳しく言うと…大昔に起きたという、邪神と聖神の戦争、とか。
イーニシュフェルトの里とか。神殺しの魔法とか。
大昔に起きたという聖戦、俺も口伝えでしか聞いてないけど。
神殺しの魔法を使ってあの聖戦を終わらせたのは、他でもないシルナの功績である。
この世界にシルナが存在していないのだったら、聖戦は終わらず、邪神が統べる世界になってしまう。
…はずだった。
それなのに、今この世界を見てみると良い。
邪神も聖神も、聖戦の話も…一度も耳にしていない。
これはどういうことなのか。
調べてみて分かった。
結論から言うと…この世界にも、一応、シルナは存在しているらしい。
ただ、俺の前に姿を現すことはない。
この世界のシルナは、俺と出会うことはない。
何だかややこしい話ばかりして、大変申し訳無いが。
この世界ではどうも、元の世界であったような、聖神と邪神の戦争は起きていないらしい。
聖戦に関する歴史の記述が、全く残されていないのである。
…まぁ、敢えて記録から抹消されているだけで、もしかしたらあったのかもしれないが。
だけど多分、聖戦が起きなかったというのは事実なのだろう。
この世界に来たときから、ずっと気になっていた。
普段、俺の中には常に…この身体の中に封印されている邪神の気配を感じていた。
いつもは、シルナが俺の身体の奥深くに邪神を封印してくれているから、気にすることはなかったが。
こうしてなくなってみると、よく分かる。
自分の中身が空っぽになったような…。
…なんつーか、内臓一つ二つ失ったような気がする。
いや、比喩だけどさ。
この世界では、俺の中に邪神がいない。
そのせいなのだろうか?…「前の」俺が出てくる気配も、全く無いのだ。
聖戦が起きなかった。俺の肉体に邪神が宿ることもなかった。
聖戦が起きなければ、神殺しの魔法が使われなかったら、俺がシルナと出会う機会はない。
俺の横にシルナがいないのは、多分それが原因なのだ。
その代わり…と言ってはなんだが。
聖戦の記述は見つけられなかったが、イーニシュフェルトの里に関する記述を見つけることは出来た。
…シルナの存在しない、偽りの世界にやって来て、およそ一週間が経過した。
とはいえ、それはこちらの世界の時間であり。
元の世界で、どれくらい時間が経過しているのかは分からない。
もしかしたら、1分とか、一時間くらいしか経ってないのかもしれないし。
あるいは…一ヶ月、一年くらい経っているのかもしれない。
もしそれくらい経ってるんだとしたら、もう決闘終わってんな。
果たしてどうなってるんだろう。
元の世界のことも気になるが、俺はこの一週間で、この世界のことをより詳しく調べた。
…と言っても、大したことは分かっていない。
ただ、この世界にはシルナが存在していないから。
シルナの存在しないことによって、果たしてどんな風に、この国の歴史が変わっているのかを確認しただけだ。
もっと詳しく言うと…大昔に起きたという、邪神と聖神の戦争、とか。
イーニシュフェルトの里とか。神殺しの魔法とか。
大昔に起きたという聖戦、俺も口伝えでしか聞いてないけど。
神殺しの魔法を使ってあの聖戦を終わらせたのは、他でもないシルナの功績である。
この世界にシルナが存在していないのだったら、聖戦は終わらず、邪神が統べる世界になってしまう。
…はずだった。
それなのに、今この世界を見てみると良い。
邪神も聖神も、聖戦の話も…一度も耳にしていない。
これはどういうことなのか。
調べてみて分かった。
結論から言うと…この世界にも、一応、シルナは存在しているらしい。
ただ、俺の前に姿を現すことはない。
この世界のシルナは、俺と出会うことはない。
何だかややこしい話ばかりして、大変申し訳無いが。
この世界ではどうも、元の世界であったような、聖神と邪神の戦争は起きていないらしい。
聖戦に関する歴史の記述が、全く残されていないのである。
…まぁ、敢えて記録から抹消されているだけで、もしかしたらあったのかもしれないが。
だけど多分、聖戦が起きなかったというのは事実なのだろう。
この世界に来たときから、ずっと気になっていた。
普段、俺の中には常に…この身体の中に封印されている邪神の気配を感じていた。
いつもは、シルナが俺の身体の奥深くに邪神を封印してくれているから、気にすることはなかったが。
こうしてなくなってみると、よく分かる。
自分の中身が空っぽになったような…。
…なんつーか、内臓一つ二つ失ったような気がする。
いや、比喩だけどさ。
この世界では、俺の中に邪神がいない。
そのせいなのだろうか?…「前の」俺が出てくる気配も、全く無いのだ。
聖戦が起きなかった。俺の肉体に邪神が宿ることもなかった。
聖戦が起きなければ、神殺しの魔法が使われなかったら、俺がシルナと出会う機会はない。
俺の横にシルナがいないのは、多分それが原因なのだ。
その代わり…と言ってはなんだが。
聖戦の記述は見つけられなかったが、イーニシュフェルトの里に関する記述を見つけることは出来た。
この作家の他の作品
表紙を見る
彼らは夢を見る。毎晩、バケモノに襲われる悪夢を。
彼らは生贄。罪を犯した人間達が生み出したバケモノを、その手で殺すことを宿命付けられた生贄。
彼らは選ばれた。「普通」であることに選ばれなかった彼ら。
裁定者たる天使が振った賽に、選ばれてしまった彼らが辿る運命は。
そして、生贄に選ばれた彼らの抱える、辛く、苦しみに満ちた過去の記憶とは…。
表紙を見る
2019年に作者が携帯小説モバスペbookに投稿した作品を移植しました。
彼らの迎えた夜明けに、祝福の歌を。
表紙を見る
2021年にモバスペbookに投稿した作品を移植しました。
エロマフィア、記念すべき第5弾。
最果てにあるレゾンデートルを、お楽しみください。
※この作品に登場する宗教、教義、宗教組織は全てフィクションです。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…