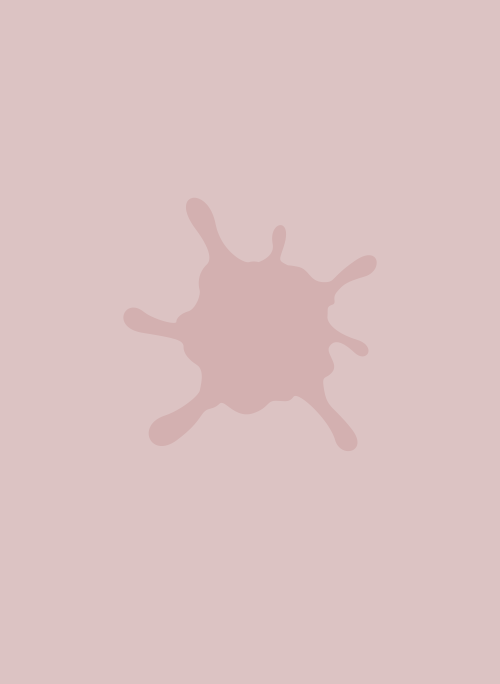未来、未来…か。
「遠くにいる人や、知らない人の未来は見えない。でも、自分の未来や目の前にいる人の未来を見ることが出来るの」
だ、そうだ。
「それは…どのくらい先まで見えるの?」
何千年、何万年後の未来まで見えるのだろうか。
それまで自分が生きていることが前提だが。
「見ようと思えば、その人の人生の最期まで見ることが出来るわ」
それは凄い。
「だけど…遠い未来であればあるほど、不確定要素がたくさん増えて…『青く』見えるから、見えたとしても本当にその通りになるかどうかは分からないわ」
と、スクルトは言った。
「青」…。
そういえば前も、「赤」だったとか口走っていたことがあったが。
その色は、スクルトの未来視の能力に何か関係があるのだろうか。
「青とか赤って言ってるのは?色が何か関係あるの」
「私が未来を見るときはね、その未来の景色が青かったり、赤かったり…黄色みがかかっていたり、オレンジだったり…。とにかく、色がついて見えるの」
結構カラフルな未来なんだね。
「赤に近いほど、その未来は確定している。逆に、青に近いほど不確定な未来で、私が見たものとは違う未来が訪れる可能性があるの」
「つまり…スクルトの未来視の能力は、常に100%確定した未来を見られる訳ではないんだね」
「そうね。実際、見えたのが『青い』未来だった場合、私が見た未来とは違う現実になったことが何度もあるわ」
…成程。
便利なような、そうでもないような…。
いや、でもその未来が「赤」…確定の未来だった場合は、100%その通りになるんだろう?
それだけでも、充分に凄い能力だ。
「数時間後とか翌日とか、近い未来を見るときは『赤』であることが多いわ。逆に遠い未来を見ようとすればするほど、色は『青』に近づくの」
「逆に言うと…『赤』は変えられない運命、『青』は変えられる可能性がある運命、ってことか」
「そうなるわね。でも…確かなことは言えないわ。遠い未来でも『赤く』見えることはあるし、数分後の未来でも、状況によっては『青く』見えたりもするし…」
…その時その時によって、見える未来の色はまちまちのようだ。
どんな色に見えたとしても、未来を見て「予習」出来るのなら、どのような未来がやってこようとも、ある程度は覚悟をして臨めそうだな。
でも…逆に、自分にとって辛い未来が見えて、それがもし変えられない…「赤」の未来だったら。
辛い運命がやって来るのを、何も出来ずに待っていることしか出来ない。
それは…凄く、辛いことだと思う。
でもスクルトは、これまで何度もそんな運命を乗り越えてきたんだろうな。
「遠くにいる人や、知らない人の未来は見えない。でも、自分の未来や目の前にいる人の未来を見ることが出来るの」
だ、そうだ。
「それは…どのくらい先まで見えるの?」
何千年、何万年後の未来まで見えるのだろうか。
それまで自分が生きていることが前提だが。
「見ようと思えば、その人の人生の最期まで見ることが出来るわ」
それは凄い。
「だけど…遠い未来であればあるほど、不確定要素がたくさん増えて…『青く』見えるから、見えたとしても本当にその通りになるかどうかは分からないわ」
と、スクルトは言った。
「青」…。
そういえば前も、「赤」だったとか口走っていたことがあったが。
その色は、スクルトの未来視の能力に何か関係があるのだろうか。
「青とか赤って言ってるのは?色が何か関係あるの」
「私が未来を見るときはね、その未来の景色が青かったり、赤かったり…黄色みがかかっていたり、オレンジだったり…。とにかく、色がついて見えるの」
結構カラフルな未来なんだね。
「赤に近いほど、その未来は確定している。逆に、青に近いほど不確定な未来で、私が見たものとは違う未来が訪れる可能性があるの」
「つまり…スクルトの未来視の能力は、常に100%確定した未来を見られる訳ではないんだね」
「そうね。実際、見えたのが『青い』未来だった場合、私が見た未来とは違う現実になったことが何度もあるわ」
…成程。
便利なような、そうでもないような…。
いや、でもその未来が「赤」…確定の未来だった場合は、100%その通りになるんだろう?
それだけでも、充分に凄い能力だ。
「数時間後とか翌日とか、近い未来を見るときは『赤』であることが多いわ。逆に遠い未来を見ようとすればするほど、色は『青』に近づくの」
「逆に言うと…『赤』は変えられない運命、『青』は変えられる可能性がある運命、ってことか」
「そうなるわね。でも…確かなことは言えないわ。遠い未来でも『赤く』見えることはあるし、数分後の未来でも、状況によっては『青く』見えたりもするし…」
…その時その時によって、見える未来の色はまちまちのようだ。
どんな色に見えたとしても、未来を見て「予習」出来るのなら、どのような未来がやってこようとも、ある程度は覚悟をして臨めそうだな。
でも…逆に、自分にとって辛い未来が見えて、それがもし変えられない…「赤」の未来だったら。
辛い運命がやって来るのを、何も出来ずに待っていることしか出来ない。
それは…凄く、辛いことだと思う。
でもスクルトは、これまで何度もそんな運命を乗り越えてきたんだろうな。
「あなたとの出会いも、未来を見て知っていたのよ」
と、スクルトは教えてくれた。
「それも、『赤い』未来だった。だからあの日、私達はどうあっても出会う運命だったのよ」
「…そうだったんだ」
「それと同じで…この戦争の行く末も、まだまだ続くわ。少なくとも50年先までは『赤』…いや、『オレンジ』くらいかしら」
つまり、戦争が50年先も続いているのは、ほぼ確定の未来という訳か。
それは…あまり知りたくない未来だったかもしれない。
いや、あと50年はこのまま耐えなければならないという、心積もりが出来たのだと思おう。
それに…バケモノである僕達に、人間の戦争がどんなに長く続こうが、大して関係ないか。
それよりも、スクルトの不思議な能力について知ることが出来たから、その方が僕にとっては重要だ。
後で聞いたところによると。
スクルトの未来視の能力が、赤だったり青だったりオレンジに見えるのは。
恐らく、スクルト自身が未来を見てしまったせいで、未来が変わってしまうせいなんじゃないか、とのこと。
小難しくてよく分からないが、スクルト曰く。
未来視の力を使って未来を見て、もしそれが自分にとって悪い未来だったら。
何としてもその未来を回避しようと、対策を立てるだろう?
例えば…これは極端な例え話だが。
一分後に自分が道端で転ぶ、という未来を見てしまったら。
一分前、つまり今現在の自分は、転ばないように対策するだろう。
その道を通らないとか、躓かないように注意深く歩くとか。
そうやって、一分後に自分が転ぶという未来を回避しようとする。
悪い未来が起きないように、現在を変えようとする。
その結果、悪い未来が回避され、別の未来がやって来ることになる。
現在を変えることで変えられる未来が、青。
現在を変えても変えられない未来が、赤。
多分、そういう認識で良いんだと思う。
というのは、全てスクルトの受け売りである。
如何せん、彼女以外にこのような能力を持っている人間がいないのだから、スクルトの解釈を信じるしかない。
「なかなか興味深い能力だね」
インチキ占い師、なんて心の中で馬鹿にしていた自分が恥ずかしい。
インチキどころか、本物の中の本物だった。
「…あなたって人は。気持ち悪いとは思わないの?」
スクルトは、若干呆れたようにそう聞いた。
「何が?」
「未来が見えるのよ?人の未来を言い当てることが出来るの。気持ち悪いでしょう?」
気持ち悪い?スクルトが?
それとも、スクルトの能力が?
…僕は、別にどうでも良いけど。
と、スクルトは教えてくれた。
「それも、『赤い』未来だった。だからあの日、私達はどうあっても出会う運命だったのよ」
「…そうだったんだ」
「それと同じで…この戦争の行く末も、まだまだ続くわ。少なくとも50年先までは『赤』…いや、『オレンジ』くらいかしら」
つまり、戦争が50年先も続いているのは、ほぼ確定の未来という訳か。
それは…あまり知りたくない未来だったかもしれない。
いや、あと50年はこのまま耐えなければならないという、心積もりが出来たのだと思おう。
それに…バケモノである僕達に、人間の戦争がどんなに長く続こうが、大して関係ないか。
それよりも、スクルトの不思議な能力について知ることが出来たから、その方が僕にとっては重要だ。
後で聞いたところによると。
スクルトの未来視の能力が、赤だったり青だったりオレンジに見えるのは。
恐らく、スクルト自身が未来を見てしまったせいで、未来が変わってしまうせいなんじゃないか、とのこと。
小難しくてよく分からないが、スクルト曰く。
未来視の力を使って未来を見て、もしそれが自分にとって悪い未来だったら。
何としてもその未来を回避しようと、対策を立てるだろう?
例えば…これは極端な例え話だが。
一分後に自分が道端で転ぶ、という未来を見てしまったら。
一分前、つまり今現在の自分は、転ばないように対策するだろう。
その道を通らないとか、躓かないように注意深く歩くとか。
そうやって、一分後に自分が転ぶという未来を回避しようとする。
悪い未来が起きないように、現在を変えようとする。
その結果、悪い未来が回避され、別の未来がやって来ることになる。
現在を変えることで変えられる未来が、青。
現在を変えても変えられない未来が、赤。
多分、そういう認識で良いんだと思う。
というのは、全てスクルトの受け売りである。
如何せん、彼女以外にこのような能力を持っている人間がいないのだから、スクルトの解釈を信じるしかない。
「なかなか興味深い能力だね」
インチキ占い師、なんて心の中で馬鹿にしていた自分が恥ずかしい。
インチキどころか、本物の中の本物だった。
「…あなたって人は。気持ち悪いとは思わないの?」
スクルトは、若干呆れたようにそう聞いた。
「何が?」
「未来が見えるのよ?人の未来を言い当てることが出来るの。気持ち悪いでしょう?」
気持ち悪い?スクルトが?
それとも、スクルトの能力が?
…僕は、別にどうでも良いけど。
「私の生まれ故郷は、私に限らず、人知を超えた不思議な能力を持って生まれた人がたくさんいたのよ」
と、スクルトは教えてくれた。
「へぇ…」
じゃあ、スクルトのその力は、血筋なのかもしれない。
「それでも、私の力は特殊過ぎた。家族でさえ…この力を恐れたのよ。気味が悪い、ってね」
「…」
「呪いの巫女だなんて呼ばれて、殺されそうになったこともあるわ」
…何故そうなるのか。
「自分が殺される未来を見ては、何とか逃げ出して、その未来を回避してきた。故郷を捨てて一人で旅をしていたのも、そのせいよ」
生まれ故郷に留まれば、スクルトの能力を気味悪がった同業の人々に、処刑されてしまいかねないから。
それで…一人で生きてきたのか。
「それなのに、あなたは私を恐れないのね」
「…僕も、スクルトに負けないくらいバケモノだからね」
未来視の能力を持っているなんて、そんな気持ち悪い人間と一緒にはいられない、なんて。
そんな偉そうなことを言える立場ではない。
人間とケルベロスのキメラ…なんていう、本物のバケモノの分際で。
どうして、スクルトを「気味が悪い」なんて言えるだろう。
それに…。
「未来なんて、見えたとしても見えなかったとしても、いずれ誰にでも訪れるものだろう?」
「それは…そうだけど」
「箱に入ったクリスマスプレゼントの中身を、クリスマス前日にこっそり盗み見るのと同じ。子供の悪戯程度の能力だよ」
僕がそう言うと、スクルトは呆気に取られたような顔をして。
そして、ふっと微笑んだ。
「今まで色んな人に出会ってきたけど、私の能力を『子供の悪戯』だと言ったのは、あなたが初めてだわ」
そうなんだ。
「…でも、ありがとう」
「僕は何もしてないよ」
「いいえ、あなたは私の心を救ってくれたわ。…だから、ありがとう」
そう言って、スクルトは嬉しそうに微笑んだ。
滅多に見られない、彼女の美しい笑顔だった。
その笑顔を守ることが出来るのなら、僕は他に何も要らなかった。
と、スクルトは教えてくれた。
「へぇ…」
じゃあ、スクルトのその力は、血筋なのかもしれない。
「それでも、私の力は特殊過ぎた。家族でさえ…この力を恐れたのよ。気味が悪い、ってね」
「…」
「呪いの巫女だなんて呼ばれて、殺されそうになったこともあるわ」
…何故そうなるのか。
「自分が殺される未来を見ては、何とか逃げ出して、その未来を回避してきた。故郷を捨てて一人で旅をしていたのも、そのせいよ」
生まれ故郷に留まれば、スクルトの能力を気味悪がった同業の人々に、処刑されてしまいかねないから。
それで…一人で生きてきたのか。
「それなのに、あなたは私を恐れないのね」
「…僕も、スクルトに負けないくらいバケモノだからね」
未来視の能力を持っているなんて、そんな気持ち悪い人間と一緒にはいられない、なんて。
そんな偉そうなことを言える立場ではない。
人間とケルベロスのキメラ…なんていう、本物のバケモノの分際で。
どうして、スクルトを「気味が悪い」なんて言えるだろう。
それに…。
「未来なんて、見えたとしても見えなかったとしても、いずれ誰にでも訪れるものだろう?」
「それは…そうだけど」
「箱に入ったクリスマスプレゼントの中身を、クリスマス前日にこっそり盗み見るのと同じ。子供の悪戯程度の能力だよ」
僕がそう言うと、スクルトは呆気に取られたような顔をして。
そして、ふっと微笑んだ。
「今まで色んな人に出会ってきたけど、私の能力を『子供の悪戯』だと言ったのは、あなたが初めてだわ」
そうなんだ。
「…でも、ありがとう」
「僕は何もしてないよ」
「いいえ、あなたは私の心を救ってくれたわ。…だから、ありがとう」
そう言って、スクルトは嬉しそうに微笑んだ。
滅多に見られない、彼女の美しい笑顔だった。
その笑顔を守ることが出来るのなら、僕は他に何も要らなかった。
僕がスクルトを恐れなかったように、スクルトもまた僕を恐れなかった。
僕の異形の姿を…。中途半端な、人間と獣を掛け合わせたようなバケモノの姿を見ても。
…罪人である、僕の姿を見ても。
スクルトは恐れなかった。変わらず、僕の隣にあり続けた。
僕は、普段は人間の姿を取り繕っている。
しかし、人間の姿は、僕の本来の姿ではない。
無理矢理変装して、人間…の、ように見せかけているだけだ。
あまり長く人間の姿でいると、窮屈で、身体がムズムズして耐えられなくなってくる。
だから、時折もとの姿に…獣の姿に戻る必要があった。
化粧を落として、すっぴんになるようなもの。
だが、僕はとても…「ノーメイク」で人様の前に姿を現せるような顔ではなかった。
人間の姿でいられなくなったとき、僕はスクルトに「少しの間、一人で待っていて欲しい」と頼み。
人目のつかない場所に駆け込んで、もとの姿に戻ることでストレス発散していた。
しかし、スクルトと出会った当初、僕はそのようなことをスクルトに話さなかった。
スクルトは何も言わず、何も聞かずに、僕がまた人間の姿を取り繕って戻ってくるのを待っていてくれた。
だが、ある日。
「ねぇ、いつも一人で何をしてるの?」
…スクルトの方から、そう尋ねてきた。
どうにも人間の姿でいるのが窮屈だから、少しもとの姿に戻ってストレス発散しよう、と。
いつも通り、スクルトに「少し待っていてくれないか」と頼んだら。
スクルトは、初めて僕にそう尋ねてきたのである。
「…それは…」
「あなたなら大丈夫だとは思うけど、このご時世だもの。あまり一人にならない方が良いと思うの」
「…」
…おっしゃることは正しいのだが。
いくらスクルトが僕を恐れなくても、あの禍々しい異形の姿を、彼女に見せたくなかった。
「…僕は、人間の姿のまま長くいられないんだ」
従って、僕は正直にスクルトに話すことにした。
「『変化(へんげ)』が解けて、もとの姿に戻ってしまう…。だから、定期的に時分で『変化』を解いて、たまにもとの姿に戻ってるんたよ」
「そうなのね」
スクルトは驚くことなく、納得したように頷いた。
そして。
「それなら、わざわざ私のいないところに行く必要はないわ。今ここで『変化』を解いたら良いじゃない」
…そう言うと思った。
スクルトは、優しいから。
「…気味が悪いから、見せたくないんだ」
「心配要らないわ。どうせ、私には見えないから」
そうなんだけど。
でも、彼女の目の前でもとの…ケルベロスと人間のキメラの姿に戻ってしまったら。
盲目であるスクルトにだって、分かるはずだ。
それがどれほど禍々しい、異形の姿であるか。
…僕はスクルトを怖がらせたくないし、万が一にでも…スクルトに「気味が悪い」と思われたくなかった。
だから、『変化』を解くなら一人でいるときに、と思ったのだが…。
「大丈夫よ、マシュリ。私はあなたのどんな姿を見ても、恐れたり怯えたりしないわ」
僕の不安を感じ取ったかのように、スクルトはそう言った。
僕の異形の姿を…。中途半端な、人間と獣を掛け合わせたようなバケモノの姿を見ても。
…罪人である、僕の姿を見ても。
スクルトは恐れなかった。変わらず、僕の隣にあり続けた。
僕は、普段は人間の姿を取り繕っている。
しかし、人間の姿は、僕の本来の姿ではない。
無理矢理変装して、人間…の、ように見せかけているだけだ。
あまり長く人間の姿でいると、窮屈で、身体がムズムズして耐えられなくなってくる。
だから、時折もとの姿に…獣の姿に戻る必要があった。
化粧を落として、すっぴんになるようなもの。
だが、僕はとても…「ノーメイク」で人様の前に姿を現せるような顔ではなかった。
人間の姿でいられなくなったとき、僕はスクルトに「少しの間、一人で待っていて欲しい」と頼み。
人目のつかない場所に駆け込んで、もとの姿に戻ることでストレス発散していた。
しかし、スクルトと出会った当初、僕はそのようなことをスクルトに話さなかった。
スクルトは何も言わず、何も聞かずに、僕がまた人間の姿を取り繕って戻ってくるのを待っていてくれた。
だが、ある日。
「ねぇ、いつも一人で何をしてるの?」
…スクルトの方から、そう尋ねてきた。
どうにも人間の姿でいるのが窮屈だから、少しもとの姿に戻ってストレス発散しよう、と。
いつも通り、スクルトに「少し待っていてくれないか」と頼んだら。
スクルトは、初めて僕にそう尋ねてきたのである。
「…それは…」
「あなたなら大丈夫だとは思うけど、このご時世だもの。あまり一人にならない方が良いと思うの」
「…」
…おっしゃることは正しいのだが。
いくらスクルトが僕を恐れなくても、あの禍々しい異形の姿を、彼女に見せたくなかった。
「…僕は、人間の姿のまま長くいられないんだ」
従って、僕は正直にスクルトに話すことにした。
「『変化(へんげ)』が解けて、もとの姿に戻ってしまう…。だから、定期的に時分で『変化』を解いて、たまにもとの姿に戻ってるんたよ」
「そうなのね」
スクルトは驚くことなく、納得したように頷いた。
そして。
「それなら、わざわざ私のいないところに行く必要はないわ。今ここで『変化』を解いたら良いじゃない」
…そう言うと思った。
スクルトは、優しいから。
「…気味が悪いから、見せたくないんだ」
「心配要らないわ。どうせ、私には見えないから」
そうなんだけど。
でも、彼女の目の前でもとの…ケルベロスと人間のキメラの姿に戻ってしまったら。
盲目であるスクルトにだって、分かるはずだ。
それがどれほど禍々しい、異形の姿であるか。
…僕はスクルトを怖がらせたくないし、万が一にでも…スクルトに「気味が悪い」と思われたくなかった。
だから、『変化』を解くなら一人でいるときに、と思ったのだが…。
「大丈夫よ、マシュリ。私はあなたのどんな姿を見ても、恐れたり怯えたりしないわ」
僕の不安を感じ取ったかのように、スクルトはそう言った。
「例えどんな姿でも、あなたはあなたでしょう?そう思えば全く怖くない。道端で知らない人に話しかけられる方が余程怖いわ」
「…」
…そんな。
…まぁ、無理もないかもしれない。スクルトはまだ、僕の本当の姿を見たことがないのだから…。
「気にしないで。こそこそ隠れる必要はない。あなたは何も悪くないんだから、恥じる必要はないのよ」
「…分かった」
そこまで言うなら、僕も覚悟を決めるよ。
…これでもし、スクルトに怖い思いをさせてしまうようなことがあったら。
僕はもう二度と、誰かの前で『変化』は使わない。
そもそもこんな力は、人に見せるようなものではないのだ。
しかし僕は、スクルトの求めに応じて、彼女の目の前で『変化』を解いた。
パン、と手を打って、くるりと一回転宙返りをする。
同時に『変化』が解けて、被っていた人間の皮が破れた。
現れたのは、罪を背負った禍々しい獣。
盲目のスクルトには見えなくても、その気配で、目の前にいるのがいかに恐ろしい異物であるか、彼女にも分かるはずだ。
普通の人だったら、この姿を目にするや、叫び声をあげて逃げ出すだろう。
これまで何度も、そうされてきた。
僕のこの姿を見て、悲鳴をあげなかった者は一人もいない。
さすがのスクルトも、思わず息を呑むだろうと思ったが…。
「それがあなたの本当の姿?」
スクルトは怯える様子も、臆する様子もなかった。
いつも通り平然と、けろりとしていた。
「…そう、だけど…」
「そうなのね」
あろうことか。
スクルトは恐れるどころか、平気な顔をして僕に歩み寄り。
バケモノの姿である僕の頭を、優しく撫で始めた。
「ふふ、毛並みふわふわね」
なんて、笑っている始末。
いや、その…。
そんな反応をされたのは初めてで、僕も何と言ったら良いのか分からない。
「…怖くないの?」
「何が?」
「こんな姿を見たのに…。これまでこの姿を見た人は皆、怖がって悲鳴をあげて…」
「どうして悲鳴をあげるの?見た目が変わっただけで、マシュリはマシュリでしょう?」
…それは。
「言ったはずよ。私は、あなたのどんな姿を見ても恐れない。あなたなら怖くないわ」
スクルト…。
…馬鹿みたいだ。今まで、そんなことを言う人は誰も…。
…。
「…スクルト」
「何?」
相変わらず、スクルトは僕の頭を撫でていた。
愛おしいものに触れるかのような、優しい手付きで。
「…ありがとう」
「…お互い様よ」
そう言って、スクルトはまた微笑んだのだった。
これ以降僕は、スクルトの目を逃れて『変化』を解くことをやめた。
宣言通り、彼女は僕のどんな姿を見ても、僕を恐れたり怯えたりはしなかったから。
ありのまま、自然体でいられる。
それがどれほど心が楽になるか、僕はスクルトに出会って初めて知ったのだった。
…しかし。
そんな気の緩みが、後にあのような悲劇を生み出す原因になったのかもしれない。
「…」
…そんな。
…まぁ、無理もないかもしれない。スクルトはまだ、僕の本当の姿を見たことがないのだから…。
「気にしないで。こそこそ隠れる必要はない。あなたは何も悪くないんだから、恥じる必要はないのよ」
「…分かった」
そこまで言うなら、僕も覚悟を決めるよ。
…これでもし、スクルトに怖い思いをさせてしまうようなことがあったら。
僕はもう二度と、誰かの前で『変化』は使わない。
そもそもこんな力は、人に見せるようなものではないのだ。
しかし僕は、スクルトの求めに応じて、彼女の目の前で『変化』を解いた。
パン、と手を打って、くるりと一回転宙返りをする。
同時に『変化』が解けて、被っていた人間の皮が破れた。
現れたのは、罪を背負った禍々しい獣。
盲目のスクルトには見えなくても、その気配で、目の前にいるのがいかに恐ろしい異物であるか、彼女にも分かるはずだ。
普通の人だったら、この姿を目にするや、叫び声をあげて逃げ出すだろう。
これまで何度も、そうされてきた。
僕のこの姿を見て、悲鳴をあげなかった者は一人もいない。
さすがのスクルトも、思わず息を呑むだろうと思ったが…。
「それがあなたの本当の姿?」
スクルトは怯える様子も、臆する様子もなかった。
いつも通り平然と、けろりとしていた。
「…そう、だけど…」
「そうなのね」
あろうことか。
スクルトは恐れるどころか、平気な顔をして僕に歩み寄り。
バケモノの姿である僕の頭を、優しく撫で始めた。
「ふふ、毛並みふわふわね」
なんて、笑っている始末。
いや、その…。
そんな反応をされたのは初めてで、僕も何と言ったら良いのか分からない。
「…怖くないの?」
「何が?」
「こんな姿を見たのに…。これまでこの姿を見た人は皆、怖がって悲鳴をあげて…」
「どうして悲鳴をあげるの?見た目が変わっただけで、マシュリはマシュリでしょう?」
…それは。
「言ったはずよ。私は、あなたのどんな姿を見ても恐れない。あなたなら怖くないわ」
スクルト…。
…馬鹿みたいだ。今まで、そんなことを言う人は誰も…。
…。
「…スクルト」
「何?」
相変わらず、スクルトは僕の頭を撫でていた。
愛おしいものに触れるかのような、優しい手付きで。
「…ありがとう」
「…お互い様よ」
そう言って、スクルトはまた微笑んだのだった。
これ以降僕は、スクルトの目を逃れて『変化』を解くことをやめた。
宣言通り、彼女は僕のどんな姿を見ても、僕を恐れたり怯えたりはしなかったから。
ありのまま、自然体でいられる。
それがどれほど心が楽になるか、僕はスクルトに出会って初めて知ったのだった。
…しかし。
そんな気の緩みが、後にあのような悲劇を生み出す原因になったのかもしれない。
スクルトは僕を恐れないどころか、僕の為に色々考えてくれているようだった。
「あなたは元々、ケルベロスと人間のキメラなのよね?」
ある日唐突に、スクルトは僕にそう聞いてきた。
「?そうだけど…」
「それなのに、どうして普段は人間の姿になってるの?」
「それは…あの姿だと人目を引くから。わざと人間の姿を装って…」
まぁ、長く人間の姿ではいられないから、たまにもとの姿に戻る必要があるのだが。
すると。
「人間の姿になれる…ってことは、他の姿にもなれるの?」
え?
「他の姿?」
「うん、そう。猫とか鳥とか」
猫って…。
「僕は…どちらかと言うと、猫より犬に近いんだけど…」
「あ、そうか…。ケルベロスは犬なのよね。でも、私は犬より猫の方が好きだわ」
スクルトは猫派であるらしい。
それは初めて知った。
「そういう他の動物にはなれないの?」
「…どうだろう?やってやれなくはないと思うけど…」
「どうせなら、色んな動物になれた方が良いんじゃないかしら」
確かに、スクルトの言う通りかもしれない。
人間は何かとしがらみが多くて、面倒だからな。
人間じゃなくて通りすがりの猫に化けたら、そういうしがらみからも逃れられそうだ。
それに何より、他ならぬスクルトの提案だから。
「やってみるよ。上手く『変化』出来るか分からないけど…」
「大丈夫よ、マシュリなら」
…。
「…それは、『赤』い未来?」
「いいえ、見てないわ。未来を見て何もかも知ってしまったら、何が起きても新鮮味がなくてつまらないから」
「それでも、僕なら大丈夫だって言えるんだ」
「勿論。マシュリなら…私達なら大丈夫よ」
そう。
そんな風に思い込みたいだけだって分かってるけど、実は僕もそう思うよ。
「この先どんなことが起きても、私とあなたの未来は明るいわ。大丈夫」
「…それも予測?」
「いいえ、これは私が『見た』未来。ちゃんと『赤』かったから、確定の未来よ」
それは心強い。
スクルトが未来を見て、しかも赤く見えたのなら大丈夫だ。
保証書付きだな。
僕はこのとき、幸福に目が眩んでいた。
だから、気づかなかったのだ。
僕達の未来が、確定して明るいものである、なんて。
ほんの少し考えたら、そんなはずがないことは分かったはずだ。
それでも僕は、気づかなかったのだ。
…あるいは、心の何処かで気づいていながら…見えなかったフリをしていたのかもしれない。
スクルトの隣りにいることが、あまりにも居心地が良くて…。
それがいつか終わってしまう日が来るなんて、万が一にでも考えたくもなかったのだ。
「あなたは元々、ケルベロスと人間のキメラなのよね?」
ある日唐突に、スクルトは僕にそう聞いてきた。
「?そうだけど…」
「それなのに、どうして普段は人間の姿になってるの?」
「それは…あの姿だと人目を引くから。わざと人間の姿を装って…」
まぁ、長く人間の姿ではいられないから、たまにもとの姿に戻る必要があるのだが。
すると。
「人間の姿になれる…ってことは、他の姿にもなれるの?」
え?
「他の姿?」
「うん、そう。猫とか鳥とか」
猫って…。
「僕は…どちらかと言うと、猫より犬に近いんだけど…」
「あ、そうか…。ケルベロスは犬なのよね。でも、私は犬より猫の方が好きだわ」
スクルトは猫派であるらしい。
それは初めて知った。
「そういう他の動物にはなれないの?」
「…どうだろう?やってやれなくはないと思うけど…」
「どうせなら、色んな動物になれた方が良いんじゃないかしら」
確かに、スクルトの言う通りかもしれない。
人間は何かとしがらみが多くて、面倒だからな。
人間じゃなくて通りすがりの猫に化けたら、そういうしがらみからも逃れられそうだ。
それに何より、他ならぬスクルトの提案だから。
「やってみるよ。上手く『変化』出来るか分からないけど…」
「大丈夫よ、マシュリなら」
…。
「…それは、『赤』い未来?」
「いいえ、見てないわ。未来を見て何もかも知ってしまったら、何が起きても新鮮味がなくてつまらないから」
「それでも、僕なら大丈夫だって言えるんだ」
「勿論。マシュリなら…私達なら大丈夫よ」
そう。
そんな風に思い込みたいだけだって分かってるけど、実は僕もそう思うよ。
「この先どんなことが起きても、私とあなたの未来は明るいわ。大丈夫」
「…それも予測?」
「いいえ、これは私が『見た』未来。ちゃんと『赤』かったから、確定の未来よ」
それは心強い。
スクルトが未来を見て、しかも赤く見えたのなら大丈夫だ。
保証書付きだな。
僕はこのとき、幸福に目が眩んでいた。
だから、気づかなかったのだ。
僕達の未来が、確定して明るいものである、なんて。
ほんの少し考えたら、そんなはずがないことは分かったはずだ。
それでも僕は、気づかなかったのだ。
…あるいは、心の何処かで気づいていながら…見えなかったフリをしていたのかもしれない。
スクルトの隣りにいることが、あまりにも居心地が良くて…。
それがいつか終わってしまう日が来るなんて、万が一にでも考えたくもなかったのだ。
この世の何処にも、自分の居場所なんてないと思っていた。
現世でも冥界でも、僕は気味悪がられ、迫害された。
愛されるどころか、生きていることさえ許されなかった。
罪を背負ったこの姿を、誰も許してくれないのだと。
そう思っていた。
いつだったかスクルトに、そう打ち明けたことがある。
「どうして、その姿が罪なの?」
スクルトは僕に尋ねた。
「…私にはそうは見えないけど。どうしてあなたが罪人なの?何か悪いことをしたの?」
「…それは…」
「何でも打ち明けて良いのよ。…私は何があっても、あなたを恐れたり蔑んだりしないわ。あなたがどんな罪を犯したのだとしても、私も一緒に同じものを背負うわ」
…どうしてそんなことを言えるのか。
僕がどんな罪を犯したか…聞いてもいないのに、何故一緒に背負うなんて言うんだ。
少しは躊躇わないのだろうか?
スクルトは、僕に甘過ぎる。
「何があったの?…聞かせて」
スクルトが僕に、あまりにも優しいから。
僕は、誰にも打ち明けたことのない自分の罪を告白してしまった。
「…僕が人間とケルベロスのキメラだってことは知ってるよね」
「えぇ」
「そもそも、どうしてそんな異形が…。魔物と人間のキメラなんて存在が、この世に存在していると思う?」
「…」
僕の質問に、スクルトはしばし無言で考えた。
そして。
「…別に、自然なことなんじゃないかしら?人間だって、白人と黒人のハーフが普通に存在してるし、それと同じでしょう?」
誰もがそんな風に、スクルトのように物分かりが良ければ良かったんだが。
人間と魔物の多様性なんてものを許すほど、頭の柔らかい者はいない。
スクルトを除いてはね。
「白人と黒人…は人間同士でしょ?僕の場合、種族が違うから…」
例えるなら、人間と犬のハーフのようなものだ。
気味が悪いと思うだろう?
僕はそういう存在なんだ。
「…もしかして、それが罪なの?互いに相容れない種族同士が結びついた存在であることが?」
スクルトはハッとして、僕にそう尋ねた。
…その通りだ。
「僕の遠い祖先…とある一匹のケルベロスが、契約していた召喚魔導師の女性と恋仲になって、その結果生まれたのが、最初のキメラ…」
もう遠い遠い昔の話。
僕も、言い伝えで聞いているだけだ。当然会ったことはない。
「でも、冥界のケルベロス達は、そんなイレギュラーを許さなかった。誇り高い冥界の魔物が人間と結ばれて、あまつさえ子供を設けるなんて許されない、って」
「…」
「僕の先祖は呪いをかけられて、同種の群れから追い出された」
「…呪いって、何なの?」
そんなの決まっている。
「未来永劫、子々孫々、生まれてくる子供は人間でもケルベロスでもない、あの恐ろしいキメラの姿になる。そんな呪いだよ」
末代に渡って、先祖が犯した罪を背負うことになった。
僕のこの姿は、先祖が受けた呪いのせいなのである。
現世でも冥界でも、僕は気味悪がられ、迫害された。
愛されるどころか、生きていることさえ許されなかった。
罪を背負ったこの姿を、誰も許してくれないのだと。
そう思っていた。
いつだったかスクルトに、そう打ち明けたことがある。
「どうして、その姿が罪なの?」
スクルトは僕に尋ねた。
「…私にはそうは見えないけど。どうしてあなたが罪人なの?何か悪いことをしたの?」
「…それは…」
「何でも打ち明けて良いのよ。…私は何があっても、あなたを恐れたり蔑んだりしないわ。あなたがどんな罪を犯したのだとしても、私も一緒に同じものを背負うわ」
…どうしてそんなことを言えるのか。
僕がどんな罪を犯したか…聞いてもいないのに、何故一緒に背負うなんて言うんだ。
少しは躊躇わないのだろうか?
スクルトは、僕に甘過ぎる。
「何があったの?…聞かせて」
スクルトが僕に、あまりにも優しいから。
僕は、誰にも打ち明けたことのない自分の罪を告白してしまった。
「…僕が人間とケルベロスのキメラだってことは知ってるよね」
「えぇ」
「そもそも、どうしてそんな異形が…。魔物と人間のキメラなんて存在が、この世に存在していると思う?」
「…」
僕の質問に、スクルトはしばし無言で考えた。
そして。
「…別に、自然なことなんじゃないかしら?人間だって、白人と黒人のハーフが普通に存在してるし、それと同じでしょう?」
誰もがそんな風に、スクルトのように物分かりが良ければ良かったんだが。
人間と魔物の多様性なんてものを許すほど、頭の柔らかい者はいない。
スクルトを除いてはね。
「白人と黒人…は人間同士でしょ?僕の場合、種族が違うから…」
例えるなら、人間と犬のハーフのようなものだ。
気味が悪いと思うだろう?
僕はそういう存在なんだ。
「…もしかして、それが罪なの?互いに相容れない種族同士が結びついた存在であることが?」
スクルトはハッとして、僕にそう尋ねた。
…その通りだ。
「僕の遠い祖先…とある一匹のケルベロスが、契約していた召喚魔導師の女性と恋仲になって、その結果生まれたのが、最初のキメラ…」
もう遠い遠い昔の話。
僕も、言い伝えで聞いているだけだ。当然会ったことはない。
「でも、冥界のケルベロス達は、そんなイレギュラーを許さなかった。誇り高い冥界の魔物が人間と結ばれて、あまつさえ子供を設けるなんて許されない、って」
「…」
「僕の先祖は呪いをかけられて、同種の群れから追い出された」
「…呪いって、何なの?」
そんなの決まっている。
「未来永劫、子々孫々、生まれてくる子供は人間でもケルベロスでもない、あの恐ろしいキメラの姿になる。そんな呪いだよ」
末代に渡って、先祖が犯した罪を背負うことになった。
僕のこの姿は、先祖が受けた呪いのせいなのである。
どれほど時が経とうと、この呪いが解けることはない。
僕は未だに、先祖の犯した罪を…。
…魔物でありながら人間と結ばれたという罪を、償い続けている。
バケモノの姿でこの世に生まれてしまったこと、これ自体が僕の贖罪なのである。
未来永劫、魔物と人間が結ばれた恥を晒し続けることが…。
…しかし。
「なんだ、そんなことだったのね」
スクルトは安堵の微笑みさえ浮かべて、何でもないと言わんばかりにそう呟いた。
…え。
「あなたがあまりに重々しく『罪人』なんて言うものだから、もっと酷いことをしたんじゃないかと思ったわ。まぁ、それでも一緒に背負うといった言葉に嘘はないけど」
「え、いや…あの」
もっと酷いことって…。
…充分酷いことなのでは?
だって、未来永劫子々孫々、永久に伝わる呪いなんだよ?
これを重罪と呼ばずして、何と呼ぶのか…。
「まず、人間と魔物が結ばれることが罪だとは、私は思わないわ。種族が違っても、気持ちが通じ合えば…そういうこともあるでしょう」
スクルトはどうやら、マイノリティーに寛容なタイプであるらしい。
だからって、人間と魔物の愛を認めるとは。
最早、寛容という言葉を通り越している気がする。
「それに、あなたは何も悪くないじゃない」
「え?」
「罪を犯したのはあなたの先祖でしょ。あなたには関係ない。マシュリは何も悪いことなんてしてないじゃない」
「…」
これには、僕は思わず面食らってしまった。
いや、それは…。
…そう、なんだろうか?
生まれたときから、お前は罪人だ、お前の存在そのものが罪だと罵られ続けた。
そのせいだろうか。僕は無意識のうちに、先祖の犯した罪を自分の犯した罪だと思い込んでいた。
「あなたの罪じゃないわ」
スクルトはそう言って、僕の両手を包み込むようにして握った。
触るな、近寄るなと言われたことはあっても、手を握られるのは初めての経験で。
どうしたら良いのか分からず、僕はどぎまぎしてしまった。
「あなたは、何も悪いことなんてしてない。この世に存在してはいけないなんて思い込む必要もない」
幼い子供に言い聞かせるような、優しい口調だった。
「心配要らないわ。あなたには、ちゃんと居場所があるから」
…居場所。
冥界からも追い出され、現世でも行く宛のない僕に、一体何処に居場所があると…。
「僕の居場所って…?」
「ここよ。私の隣。ここがあなたの居場所」
そう言われて、僕はハッとした。
…スクルトの隣が、僕の居場所?
そんなこと言って良いのか。許されるのか?
だって僕は…バケモノで、半端者で、罪人で…。
こんな人間は、何処にも居場所なんてないと思っていた。
…それなのに。
「あなたはバケモノでも罪人でもない。人間よ。私達と同じ人間。孤独に苦しみ、疎外感に悩み、それでも何とか生きる望みを必死に探してる…。誰よりも人間らしい人間よ」
あまつさえこの僕を、人間と呼ぶなど。
何処からどう見ても、人間には見えないはずなのに。
スクルトは当たり前のように、僕を人間だと言ったのだ。
僕は未だに、先祖の犯した罪を…。
…魔物でありながら人間と結ばれたという罪を、償い続けている。
バケモノの姿でこの世に生まれてしまったこと、これ自体が僕の贖罪なのである。
未来永劫、魔物と人間が結ばれた恥を晒し続けることが…。
…しかし。
「なんだ、そんなことだったのね」
スクルトは安堵の微笑みさえ浮かべて、何でもないと言わんばかりにそう呟いた。
…え。
「あなたがあまりに重々しく『罪人』なんて言うものだから、もっと酷いことをしたんじゃないかと思ったわ。まぁ、それでも一緒に背負うといった言葉に嘘はないけど」
「え、いや…あの」
もっと酷いことって…。
…充分酷いことなのでは?
だって、未来永劫子々孫々、永久に伝わる呪いなんだよ?
これを重罪と呼ばずして、何と呼ぶのか…。
「まず、人間と魔物が結ばれることが罪だとは、私は思わないわ。種族が違っても、気持ちが通じ合えば…そういうこともあるでしょう」
スクルトはどうやら、マイノリティーに寛容なタイプであるらしい。
だからって、人間と魔物の愛を認めるとは。
最早、寛容という言葉を通り越している気がする。
「それに、あなたは何も悪くないじゃない」
「え?」
「罪を犯したのはあなたの先祖でしょ。あなたには関係ない。マシュリは何も悪いことなんてしてないじゃない」
「…」
これには、僕は思わず面食らってしまった。
いや、それは…。
…そう、なんだろうか?
生まれたときから、お前は罪人だ、お前の存在そのものが罪だと罵られ続けた。
そのせいだろうか。僕は無意識のうちに、先祖の犯した罪を自分の犯した罪だと思い込んでいた。
「あなたの罪じゃないわ」
スクルトはそう言って、僕の両手を包み込むようにして握った。
触るな、近寄るなと言われたことはあっても、手を握られるのは初めての経験で。
どうしたら良いのか分からず、僕はどぎまぎしてしまった。
「あなたは、何も悪いことなんてしてない。この世に存在してはいけないなんて思い込む必要もない」
幼い子供に言い聞かせるような、優しい口調だった。
「心配要らないわ。あなたには、ちゃんと居場所があるから」
…居場所。
冥界からも追い出され、現世でも行く宛のない僕に、一体何処に居場所があると…。
「僕の居場所って…?」
「ここよ。私の隣。ここがあなたの居場所」
そう言われて、僕はハッとした。
…スクルトの隣が、僕の居場所?
そんなこと言って良いのか。許されるのか?
だって僕は…バケモノで、半端者で、罪人で…。
こんな人間は、何処にも居場所なんてないと思っていた。
…それなのに。
「あなたはバケモノでも罪人でもない。人間よ。私達と同じ人間。孤独に苦しみ、疎外感に悩み、それでも何とか生きる望みを必死に探してる…。誰よりも人間らしい人間よ」
あまつさえこの僕を、人間と呼ぶなど。
何処からどう見ても、人間には見えないはずなのに。
スクルトは当たり前のように、僕を人間だと言ったのだ。
「大丈夫よ。あなたの未来は明るいわ。私もあなたと出会って、初めて気づいたんだもの」
気づいた?
「…何に?」
「世の中は案外、捨てたものじゃないってね」
スクルトは、微笑みながらそう言った。
…そう。そうか。
そんな風に思っても良いんだ。
それは許されることなんだ…。
「…君にそう言ってもらえるなんてね」
確かにそうだね。
君みたいな人に出会って、こんな風に孤独が埋められて。
こんな僕でも、人を愛することを。
その幸福を許されるのなら。
世の中は案外、捨てたものじゃないのかもしれない。
そう思ったとき、僕は初めて世界が色鮮かに見えた。
これまで僕にとってこの世界は、モノクロに等しかった。
だけど、今僕は初めて、世界はこんなに美しかったのだと知った。
スクルトみたいな人に出会えて、その人を愛して愛されて、共に明るい未来を望めるのなら…。
僕がこの世界に生まれてきたことも、あながち不幸ではなかったのかもしれない。
「…ありがとう、スクルト」
「いいえ、どういたしまして」
スクルトは僕達の未来が明るいと言った。
それは『赤』い未来で、保証された運命であると。
だから僕は、すっかり安心しきっていた。
罪人の身に許された初めての幸福を、一身に受け止め。
これからは希望を持って生きて良いんだ。僕も人並みの幸せを手に入れることが出来るんだ。
僕にもその権利があるんだ…。
そんな風に思い込んで、僕は自分が咎を負うべき存在であるということを忘れた。
…だけど、運命は。
僕に課せられた宿命は。
僕が贖罪の義務を勝手に放棄することを、決して許さなかった。
気づいた?
「…何に?」
「世の中は案外、捨てたものじゃないってね」
スクルトは、微笑みながらそう言った。
…そう。そうか。
そんな風に思っても良いんだ。
それは許されることなんだ…。
「…君にそう言ってもらえるなんてね」
確かにそうだね。
君みたいな人に出会って、こんな風に孤独が埋められて。
こんな僕でも、人を愛することを。
その幸福を許されるのなら。
世の中は案外、捨てたものじゃないのかもしれない。
そう思ったとき、僕は初めて世界が色鮮かに見えた。
これまで僕にとってこの世界は、モノクロに等しかった。
だけど、今僕は初めて、世界はこんなに美しかったのだと知った。
スクルトみたいな人に出会えて、その人を愛して愛されて、共に明るい未来を望めるのなら…。
僕がこの世界に生まれてきたことも、あながち不幸ではなかったのかもしれない。
「…ありがとう、スクルト」
「いいえ、どういたしまして」
スクルトは僕達の未来が明るいと言った。
それは『赤』い未来で、保証された運命であると。
だから僕は、すっかり安心しきっていた。
罪人の身に許された初めての幸福を、一身に受け止め。
これからは希望を持って生きて良いんだ。僕も人並みの幸せを手に入れることが出来るんだ。
僕にもその権利があるんだ…。
そんな風に思い込んで、僕は自分が咎を負うべき存在であるということを忘れた。
…だけど、運命は。
僕に課せられた宿命は。
僕が贖罪の義務を勝手に放棄することを、決して許さなかった。
この作家の他の作品
表紙を見る
彼らは夢を見る。毎晩、バケモノに襲われる悪夢を。
彼らは生贄。罪を犯した人間達が生み出したバケモノを、その手で殺すことを宿命付けられた生贄。
彼らは選ばれた。「普通」であることに選ばれなかった彼ら。
裁定者たる天使が振った賽に、選ばれてしまった彼らが辿る運命は。
そして、生贄に選ばれた彼らの抱える、辛く、苦しみに満ちた過去の記憶とは…。
表紙を見る
2019年に作者が携帯小説モバスペbookに投稿した作品を移植しました。
彼らの迎えた夜明けに、祝福の歌を。
表紙を見る
2021年にモバスペbookに投稿した作品を移植しました。
エロマフィア、記念すべき第5弾。
最果てにあるレゾンデートルを、お楽しみください。
※この作品に登場する宗教、教義、宗教組織は全てフィクションです。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…