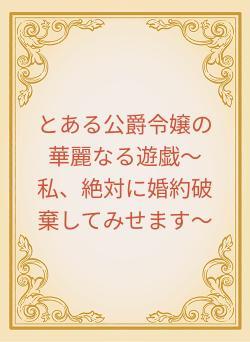確かに、中学時代は朝が苦手な私のために迎えに来てくれていたけど…。
「別に夏希にお世話してもらってたわけじゃ…」
「何言ってんの?あんた、夏希くんのおかげで何度遅刻を免れたことか…。感謝しないとダメよ」
「そりゃ。何度かは、そういう時もあったけど…」
バツが悪くなり、私は母からふいっと、視線をそらした。
そして。
「あ、そろそろ出ないとだ。お母さん、おにぎりとお弁当ありがとう。いってきまーす」
母が用意してくれた朝ご飯用のおにぎりと、お昼のお弁当を手に持ち、私は足早にリビングを後にする。
これ以上、ここに滞在すれば学校に遅刻する上に、母の小言を聞く羽目になることを察知したのだ。
「はいはい。気をつけてね。…まぁ、夏希くんだっていつまでも心春優先ってわけにはいかないってことよね…ハァ…」
ため息混じりに、ポツリと呟いた母の言葉がなぜか耳に残った。
玄関を出て、学校まで続く道を1人進む私。
自分から夏希に"学校ではお互い干渉するのは最低限にしよう"と提案したくせに、母から言われた言葉になぜかチクンと胸が痛む。
「別に…夏希がいなくたって自分でなんとかできるし」
そう言い聞かせるように口に出した言葉を噛み締めて、私は歩くスピードを早めたのだったー…。