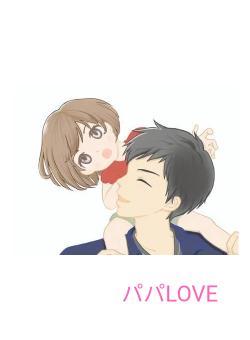私は都内の高校に通う上城真一。高校3年生。高校へは主席で合格し、入学後も成績は常に学年でもトップクラス。高校卒業後は大学に進学するつもりだ。
父は弁護士で母は国会議員をやっているので、両親からは弁護士か検察官、政治家になれと強く言われている。私自身もそんな両親を見て育ってきたので、両親の様な仕事をすることに憧れを抱いていた。
高校生活では3年間、部活は何もやらないできた。唯一やってきたのは勉強。四六時中勉強をしてきた。暇さえあれば参考書を開き、色々な知識を頭に叩き込んできた。休み時間も勉強をしていた。放課後になると、静かな空間を求めて図書室にやって来て、2〜3時間勉強をしてから帰宅する。帰宅してからは家庭教師が19時にやって来て22時まで勉強をした。高校生活は、そのような生活を送ってきた。
私にとって高校とは勉強しに行く場であって、青春を謳歌する場所ではなかった。
友達はというと、特別仲の良い人はいなかった。仲間はずれにされたり、いじめにあっている訳ではなかった。友達が欲しいとか、必要とか思えなかったので、積極的に話しかけたり、話しかけられても一言二言返す程度で楽しみもしなかった。
唯一友達と言えるかどうかはわからないけど、奥村大志という人物がいた。彼にも友達がいなかった。彼はどちらかというと、いじめられるタイプだった。悪く言うと何をやらせても鈍臭いし、トロかった。身長165CM体重100キロという肥満体質は、他の人間から敬遠された。彼は夏でも冬でもいつも汗をかき、タオルで額を拭っていた。暑苦しいとかむさ苦しいと思われていたのだろう。それが原因かわからないけど、クラスのどのグループにも迎え入れてもらえなかった。
そんな友達のいない奥村くんが、友達のいない私に近づいてくるのは自然の成り行きだったのかもしれない。そんな彼のクラスでの立場を見ていたので、私は他の人間と同じようには接しなかったし、どちらかというと好意的に接していた。
「上城くん、パン食べる?」
彼は、休み時間になると買ってきたパンを私に勧めてきた。彼は昼食になるまで待ちきれずに、休み時間になるたびにパンを食べていた。そりゃあ、太るわけだ。
「大丈夫です」
嫌だから断った訳ではなく、お腹が空いてないからそう答えただけだった。だけど彼は少しばかり寂しそうな顔をした。
「上城くん、駅前に焼肉の食べ放題の店ができたんだ。一緒に行かない?」
「大丈夫です」
彼は時々、私を食事に誘ってくれた。でも、私は学校が終わって家に帰れば家庭教師の先生と勉強しなければならない。行きたいと思うことはあっても、断るしかなかった。彼は寂しそうな顔をした。
でも、彼は次の日になれば昨日のことなど忘れてしまったかのように「パン食べる?」「〇〇に食べに行かない?」と聞いてきた。断られるのをわかっていても聞いてきた。面白い人だと思った。
そんな私の勉強一色の高校生活を変えてしまう、そんな出会いがあった。
学校が終わると、いつものように学校から駅までの通学路を歩いていた。住宅街を歩いていると、見覚えのある制服姿の女子生徒が公園に入っていくのが見えた。確か彼女は隣のクラスの···。名前までは出てこなかったけど、隣のクラスの女子生徒に間違いなかった。学校でよく見かける訳ではないけど、彼女の外見は1度見たら忘れることはないだろう。肩まである金髪に鼻ピアス。中々の存在感だ。学校でも異色を放っていた。
それにしても何をしているのだろう? そんな言葉が脳裏をよぎったけど、ここは公園。小休止か遊びに来たのだろう。もしくは人目につかないところでタバコでも吸おうというのだろうか?
いつもなら、それ以上は興味をもつことなどなかったであろう。でも、今日は何故か違った。気づくと物陰に隠れて女子生徒の様子を観察している自分がいた。
彼女は手に持っていた袋から何かを取り出した。
「チビ〜チビ〜」
彼女は手に持った何かをチラつかせながら名前を呼び始めた。すると木の陰から小さな生き物がチョロチョロと姿を表した。白い子猫だった。彼女は手に持っている物を小さく契り、子猫の口元に持って行った。すると子猫は勢いよくムシャムシャと食べ始めた。よほどお腹を空かせていたのだろう。一瞬で全てを平らげてしまった。
「また、明日の夕方に来るからね」
彼女は子猫の背中を優しく撫でながらそう言った。そう言った彼女ではあったが、それからしばらくの間は子猫を触っていた。結局、彼女は1時間以上子猫と戯れてから公園をあとにした。私は一連の出来事を黙って見つめていた。彼女の容姿からは想像できない行いに、只々驚いていた。
彼女のしている行為には賛否両論あるだろう。無責任で軽率な行為だと心無いことを言う人間はいるかもしれない。でも、私にはその行為は善であり決して悪ではなかった。何か力になれることがないか、何か力になりたいとさえ思えた。
私は彼女がいなくなった子猫のそばに行き、その場にしゃがんだ。
「君は誰かに捨てられたんだね。かわいそうに…」
私にはその子猫の頭を撫でてあげることしか出来なかった。
次の日もさらに次の日も、私は学校の帰りに公園に立ち寄った。すると彼女は毎日やって来ては、子猫にご飯をあげていた。毎日かかさずご飯を与えていた。
そんな心優しい彼女ではあるが、学校で会うことはあまりなかった。隣のクラスなので、タイミングが合わなければ会えなかったのかもしれないけど、それにしても会う機会は少なかった。
彼女が学校を休みがちだったというのは、あとでわかった。
それでも、夕方にあの場所に行けば私は彼女に会えた。彼女自身に会いたかったのか? 子猫にご飯を与えている心優しい彼女に会いたかったのか? それはナンセンスだけど、答えを出そうとは思わなかった。
そんな日々が3週間を過ぎようとしていた。今日も電車を乗り継いで、学校へと向かっていた。電車に乗り込むと空席があったので、席に座った。辺りを見回すと彼女がいた。彼女も席に座っていた。どうやら今日は学校に行くようだった。彼女とは時々こうして同じ電車に乗ることがあった。私は気づくと彼女を見ていた。彼女を目で追っていた。
電車が次の駅で止まった。乗車口からは数人が中に入ってきた。年配のご婦人がいるのを目で確認した。
「おばあちゃん、どうぞっ」
私がご老人を目で捉えるのと同時に、声をかけている人がいた。
彼女だった。
一瞬の迷いなど全く無く、声をかけていた。彼女は優しかった。人にも動物にも。人は見かけによらないとよく言うけど、本当にそうだと思った。彼女は金髪に鼻ピアスという、高校生らしからぬ風貌をしてはいるけど、本当に心が優しく美しかった。
彼女の名前は日比野ひかり。直ぐに知ることが出来た。でも彼女は私の名前を知ることも存在自体を知ることもないだろう。
それでも私は彼女の力になりたいと思った。お節介で無責任だと思ったけど、何もせずにはいられなかった。
だから私も毎朝、学校に向かう途中で公園に寄って子猫にご飯をあげた。朝食は私が与えて、夕食は彼女が与える。いつしかこのシステムが出来上がっていた。
でも、いつまでもこんなことを続けて行くことは出来ないだろうし、良くはないのはわかっていた。捨て猫がいるのを近隣の住人が保健所に連絡しないとも限らないし、子猫自体がいつかこの場所を離れてしまう可能性も捨てきれない。どのみち、早く何かの手を打たなければならなかった。
私は急いだ。あの子猫の飼い主を見つけることを…。殆んど交流のないクラスメイトに、子猫を飼ってもらえないか聞いて回った。中学校の時のクラスメイトにも電話で頼んでみたりもした。でも、飼ってくれるという人は見つからなかった。
あの子猫と出会ってから3週間が経とうとしていた。
「上城くん、子猫の飼い主を探してるんだって?」
昼休みに入り、席に座っている私に声をかけてきたのは奥村くんだった。そう言えば、彼にはまだ聞いてなかった。
「そうなんです。色々とあたってはみたけど、まだ見つかってないんです」
「ふ〜ん、そうなんだ」
「困りました…」
「パン食べる?」
「パンですか? そうですね、もらいましょうか?」
「えっ…食べるの?」
「えぇ、まあ···まだ何も食べていないので」
「そっ、そう···これオススメのパンなんだ。食べて」
「はい、ありがとうございます」
奥村くんは、今まで見たこともないような屈託のない笑顔でパンを渡してきた。
「とっても美味しいです」
「よかったぁ」
「上城くん、誰も飼ってくれる人がいないなら、僕んちで飼うよ」
「えっ…本当ですか?」
「本当だよ」
「勝手に決めちゃって親に怒られませんか?」
「大丈夫だよ。僕んち猫を2匹飼ってるんだ。捨て猫がいるって言えば、猫好きの母親が黙ってないよ」
「それならいいんですけど。親に飼えるか確認して下さい」
「わかった」
その日の夜、奥村くんから電話があり、飼っても大丈夫だから早めに迎えに行こうと連絡があった。この日は嬉しくて眠れなかった。
−−翌日
奥村くんと子猫を迎えに行く手順を話し合った。決行日は明後日の土曜日。
午前中に奥村くんが母親と一緒に車で公園まで来てもらい、私があらかじめケースに入れておいた子猫を奥村くんに渡すというものだった。心配はただ1つ…。彼女だった。
突然、あの場所から子猫がいなくなってしまったら、探すかもしれない。保健所に連れて行かれてしまったと、涙を流すかもしれない。ショックを受けて途方にくれることは間違いない。どうすればいいかを考えた。私が自ら名乗り出るのも考えた。それが一番手っ取り早い方法だ。私の口から説明すれば彼女も納得するだろう。でも、それはしたくない。私の勝手なわがままだ。飼い主になる奥村くんに事情を説明してもらおうかとも考えた。でも、これ以上迷惑はかけられない。考える時間などなかった。
−−土曜日
朝の6時前。私は公園に来ていた。人ができるだけ少ない時間に決行しようということになっていた。とは言っても、私たちを邪魔するものは何もなかった。
私は奥村くんから借りてきたキャリーケースに子猫を入れる準備をしていた。
プルルル−−プルルル−−
メールが入った。
どうやら奥村くんを乗せた車が到着したようだ。私は急いで子猫をケースに入れて車まで走った。誰も見ている者はいなかった。公園の前に停まっている車の前まで行くと、後ろのドアが開き、奥村くんが顔を出してきた。
「おはよう」
「おはようございます。よろしくお願いします」
私は奥村くんとガッチリ握手を交わし、母親に頭を下げた。そして何事もなかったように車は走り出した。
夕方になろうとしていた。彼女はまだ来ていない。でも、もうそろそろ来る時間だ。私はいつも子猫がいる場所に、ある物をいれた手提げ袋を置いた。
5分が経過した頃、彼女が歩いて来るのが見えた。彼女は公園の中に入り、いつもの場所まで行くと、手提げ袋があるのに気づいた。彼女は手提げ袋を手に取り、中身を取り出した。私が用意した子猫のぬいぐるみと手紙だった。彼女は手紙を読み始めた。
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
こんにちは
突然のお手紙、驚かれたと思います。
あなたが夕方に子猫にご飯をあげているのを少し前に知りました。
私もそれを見て、朝にご飯をあげることにしました。
でも、このままではいけないと思いました。
保健所に連れて行かれるかもしれないし、子猫が道路に飛び出して事故にあってしまうかもしれません。
悪い人間に捕まって、殺されてしまうかもしれません。
だから、そうなる前に私は飼い主を探しました。
運良く飼ってくださる人が見つかりました。
信頼の出来る人です。
安心して下さい。
今までありがとうございました。
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
彼女は手紙を読み終えると、辺りをキョロキョロと見始めた。
「ありがとう。あなたは誰? どこかにいるの? どこかで見てるんでしょ?」
彼女は叫んでいた。でも、誰も答える訳などなく、公園は静寂に包まれていた。私はとっさに身を隠した。
「ありがとう、親切な人。ありがとう」
私こそありがとう。
この日から、私と彼女の共通の目的はなくなった。彼女と子猫を初めて見た以前の生活に戻りつつあった。でも、私は彼女を色んなところで見た。彼女を見つけるのが上手になっているのかもしれない。もしくは彼女がいないかと、いつもアンテナを立てているのかもしれない。
それにしても彼女は相変わらず誰に対しても親切だった。老人にも子供にも誰にでも親切だった。私には決して出来ない、そんな彼女の姿を見るのが微笑ましかった。
今日は電車の中で彼女を見なかった。隣のクラスを覗いてみたけど、彼女の席は空席のままだった。
「何か私のクラスに用ですか?」
「いえ、何でもないです」
隣のクラスの女子生徒に声をかけられてしまった。
「時々、見に来てますよね?」
「そんなことは…」
強気な女子生徒を前にタジタジになってしまった。
「愛実、どうかした?」
「ううん、何でもない。千夏、行こ」
愛実という女子生徒は目を細めて私を見ていた。私がこうして隣のクラスを覗いているのを、他の生徒にも怪しまれているのであろうか? 気をつけなければいけない。
「上城くん、どうしたの?」
「奥村くん。実はあの女子生徒にちょっと…」
「あぁ…泉田さんね。陸上部のエースだよ。性格キツイらしいよ」
「なるほど…」
「隣にいる鈴木さんは茶道部の部長。美人でおしとやかだから男子生徒からは人気があるんだ」
「そうなんですか。えらい詳しいですね?」
「隣のクラスに中学時代からの友達がいるんだ。そいつから色々と教えてもらっている訳さ」
奥村くんは鼻をこすりながら得意げに話していた。
「金髪の女子がいますよね?」
「あぁ、日比野のことね。あいつには関わらない方がいいよ。あんまり良い噂聞かないし。危ない奴らと付き合ってるみたいだし」
「そうなんですか…」
たぶん、根も葉もない噂だろう。信じるつもりなど全くなかった。
放課後になり図書室に来ているけど、休み時間の出来事が頭をよぎっていた。
泉田さんと鈴木さん…
彼女の悪い噂…
考えないようにしているけど、思い出してしまう。
「はぁ〜」
小さくため息をついた。
「あなた、また勉強してるの?」
集中しようと参考書を読み漁っていると、声をかけられた。顔を上げて見てみると…日比野ひかりさん…その人だった。
「そうですけど、何ですか?」
胸の鼓動がドックンドックンと高鳴っているのがわかった。
でも、何で彼女がここに…
今日は学校には来ていないはず…
「そんなに毎日勉強ばっかりして、どうするの?」
「〝どうするの?〟って、面白いことを聞くんですね?」
「全然面白くないから! 真面目に答えなよ!」
「はぁ···。勉強しといて損することなんてありませんから」
「何か目標があって勉強している訳じゃないの? そんなの意味ないじゃん。そんな曖昧な目標ならやめた方がいいんじゃないの?」
「目標がない訳ではありませんよ。父親が弁護士、母親が国会議員をしているので、両親からは弁護士か検事、もしくは政治家になれと言われています。だから死ぬほど勉強して司法試験に合格するんです」
平静を装ってはいるが、内心いつボロが出ないか心配だった。
「それって親に言われたから?」
「言われたからと言われればそういうことになります」
「ふ~ん、情けないね」
それにしても、何で彼女は私が毎日放課後に図書室で勉強をしていることを知っているのだろうか? 見られてた? そんな訳はない。私は彼女を見ていない。
「日比野さん…ですよね? 隣のクラスの?」
「うん。あなたは上城真一くん」
「知ってもらえてるなんて意外です」
「もちろん知ってるよ。頭いいんだよね」
「頭が良いかはわかりません。勉強で少しばかり良い成績を取れてるだけです」
「それを頭が良いって言うんじゃないの?」
「私は頭が良いことよりも人に優しく出来る人間の方が尊敬できます」
「たとえば?」
「電車の中でお年寄りに席を譲ってあげたり、小さな生き物の命を大切にしたりすることですかね」
あなたのことですよ。これ以上事細かく言ってしまうと、いつも遠くで彼女を見ていることを勘ぐられてしまうかもしれない。これくらいでやめておこう。
「そぉ?」
彼女は嬉しそうに微笑んでいた。わかりやすい人ですね。
彼女は私が勉強している間、図書室の中をブラブラしていた。そして時々戻って来ては、持ってきた本を広げて読み始めた。向かい側に座る彼女の手元を見ると、読んでいるのは飛び出す絵本だった。彼女は絵本をめくるたびに「わぁ」とか「おぉ」とリアクションをしていた。
「クスッ」
「今、笑った?」
「笑ってませんよ」
「バカにしてる?」
「してませんよ」
「だったら何?」
「そうですね···無邪気で可愛いと」
彼女は何も言わずに席を立つと、スキップをして行ってしまった。照れてるのだろうか? 気分を良くしたようにも見える。そんな感じで今日の放課後は終わった。
−−翌日
授業中は彼女のことばかり考えていた。どうして急に図書室にきたのか? あれは明らかに私に会いに来ていた。でもどうして? 答えなど出る訳などないのに、頭の中で自問自答を繰り返していた。
今日の2時間目は数学の授業。教師は太田海斗、28歳。まだ教師になって4年くらいだろう。早稲田大学出身らしく頭は切れた。教え方も上手で生徒の質問に丁寧に答えてあげる熱心な教師だった。太田先生は黒板に問題を書き、生徒に解くよう指示を出した。生徒は自分の机と向き合い、必死になって問題を解こうとしている。そんな姿を見ながら、太田先生は教室内を歩いていた。私の横を通り過ぎた。ふとタバコの匂いが鼻をついた。この匂いはMarlboro。家庭教師が外で吸っているのを近くで嗅いだことがあるので間違いないだろう。それに胸ポケットから見える赤に白の箱は、より一層確信を強めた。でも、校内は禁煙のはず。どこで吸っているのだろうか?
そんなことを考えながら太田先生を見ていたら、前に出て黒板に回答を書くように言われた。特に何の問題もなく答えを解いていく姿に、太田先生は面白くなさそうな顔をしていた。性格は悪そうだ。でも残念ながら、これくらいの問題なら朝飯前だ。
午前中の授業が終わり昼休みに入った。奥村くんと学食に向かっていると、隣のクラスがザワついているのがわかった。学年主任の小島先生が彼女を連れて教室を出ようとしていた。
えっ…何があったんだ?
「上城くん、どこ行く気?」
彼女を追いかけようとする私を奥村くんは制止した。
「ちょっと待ってて」
奥村くんはそう言うと、隣のクラスの中に入り、前に話してくれた中学時代の友達に何かを聞いている様子だった。少し経つと奥村くんは戻って来て言った。
「日比野さん、タバコを吸ってるという疑いをかけられたらしい」
「本当ですか? でも何故それを私に?」
「そっ、それは···僕、こういう類のスキャンダルとか目がなくて」
奥村くんは、もみあげを掻きながら必死になって理由を語ってた。それから食堂でランチを食べながら、奥村くんは詳しい経緯について話してくれた。
「前にも疑われたことがあるらいしよ」
「吸っているのを見られたんですか?」
「不良グループの岩崎が吸ってるのを見つかったらしくて、仲の良い日比野さんにも疑いの目が向けられたって訳さ」
「そうなんですか…」
彼女が心配だった。彼女がタバコを吸っているか吸っていないかはわからない。吸っていようが吸っていまいが、どちらでも構わない。ただ未成年者のタバコの喫煙は法律で禁じられてる。決まりは決まりだ。決まりを破れば罰せられるのは当たり前だ。ただ彼女が心配だった。
こっぴどく怒られてるんじゃないか?
怒られて落ち込んでいるんじゃないか?
心配で仕方なかった。
「今回はタバコを手に持ってたらしいよ。閉まっとけばいいものを、手に持って歩いていたらしい。今回ばかりは言い逃れは出来ないんじゃないかな」
「本当に吸っている人が手に持って歩きますかね? 捕まえて下さいって言っているようなもんですよ」
「確かに言われてみれば…」
昼食を終えた私は、教室に戻る前に1人で職員室に向かった。職員室に入り、学年主任の小島先生の席に目を向けると、小島先生の姿はあるものの彼女は既にいなくなっていた。自然と小島先生の席に向けて足が進んでいた。
「小島先生…」
「上城くんか、どうした?」
「日比野さんが、こちらに来ていると聞いたもので…」
「日比野に何か用でも?」
「はい」
自分でも思い切った行動に出たと驚いていた。
「今は別の教室で教頭先生から色々と聞かれている頃だ。君みたいな優等生が日比野なんかと付き合わない方がいいと思うぞ」
「あの、日比野さんが持っていたというタバコは? ちょっと確認したいことがあって…」
「そうなのか? 特別だぞ」
小島先生は不審そうな顔をしながら机から例のタバコを取り出した。
「こっ、これは…先生、4組の3時間目の授業は数学ではありませんでしたか?」
「私の授業の前は確かに数学だが。それが何だ?」
「なるほど…」
私は小島先生に確認してもらいたいことがあると伝えてから職員室をあとにした。多分もう大丈夫だろう。
−−放課後
いつものように図書室で勉強をしていた。今日は私らしくないことをした。少し疲れた。
「今日も勉強? 他にすることないの?」
「えぇ、まぁ…」
昨日に続き、今日も彼女はやって来た。
「放課後に図書室に来て、毎日勉強している人なんて、あなたくらいなものよ」
「駄目ですか?」
「駄目に決まってるでしょ!」
「どうしてですか?」
「どっ、どうして? だっ、駄目なものは駄目なの! 理由なんてないわ!」
「勉強は楽しいですよ」
「私は嫌い。社会に出て数学の方程式なんて使わないし、何のために勉強してるのかわからない」
「将来の夢は?」
「特にない。早く就職して独立したい」
「そうですか」
「それより、聞いてよ。今日、学年主任の小島と数学の太田に頭を下げられちゃった」
「何かあったんですか?」
理由は聞かなくてもわかった。
「実は私、タバコを手に持ってたら吸ってるって疑われたの。でも持っていたタバコが太田のだってことがわかって、アイツら慌てて謝ってきたって訳なの」
「それは良かった」
「誰かが私の持っていたタバコは太田の物だってことを言ってくれたみたいなの。一体誰だったんだろう?」
「私にはわかりかねますけど、疑いが晴れてよかったですね」
「本当はあなたが助けてくれたんじゃないの? ってそんな訳ないわね」
「はい、私ではありません」
何はともあれ一件落着です。
−−今日は土曜日。
午前中から最寄りの駅から5分くらいにある図書館に来ていた。もちろん目的は勉強をするためだ。快適な空間で勉強がはかどっていたので時間が過ぎるのを忘れてしまっていた。気づくと午後の2時になっていた。軽い昼食を取ろうとコンビニに寄ることにした。
「あっ…」
偶然にしては運命を感じぜずにはいられなかった。彼女が本を立ち読みしているのが、外からでもわかった。声をかけるかかけないかを考えていた。プライベートな休日の時間に私が入り込んでいいか迷った。しばらくは彼女に気づかれないように、外で様子を伺っていた。動く気配が全くなかったので、とりあえず店内に入ってみた。
買い物をしていて彼女が私に気づいたのなら気づかなかったふりをしよう。私はサンドイッチとサラダをカゴに入れ、レジの横にあるホットコーナーを見ていると、中学生くらいの男子の4人組が騒ぎながら店内に入ってきた。それとタイミングを同じにして、彼女が動き出した。彼女はチョコレート売場に行くと、商品を手に取って何を買おうか迷っていた。
すると先程の4人組がチョコレート売場の隣りにあるカード売り場の前にやって来た。その中のAがやたらと周りをキョロキョロと見回し始めた。あからさまに怪しかった。考えられるのは唯一つ。万引きをしようとしている。先程のAは見張り役と言ったところだろう。彼女は未だにチョコレートを手に取り選んでいた。このままだと、万引きに巻き込まれる恐れがある。念のために…。
私は物陰でことの成り行きを見守った。とうとう4人組の3人が動き始めた。実行犯と思われるBの前にCが立って店員の死角を作り出した。Dは店で1番安い10円のお菓子をレジに持って行って買い物をし始めた。2人いる店員はレジで接客をしている状態。まさに万引きをするには絶好の場面を作り出していた。そして実行犯のBがカードを手に取ると、素早くポケットに押し込んだ。それからもBはカードを何度か手に取ってはポケットに押し込んだ。かなりの数を万引きしていた。許せない行為だ。そして満足したのか、実行犯のBが他のメンバーに声をかけると、逃げるように店を出て行ってしまった。店員の2人は、まだレジで接客中だった。マズイなと思った。
ところが次の瞬間···
2人しかいないと思っていたレジの店員とは別の店員がレジ横の扉から飛び出してきた。
「ちょっと君いいかな?」
「何ですか?」
案の定、彼女は万引き事件に巻き込まれてしまった。
「事務所に来なさい!」
「ちょ、ちょっと待って…」
彼女は腕を捕まれ、連れられて行ってしまった。私は買い物カゴを床に置くと、店の外に出てダッシュをした。万引き犯たちを必死に追いかけた。しばらく走っていると、彼らに追いついた。彼らはバカふざけをしながらゲームセンターに入って行った。
私は直ぐに警察に電話をして、事情を事細かく説明した。そして中の様子を覗うと、4人組の連中は呑気にゲームをして遊んでいた。今頃、コンビニでは彼女は事情聴取をされているだろう。早くしないと···。
私は次にコンビニに電話をした。信じてもらえるかわからないけど、彼女は万引き犯とは無関係であること、事実無根であることを必死に訴えた。そして隠れて撮っていた万引きの瞬間をとらえた動画を店舗責任者に送った。また、万引きが行われた時刻を教えて、店の防犯カメラの映像を確認してもらうようにお願いした。
電話を終えると、制服を着た警官が3人でやって来た。私は警官に説明をし、動画を見せた。既に私の周りには警官が6人くらい集まっていた。そして数名の警官が中に入り、残りの警官か外で見張りをしていた。数分後、警官は4人を連れて店から出てくると、停まっていたパトカーに乗せて走り出した。
もう大丈夫でしょう。私は買い物カゴに商品を入れたままにしていたのを思い出し、コンビニに引き返した。
コンビニに戻って来ると、商品が入ったカゴはそのままになっていた。お会計を済ませにレジに持って行った。店員が商品のスキャンを終えて財布からお金を取り出していると、レジの横の扉から彼女が何食わぬ顔で出てきた。
「あれ? 上城くん?」
「どっ、どうも…」
彼女は商品がパンパンに入った袋を手に持っていた。
「買い物?」
「えぇ、まぁ…」
「何か歯切れが悪いわね」
「そうですか? そんなことないですけどね…」
あんなことがあった直後にも関わらず、意外にも彼女は元気そうだった。
「これ、お店の人にもらったの。一緒に食べない?」
「いいですけど、持って帰って食べた方がいいんじゃないですか?」
「いいの、いいの。イッパイあるから」
それから近くの公園に行き、空いてるベンチに2人で腰かけた。
「サンドイッチ買ったんですけど、食べませんか?」
「お昼まだ食べてないの?」
「えぇ。たまごとツナはどちらが好きですか?」
「たまご」
私と彼女は黙ってサンドイッチを食べた。
「フンフン♪フンフンフ〜ン♪」
彼女は足をバタつかせながら、鼻歌を歌っていた。
「何も聞かないのね?」
「聞いた方がよかったですか?」
「別に」
「元気そうで何よりです」
「フンフンフン♪フンフンフ〜ン♪」
彼女は何も答えず、鼻歌を歌っていた。
−−2日後
教室の窓から彼女が登校する姿が見えた。バイクの後ろに乗せて来てもらったようだ。彼女はバイクから降りると、バイバイと手を振って見送っていた。
「バイクの人、暴走族の総長だよ」
窓の外を眺めている私の隣で奥村くんがそう言った。
「そうなんですか…」
「日比野さん、暴走族のメンバーって噂になってるよ」
「詳しいですね?」
「中学から一緒の友達が情報ツウなんだ」
「あぁ、隣のクラスの上尾くんですね?」
「うん。結構、ネタがあるみたいだから今度聞いとくよ。それより、日比野さんと仲の良い6組の棚橋くんも暴走族と関係があるらしいんだ」
「何か悪いことに巻き込まれなきゃいいんですけどね」
「心配? だよね?」
「えぇ…」
いつからだろうか? 奥村くんは私が日比野さんに関心があると思っているらしかった。
−−放課後
「ここ座るわよ」
「またあなたですか?」
そんな言い方をしたけど、胸が高鳴るのを感じていた。
「何か文句ある?」
「ありませんけど…」
「何なの? 来ちゃ悪いの?」
「悪くはないです」
「だったら座ってもいいでしょ?」
「どうぞ」
「フフッ」
彼女はイタズラっぽく微笑むと、私の向かい側の席に座った。
「それにしても図書室って空気が重いわね。息苦しい」
「1つ聞いてもいいですか?」
「何?」
「どうして居心地の悪い図書室に毎日のように来てるんですか?」
「あっ、あなたになんて答える必要ないわ!」
顔を真っ赤にして、ムキになってそう答える彼女は何だかとても愛おしかった。
「そうですか…」
素直じゃないのはお互い様ですけどね。
「今日、日比野さんが登校する姿を見ましたよ」
何かを確認したい訳ではなかったけど、思い切って切り出してみた。
「あっそう。それで?」
彼女は、やはり触れてほしくはないようだった。あからさまに、怪訝そうな顔をしていた。
「いや、何でもありません」
「私のこと見てたんだ?」
「えぇ、まぁ…」
「ストーカー?」
「では、ありません」
とは言え、最近の私は彼女に遭遇することが多々あり、変な誤解を招く可能性は十分にあった。
「じゃあ何? 私のこと気になるんだ?」
「ハハハハハ…」
それはあなたの方でしょうとは口が裂けても言える訳もなく、笑ってごまかすので精一杯だった。
「笑ってごまかすな! もしかしてストーカー?」
「違いますよ…」
「やだぁ、怖い〜〜」
「何でそうなるんですか?」
「私のクラスの中を覗き見している男子がいるって愛実が言ってたんだよね。もしかして?」
「はい、私ですよ」
彼女が言う愛実と言うのは、あの気の強そうな泉田さんのことだ。確かに疑いの目で見られてたような…。
「誰を見てたの?」
「窓際の席の後ろから2番目の女子に少しばかり興味があって」
「ふ〜ん、その子とはどうなったの?」
「特に何の進展もありません。でも、まだわかりません」
「乞うご期待ってヤツね」
そう言うと、彼女はポケットの中から取り出したキャンディーを私にくれた。
「じゃあ、また明日」
彼女はスキップと言えなくもない軽快な足取りで図書室を出て行った。
−−翌日
図書室に入ると、まず初めにすることは彼女を探すこと。読みたい本を探す訳でもなく、図書室の中を探索した。
あっ…
すると、手を後ろに組みながら、つまらなそうに歩いている彼女の姿を目に捉えた。彼女は私には気づいていない。私は彼女の姿を確認すると、席についてカバンから参考書を取り出し始めた。
「やっほー」
しばらくすると私の存在に気づいた彼女が足早にやって来てそう言った。
「どうも」
「奇遇ねぇ」
「必然ですね」
「何それ?」
「出会うべくして出会ったということです」
彼女の目的は私。私に会うために来ている。彼女は授業に出ていない日も、放課後になると図書室にやって来た。ただ私に会うために。私は勉強をするために図書室に来ている。将来のために勉強をしに来ている。彼女がいれば勉強などはかどるはずはなかった。実際に彼女と図書室で会うようになってからは、私のノートは空白のままだ。そんなことはわかってて図書室に来ていた。だとするならば私は勉強をするという口実で彼女に会いに来ているということになる。つまり、私は彼女に会いたかった。
「何ですか?」
「何?」
「先程から私が勉強しているのを、ずっと見ていますけど」
「いけない?」
「構いませんけど、やりづらいです」
彼女は私の真向かいの席に座ると、両手を頬に当てて私を凝視していた。
「気にしないで! 邪魔はしないから」
「そう言われても、ちょっと…」
「いいから早く続きをやりなさいよ!」
彼女は私のシャープペンを手に取ると、白紙のノートをトントン叩いてきた。
「・・・・・。やっぱり集中出来ませんよ」
「だったら休憩しようよ」
「ふぅ~。そうすることにしましょう」
−−翌日
今日も放課後になり図書室にやって来ると、彼女の姿を探しに室内を歩き回った。
あれ?
おかしいなぁ?
まだ彼女は来てなかった。授業には出ているのは確認済みなので、まだ学校にいるはずなのに…。どうしたのだろう?
仕方なく席について机と向き合ってみたものの、彼女の顔ばかりが頭に浮かんでしまい、勉強どころではなかった。
気がつくと図書室の建物から外に出て彼女が来るのを待ちわびている私がそこにいた。いくら待っても来なかった。席に戻り参考書を開いても、何も身につかなかった。
「上城くん、もう閉館の時間になるわよ」
図書室の職員の佐々木さんに声をかけられた。しかも名前を覚えられてる。時計を見ると、閉館時間の18時になろうとしていた。
「すいません、今片づけて出ます」
「金髪の子、来なかったわね。日比野さんって言ったっけ?」
「あっ、はい」
「いつも早くに来てあなたを待ってたんだけどね」
色々とツッコミどころが満載だけど、私たちの情報は筒抜けのようだ。帰り支度を済ませて外に出たものの、直ぐに帰る気にはなれなかった。しばらくは、部活帰りの生徒たちの様子を眺めていた。
15分くらい経った頃、遠くの方から鼻歌交じりにテンポよく歩いてくる彼女の姿があった。
「今日は遅かったですね? 図書室から閉め出されましたよ」
「先生に職員室に呼び出されちゃって」
「どうかされたんですか?」
「別に」
「大丈夫なんですか?」
「何が?」
「学校を辞めさせられるようなことはありませんよね?」
「どういう意味? もしかして私が悪さして退学になるんじゃないかと思ってる?」
「違いますよ」
彼女が怒るのは無理もなかった。私の言い方が悪かったのは自覚していた。
「どうせあなたには私が不良にしか見えないんでしょ? 学校サボって悪い連中と付き合って、タバコ吸って、万引きして人に迷惑ばかりかけてる世の中の落ちこぼれくらいにしか見えてないんでしょ?」
彼女は持っていたカバンを地面に叩きつけて怒っていた
「誤解です。私はただ、あなっ‥」
「いいよ! いつも言われてることだから。でも、あなただけにはそんな風に思われたくなかった!」
「すいません。謝ります」
「うるさいっ! バカッ!」
彼女はそう吐き捨てると、地面のカバンを乱暴に拾い上げ走り去ってしまった。一瞬だったけど、彼女の頬に光るものが見えたような気がした。
−−3日後
「今日もあの子来なかったわね?」
「はい、もう3日になります」
図書室の閉館の時間が近づいたので片づけをしていると、職員の佐々木さんに声をかけられた。彼女が図書室に来なくなって、早くも3日の時が流れていた。彼女に会えない日々はとても長く感じられた。
「ケンカでもしたのかい?」
「ケンカという程のものではなかったはずなんですけど、誤解されてしまったようです」
「そうなのかい。それなら早く謝って仲直りするといいわね。時間が経てば経つほど修正が効かなくなるものよ。私みたいな図書室のおばさんの言うことも、たまには役に立つんだから」
「はい、ありがとうございます。それにしても、いつも騒がしくてすいません。迷惑じゃないですか?」
「迷惑ねぇ…それは、あなたじゃなくてあの子の方だけどね。それに、あなたたち以外に放課後に図書室に来る生徒なんていないから、来てくれるだけ嬉しいし有り難いわ」
「そう言ってもらえると助かります」
私の言い方のせいで彼女に不快な思いをさせ怒らせてしまったのは事実。不可抗力だったとしても、傷つけてしまったことへの言い逃れは出来ない。あれから彼女は学校にも来ていなかった。こんなことなら連絡先を聞いておくんだった。とは言え、いまいち進展しない私と彼女の距離感では、連絡先を交換するのはもう少しあとかもしれないし、今の距離感は決して嫌いじゃなかった。でも、彼女と離れて気がついたこともあった。私は彼女のことをもっと知りたいし、今よりもっと近づきたい。
彼女が学校に来なくなって1週間になる。私のせいだ。私が彼女を傷つけるようなことを言ったから。会って謝って許してもらい、今までのように戻りたい。そうしないといても立っても居られない。彼女に会えないと心が締めつけられるように苦しい。会いたい。こんな気持ちは初めてだ。
今は少しでも彼女に関する情報が欲しかった。私は昼休みになると隣のクラスの前のドアから中の様子を覗っていた。彼女の友達の鈴木さんを探した。でも、鈴木さんの姿はどこにもなかった。もう1人の友達の泉田さんもいないところをみると、2人で学食にでも行っているのかもしれない。
「あれ? あなたは確か…」
後ろから声をかけてきたのは、鈴木さんだった。鈴木さんの横には私を睨んでいる泉田さんの姿もあった。
「すいません、日比野さんは今日も学校へは来ていませんか?」
「日比野さん? あぁ、ひかりのことね?」
「はい。その日比野さんは今どこに?」
「今日は来てないわよ。っていうかさ、あなた5組の上城くんだよね?」
「はい、そうですけど」
「やっぱりね。でも、どうして成績も学年でトップクラスの上城くんが、ひかりなんかと知り合いな訳? 何か弱みでも握られてる?」
「そういう訳じゃありませんけど…。あの、日比野さんはどういう方なんですか?」
私と鈴木さんが話している横で、不服そうな顔をしている泉田さんがチラチラと視界の片隅に入ってくる。
「ひかりは、家庭の問題とか色々あって、あんな風になっちゃってるけど、優しくて友達想いで、真面目で本当に良い子よ。髪は金髪で不良っぽいし、授業も殆んど出ないけどそんなんじゃないわよ」
「随分と、日比野さんのことを詳しいんですね?」
「まぁね。だって私ひかりの親友だもん。中学時代からの付き合いよ。ちなみに私は、鈴木千夏。よろしくね」
「よろしくお願いします」
「こっちも中学からの友達の泉田愛実」
「よろしくお願いします」
「フンッ」
泉田さんは目を細めて私を見ると、そっぽを向いて教室に入ってしまった。
「私、嫌われてます?」
「まぁ、色々とあるのよ」
「そうですか…」
鈴木さんが言っている“色々”が何かはわからないけど、泉田さんを不快にさせるようなことをしたのは間違いないようだ。
「ひかりには、上城くんが訪ねて来てくれたことメールで送っとくね」
「お願いします」
−−翌日
もう1度隣のクラスに顔を出してみた。すると私の顔を見るなり、鈴木さんが走ってやって来てくれた。
「日比野さんは今日も来てないんですね?」
「うん。メールを送ったんだけど、返信はなかったのよね」
何となくそうなるんじゃないかとは予想出来た。私は自分の謝罪の気持ちを伝えるためにはどうしたらいいかを、昨日家に帰ってから考えた。考えた結果、ある1つの答えを導き出した。それは手紙で思いを綴り、読んでもらう。言葉では上手く伝えられない思いでも、手紙ならきっと伝えられる。話は聞いてもらえないけど、手紙なら読んでもらえるかもしれない。だから私は昨日の晩は遅くまでかけて手紙を書いた。読んでもらえるまで毎日でも手紙を書いて行こうと決意した。
「手紙かぁ。いいかもね」
「良かった」
「私も、ひかりがこのままだと困るし、出来ることはやらせてもらうわ」
鈴木さんに手紙のことを説明すると協力してくれると言ってくれた。
「ありがとうございます」
「私がひかりに直接渡してきてあげる」
「ちょっと待って。その役、私がやらせてもらうわ」
私と鈴木さんの会話を聞いていた泉田さんが話に割って入ってきた。しかも、泉田さんが手紙を渡してくれると言ってきた。あんなり私を毛嫌いしていた泉田さんが急に協力的に…。にわかには信じられなかった。
「ホントに? 愛実に任せていいの?」
「任せてちょうだい。私だって愛実に早く学校に来てもらいたいし」
「ご協力ありがとうございます」
そして、私は昨日書いた手紙を泉田さんに預けた。
あれから1週間が経った。手紙は5通書き、全て泉田さんに渡した。でも、何の反応もなかった。おかしいなぁ、ちゃんと読んでもらってるんだろうか? 読んでるのに無視されてる可能性もある。心配になってきた。とりあえず今日も、昨日書いた手紙を泉田さんに渡した。今日は確認したいことがあった。
放課後になると、図書室は行かずに廊下の隅に隠れて隣のクラスを監視した。
「上城くん、何やってるの?」
「泉田さんが出てくるのを待ってるんです」
「どうして?」
「泉田さんが私の手紙をちゃんと日比野さんに渡しているかを確認するためです」
「そうなんだ」
「って言うか、何で奥村くんがここに?」
「泉田さんのあとをつけるんだね?」
「まっ、まぁ、そういうことになりますけど…」
「僕も一緒に付き合うよ」
泉田さんの尾行に奥村くんも来ることになった。心強いと言えば心強い。
それから私たちは泉田さんを尾行した。泉田さんは学校を出ると、駅の近くのMACに立ち寄った。泉田さんの席には、ハンバーガーとポテトとドリンクが置かれていた。とりあえず、私はドリンクだけを注文し、奥村くんはセットメニューを注文した。泉田さんを見ると、スマホを操作しながらダラダラと食事をしている。動画を見ているらしく、時折笑顔が溢れていた。時間がかかりそうだ。
それからも泉田さんは食べては動画を見るという行為を繰り返し、30分ほどMACに滞在した。店を出ると今度は本屋に入り、立ち読みを始めた。
「泉田さん、手紙届ける気ないんじゃないのかな?」
「もう少し待ってみましょう」
「本当に届ける気があるなら、こんなに寄り道しないよね?」
「確かに…」
奥村くんの言う通りかもしれない。ちょっと寄り道しすぎだ。
15分経ち満足したのか、何も買わずに店を出て駅に向かった。改札を抜けて向かった先は下りのホームだった。
「自宅に向かってない?」
「日比野さんの家へ行くなら上りですからね…」
「まだつけるの?」
「ここまで来たら、最後まで見届けたいです」
「わかった。でも絶望的だと思うよ」
「はい…」
3つ目の駅で電車を降りると、今度は駅構内にあるコンビニに寄っていた。見つからないように外で待っていると、片手に買い物袋を下げて出てきた。ポテトチップなどのお菓子が入っているのが袋の外からでもわかった。
「家帰るまで、どんだけ寄り道するんだよ」
奥村くんは声を荒らげて、そう言った。
「奥村くんっ」
奥村くんの腕を引っ張って、建物の影に隠れた。奥村くんの声に反応した泉田さんが辺りをキョロキョロ見回していた。しばらくは息を潜めて、泉田さんが歩き出すのを待った。
ようやく歩き出したかと思ったら、駅から5分くらいの所にある公園に寄ってベンチに座ると、先程買ったお菓子を食べ始めた。時刻は19時を回っていた。いつもこんなことをしているのだろうか? 泉田さんは就職クラスだけど、他にするべきことがあるのではないだろうか?
お菓子を食べ終わった泉田さんが、そのあと自宅に帰ったのは言うまでもなかった。
「こうなるとわかってたけど、頭くるよね。手紙はどうしたんだよ!」
「今までも渡してなかったということですね」
「明日、泉田さんに言おうよ」
「いえ、見なかったことにしましょう」
奥村くんは納得していない様子だった。
泉田さんは自分から手紙を渡すと言ってくれた。信じて渡していたのに裏切られた。でも、不思議と怒る気持ちにはなれなかった。
−−翌日
隣のクラスを覗いていると、鈴木さんが直ぐに駆け寄って来てくれた。
「あの、日比野さんは?」
「今日も来てないわよ。そういえば手紙を書いて渡してるんだよね」
「えぇ、まぁ…」
手紙という言葉を聞いて、何も言えなくなってしまった。
「愛実に渡してもらうよう頼んだんだよね?」
「そっ、そうなんですけどね…」
「おかしいわね。ひかりのことだから、手紙を読んだなら何かしらの反応があってもいいんだけど…」
「・・・・・」
「ちょっと待って…もしかして、愛実のやつ渡してないんじゃ…」
鈴木さんはそう言うと、泉田さんが座る席まで歩いて行った。遠くから見ていても、鈴木さんが泉田さんに対して声を荒らげて怒っているのがわかった。
パシッ…
次の瞬間、鈴木さんが泉田さんの頬を思いっきり引っ叩いていた。
すると泉田さんは、両手を顔に当てて泣き出してしまった。普段の温厚な鈴木さんとは思えない行動に唖然としてしまい、見守ることしか出来なかった。
「えぇぇ…」
そこまでしなくても…
「上城くん、本当にごめんなさい。愛実、手紙を渡してなかったの」
私のところに戻って来た鈴木さんは、深々と頭を下げて謝ってきた。
「みたいですね」
「知ってたの?」
「昨日知りました」
「そうなんだ。ホントにごめん」
「もういいですよ」
「愛実はひかりのことを妹のようにかわいがってたから、上城くんに取られるんじゃないか心配だったんだと思う。悪い子じゃないの。それに上城くんのことも決して嫌ってる訳じゃないのよ」
「ひかりさんの親友が悪い人の訳ありません。あまり怒らないであげて下さい」
「ありがとう。本当に優しいのね。ひかりが好きになる気持ちもわかる気がする」
「・・・・・」
「ごめん、余計なこと言っちゃった」
「いいえ。それにしても心配ですね」
「そんなに心配なら、ひかりの自宅に行ってみたらいいじゃない? どお?」
「そうですね。行ってみます」
最初からそうしとけば良かったのかもしれない。
「ちょ、ちょっと待って。もしかしたら自宅にはいないかもしれない。今、地図書くから待ってて」
「ありがとうございます」
「はい、これ。ここに行けばひかりに会えると思うわ。十分気を付けてね」
「そんなに危険なところなんですか?」
「そうねぇ、危険ね。威圧的な態度をとってくるかもしれないわね」
「そんなに危険なところで、日比野さんは何をしているんですか?」
「上城くん、ひかりを危険な輩から救ってあげて!」
「わっ、わかりました。任せて下さい」
鈴木さんの言う危険なところがどこかなどわかるはずもなく、只々不安が募る一方であった。
学校が終わると、鈴木さんから渡された地図を頼りに、彼女がいるという場所に訪れた。
あれ?
ここって…
地図が間違っているのだろうか?
「すいませ~ん」
とりあえず中に入って、彼女に繋がる情報がないかをあたってみることにした。
「は~い。いらっしゃいまっ‥あっ…」
「日比野さん、ここで何を?」
「上城くん…」
私の前に現れたのは、私服にエプロン姿の彼女だった。
「もしかして、ペットショップでアルバイトしているんですか?」
「どうしてここが?」
「鈴木千夏さんに聞きました。〝ひかりを危険な輩から救ってあげて〟って言われて。まさかこんなところにいたなんて想定外でした」
「ヴヴゥゥゥ――ワンワンッ!」
「ワンワンワンッ!」
「ガルルルル――ワンワンッ」
ゲージの中に入っている犬たちが、突然私に向かって一斉に吠え始めた。
「私、何かやたらと吠えられていませんか?」
「いつもはおとなしいのに今日はどうしたんだろ? やっぱり動物にも良い人間か悪い人間かは、わかるものなのね」
「私は悪い人間だと思われたんでしょうか?」
「当然よ。私のことを不良とか言って、傷つけたんだから…」
「言ったのは私ではないんですけどね」
「言ったようなものよ」
「少しいいですか?」
「何? 何かよう?」
「話を出来ませんか?」
「・・・・・」
彼女は戸惑いを隠せない様子だった。
「店長〜」
沈黙の後、彼女は店の奥にいる、この店の店主を呼んでいた。
「休憩してきていいよ。ひかりちゃんにお客さんなんて滅多にないからね」
女性の店主は私が彼女を訪ねてきたことに気づいたらしく、嫌な顔ひとつせずに笑顔でそう言ってくれた。
「店長ありがとう。直ぐに戻って来るから」
それから私たちは住宅の一角にある公園に移動した。
「今日も学校には来ませんでしたね?」
「バイト先まで押しかけるなんて趣味悪いわよ!」
「急に来なくなるから、気になって勉強に身が入らないんです」
「私には関係ないわ!」
「もう来ないんですか?」
「どうして行かなきゃいけないの?」
「それならどうして私が勉強している図書室に来て、いつも私の隣に座っていたんですか?」
「いたいからいただけよ。何か文句ある?」
「もちろんありますよ」
「何よ! 言ってみなさいよ!」
「突然私の前に現れたと思ったら、私の世界にズケズケと入り込んで来て…気付いたら傍にいるのが普通になっていて…ちょっとしたイザコザで誤解されたと思ったら、突然私の前から消えてしまって…」
「何が言いたいのか全然わかんないんだけど?」
「つまりですね。勝手に私の前からいなくならないで下さい! 気になって勉強に手がつけられないし、毎晩胸の辺りが苦しくて眠れないんです」
「そんなの私のせいじゃないもん。私があなたの恋人ならまだしも、付き合ってる訳でも何でもないじゃない。私に言われても困るんだけど…」
「それなら、私と付き合って恋人になってもらえませんか?」
「嫌よ」
「どうしてですか?」
「絶対後悔したって思うに決まってるもん」
「もう既に後悔していますよ。あなたに出逢うまで無駄に17年も生きて来てしまったことを…」
彼女は何も言わずに、両手で目をこすっていた。
「好きなんですよ。あなたのことが」
「私だって…」
こうして私と彼女の恋は始まった。
私が彼女の彼氏になってから1週間が経った。電話番号とメールアドレスの交換はしていたので、いつでもどこでも繋がっていられた。彼女は思いのほか、独占欲が強いし束縛も強かった。でも特に嫌だとは思わなかった。お互い初めての恋人だったので、とにかく毎日がドキドキで楽しかった。何もしてなくても嬉しくて自然と笑みがこぼれてしまう。世界の色が何色か増えて明るくなったようだった。好きな人が恋人になるのが、こんなにも幸せだとは知らなかった。
いつも一緒にいたい。
顔を見ていたい。
声が聞きたい。
話がしたい。
見つめ合っていたい。
何ならキスをしたい。
あげればきりないくらい彼女に夢中の私がいた。そんな気持ちもあれば、逆に心配や不安もつきまとう。
どこにいるのか?
誰といるのか?
異性と会っていないか?
異性と話していないか?
この気持ちを払拭したくて連絡をする。声を聞くだけで気持ちが落ち着く。そんなことをしなくも彼女が私に夢中なのはわかっているはずなのに…。
また、彼女は1日に電話を何十回としてくる。朝だろうと昼だろうと夜中だろうが電話をしてくる。電話に出ないと怒る。メールは1日に50回は優に越える。もちろん返事をしないと怒る。彼女がしなくても、もしかしたら私がしていたかもしれない。それだけ恋は盲目なのだ。
彼女は毎朝、駅の改札口で待っていてくれた。そして学校までの通学路を一緒に歩いた。彼女は終始私と手を繋いだり抱きついたりしてきた。周りの視線を気になりつつも、少しばかり優越感に浸った。
学校では休み時間になると私の教室にやって来ては、前の席に座ってお喋りをした。昼食も食堂で一緒に食べた。放課後は教室に残って動画を観たりして楽しんだ。帰る間際になると、彼女はいつも目に涙を溜めて「帰りたくない」と涙ながらに訴えてきた。だからしばらくは電車のホームのベンチに座って手を繋ぎ、ただ行き交う人を眺めていた。
家に帰っても電話で何時間も話をした。夜中に突然電話してくることもあった。彼女は私に会いたくなると夜中でも会いに来た。私らしくないけど、私から会いに行ったこともある。こうして私と彼女は四六時中一緒にいた。
今日も1日中彼女といた。でも、放課後になると教室に来るはずの彼女が何故かやって来なかった。隣のクラスに行き、教室に残っていた鈴木さんに訪ねてみた。
「何も言ってなかったけど、どうしたのかな?」
鈴木さんはそう言った後、彼女に電話をかけてくれた。
「電源入ってないね」
「さっきはコールはしたんですけど…」
「バイトとか急用じゃないのかな? ひかりのことだから、上城くんに何も言わずに帰ることなんてないと思うんだけどな…」
「そうですよね」
そう言ったものの、嫌な予感が脳裏をよぎっていた。もしかしたらと思い、図書室を覗いてみたけど彼女はいなかった。何だか嫌な胸騒ぎがして、このまま図書室で勉強をする気にはなれなかった。
そのまま図書室を出て、校門に向かって歩いていると、校門を抜けた先には見慣れないガラの悪い連中が3人ほどいた。目を合わせないように下を向いて歩いていると、私の前を何かが立ち塞がった。顔を上げると先程の連中だった。
「おいお前、上城真一だな?」
「はい、そうですけど…」
私の名前を呼んだこの人は決して私の知り合いではない。目も合わせてないし、彼らの気に障るようなことはしてはいないはず…。声をかけられる覚えはない。私に声をかけてくるなんて、どういう要件だ。
「ちょっと顔かせや?」
「はい…」
そう言うと、校門から少し離れた場所まで連れられて来てしまった。
「俺らは、この辺一帯を取り仕切ってる龍神会っていう暴走族のもんだ」
「そんな方たちが私に何のようでしょう?」
「うちの総長がお前にこれを渡してこいってな」
彼らのうちの1人から半紙と思われる紙を渡された。
「読んでみろ」
「はい」
四つ折りにされた紙を広げると、そこには筆で書かれたプロ並みの達筆の文字が綴られていた。
「すごい達筆ですね」
「いいから、さっさと読め」
目を通すとそこには…
【日比野ひかりは預かった。返して欲しければ、18時に1人で〇〇埠頭の第三倉庫に来い。警察や誰かに知らせたら面倒なことになるからな】
この文章を読んだ限り、彼女は暴走族に拉致されたらしい。色々とツッコミどころがあるけど、18時までに1人で行かなければならない。
「遅れずに来いよ」
「わかりました」
連中は私の体にワザと肩をぶつけると「じゃあな」と言って去って行った。それにしても大変なことになった。本当に私一人で行って大丈夫なのだろうか? 不安しかなかった。でも、 迷っている暇はなかった。
直ぐに学校までタクシーを呼んだ。親から渡されていたタクシーチケットを使って指定された場所に向かった。そして、目的の場所の近くで降ろしてもらうと、第三倉庫が見えてきた。ここに彼女が捕まっているのか…。
倉庫の前まで来ると、バイクのエンジンをふかしている爆音が嫌になるほど聞こえてきた。地面が揺れ体が震えているような感覚に陥った。倉庫の中に入り、恐る恐る歩みを進めていくと、突然おびただしい数の光に照らされた。一瞬目がくらんだけど、それがバイクのライトだというのが徐々にわかってきた。バイクには特攻服を身にまとい、金属バットや鉄パイプを手に持った連中が何十人といた。
「よく1人で来たな。大したもんだ」
バイクがずらっと並べてある1番奥から出てきた人物がこちらに歩いて来てそう言った。男は身長が190cmを超えるような大男だった。ガタイもかなりいい。
「来ました。約束ですから」
「俺はこの暴走族の総長の柏木だ。あんた俺たちがどういう人間かわかって来たんだろ?」
「はい…」
「そうか、来たのは褒めてやる。でも、ただで帰す訳にはいかねえ」
「じゃ、じゃあどうしたら?」
「そうだな、1発ずつ順番に殴り合うってのはどうだ?」
柏木という男は不敵な笑みを浮かべ、舌なめずりをしていた。
「断っても無駄なのはわかっています」
「なら話は早い。早速始めようか?」
「はい…」
覚悟を決めるしかなかった。彼女を助け出すためなら何でもやるつもりだ。でも、私は喧嘩などしたことないし、まして人を殴ったことなどない。
「そうしたら、特別サービスだ。お前から殴っていいぞ。その1発で俺を仕留めることが出来たらお前の勝ちだ」
「わかりました」
「いいぞ、こいっ!」
「はいっ」
私は右手を強く握りしめ、思いっきり力を込めた。そして男に向かって体ごと力いっぱい殴りかかった。
「あぁぁぁぁぁっ」
ゴッ…
「えっ…」
男は私の拳を顔面で受け止めた。
しかも、笑ってる。
「いいねえ。なかなかだ。でも、そんなパンチじゃ何十年経ったって俺には叶わねえ」
「・・・・・」
「そしたら次は俺の番だな。覚悟しな!」
男は私に握り拳を見せると、思いきり振りかぶった。もう駄目だ。でも、逃げる訳にはいかない。
「こんなもんでいいだろ。上城、目を開けていいぞ」
「えっ…」
「悪かったな。茶番に付き合わせちまって。出て来いよひかり!」
男がそう言うと、物影から彼女がうつむき加減に現れた。
「日比野さん…」
「ひかりは何も悪くねえんだ」
「どういうことですか?」
「ひかりに恋人が出来たっていうから試させてもらった。お前は誰にも言わずにここに来た。そして負けるとわかっていた俺とのゲームに乗っかった。合格だ」
男は私の肩を掴んで揺さぶってきた。
「ごっ、ごうかくですか…ハハハハハッ…」
「上城、お前にはどんなことがあっても、ひかりを守っていく覚悟はあるか?」
「もちろんです」
「死ぬ覚悟はあるか?」
「あります」
「そっか。だってよ、ひかり」
「うるせえクソアニキ!」
彼女は男に向けてアッカンベーをしていた。
「こいつは、3歳離れた俺の幼馴染み。妹のようなもんだ。ちなみに、ひかりはうちの暴走族のメンバーじゃねえからな」
「私は日比野さんが暴走族のメンバーでも何でも構いません。私はありのままの日比野さんが好きなんです」
「お前は面白え奴だな」
男は腹を抱えて笑っていた。
「真面目に言ってるんてすけど…」
「お前は、ひかりを命をかけて守れ。お前とひかりの2人は俺が命をかけて守ってやる」
男は握った拳を私の胸に押し当ててそう言った。見かけとは違って情に厚い人のようだ。日比野さんの幼馴染みなんだから良い人に決まってる。
それから私と彼女は暴走族の皆さんに見守られながら第三倉庫をあとにした。
「上城くん、怒ってる?」
私の横を歩く彼女は、恐る恐る上目遣いでそう聞いてきた。
「何がですか?」
「アニキの奴があんなことして…」
「怒ってませんよ。日比野さんは何も悪くないじゃないですか」
「そうだけど…」
「それに柏木さんが、あなたを心配する気持ちもわかります。大切に思ってくれる人がいることは有り難いことですよ」
「上城…しっ、しんいち…」
「何ですか?」
彼女が私を初めて名前で呼んだ瞬間だった。
「何ですか? じゃないでしょ! 今、あなたのことを名前で呼んだんだよ。もっと何かリアクションしてよ!」
顔を真っ赤にしてそう言った彼女の様子から、恥ずかしいのに無理して名前を呼んだのが嫌というほど伝わってきた。
「すいません。でも嬉しかったですよ。ひかりさん…」
「ひかりでいいよ」
「名前を呼び捨てで言うなんて初めてです」
「さあ、早く」
彼女は私の前に立ち塞がり強く迫ってきた。
「ひっ、ひかり…」
「いい感じ。それより、さっきアニキに言ったことたけど本気?」
「何か言いましたっけ?」
「私のために死ぬ覚悟があるって言ったこと…」
「冗談でそんなこといいませんよ。本気です」
「そっ、そう…」
「迷惑でしたか?」
「そう言うことを本気で言うの、テレビや映画の中だけだと思ってた。まさか私が言われるなんて思わなかった」
「私とひかりのラブストーリーはドラマや映画じゃ語りきれませんけどね」
「だよねぇ」
彼女は背伸びをすると私の首に手を回して抱きついてきた。私は彼女の背中に手を回し抱きしめた。そしてその愛おしい彼女の唇にキスをした。
プルルルル−−プルルルル−−
『もしもし』
『どこにいるんですか? 約束通りに公園に来ましたよ』
『今行くから待ってて』
『はい』
『笑わないでよ』
『何をですか?』
『私を見ても』
『何だかわかりませんが、笑いませんよ』
『絶対だからね!』
『絶対に笑いません』
10分後――
「お待たせ!」
「あっ…」
「どぉ?」
「きゅ、急にどうしたんですか?」
「そんなことどうでもいいから感想は?」
「感想ですか…とっても似合うと思います。素敵です」
「本当にそう思ってる?」
「思っています。金髪も嫌いじゃありませんでしたけど、黒髪のあなたも嫌いじゃありません」
私の前に現れたひかりは髪をショートボブくらいに短く切り、黒く染めていた。
「〝嫌いじゃありません〟何その言い方? 何なのっ!」
「怒らないで下さい。これでも結構照れながら言っているんですから」
「そうは見えないけど」
「訂正します。金髪のあなたも好きでしたけど、黒髪のあなたはもっともっと大好きです」
「あっ、ありがとう」
「でも、なぜ黒髪に?」
「だって、学年で優等生のあなたの隣に金髪の彼女がいたら変でしょ?」
「まぁ、一応校則があるので金髪はまずいと思いますが、私の彼女が金髪だろうが黒髪だろうが、他の方には関係ありませんよ」
「黒髪にしても、真一とは不釣り合いかもしれないけど、出来るだけあなたに相応しい女性になろうと思ったの」
「あなたにもそんなに可愛らしい一面があったんですね?」
「ブッ飛ばすよ!」
ひかりは握り拳を私の前でチラつかせてそう言った。
「まぁまぁ。でも、相応しいとか相応しくないとか、そんなものありませんよ。金髪のあなたが私に相応しくないとは思いませんし、黒髪のあなたが私に相応しいとも思いません」
「だけど、世間的にはダメでしょ?」
「大切なのは私があなたを好きで、あなたが私を好きということです」
「マジでムカつくんだけど。黒髪にした意味ないじゃん…」
「そんなことありません。私のために黒髪にしてくれたあなたの気持ちはすごく嬉しいし、そんなあなたを前よりもっと愛おしく想います。つまりあなたを、好きで好きで仕方ないということです」
ひかりの気持ちが嬉しくて自然と涙が溢れてきた。私の彼女はなんて純情で可愛らしいんでしょうか。
「………なら許す」
「ありがとうございます」
その日は、暗くなるまで公園で寄り添い、ただ空を眺めていた。
「この問題どうやるの?」
「これは、こうやってこうやって解くんです。わかりまっ‥。はぁ…何で私を見つめてるんですか?」
「だって勉強を教えてる姿がカッコイイなぁっと思って」
「はいはい、ありがとうございます。嬉しいですけど、今はそんなことしてる場合じゃないですよ。テストが1週間後に控えているんですから」
「わかってる。今度のテストで赤点とったら進級出来ないんでしょ?」
「そうです。わかっているなら真面目に勉強して下さい!」
「は〜い」
ひかりは出席日数は担任の先生のおかげで何とかギリギリセーフだけど、成績の方に問題があった。前回のテストも赤点を取り、再試再試と2度もテストをやり直しをさせられていた。
「そしたら次にこのもんだっ‥」
「店員さ~ん、すいませ~ん。追加で山盛りポテト1つ下さ~い」
「ちょ、ちょっと何で注文しているんですか? って言うか、そもそも何でファミレスでテスト勉強なんですか?」
「仕方ないでしょ。図書室は18時までしか使えないんだから」
「だからって、もっと落ち着ける場所があったと思いますけど」
「落ち着ける場所って? ラブホとか? でも、ラブホなんか行ったんじゃ、真一が勉強にならないんじゃないの?」
何も言い返せなくなってしまった。ひかりは私が、この手の話が苦手なのをわかっていて、わざとする。
「・・・・・。さぁ、ふざけてないで始めますよ!」
「もぉ~、そういう話をすると顔を赤くしてムキになって怒るんだから。ちょっとくらい、いいじゃない」
「どうしたら真面目に勉強してくれるんですか?」
「キスしてくれたらいいよ」
「じゃ、じゃあ…店を出たらしますから、しっかり勉強して下さい」
「ダメっ! 今して! 今してくれないなら勉強なんてしないから!」
「〝勉強なんてしないから〟って、あなたのための勉強ですよ。何言っちゃっているんですか!」
突然の彼女の申し出に声が裏返ってしまった。
「あぁぁぁぁぁ~〜。いちいちうるさいな! するのかしないのかハッキリしてよ!」
「しっ、しますよ。進級してもらわなきゃ困りますからね」
「ならしてよ。目をつぶってあげるから早くしてよね」
「誰かに見られていませんか?」
夕食時ということもあり、店内は席が埋まりつつあり、人もそれなりに大勢いた。
「気にしないで。私を好きなら、そんなことは気にせずに出来るはずよ。これで真一の私に対する気持ちがわかるわね」
「わかりました。しますよ、いいですか?」
「うん」
チュッ…
目をつぶっているひかりの唇にライトキスをした。
「ほっ、本当にするんだ。ビックリなんだけど…」
「私の気持ちを疑われては困りますから」
「だったら私もお返し!」
ブチュッー…
ひかりは私の頬を手で押さえつけると、プレッシャーキスをしてきた。唇が重なっている時間は、ものすごく長く感じられた。こんな感じで試験までの数日は、2人で勉強をした。その甲斐があってか、テストは赤点ギリギリてクリアした。
−−数日後
「私のこと飽きたの?」
「どっ、どうしてですか?」
学校からの帰り道、ひかりから思わぬ言葉をかけられた。
「最近学校終わってから会う回数が減ったような気がするし…」
「そんなことないですよね?」
「それに変な噂も聞いてるし…」
「変な噂? 何ですかそれ?」
「自分の胸に聞いてみたら!」
「そうしてみます」
変な噂…
それはひかりにとって嫌な話、おもしろくない話ということには違いないと思うけど何も思い浮かばない。
「どお?」
「・・・・・。やっぱり何も出てきません。それより次のテストまで1ヶ月を切ったので、今のうちから勉強を始めましょう。前回は何とか赤点は免れましたが、ギリギリで危なかったんですからね」
「こんな気持ちのままじゃテスト勉強なんて出来ない!」
「何か色々と誤解されているようなので、弁解させて頂きます」
「どうせ言い訳でしょ?」
「そんなこと言わずに聞いて下さい。始めに、会う回数が減ったという話ですが、平日は学校が終わったあとに3日、土日は毎週のように会ってるじゃないですか」
「前は平日も4日とか5日も会ってた」
「それは、ひかっ‥」
プルルルル――プルルルル――
私の言葉を遮るように電話が鳴った。
「電話鳴ってるわよ。さっさと出なさいよ」
「あっ、はい。では失礼します」
ピッ…
『もしもし』
『もしもし上城くん、頼みがあるんだけど』
『はい、何ですか?』
『実はね、今日のしっ‥』
ひかりは突然、耳に当てていたスマホを引ったくると私を睨みつけた。
「ちょっと誰? 女でしょ?」
「そうですけど、彼女はわっ‥」
「バカッ! 信じてたのに!」
「何を言っているんですか? ごっ、誤解です!」
「何が誤解よ! 私のことなんて遊びだったんでしょ!」
「違います。話をちゃんと聞いて下さい」
「聞くもんですか! こんなスマホがあるからいけないのよ!」
「ちょ、ちょっと、私のスマホをどうするんですか?」
「うるさい! こんなもの!」
バンッ…
地面に叩きつけられたスマホは、画面は割れて、部品の一部が露出してしまった。
「あぁ…」
「真一なんて、サイテーよ!」
「まっ、待って下さい。明日は会えますよね?」
「もう別れてやるんだから! さよなら!」
パシッ…
ひかりは私の頬を思いきり叩くと、泣きながら走って行ってしまった。
−−翌日
今日は朝から、ひかりは私を避けていた。全く私に近づこうとしなかった。
放課後になると急いでひかりのクラスを訪れてみた。しかし、ひかりの姿はどこにもなかった。
「さっきまでいたんだけど、どこ行ったんだろ?」
鈴木さんにひかりの居場所を尋ねたものの、わからないようだった。
図書室や食堂など、心当たりがある場所には全てあたってみた。それでもいなかったので、階段を駆け足で登って行った。
「探しましたよ。まさか屋上にいるとは思いませんでした」
ひかりはフェンスを掴んで遠くを眺めていた。
「上城くんには関係ないじゃない」
「上城くん? まだ怒っているんですか?」
「何を怒る必要があるの?」
「ひかり、本当に誤解なんですよ」
「誤解? そんなに誤解を解きたいなら電話してくればよかったでしょ! 電話の1本もよこさないで何が誤解よ!」
「ふぅ~。とりあえずその話は置いときましょう」
「やだっ!」
ひかりは大声で叫ぶと、反対側のフェンスに向かって歩き出した。
「ひかり…」
「なに?」
「お誕生日おめでとう!」
「誕生日?」
「やっぱり忘れていたんですね? 今日はひかりの誕生日ですよ」
「あっ…そういえば…」
「こんな大事な日を忘れないで下さいよ」
「真一のせいでしょ!」
「そうですね、すいませんでした。お詫びのしるしに、誕生日プレゼントを用意させてもらいました。どうぞこれを」
背後に隠していたプレゼントをひかりに差し出した。
「何これ?」
「開けて見て下さい」
「ゆっ、指輪?」
「そうです。でも、ただの指輪ではありません」
「どういうこと? 私にはとってもキレイな指輪にしか見えないけど」
「婚約指輪です」
「えっ…」
「何年か経って、お互い大人になったら結婚しましょう」
「本気?」
「本気です。嘘偽りはありません」
「いいの私で?」
「あなたでなければ駄目なんです。それに、これくらいしなければ私の気持ちはわかってもらえなさそうなので」
「真一っ!」
ひかりは私の胸に飛び込んで来ると、これ以上ない力で抱きしめてきた。
「そんなに強く抱きしめられたら痛いですよ」
「うるさい!」
「このままでいいから聞いて下さい。私たちの会う回数が減ったのは、ひかりがバイトの日数を増やしたせいですよ。それに実は秘密にしてたんですけど、ひかりの誕生日プレゼントを買うために短期のバイトをしていたんです。昨日の電話の女性はバイト仲間の町田さんです。急用ができたのでバイトを代わって欲しいという電話でした。変な噂を耳にしたというのは、たぶんデパートでいとこの晴美さんと一緒に歩いていたところを偶然誰かに見られたのでしょう。晴美さんには指輪を買うのを付き合ってもらいました。ついでに言わせてもらうと、昨日電話の1本もかけられなかったのは、あなたにスマホを壊されたからです」
「えぇぇぇぇっ…全部私が悪いんじゃん。ゴメン…」
ひかりは私の胸の中から顔を上げると、潤んだ瞳で私をジッと見て謝っていた。
「いいんですよ。私もあなたを不安にさせていた訳ですから」
「真一、大好きだよ!」
「はい、私もです」
それから私とひかりは互いの指に指輪をはめあった。まるで結婚式の指輪の交換のように…永遠の愛を誓いあった。
父は弁護士で母は国会議員をやっているので、両親からは弁護士か検察官、政治家になれと強く言われている。私自身もそんな両親を見て育ってきたので、両親の様な仕事をすることに憧れを抱いていた。
高校生活では3年間、部活は何もやらないできた。唯一やってきたのは勉強。四六時中勉強をしてきた。暇さえあれば参考書を開き、色々な知識を頭に叩き込んできた。休み時間も勉強をしていた。放課後になると、静かな空間を求めて図書室にやって来て、2〜3時間勉強をしてから帰宅する。帰宅してからは家庭教師が19時にやって来て22時まで勉強をした。高校生活は、そのような生活を送ってきた。
私にとって高校とは勉強しに行く場であって、青春を謳歌する場所ではなかった。
友達はというと、特別仲の良い人はいなかった。仲間はずれにされたり、いじめにあっている訳ではなかった。友達が欲しいとか、必要とか思えなかったので、積極的に話しかけたり、話しかけられても一言二言返す程度で楽しみもしなかった。
唯一友達と言えるかどうかはわからないけど、奥村大志という人物がいた。彼にも友達がいなかった。彼はどちらかというと、いじめられるタイプだった。悪く言うと何をやらせても鈍臭いし、トロかった。身長165CM体重100キロという肥満体質は、他の人間から敬遠された。彼は夏でも冬でもいつも汗をかき、タオルで額を拭っていた。暑苦しいとかむさ苦しいと思われていたのだろう。それが原因かわからないけど、クラスのどのグループにも迎え入れてもらえなかった。
そんな友達のいない奥村くんが、友達のいない私に近づいてくるのは自然の成り行きだったのかもしれない。そんな彼のクラスでの立場を見ていたので、私は他の人間と同じようには接しなかったし、どちらかというと好意的に接していた。
「上城くん、パン食べる?」
彼は、休み時間になると買ってきたパンを私に勧めてきた。彼は昼食になるまで待ちきれずに、休み時間になるたびにパンを食べていた。そりゃあ、太るわけだ。
「大丈夫です」
嫌だから断った訳ではなく、お腹が空いてないからそう答えただけだった。だけど彼は少しばかり寂しそうな顔をした。
「上城くん、駅前に焼肉の食べ放題の店ができたんだ。一緒に行かない?」
「大丈夫です」
彼は時々、私を食事に誘ってくれた。でも、私は学校が終わって家に帰れば家庭教師の先生と勉強しなければならない。行きたいと思うことはあっても、断るしかなかった。彼は寂しそうな顔をした。
でも、彼は次の日になれば昨日のことなど忘れてしまったかのように「パン食べる?」「〇〇に食べに行かない?」と聞いてきた。断られるのをわかっていても聞いてきた。面白い人だと思った。
そんな私の勉強一色の高校生活を変えてしまう、そんな出会いがあった。
学校が終わると、いつものように学校から駅までの通学路を歩いていた。住宅街を歩いていると、見覚えのある制服姿の女子生徒が公園に入っていくのが見えた。確か彼女は隣のクラスの···。名前までは出てこなかったけど、隣のクラスの女子生徒に間違いなかった。学校でよく見かける訳ではないけど、彼女の外見は1度見たら忘れることはないだろう。肩まである金髪に鼻ピアス。中々の存在感だ。学校でも異色を放っていた。
それにしても何をしているのだろう? そんな言葉が脳裏をよぎったけど、ここは公園。小休止か遊びに来たのだろう。もしくは人目につかないところでタバコでも吸おうというのだろうか?
いつもなら、それ以上は興味をもつことなどなかったであろう。でも、今日は何故か違った。気づくと物陰に隠れて女子生徒の様子を観察している自分がいた。
彼女は手に持っていた袋から何かを取り出した。
「チビ〜チビ〜」
彼女は手に持った何かをチラつかせながら名前を呼び始めた。すると木の陰から小さな生き物がチョロチョロと姿を表した。白い子猫だった。彼女は手に持っている物を小さく契り、子猫の口元に持って行った。すると子猫は勢いよくムシャムシャと食べ始めた。よほどお腹を空かせていたのだろう。一瞬で全てを平らげてしまった。
「また、明日の夕方に来るからね」
彼女は子猫の背中を優しく撫でながらそう言った。そう言った彼女ではあったが、それからしばらくの間は子猫を触っていた。結局、彼女は1時間以上子猫と戯れてから公園をあとにした。私は一連の出来事を黙って見つめていた。彼女の容姿からは想像できない行いに、只々驚いていた。
彼女のしている行為には賛否両論あるだろう。無責任で軽率な行為だと心無いことを言う人間はいるかもしれない。でも、私にはその行為は善であり決して悪ではなかった。何か力になれることがないか、何か力になりたいとさえ思えた。
私は彼女がいなくなった子猫のそばに行き、その場にしゃがんだ。
「君は誰かに捨てられたんだね。かわいそうに…」
私にはその子猫の頭を撫でてあげることしか出来なかった。
次の日もさらに次の日も、私は学校の帰りに公園に立ち寄った。すると彼女は毎日やって来ては、子猫にご飯をあげていた。毎日かかさずご飯を与えていた。
そんな心優しい彼女ではあるが、学校で会うことはあまりなかった。隣のクラスなので、タイミングが合わなければ会えなかったのかもしれないけど、それにしても会う機会は少なかった。
彼女が学校を休みがちだったというのは、あとでわかった。
それでも、夕方にあの場所に行けば私は彼女に会えた。彼女自身に会いたかったのか? 子猫にご飯を与えている心優しい彼女に会いたかったのか? それはナンセンスだけど、答えを出そうとは思わなかった。
そんな日々が3週間を過ぎようとしていた。今日も電車を乗り継いで、学校へと向かっていた。電車に乗り込むと空席があったので、席に座った。辺りを見回すと彼女がいた。彼女も席に座っていた。どうやら今日は学校に行くようだった。彼女とは時々こうして同じ電車に乗ることがあった。私は気づくと彼女を見ていた。彼女を目で追っていた。
電車が次の駅で止まった。乗車口からは数人が中に入ってきた。年配のご婦人がいるのを目で確認した。
「おばあちゃん、どうぞっ」
私がご老人を目で捉えるのと同時に、声をかけている人がいた。
彼女だった。
一瞬の迷いなど全く無く、声をかけていた。彼女は優しかった。人にも動物にも。人は見かけによらないとよく言うけど、本当にそうだと思った。彼女は金髪に鼻ピアスという、高校生らしからぬ風貌をしてはいるけど、本当に心が優しく美しかった。
彼女の名前は日比野ひかり。直ぐに知ることが出来た。でも彼女は私の名前を知ることも存在自体を知ることもないだろう。
それでも私は彼女の力になりたいと思った。お節介で無責任だと思ったけど、何もせずにはいられなかった。
だから私も毎朝、学校に向かう途中で公園に寄って子猫にご飯をあげた。朝食は私が与えて、夕食は彼女が与える。いつしかこのシステムが出来上がっていた。
でも、いつまでもこんなことを続けて行くことは出来ないだろうし、良くはないのはわかっていた。捨て猫がいるのを近隣の住人が保健所に連絡しないとも限らないし、子猫自体がいつかこの場所を離れてしまう可能性も捨てきれない。どのみち、早く何かの手を打たなければならなかった。
私は急いだ。あの子猫の飼い主を見つけることを…。殆んど交流のないクラスメイトに、子猫を飼ってもらえないか聞いて回った。中学校の時のクラスメイトにも電話で頼んでみたりもした。でも、飼ってくれるという人は見つからなかった。
あの子猫と出会ってから3週間が経とうとしていた。
「上城くん、子猫の飼い主を探してるんだって?」
昼休みに入り、席に座っている私に声をかけてきたのは奥村くんだった。そう言えば、彼にはまだ聞いてなかった。
「そうなんです。色々とあたってはみたけど、まだ見つかってないんです」
「ふ〜ん、そうなんだ」
「困りました…」
「パン食べる?」
「パンですか? そうですね、もらいましょうか?」
「えっ…食べるの?」
「えぇ、まあ···まだ何も食べていないので」
「そっ、そう···これオススメのパンなんだ。食べて」
「はい、ありがとうございます」
奥村くんは、今まで見たこともないような屈託のない笑顔でパンを渡してきた。
「とっても美味しいです」
「よかったぁ」
「上城くん、誰も飼ってくれる人がいないなら、僕んちで飼うよ」
「えっ…本当ですか?」
「本当だよ」
「勝手に決めちゃって親に怒られませんか?」
「大丈夫だよ。僕んち猫を2匹飼ってるんだ。捨て猫がいるって言えば、猫好きの母親が黙ってないよ」
「それならいいんですけど。親に飼えるか確認して下さい」
「わかった」
その日の夜、奥村くんから電話があり、飼っても大丈夫だから早めに迎えに行こうと連絡があった。この日は嬉しくて眠れなかった。
−−翌日
奥村くんと子猫を迎えに行く手順を話し合った。決行日は明後日の土曜日。
午前中に奥村くんが母親と一緒に車で公園まで来てもらい、私があらかじめケースに入れておいた子猫を奥村くんに渡すというものだった。心配はただ1つ…。彼女だった。
突然、あの場所から子猫がいなくなってしまったら、探すかもしれない。保健所に連れて行かれてしまったと、涙を流すかもしれない。ショックを受けて途方にくれることは間違いない。どうすればいいかを考えた。私が自ら名乗り出るのも考えた。それが一番手っ取り早い方法だ。私の口から説明すれば彼女も納得するだろう。でも、それはしたくない。私の勝手なわがままだ。飼い主になる奥村くんに事情を説明してもらおうかとも考えた。でも、これ以上迷惑はかけられない。考える時間などなかった。
−−土曜日
朝の6時前。私は公園に来ていた。人ができるだけ少ない時間に決行しようということになっていた。とは言っても、私たちを邪魔するものは何もなかった。
私は奥村くんから借りてきたキャリーケースに子猫を入れる準備をしていた。
プルルル−−プルルル−−
メールが入った。
どうやら奥村くんを乗せた車が到着したようだ。私は急いで子猫をケースに入れて車まで走った。誰も見ている者はいなかった。公園の前に停まっている車の前まで行くと、後ろのドアが開き、奥村くんが顔を出してきた。
「おはよう」
「おはようございます。よろしくお願いします」
私は奥村くんとガッチリ握手を交わし、母親に頭を下げた。そして何事もなかったように車は走り出した。
夕方になろうとしていた。彼女はまだ来ていない。でも、もうそろそろ来る時間だ。私はいつも子猫がいる場所に、ある物をいれた手提げ袋を置いた。
5分が経過した頃、彼女が歩いて来るのが見えた。彼女は公園の中に入り、いつもの場所まで行くと、手提げ袋があるのに気づいた。彼女は手提げ袋を手に取り、中身を取り出した。私が用意した子猫のぬいぐるみと手紙だった。彼女は手紙を読み始めた。
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
こんにちは
突然のお手紙、驚かれたと思います。
あなたが夕方に子猫にご飯をあげているのを少し前に知りました。
私もそれを見て、朝にご飯をあげることにしました。
でも、このままではいけないと思いました。
保健所に連れて行かれるかもしれないし、子猫が道路に飛び出して事故にあってしまうかもしれません。
悪い人間に捕まって、殺されてしまうかもしれません。
だから、そうなる前に私は飼い主を探しました。
運良く飼ってくださる人が見つかりました。
信頼の出来る人です。
安心して下さい。
今までありがとうございました。
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
彼女は手紙を読み終えると、辺りをキョロキョロと見始めた。
「ありがとう。あなたは誰? どこかにいるの? どこかで見てるんでしょ?」
彼女は叫んでいた。でも、誰も答える訳などなく、公園は静寂に包まれていた。私はとっさに身を隠した。
「ありがとう、親切な人。ありがとう」
私こそありがとう。
この日から、私と彼女の共通の目的はなくなった。彼女と子猫を初めて見た以前の生活に戻りつつあった。でも、私は彼女を色んなところで見た。彼女を見つけるのが上手になっているのかもしれない。もしくは彼女がいないかと、いつもアンテナを立てているのかもしれない。
それにしても彼女は相変わらず誰に対しても親切だった。老人にも子供にも誰にでも親切だった。私には決して出来ない、そんな彼女の姿を見るのが微笑ましかった。
今日は電車の中で彼女を見なかった。隣のクラスを覗いてみたけど、彼女の席は空席のままだった。
「何か私のクラスに用ですか?」
「いえ、何でもないです」
隣のクラスの女子生徒に声をかけられてしまった。
「時々、見に来てますよね?」
「そんなことは…」
強気な女子生徒を前にタジタジになってしまった。
「愛実、どうかした?」
「ううん、何でもない。千夏、行こ」
愛実という女子生徒は目を細めて私を見ていた。私がこうして隣のクラスを覗いているのを、他の生徒にも怪しまれているのであろうか? 気をつけなければいけない。
「上城くん、どうしたの?」
「奥村くん。実はあの女子生徒にちょっと…」
「あぁ…泉田さんね。陸上部のエースだよ。性格キツイらしいよ」
「なるほど…」
「隣にいる鈴木さんは茶道部の部長。美人でおしとやかだから男子生徒からは人気があるんだ」
「そうなんですか。えらい詳しいですね?」
「隣のクラスに中学時代からの友達がいるんだ。そいつから色々と教えてもらっている訳さ」
奥村くんは鼻をこすりながら得意げに話していた。
「金髪の女子がいますよね?」
「あぁ、日比野のことね。あいつには関わらない方がいいよ。あんまり良い噂聞かないし。危ない奴らと付き合ってるみたいだし」
「そうなんですか…」
たぶん、根も葉もない噂だろう。信じるつもりなど全くなかった。
放課後になり図書室に来ているけど、休み時間の出来事が頭をよぎっていた。
泉田さんと鈴木さん…
彼女の悪い噂…
考えないようにしているけど、思い出してしまう。
「はぁ〜」
小さくため息をついた。
「あなた、また勉強してるの?」
集中しようと参考書を読み漁っていると、声をかけられた。顔を上げて見てみると…日比野ひかりさん…その人だった。
「そうですけど、何ですか?」
胸の鼓動がドックンドックンと高鳴っているのがわかった。
でも、何で彼女がここに…
今日は学校には来ていないはず…
「そんなに毎日勉強ばっかりして、どうするの?」
「〝どうするの?〟って、面白いことを聞くんですね?」
「全然面白くないから! 真面目に答えなよ!」
「はぁ···。勉強しといて損することなんてありませんから」
「何か目標があって勉強している訳じゃないの? そんなの意味ないじゃん。そんな曖昧な目標ならやめた方がいいんじゃないの?」
「目標がない訳ではありませんよ。父親が弁護士、母親が国会議員をしているので、両親からは弁護士か検事、もしくは政治家になれと言われています。だから死ぬほど勉強して司法試験に合格するんです」
平静を装ってはいるが、内心いつボロが出ないか心配だった。
「それって親に言われたから?」
「言われたからと言われればそういうことになります」
「ふ~ん、情けないね」
それにしても、何で彼女は私が毎日放課後に図書室で勉強をしていることを知っているのだろうか? 見られてた? そんな訳はない。私は彼女を見ていない。
「日比野さん…ですよね? 隣のクラスの?」
「うん。あなたは上城真一くん」
「知ってもらえてるなんて意外です」
「もちろん知ってるよ。頭いいんだよね」
「頭が良いかはわかりません。勉強で少しばかり良い成績を取れてるだけです」
「それを頭が良いって言うんじゃないの?」
「私は頭が良いことよりも人に優しく出来る人間の方が尊敬できます」
「たとえば?」
「電車の中でお年寄りに席を譲ってあげたり、小さな生き物の命を大切にしたりすることですかね」
あなたのことですよ。これ以上事細かく言ってしまうと、いつも遠くで彼女を見ていることを勘ぐられてしまうかもしれない。これくらいでやめておこう。
「そぉ?」
彼女は嬉しそうに微笑んでいた。わかりやすい人ですね。
彼女は私が勉強している間、図書室の中をブラブラしていた。そして時々戻って来ては、持ってきた本を広げて読み始めた。向かい側に座る彼女の手元を見ると、読んでいるのは飛び出す絵本だった。彼女は絵本をめくるたびに「わぁ」とか「おぉ」とリアクションをしていた。
「クスッ」
「今、笑った?」
「笑ってませんよ」
「バカにしてる?」
「してませんよ」
「だったら何?」
「そうですね···無邪気で可愛いと」
彼女は何も言わずに席を立つと、スキップをして行ってしまった。照れてるのだろうか? 気分を良くしたようにも見える。そんな感じで今日の放課後は終わった。
−−翌日
授業中は彼女のことばかり考えていた。どうして急に図書室にきたのか? あれは明らかに私に会いに来ていた。でもどうして? 答えなど出る訳などないのに、頭の中で自問自答を繰り返していた。
今日の2時間目は数学の授業。教師は太田海斗、28歳。まだ教師になって4年くらいだろう。早稲田大学出身らしく頭は切れた。教え方も上手で生徒の質問に丁寧に答えてあげる熱心な教師だった。太田先生は黒板に問題を書き、生徒に解くよう指示を出した。生徒は自分の机と向き合い、必死になって問題を解こうとしている。そんな姿を見ながら、太田先生は教室内を歩いていた。私の横を通り過ぎた。ふとタバコの匂いが鼻をついた。この匂いはMarlboro。家庭教師が外で吸っているのを近くで嗅いだことがあるので間違いないだろう。それに胸ポケットから見える赤に白の箱は、より一層確信を強めた。でも、校内は禁煙のはず。どこで吸っているのだろうか?
そんなことを考えながら太田先生を見ていたら、前に出て黒板に回答を書くように言われた。特に何の問題もなく答えを解いていく姿に、太田先生は面白くなさそうな顔をしていた。性格は悪そうだ。でも残念ながら、これくらいの問題なら朝飯前だ。
午前中の授業が終わり昼休みに入った。奥村くんと学食に向かっていると、隣のクラスがザワついているのがわかった。学年主任の小島先生が彼女を連れて教室を出ようとしていた。
えっ…何があったんだ?
「上城くん、どこ行く気?」
彼女を追いかけようとする私を奥村くんは制止した。
「ちょっと待ってて」
奥村くんはそう言うと、隣のクラスの中に入り、前に話してくれた中学時代の友達に何かを聞いている様子だった。少し経つと奥村くんは戻って来て言った。
「日比野さん、タバコを吸ってるという疑いをかけられたらしい」
「本当ですか? でも何故それを私に?」
「そっ、それは···僕、こういう類のスキャンダルとか目がなくて」
奥村くんは、もみあげを掻きながら必死になって理由を語ってた。それから食堂でランチを食べながら、奥村くんは詳しい経緯について話してくれた。
「前にも疑われたことがあるらいしよ」
「吸っているのを見られたんですか?」
「不良グループの岩崎が吸ってるのを見つかったらしくて、仲の良い日比野さんにも疑いの目が向けられたって訳さ」
「そうなんですか…」
彼女が心配だった。彼女がタバコを吸っているか吸っていないかはわからない。吸っていようが吸っていまいが、どちらでも構わない。ただ未成年者のタバコの喫煙は法律で禁じられてる。決まりは決まりだ。決まりを破れば罰せられるのは当たり前だ。ただ彼女が心配だった。
こっぴどく怒られてるんじゃないか?
怒られて落ち込んでいるんじゃないか?
心配で仕方なかった。
「今回はタバコを手に持ってたらしいよ。閉まっとけばいいものを、手に持って歩いていたらしい。今回ばかりは言い逃れは出来ないんじゃないかな」
「本当に吸っている人が手に持って歩きますかね? 捕まえて下さいって言っているようなもんですよ」
「確かに言われてみれば…」
昼食を終えた私は、教室に戻る前に1人で職員室に向かった。職員室に入り、学年主任の小島先生の席に目を向けると、小島先生の姿はあるものの彼女は既にいなくなっていた。自然と小島先生の席に向けて足が進んでいた。
「小島先生…」
「上城くんか、どうした?」
「日比野さんが、こちらに来ていると聞いたもので…」
「日比野に何か用でも?」
「はい」
自分でも思い切った行動に出たと驚いていた。
「今は別の教室で教頭先生から色々と聞かれている頃だ。君みたいな優等生が日比野なんかと付き合わない方がいいと思うぞ」
「あの、日比野さんが持っていたというタバコは? ちょっと確認したいことがあって…」
「そうなのか? 特別だぞ」
小島先生は不審そうな顔をしながら机から例のタバコを取り出した。
「こっ、これは…先生、4組の3時間目の授業は数学ではありませんでしたか?」
「私の授業の前は確かに数学だが。それが何だ?」
「なるほど…」
私は小島先生に確認してもらいたいことがあると伝えてから職員室をあとにした。多分もう大丈夫だろう。
−−放課後
いつものように図書室で勉強をしていた。今日は私らしくないことをした。少し疲れた。
「今日も勉強? 他にすることないの?」
「えぇ、まぁ…」
昨日に続き、今日も彼女はやって来た。
「放課後に図書室に来て、毎日勉強している人なんて、あなたくらいなものよ」
「駄目ですか?」
「駄目に決まってるでしょ!」
「どうしてですか?」
「どっ、どうして? だっ、駄目なものは駄目なの! 理由なんてないわ!」
「勉強は楽しいですよ」
「私は嫌い。社会に出て数学の方程式なんて使わないし、何のために勉強してるのかわからない」
「将来の夢は?」
「特にない。早く就職して独立したい」
「そうですか」
「それより、聞いてよ。今日、学年主任の小島と数学の太田に頭を下げられちゃった」
「何かあったんですか?」
理由は聞かなくてもわかった。
「実は私、タバコを手に持ってたら吸ってるって疑われたの。でも持っていたタバコが太田のだってことがわかって、アイツら慌てて謝ってきたって訳なの」
「それは良かった」
「誰かが私の持っていたタバコは太田の物だってことを言ってくれたみたいなの。一体誰だったんだろう?」
「私にはわかりかねますけど、疑いが晴れてよかったですね」
「本当はあなたが助けてくれたんじゃないの? ってそんな訳ないわね」
「はい、私ではありません」
何はともあれ一件落着です。
−−今日は土曜日。
午前中から最寄りの駅から5分くらいにある図書館に来ていた。もちろん目的は勉強をするためだ。快適な空間で勉強がはかどっていたので時間が過ぎるのを忘れてしまっていた。気づくと午後の2時になっていた。軽い昼食を取ろうとコンビニに寄ることにした。
「あっ…」
偶然にしては運命を感じぜずにはいられなかった。彼女が本を立ち読みしているのが、外からでもわかった。声をかけるかかけないかを考えていた。プライベートな休日の時間に私が入り込んでいいか迷った。しばらくは彼女に気づかれないように、外で様子を伺っていた。動く気配が全くなかったので、とりあえず店内に入ってみた。
買い物をしていて彼女が私に気づいたのなら気づかなかったふりをしよう。私はサンドイッチとサラダをカゴに入れ、レジの横にあるホットコーナーを見ていると、中学生くらいの男子の4人組が騒ぎながら店内に入ってきた。それとタイミングを同じにして、彼女が動き出した。彼女はチョコレート売場に行くと、商品を手に取って何を買おうか迷っていた。
すると先程の4人組がチョコレート売場の隣りにあるカード売り場の前にやって来た。その中のAがやたらと周りをキョロキョロと見回し始めた。あからさまに怪しかった。考えられるのは唯一つ。万引きをしようとしている。先程のAは見張り役と言ったところだろう。彼女は未だにチョコレートを手に取り選んでいた。このままだと、万引きに巻き込まれる恐れがある。念のために…。
私は物陰でことの成り行きを見守った。とうとう4人組の3人が動き始めた。実行犯と思われるBの前にCが立って店員の死角を作り出した。Dは店で1番安い10円のお菓子をレジに持って行って買い物をし始めた。2人いる店員はレジで接客をしている状態。まさに万引きをするには絶好の場面を作り出していた。そして実行犯のBがカードを手に取ると、素早くポケットに押し込んだ。それからもBはカードを何度か手に取ってはポケットに押し込んだ。かなりの数を万引きしていた。許せない行為だ。そして満足したのか、実行犯のBが他のメンバーに声をかけると、逃げるように店を出て行ってしまった。店員の2人は、まだレジで接客中だった。マズイなと思った。
ところが次の瞬間···
2人しかいないと思っていたレジの店員とは別の店員がレジ横の扉から飛び出してきた。
「ちょっと君いいかな?」
「何ですか?」
案の定、彼女は万引き事件に巻き込まれてしまった。
「事務所に来なさい!」
「ちょ、ちょっと待って…」
彼女は腕を捕まれ、連れられて行ってしまった。私は買い物カゴを床に置くと、店の外に出てダッシュをした。万引き犯たちを必死に追いかけた。しばらく走っていると、彼らに追いついた。彼らはバカふざけをしながらゲームセンターに入って行った。
私は直ぐに警察に電話をして、事情を事細かく説明した。そして中の様子を覗うと、4人組の連中は呑気にゲームをして遊んでいた。今頃、コンビニでは彼女は事情聴取をされているだろう。早くしないと···。
私は次にコンビニに電話をした。信じてもらえるかわからないけど、彼女は万引き犯とは無関係であること、事実無根であることを必死に訴えた。そして隠れて撮っていた万引きの瞬間をとらえた動画を店舗責任者に送った。また、万引きが行われた時刻を教えて、店の防犯カメラの映像を確認してもらうようにお願いした。
電話を終えると、制服を着た警官が3人でやって来た。私は警官に説明をし、動画を見せた。既に私の周りには警官が6人くらい集まっていた。そして数名の警官が中に入り、残りの警官か外で見張りをしていた。数分後、警官は4人を連れて店から出てくると、停まっていたパトカーに乗せて走り出した。
もう大丈夫でしょう。私は買い物カゴに商品を入れたままにしていたのを思い出し、コンビニに引き返した。
コンビニに戻って来ると、商品が入ったカゴはそのままになっていた。お会計を済ませにレジに持って行った。店員が商品のスキャンを終えて財布からお金を取り出していると、レジの横の扉から彼女が何食わぬ顔で出てきた。
「あれ? 上城くん?」
「どっ、どうも…」
彼女は商品がパンパンに入った袋を手に持っていた。
「買い物?」
「えぇ、まぁ…」
「何か歯切れが悪いわね」
「そうですか? そんなことないですけどね…」
あんなことがあった直後にも関わらず、意外にも彼女は元気そうだった。
「これ、お店の人にもらったの。一緒に食べない?」
「いいですけど、持って帰って食べた方がいいんじゃないですか?」
「いいの、いいの。イッパイあるから」
それから近くの公園に行き、空いてるベンチに2人で腰かけた。
「サンドイッチ買ったんですけど、食べませんか?」
「お昼まだ食べてないの?」
「えぇ。たまごとツナはどちらが好きですか?」
「たまご」
私と彼女は黙ってサンドイッチを食べた。
「フンフン♪フンフンフ〜ン♪」
彼女は足をバタつかせながら、鼻歌を歌っていた。
「何も聞かないのね?」
「聞いた方がよかったですか?」
「別に」
「元気そうで何よりです」
「フンフンフン♪フンフンフ〜ン♪」
彼女は何も答えず、鼻歌を歌っていた。
−−2日後
教室の窓から彼女が登校する姿が見えた。バイクの後ろに乗せて来てもらったようだ。彼女はバイクから降りると、バイバイと手を振って見送っていた。
「バイクの人、暴走族の総長だよ」
窓の外を眺めている私の隣で奥村くんがそう言った。
「そうなんですか…」
「日比野さん、暴走族のメンバーって噂になってるよ」
「詳しいですね?」
「中学から一緒の友達が情報ツウなんだ」
「あぁ、隣のクラスの上尾くんですね?」
「うん。結構、ネタがあるみたいだから今度聞いとくよ。それより、日比野さんと仲の良い6組の棚橋くんも暴走族と関係があるらしいんだ」
「何か悪いことに巻き込まれなきゃいいんですけどね」
「心配? だよね?」
「えぇ…」
いつからだろうか? 奥村くんは私が日比野さんに関心があると思っているらしかった。
−−放課後
「ここ座るわよ」
「またあなたですか?」
そんな言い方をしたけど、胸が高鳴るのを感じていた。
「何か文句ある?」
「ありませんけど…」
「何なの? 来ちゃ悪いの?」
「悪くはないです」
「だったら座ってもいいでしょ?」
「どうぞ」
「フフッ」
彼女はイタズラっぽく微笑むと、私の向かい側の席に座った。
「それにしても図書室って空気が重いわね。息苦しい」
「1つ聞いてもいいですか?」
「何?」
「どうして居心地の悪い図書室に毎日のように来てるんですか?」
「あっ、あなたになんて答える必要ないわ!」
顔を真っ赤にして、ムキになってそう答える彼女は何だかとても愛おしかった。
「そうですか…」
素直じゃないのはお互い様ですけどね。
「今日、日比野さんが登校する姿を見ましたよ」
何かを確認したい訳ではなかったけど、思い切って切り出してみた。
「あっそう。それで?」
彼女は、やはり触れてほしくはないようだった。あからさまに、怪訝そうな顔をしていた。
「いや、何でもありません」
「私のこと見てたんだ?」
「えぇ、まぁ…」
「ストーカー?」
「では、ありません」
とは言え、最近の私は彼女に遭遇することが多々あり、変な誤解を招く可能性は十分にあった。
「じゃあ何? 私のこと気になるんだ?」
「ハハハハハ…」
それはあなたの方でしょうとは口が裂けても言える訳もなく、笑ってごまかすので精一杯だった。
「笑ってごまかすな! もしかしてストーカー?」
「違いますよ…」
「やだぁ、怖い〜〜」
「何でそうなるんですか?」
「私のクラスの中を覗き見している男子がいるって愛実が言ってたんだよね。もしかして?」
「はい、私ですよ」
彼女が言う愛実と言うのは、あの気の強そうな泉田さんのことだ。確かに疑いの目で見られてたような…。
「誰を見てたの?」
「窓際の席の後ろから2番目の女子に少しばかり興味があって」
「ふ〜ん、その子とはどうなったの?」
「特に何の進展もありません。でも、まだわかりません」
「乞うご期待ってヤツね」
そう言うと、彼女はポケットの中から取り出したキャンディーを私にくれた。
「じゃあ、また明日」
彼女はスキップと言えなくもない軽快な足取りで図書室を出て行った。
−−翌日
図書室に入ると、まず初めにすることは彼女を探すこと。読みたい本を探す訳でもなく、図書室の中を探索した。
あっ…
すると、手を後ろに組みながら、つまらなそうに歩いている彼女の姿を目に捉えた。彼女は私には気づいていない。私は彼女の姿を確認すると、席についてカバンから参考書を取り出し始めた。
「やっほー」
しばらくすると私の存在に気づいた彼女が足早にやって来てそう言った。
「どうも」
「奇遇ねぇ」
「必然ですね」
「何それ?」
「出会うべくして出会ったということです」
彼女の目的は私。私に会うために来ている。彼女は授業に出ていない日も、放課後になると図書室にやって来た。ただ私に会うために。私は勉強をするために図書室に来ている。将来のために勉強をしに来ている。彼女がいれば勉強などはかどるはずはなかった。実際に彼女と図書室で会うようになってからは、私のノートは空白のままだ。そんなことはわかってて図書室に来ていた。だとするならば私は勉強をするという口実で彼女に会いに来ているということになる。つまり、私は彼女に会いたかった。
「何ですか?」
「何?」
「先程から私が勉強しているのを、ずっと見ていますけど」
「いけない?」
「構いませんけど、やりづらいです」
彼女は私の真向かいの席に座ると、両手を頬に当てて私を凝視していた。
「気にしないで! 邪魔はしないから」
「そう言われても、ちょっと…」
「いいから早く続きをやりなさいよ!」
彼女は私のシャープペンを手に取ると、白紙のノートをトントン叩いてきた。
「・・・・・。やっぱり集中出来ませんよ」
「だったら休憩しようよ」
「ふぅ~。そうすることにしましょう」
−−翌日
今日も放課後になり図書室にやって来ると、彼女の姿を探しに室内を歩き回った。
あれ?
おかしいなぁ?
まだ彼女は来てなかった。授業には出ているのは確認済みなので、まだ学校にいるはずなのに…。どうしたのだろう?
仕方なく席について机と向き合ってみたものの、彼女の顔ばかりが頭に浮かんでしまい、勉強どころではなかった。
気がつくと図書室の建物から外に出て彼女が来るのを待ちわびている私がそこにいた。いくら待っても来なかった。席に戻り参考書を開いても、何も身につかなかった。
「上城くん、もう閉館の時間になるわよ」
図書室の職員の佐々木さんに声をかけられた。しかも名前を覚えられてる。時計を見ると、閉館時間の18時になろうとしていた。
「すいません、今片づけて出ます」
「金髪の子、来なかったわね。日比野さんって言ったっけ?」
「あっ、はい」
「いつも早くに来てあなたを待ってたんだけどね」
色々とツッコミどころが満載だけど、私たちの情報は筒抜けのようだ。帰り支度を済ませて外に出たものの、直ぐに帰る気にはなれなかった。しばらくは、部活帰りの生徒たちの様子を眺めていた。
15分くらい経った頃、遠くの方から鼻歌交じりにテンポよく歩いてくる彼女の姿があった。
「今日は遅かったですね? 図書室から閉め出されましたよ」
「先生に職員室に呼び出されちゃって」
「どうかされたんですか?」
「別に」
「大丈夫なんですか?」
「何が?」
「学校を辞めさせられるようなことはありませんよね?」
「どういう意味? もしかして私が悪さして退学になるんじゃないかと思ってる?」
「違いますよ」
彼女が怒るのは無理もなかった。私の言い方が悪かったのは自覚していた。
「どうせあなたには私が不良にしか見えないんでしょ? 学校サボって悪い連中と付き合って、タバコ吸って、万引きして人に迷惑ばかりかけてる世の中の落ちこぼれくらいにしか見えてないんでしょ?」
彼女は持っていたカバンを地面に叩きつけて怒っていた
「誤解です。私はただ、あなっ‥」
「いいよ! いつも言われてることだから。でも、あなただけにはそんな風に思われたくなかった!」
「すいません。謝ります」
「うるさいっ! バカッ!」
彼女はそう吐き捨てると、地面のカバンを乱暴に拾い上げ走り去ってしまった。一瞬だったけど、彼女の頬に光るものが見えたような気がした。
−−3日後
「今日もあの子来なかったわね?」
「はい、もう3日になります」
図書室の閉館の時間が近づいたので片づけをしていると、職員の佐々木さんに声をかけられた。彼女が図書室に来なくなって、早くも3日の時が流れていた。彼女に会えない日々はとても長く感じられた。
「ケンカでもしたのかい?」
「ケンカという程のものではなかったはずなんですけど、誤解されてしまったようです」
「そうなのかい。それなら早く謝って仲直りするといいわね。時間が経てば経つほど修正が効かなくなるものよ。私みたいな図書室のおばさんの言うことも、たまには役に立つんだから」
「はい、ありがとうございます。それにしても、いつも騒がしくてすいません。迷惑じゃないですか?」
「迷惑ねぇ…それは、あなたじゃなくてあの子の方だけどね。それに、あなたたち以外に放課後に図書室に来る生徒なんていないから、来てくれるだけ嬉しいし有り難いわ」
「そう言ってもらえると助かります」
私の言い方のせいで彼女に不快な思いをさせ怒らせてしまったのは事実。不可抗力だったとしても、傷つけてしまったことへの言い逃れは出来ない。あれから彼女は学校にも来ていなかった。こんなことなら連絡先を聞いておくんだった。とは言え、いまいち進展しない私と彼女の距離感では、連絡先を交換するのはもう少しあとかもしれないし、今の距離感は決して嫌いじゃなかった。でも、彼女と離れて気がついたこともあった。私は彼女のことをもっと知りたいし、今よりもっと近づきたい。
彼女が学校に来なくなって1週間になる。私のせいだ。私が彼女を傷つけるようなことを言ったから。会って謝って許してもらい、今までのように戻りたい。そうしないといても立っても居られない。彼女に会えないと心が締めつけられるように苦しい。会いたい。こんな気持ちは初めてだ。
今は少しでも彼女に関する情報が欲しかった。私は昼休みになると隣のクラスの前のドアから中の様子を覗っていた。彼女の友達の鈴木さんを探した。でも、鈴木さんの姿はどこにもなかった。もう1人の友達の泉田さんもいないところをみると、2人で学食にでも行っているのかもしれない。
「あれ? あなたは確か…」
後ろから声をかけてきたのは、鈴木さんだった。鈴木さんの横には私を睨んでいる泉田さんの姿もあった。
「すいません、日比野さんは今日も学校へは来ていませんか?」
「日比野さん? あぁ、ひかりのことね?」
「はい。その日比野さんは今どこに?」
「今日は来てないわよ。っていうかさ、あなた5組の上城くんだよね?」
「はい、そうですけど」
「やっぱりね。でも、どうして成績も学年でトップクラスの上城くんが、ひかりなんかと知り合いな訳? 何か弱みでも握られてる?」
「そういう訳じゃありませんけど…。あの、日比野さんはどういう方なんですか?」
私と鈴木さんが話している横で、不服そうな顔をしている泉田さんがチラチラと視界の片隅に入ってくる。
「ひかりは、家庭の問題とか色々あって、あんな風になっちゃってるけど、優しくて友達想いで、真面目で本当に良い子よ。髪は金髪で不良っぽいし、授業も殆んど出ないけどそんなんじゃないわよ」
「随分と、日比野さんのことを詳しいんですね?」
「まぁね。だって私ひかりの親友だもん。中学時代からの付き合いよ。ちなみに私は、鈴木千夏。よろしくね」
「よろしくお願いします」
「こっちも中学からの友達の泉田愛実」
「よろしくお願いします」
「フンッ」
泉田さんは目を細めて私を見ると、そっぽを向いて教室に入ってしまった。
「私、嫌われてます?」
「まぁ、色々とあるのよ」
「そうですか…」
鈴木さんが言っている“色々”が何かはわからないけど、泉田さんを不快にさせるようなことをしたのは間違いないようだ。
「ひかりには、上城くんが訪ねて来てくれたことメールで送っとくね」
「お願いします」
−−翌日
もう1度隣のクラスに顔を出してみた。すると私の顔を見るなり、鈴木さんが走ってやって来てくれた。
「日比野さんは今日も来てないんですね?」
「うん。メールを送ったんだけど、返信はなかったのよね」
何となくそうなるんじゃないかとは予想出来た。私は自分の謝罪の気持ちを伝えるためにはどうしたらいいかを、昨日家に帰ってから考えた。考えた結果、ある1つの答えを導き出した。それは手紙で思いを綴り、読んでもらう。言葉では上手く伝えられない思いでも、手紙ならきっと伝えられる。話は聞いてもらえないけど、手紙なら読んでもらえるかもしれない。だから私は昨日の晩は遅くまでかけて手紙を書いた。読んでもらえるまで毎日でも手紙を書いて行こうと決意した。
「手紙かぁ。いいかもね」
「良かった」
「私も、ひかりがこのままだと困るし、出来ることはやらせてもらうわ」
鈴木さんに手紙のことを説明すると協力してくれると言ってくれた。
「ありがとうございます」
「私がひかりに直接渡してきてあげる」
「ちょっと待って。その役、私がやらせてもらうわ」
私と鈴木さんの会話を聞いていた泉田さんが話に割って入ってきた。しかも、泉田さんが手紙を渡してくれると言ってきた。あんなり私を毛嫌いしていた泉田さんが急に協力的に…。にわかには信じられなかった。
「ホントに? 愛実に任せていいの?」
「任せてちょうだい。私だって愛実に早く学校に来てもらいたいし」
「ご協力ありがとうございます」
そして、私は昨日書いた手紙を泉田さんに預けた。
あれから1週間が経った。手紙は5通書き、全て泉田さんに渡した。でも、何の反応もなかった。おかしいなぁ、ちゃんと読んでもらってるんだろうか? 読んでるのに無視されてる可能性もある。心配になってきた。とりあえず今日も、昨日書いた手紙を泉田さんに渡した。今日は確認したいことがあった。
放課後になると、図書室は行かずに廊下の隅に隠れて隣のクラスを監視した。
「上城くん、何やってるの?」
「泉田さんが出てくるのを待ってるんです」
「どうして?」
「泉田さんが私の手紙をちゃんと日比野さんに渡しているかを確認するためです」
「そうなんだ」
「って言うか、何で奥村くんがここに?」
「泉田さんのあとをつけるんだね?」
「まっ、まぁ、そういうことになりますけど…」
「僕も一緒に付き合うよ」
泉田さんの尾行に奥村くんも来ることになった。心強いと言えば心強い。
それから私たちは泉田さんを尾行した。泉田さんは学校を出ると、駅の近くのMACに立ち寄った。泉田さんの席には、ハンバーガーとポテトとドリンクが置かれていた。とりあえず、私はドリンクだけを注文し、奥村くんはセットメニューを注文した。泉田さんを見ると、スマホを操作しながらダラダラと食事をしている。動画を見ているらしく、時折笑顔が溢れていた。時間がかかりそうだ。
それからも泉田さんは食べては動画を見るという行為を繰り返し、30分ほどMACに滞在した。店を出ると今度は本屋に入り、立ち読みを始めた。
「泉田さん、手紙届ける気ないんじゃないのかな?」
「もう少し待ってみましょう」
「本当に届ける気があるなら、こんなに寄り道しないよね?」
「確かに…」
奥村くんの言う通りかもしれない。ちょっと寄り道しすぎだ。
15分経ち満足したのか、何も買わずに店を出て駅に向かった。改札を抜けて向かった先は下りのホームだった。
「自宅に向かってない?」
「日比野さんの家へ行くなら上りですからね…」
「まだつけるの?」
「ここまで来たら、最後まで見届けたいです」
「わかった。でも絶望的だと思うよ」
「はい…」
3つ目の駅で電車を降りると、今度は駅構内にあるコンビニに寄っていた。見つからないように外で待っていると、片手に買い物袋を下げて出てきた。ポテトチップなどのお菓子が入っているのが袋の外からでもわかった。
「家帰るまで、どんだけ寄り道するんだよ」
奥村くんは声を荒らげて、そう言った。
「奥村くんっ」
奥村くんの腕を引っ張って、建物の影に隠れた。奥村くんの声に反応した泉田さんが辺りをキョロキョロ見回していた。しばらくは息を潜めて、泉田さんが歩き出すのを待った。
ようやく歩き出したかと思ったら、駅から5分くらいの所にある公園に寄ってベンチに座ると、先程買ったお菓子を食べ始めた。時刻は19時を回っていた。いつもこんなことをしているのだろうか? 泉田さんは就職クラスだけど、他にするべきことがあるのではないだろうか?
お菓子を食べ終わった泉田さんが、そのあと自宅に帰ったのは言うまでもなかった。
「こうなるとわかってたけど、頭くるよね。手紙はどうしたんだよ!」
「今までも渡してなかったということですね」
「明日、泉田さんに言おうよ」
「いえ、見なかったことにしましょう」
奥村くんは納得していない様子だった。
泉田さんは自分から手紙を渡すと言ってくれた。信じて渡していたのに裏切られた。でも、不思議と怒る気持ちにはなれなかった。
−−翌日
隣のクラスを覗いていると、鈴木さんが直ぐに駆け寄って来てくれた。
「あの、日比野さんは?」
「今日も来てないわよ。そういえば手紙を書いて渡してるんだよね」
「えぇ、まぁ…」
手紙という言葉を聞いて、何も言えなくなってしまった。
「愛実に渡してもらうよう頼んだんだよね?」
「そっ、そうなんですけどね…」
「おかしいわね。ひかりのことだから、手紙を読んだなら何かしらの反応があってもいいんだけど…」
「・・・・・」
「ちょっと待って…もしかして、愛実のやつ渡してないんじゃ…」
鈴木さんはそう言うと、泉田さんが座る席まで歩いて行った。遠くから見ていても、鈴木さんが泉田さんに対して声を荒らげて怒っているのがわかった。
パシッ…
次の瞬間、鈴木さんが泉田さんの頬を思いっきり引っ叩いていた。
すると泉田さんは、両手を顔に当てて泣き出してしまった。普段の温厚な鈴木さんとは思えない行動に唖然としてしまい、見守ることしか出来なかった。
「えぇぇ…」
そこまでしなくても…
「上城くん、本当にごめんなさい。愛実、手紙を渡してなかったの」
私のところに戻って来た鈴木さんは、深々と頭を下げて謝ってきた。
「みたいですね」
「知ってたの?」
「昨日知りました」
「そうなんだ。ホントにごめん」
「もういいですよ」
「愛実はひかりのことを妹のようにかわいがってたから、上城くんに取られるんじゃないか心配だったんだと思う。悪い子じゃないの。それに上城くんのことも決して嫌ってる訳じゃないのよ」
「ひかりさんの親友が悪い人の訳ありません。あまり怒らないであげて下さい」
「ありがとう。本当に優しいのね。ひかりが好きになる気持ちもわかる気がする」
「・・・・・」
「ごめん、余計なこと言っちゃった」
「いいえ。それにしても心配ですね」
「そんなに心配なら、ひかりの自宅に行ってみたらいいじゃない? どお?」
「そうですね。行ってみます」
最初からそうしとけば良かったのかもしれない。
「ちょ、ちょっと待って。もしかしたら自宅にはいないかもしれない。今、地図書くから待ってて」
「ありがとうございます」
「はい、これ。ここに行けばひかりに会えると思うわ。十分気を付けてね」
「そんなに危険なところなんですか?」
「そうねぇ、危険ね。威圧的な態度をとってくるかもしれないわね」
「そんなに危険なところで、日比野さんは何をしているんですか?」
「上城くん、ひかりを危険な輩から救ってあげて!」
「わっ、わかりました。任せて下さい」
鈴木さんの言う危険なところがどこかなどわかるはずもなく、只々不安が募る一方であった。
学校が終わると、鈴木さんから渡された地図を頼りに、彼女がいるという場所に訪れた。
あれ?
ここって…
地図が間違っているのだろうか?
「すいませ~ん」
とりあえず中に入って、彼女に繋がる情報がないかをあたってみることにした。
「は~い。いらっしゃいまっ‥あっ…」
「日比野さん、ここで何を?」
「上城くん…」
私の前に現れたのは、私服にエプロン姿の彼女だった。
「もしかして、ペットショップでアルバイトしているんですか?」
「どうしてここが?」
「鈴木千夏さんに聞きました。〝ひかりを危険な輩から救ってあげて〟って言われて。まさかこんなところにいたなんて想定外でした」
「ヴヴゥゥゥ――ワンワンッ!」
「ワンワンワンッ!」
「ガルルルル――ワンワンッ」
ゲージの中に入っている犬たちが、突然私に向かって一斉に吠え始めた。
「私、何かやたらと吠えられていませんか?」
「いつもはおとなしいのに今日はどうしたんだろ? やっぱり動物にも良い人間か悪い人間かは、わかるものなのね」
「私は悪い人間だと思われたんでしょうか?」
「当然よ。私のことを不良とか言って、傷つけたんだから…」
「言ったのは私ではないんですけどね」
「言ったようなものよ」
「少しいいですか?」
「何? 何かよう?」
「話を出来ませんか?」
「・・・・・」
彼女は戸惑いを隠せない様子だった。
「店長〜」
沈黙の後、彼女は店の奥にいる、この店の店主を呼んでいた。
「休憩してきていいよ。ひかりちゃんにお客さんなんて滅多にないからね」
女性の店主は私が彼女を訪ねてきたことに気づいたらしく、嫌な顔ひとつせずに笑顔でそう言ってくれた。
「店長ありがとう。直ぐに戻って来るから」
それから私たちは住宅の一角にある公園に移動した。
「今日も学校には来ませんでしたね?」
「バイト先まで押しかけるなんて趣味悪いわよ!」
「急に来なくなるから、気になって勉強に身が入らないんです」
「私には関係ないわ!」
「もう来ないんですか?」
「どうして行かなきゃいけないの?」
「それならどうして私が勉強している図書室に来て、いつも私の隣に座っていたんですか?」
「いたいからいただけよ。何か文句ある?」
「もちろんありますよ」
「何よ! 言ってみなさいよ!」
「突然私の前に現れたと思ったら、私の世界にズケズケと入り込んで来て…気付いたら傍にいるのが普通になっていて…ちょっとしたイザコザで誤解されたと思ったら、突然私の前から消えてしまって…」
「何が言いたいのか全然わかんないんだけど?」
「つまりですね。勝手に私の前からいなくならないで下さい! 気になって勉強に手がつけられないし、毎晩胸の辺りが苦しくて眠れないんです」
「そんなの私のせいじゃないもん。私があなたの恋人ならまだしも、付き合ってる訳でも何でもないじゃない。私に言われても困るんだけど…」
「それなら、私と付き合って恋人になってもらえませんか?」
「嫌よ」
「どうしてですか?」
「絶対後悔したって思うに決まってるもん」
「もう既に後悔していますよ。あなたに出逢うまで無駄に17年も生きて来てしまったことを…」
彼女は何も言わずに、両手で目をこすっていた。
「好きなんですよ。あなたのことが」
「私だって…」
こうして私と彼女の恋は始まった。
私が彼女の彼氏になってから1週間が経った。電話番号とメールアドレスの交換はしていたので、いつでもどこでも繋がっていられた。彼女は思いのほか、独占欲が強いし束縛も強かった。でも特に嫌だとは思わなかった。お互い初めての恋人だったので、とにかく毎日がドキドキで楽しかった。何もしてなくても嬉しくて自然と笑みがこぼれてしまう。世界の色が何色か増えて明るくなったようだった。好きな人が恋人になるのが、こんなにも幸せだとは知らなかった。
いつも一緒にいたい。
顔を見ていたい。
声が聞きたい。
話がしたい。
見つめ合っていたい。
何ならキスをしたい。
あげればきりないくらい彼女に夢中の私がいた。そんな気持ちもあれば、逆に心配や不安もつきまとう。
どこにいるのか?
誰といるのか?
異性と会っていないか?
異性と話していないか?
この気持ちを払拭したくて連絡をする。声を聞くだけで気持ちが落ち着く。そんなことをしなくも彼女が私に夢中なのはわかっているはずなのに…。
また、彼女は1日に電話を何十回としてくる。朝だろうと昼だろうと夜中だろうが電話をしてくる。電話に出ないと怒る。メールは1日に50回は優に越える。もちろん返事をしないと怒る。彼女がしなくても、もしかしたら私がしていたかもしれない。それだけ恋は盲目なのだ。
彼女は毎朝、駅の改札口で待っていてくれた。そして学校までの通学路を一緒に歩いた。彼女は終始私と手を繋いだり抱きついたりしてきた。周りの視線を気になりつつも、少しばかり優越感に浸った。
学校では休み時間になると私の教室にやって来ては、前の席に座ってお喋りをした。昼食も食堂で一緒に食べた。放課後は教室に残って動画を観たりして楽しんだ。帰る間際になると、彼女はいつも目に涙を溜めて「帰りたくない」と涙ながらに訴えてきた。だからしばらくは電車のホームのベンチに座って手を繋ぎ、ただ行き交う人を眺めていた。
家に帰っても電話で何時間も話をした。夜中に突然電話してくることもあった。彼女は私に会いたくなると夜中でも会いに来た。私らしくないけど、私から会いに行ったこともある。こうして私と彼女は四六時中一緒にいた。
今日も1日中彼女といた。でも、放課後になると教室に来るはずの彼女が何故かやって来なかった。隣のクラスに行き、教室に残っていた鈴木さんに訪ねてみた。
「何も言ってなかったけど、どうしたのかな?」
鈴木さんはそう言った後、彼女に電話をかけてくれた。
「電源入ってないね」
「さっきはコールはしたんですけど…」
「バイトとか急用じゃないのかな? ひかりのことだから、上城くんに何も言わずに帰ることなんてないと思うんだけどな…」
「そうですよね」
そう言ったものの、嫌な予感が脳裏をよぎっていた。もしかしたらと思い、図書室を覗いてみたけど彼女はいなかった。何だか嫌な胸騒ぎがして、このまま図書室で勉強をする気にはなれなかった。
そのまま図書室を出て、校門に向かって歩いていると、校門を抜けた先には見慣れないガラの悪い連中が3人ほどいた。目を合わせないように下を向いて歩いていると、私の前を何かが立ち塞がった。顔を上げると先程の連中だった。
「おいお前、上城真一だな?」
「はい、そうですけど…」
私の名前を呼んだこの人は決して私の知り合いではない。目も合わせてないし、彼らの気に障るようなことはしてはいないはず…。声をかけられる覚えはない。私に声をかけてくるなんて、どういう要件だ。
「ちょっと顔かせや?」
「はい…」
そう言うと、校門から少し離れた場所まで連れられて来てしまった。
「俺らは、この辺一帯を取り仕切ってる龍神会っていう暴走族のもんだ」
「そんな方たちが私に何のようでしょう?」
「うちの総長がお前にこれを渡してこいってな」
彼らのうちの1人から半紙と思われる紙を渡された。
「読んでみろ」
「はい」
四つ折りにされた紙を広げると、そこには筆で書かれたプロ並みの達筆の文字が綴られていた。
「すごい達筆ですね」
「いいから、さっさと読め」
目を通すとそこには…
【日比野ひかりは預かった。返して欲しければ、18時に1人で〇〇埠頭の第三倉庫に来い。警察や誰かに知らせたら面倒なことになるからな】
この文章を読んだ限り、彼女は暴走族に拉致されたらしい。色々とツッコミどころがあるけど、18時までに1人で行かなければならない。
「遅れずに来いよ」
「わかりました」
連中は私の体にワザと肩をぶつけると「じゃあな」と言って去って行った。それにしても大変なことになった。本当に私一人で行って大丈夫なのだろうか? 不安しかなかった。でも、 迷っている暇はなかった。
直ぐに学校までタクシーを呼んだ。親から渡されていたタクシーチケットを使って指定された場所に向かった。そして、目的の場所の近くで降ろしてもらうと、第三倉庫が見えてきた。ここに彼女が捕まっているのか…。
倉庫の前まで来ると、バイクのエンジンをふかしている爆音が嫌になるほど聞こえてきた。地面が揺れ体が震えているような感覚に陥った。倉庫の中に入り、恐る恐る歩みを進めていくと、突然おびただしい数の光に照らされた。一瞬目がくらんだけど、それがバイクのライトだというのが徐々にわかってきた。バイクには特攻服を身にまとい、金属バットや鉄パイプを手に持った連中が何十人といた。
「よく1人で来たな。大したもんだ」
バイクがずらっと並べてある1番奥から出てきた人物がこちらに歩いて来てそう言った。男は身長が190cmを超えるような大男だった。ガタイもかなりいい。
「来ました。約束ですから」
「俺はこの暴走族の総長の柏木だ。あんた俺たちがどういう人間かわかって来たんだろ?」
「はい…」
「そうか、来たのは褒めてやる。でも、ただで帰す訳にはいかねえ」
「じゃ、じゃあどうしたら?」
「そうだな、1発ずつ順番に殴り合うってのはどうだ?」
柏木という男は不敵な笑みを浮かべ、舌なめずりをしていた。
「断っても無駄なのはわかっています」
「なら話は早い。早速始めようか?」
「はい…」
覚悟を決めるしかなかった。彼女を助け出すためなら何でもやるつもりだ。でも、私は喧嘩などしたことないし、まして人を殴ったことなどない。
「そうしたら、特別サービスだ。お前から殴っていいぞ。その1発で俺を仕留めることが出来たらお前の勝ちだ」
「わかりました」
「いいぞ、こいっ!」
「はいっ」
私は右手を強く握りしめ、思いっきり力を込めた。そして男に向かって体ごと力いっぱい殴りかかった。
「あぁぁぁぁぁっ」
ゴッ…
「えっ…」
男は私の拳を顔面で受け止めた。
しかも、笑ってる。
「いいねえ。なかなかだ。でも、そんなパンチじゃ何十年経ったって俺には叶わねえ」
「・・・・・」
「そしたら次は俺の番だな。覚悟しな!」
男は私に握り拳を見せると、思いきり振りかぶった。もう駄目だ。でも、逃げる訳にはいかない。
「こんなもんでいいだろ。上城、目を開けていいぞ」
「えっ…」
「悪かったな。茶番に付き合わせちまって。出て来いよひかり!」
男がそう言うと、物影から彼女がうつむき加減に現れた。
「日比野さん…」
「ひかりは何も悪くねえんだ」
「どういうことですか?」
「ひかりに恋人が出来たっていうから試させてもらった。お前は誰にも言わずにここに来た。そして負けるとわかっていた俺とのゲームに乗っかった。合格だ」
男は私の肩を掴んで揺さぶってきた。
「ごっ、ごうかくですか…ハハハハハッ…」
「上城、お前にはどんなことがあっても、ひかりを守っていく覚悟はあるか?」
「もちろんです」
「死ぬ覚悟はあるか?」
「あります」
「そっか。だってよ、ひかり」
「うるせえクソアニキ!」
彼女は男に向けてアッカンベーをしていた。
「こいつは、3歳離れた俺の幼馴染み。妹のようなもんだ。ちなみに、ひかりはうちの暴走族のメンバーじゃねえからな」
「私は日比野さんが暴走族のメンバーでも何でも構いません。私はありのままの日比野さんが好きなんです」
「お前は面白え奴だな」
男は腹を抱えて笑っていた。
「真面目に言ってるんてすけど…」
「お前は、ひかりを命をかけて守れ。お前とひかりの2人は俺が命をかけて守ってやる」
男は握った拳を私の胸に押し当ててそう言った。見かけとは違って情に厚い人のようだ。日比野さんの幼馴染みなんだから良い人に決まってる。
それから私と彼女は暴走族の皆さんに見守られながら第三倉庫をあとにした。
「上城くん、怒ってる?」
私の横を歩く彼女は、恐る恐る上目遣いでそう聞いてきた。
「何がですか?」
「アニキの奴があんなことして…」
「怒ってませんよ。日比野さんは何も悪くないじゃないですか」
「そうだけど…」
「それに柏木さんが、あなたを心配する気持ちもわかります。大切に思ってくれる人がいることは有り難いことですよ」
「上城…しっ、しんいち…」
「何ですか?」
彼女が私を初めて名前で呼んだ瞬間だった。
「何ですか? じゃないでしょ! 今、あなたのことを名前で呼んだんだよ。もっと何かリアクションしてよ!」
顔を真っ赤にしてそう言った彼女の様子から、恥ずかしいのに無理して名前を呼んだのが嫌というほど伝わってきた。
「すいません。でも嬉しかったですよ。ひかりさん…」
「ひかりでいいよ」
「名前を呼び捨てで言うなんて初めてです」
「さあ、早く」
彼女は私の前に立ち塞がり強く迫ってきた。
「ひっ、ひかり…」
「いい感じ。それより、さっきアニキに言ったことたけど本気?」
「何か言いましたっけ?」
「私のために死ぬ覚悟があるって言ったこと…」
「冗談でそんなこといいませんよ。本気です」
「そっ、そう…」
「迷惑でしたか?」
「そう言うことを本気で言うの、テレビや映画の中だけだと思ってた。まさか私が言われるなんて思わなかった」
「私とひかりのラブストーリーはドラマや映画じゃ語りきれませんけどね」
「だよねぇ」
彼女は背伸びをすると私の首に手を回して抱きついてきた。私は彼女の背中に手を回し抱きしめた。そしてその愛おしい彼女の唇にキスをした。
プルルルル−−プルルルル−−
『もしもし』
『どこにいるんですか? 約束通りに公園に来ましたよ』
『今行くから待ってて』
『はい』
『笑わないでよ』
『何をですか?』
『私を見ても』
『何だかわかりませんが、笑いませんよ』
『絶対だからね!』
『絶対に笑いません』
10分後――
「お待たせ!」
「あっ…」
「どぉ?」
「きゅ、急にどうしたんですか?」
「そんなことどうでもいいから感想は?」
「感想ですか…とっても似合うと思います。素敵です」
「本当にそう思ってる?」
「思っています。金髪も嫌いじゃありませんでしたけど、黒髪のあなたも嫌いじゃありません」
私の前に現れたひかりは髪をショートボブくらいに短く切り、黒く染めていた。
「〝嫌いじゃありません〟何その言い方? 何なのっ!」
「怒らないで下さい。これでも結構照れながら言っているんですから」
「そうは見えないけど」
「訂正します。金髪のあなたも好きでしたけど、黒髪のあなたはもっともっと大好きです」
「あっ、ありがとう」
「でも、なぜ黒髪に?」
「だって、学年で優等生のあなたの隣に金髪の彼女がいたら変でしょ?」
「まぁ、一応校則があるので金髪はまずいと思いますが、私の彼女が金髪だろうが黒髪だろうが、他の方には関係ありませんよ」
「黒髪にしても、真一とは不釣り合いかもしれないけど、出来るだけあなたに相応しい女性になろうと思ったの」
「あなたにもそんなに可愛らしい一面があったんですね?」
「ブッ飛ばすよ!」
ひかりは握り拳を私の前でチラつかせてそう言った。
「まぁまぁ。でも、相応しいとか相応しくないとか、そんなものありませんよ。金髪のあなたが私に相応しくないとは思いませんし、黒髪のあなたが私に相応しいとも思いません」
「だけど、世間的にはダメでしょ?」
「大切なのは私があなたを好きで、あなたが私を好きということです」
「マジでムカつくんだけど。黒髪にした意味ないじゃん…」
「そんなことありません。私のために黒髪にしてくれたあなたの気持ちはすごく嬉しいし、そんなあなたを前よりもっと愛おしく想います。つまりあなたを、好きで好きで仕方ないということです」
ひかりの気持ちが嬉しくて自然と涙が溢れてきた。私の彼女はなんて純情で可愛らしいんでしょうか。
「………なら許す」
「ありがとうございます」
その日は、暗くなるまで公園で寄り添い、ただ空を眺めていた。
「この問題どうやるの?」
「これは、こうやってこうやって解くんです。わかりまっ‥。はぁ…何で私を見つめてるんですか?」
「だって勉強を教えてる姿がカッコイイなぁっと思って」
「はいはい、ありがとうございます。嬉しいですけど、今はそんなことしてる場合じゃないですよ。テストが1週間後に控えているんですから」
「わかってる。今度のテストで赤点とったら進級出来ないんでしょ?」
「そうです。わかっているなら真面目に勉強して下さい!」
「は〜い」
ひかりは出席日数は担任の先生のおかげで何とかギリギリセーフだけど、成績の方に問題があった。前回のテストも赤点を取り、再試再試と2度もテストをやり直しをさせられていた。
「そしたら次にこのもんだっ‥」
「店員さ~ん、すいませ~ん。追加で山盛りポテト1つ下さ~い」
「ちょ、ちょっと何で注文しているんですか? って言うか、そもそも何でファミレスでテスト勉強なんですか?」
「仕方ないでしょ。図書室は18時までしか使えないんだから」
「だからって、もっと落ち着ける場所があったと思いますけど」
「落ち着ける場所って? ラブホとか? でも、ラブホなんか行ったんじゃ、真一が勉強にならないんじゃないの?」
何も言い返せなくなってしまった。ひかりは私が、この手の話が苦手なのをわかっていて、わざとする。
「・・・・・。さぁ、ふざけてないで始めますよ!」
「もぉ~、そういう話をすると顔を赤くしてムキになって怒るんだから。ちょっとくらい、いいじゃない」
「どうしたら真面目に勉強してくれるんですか?」
「キスしてくれたらいいよ」
「じゃ、じゃあ…店を出たらしますから、しっかり勉強して下さい」
「ダメっ! 今して! 今してくれないなら勉強なんてしないから!」
「〝勉強なんてしないから〟って、あなたのための勉強ですよ。何言っちゃっているんですか!」
突然の彼女の申し出に声が裏返ってしまった。
「あぁぁぁぁぁ~〜。いちいちうるさいな! するのかしないのかハッキリしてよ!」
「しっ、しますよ。進級してもらわなきゃ困りますからね」
「ならしてよ。目をつぶってあげるから早くしてよね」
「誰かに見られていませんか?」
夕食時ということもあり、店内は席が埋まりつつあり、人もそれなりに大勢いた。
「気にしないで。私を好きなら、そんなことは気にせずに出来るはずよ。これで真一の私に対する気持ちがわかるわね」
「わかりました。しますよ、いいですか?」
「うん」
チュッ…
目をつぶっているひかりの唇にライトキスをした。
「ほっ、本当にするんだ。ビックリなんだけど…」
「私の気持ちを疑われては困りますから」
「だったら私もお返し!」
ブチュッー…
ひかりは私の頬を手で押さえつけると、プレッシャーキスをしてきた。唇が重なっている時間は、ものすごく長く感じられた。こんな感じで試験までの数日は、2人で勉強をした。その甲斐があってか、テストは赤点ギリギリてクリアした。
−−数日後
「私のこと飽きたの?」
「どっ、どうしてですか?」
学校からの帰り道、ひかりから思わぬ言葉をかけられた。
「最近学校終わってから会う回数が減ったような気がするし…」
「そんなことないですよね?」
「それに変な噂も聞いてるし…」
「変な噂? 何ですかそれ?」
「自分の胸に聞いてみたら!」
「そうしてみます」
変な噂…
それはひかりにとって嫌な話、おもしろくない話ということには違いないと思うけど何も思い浮かばない。
「どお?」
「・・・・・。やっぱり何も出てきません。それより次のテストまで1ヶ月を切ったので、今のうちから勉強を始めましょう。前回は何とか赤点は免れましたが、ギリギリで危なかったんですからね」
「こんな気持ちのままじゃテスト勉強なんて出来ない!」
「何か色々と誤解されているようなので、弁解させて頂きます」
「どうせ言い訳でしょ?」
「そんなこと言わずに聞いて下さい。始めに、会う回数が減ったという話ですが、平日は学校が終わったあとに3日、土日は毎週のように会ってるじゃないですか」
「前は平日も4日とか5日も会ってた」
「それは、ひかっ‥」
プルルルル――プルルルル――
私の言葉を遮るように電話が鳴った。
「電話鳴ってるわよ。さっさと出なさいよ」
「あっ、はい。では失礼します」
ピッ…
『もしもし』
『もしもし上城くん、頼みがあるんだけど』
『はい、何ですか?』
『実はね、今日のしっ‥』
ひかりは突然、耳に当てていたスマホを引ったくると私を睨みつけた。
「ちょっと誰? 女でしょ?」
「そうですけど、彼女はわっ‥」
「バカッ! 信じてたのに!」
「何を言っているんですか? ごっ、誤解です!」
「何が誤解よ! 私のことなんて遊びだったんでしょ!」
「違います。話をちゃんと聞いて下さい」
「聞くもんですか! こんなスマホがあるからいけないのよ!」
「ちょ、ちょっと、私のスマホをどうするんですか?」
「うるさい! こんなもの!」
バンッ…
地面に叩きつけられたスマホは、画面は割れて、部品の一部が露出してしまった。
「あぁ…」
「真一なんて、サイテーよ!」
「まっ、待って下さい。明日は会えますよね?」
「もう別れてやるんだから! さよなら!」
パシッ…
ひかりは私の頬を思いきり叩くと、泣きながら走って行ってしまった。
−−翌日
今日は朝から、ひかりは私を避けていた。全く私に近づこうとしなかった。
放課後になると急いでひかりのクラスを訪れてみた。しかし、ひかりの姿はどこにもなかった。
「さっきまでいたんだけど、どこ行ったんだろ?」
鈴木さんにひかりの居場所を尋ねたものの、わからないようだった。
図書室や食堂など、心当たりがある場所には全てあたってみた。それでもいなかったので、階段を駆け足で登って行った。
「探しましたよ。まさか屋上にいるとは思いませんでした」
ひかりはフェンスを掴んで遠くを眺めていた。
「上城くんには関係ないじゃない」
「上城くん? まだ怒っているんですか?」
「何を怒る必要があるの?」
「ひかり、本当に誤解なんですよ」
「誤解? そんなに誤解を解きたいなら電話してくればよかったでしょ! 電話の1本もよこさないで何が誤解よ!」
「ふぅ~。とりあえずその話は置いときましょう」
「やだっ!」
ひかりは大声で叫ぶと、反対側のフェンスに向かって歩き出した。
「ひかり…」
「なに?」
「お誕生日おめでとう!」
「誕生日?」
「やっぱり忘れていたんですね? 今日はひかりの誕生日ですよ」
「あっ…そういえば…」
「こんな大事な日を忘れないで下さいよ」
「真一のせいでしょ!」
「そうですね、すいませんでした。お詫びのしるしに、誕生日プレゼントを用意させてもらいました。どうぞこれを」
背後に隠していたプレゼントをひかりに差し出した。
「何これ?」
「開けて見て下さい」
「ゆっ、指輪?」
「そうです。でも、ただの指輪ではありません」
「どういうこと? 私にはとってもキレイな指輪にしか見えないけど」
「婚約指輪です」
「えっ…」
「何年か経って、お互い大人になったら結婚しましょう」
「本気?」
「本気です。嘘偽りはありません」
「いいの私で?」
「あなたでなければ駄目なんです。それに、これくらいしなければ私の気持ちはわかってもらえなさそうなので」
「真一っ!」
ひかりは私の胸に飛び込んで来ると、これ以上ない力で抱きしめてきた。
「そんなに強く抱きしめられたら痛いですよ」
「うるさい!」
「このままでいいから聞いて下さい。私たちの会う回数が減ったのは、ひかりがバイトの日数を増やしたせいですよ。それに実は秘密にしてたんですけど、ひかりの誕生日プレゼントを買うために短期のバイトをしていたんです。昨日の電話の女性はバイト仲間の町田さんです。急用ができたのでバイトを代わって欲しいという電話でした。変な噂を耳にしたというのは、たぶんデパートでいとこの晴美さんと一緒に歩いていたところを偶然誰かに見られたのでしょう。晴美さんには指輪を買うのを付き合ってもらいました。ついでに言わせてもらうと、昨日電話の1本もかけられなかったのは、あなたにスマホを壊されたからです」
「えぇぇぇぇっ…全部私が悪いんじゃん。ゴメン…」
ひかりは私の胸の中から顔を上げると、潤んだ瞳で私をジッと見て謝っていた。
「いいんですよ。私もあなたを不安にさせていた訳ですから」
「真一、大好きだよ!」
「はい、私もです」
それから私とひかりは互いの指に指輪をはめあった。まるで結婚式の指輪の交換のように…永遠の愛を誓いあった。