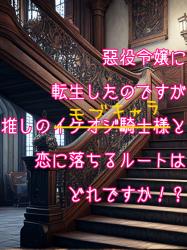「君がどこまで立花財閥のことを知っているかは分からないけれど、最近は赤字ばかりが増えていたんだ。あのお見合いは、立花側からしたらかなりいい話だったと思うよ。あそこの社長さん、やり手だから」
「じゃあ、なんで彼は立花家との縁談を?」
「それはね、僕が頼んだから。あんな将来性のある企業、桜堂が易々逃すわけがない。僕が桜堂グループの傘下に入れる代わりに、君との縁談を演じてくれるよう頼んだんだ」
「――全部、悠賀様がしたことだったのですか……?」
「ああ。君が『立花依恋』だと確証を得てすぐ、どうにか君の心を僕に向けて欲しくて、立花家にも君を見つけて欲しくて――宣戦布告という意味でだよ――君をパーティーのパートナーに誘った。残業だと言えば、君は断らないだろうから」
悠賀様は申し訳なさそうに眉をひそめた。
「けれど、立花財閥が君を攫いに来るのが思いのほか早くてね。立花家での君の味方も見つけたし、君のことは彼女に頼んでおいたんだけれど、……それでも、依恋には怖い思いをさせてしまったね」
「晶子さん……」
晶子さんは立花家に呼ばれたと言っていたけれど、本当は悠賀様に頼まれて立花家に戻ったんだ。
そういえば、彼女に『きっと幸せは訪れる』とか、言われたような……?
「立花家を解体するのは、立花家にもいいことだと思う。あのままじゃ赤字が募って、どっちにしろ解体せざるを得なかったと思うんだ。傘下の企業は、桜堂が引き受けた。これから立花家は、元来の重工業のみに戻ってもらって――」
じっと聞いていれば、悠賀様は私だけじゃない、立花家の未来も考えてくれていることが分かる。
でも、それって――。
「どうして悠賀様は、そこまで立花家を? 確か、互いに敵視していると――」
「立花家の人たちからしたらそうかもね。けれど、桜堂は江戸からの旧家。立花は大正からの新興財閥。確かに一時は力が強かったけれど、桜堂には及ばないよ。それに――」
悠賀様は私の頭をそっと撫でた。
「立花家は、君が育った場所だ。全部を無くしたら、君が嫌がると思ったんだ」
「悠賀様……」
この人は、やっぱりとても優しい人。
温和怜悧な、御曹司様。
「まあ、僕としてはそんな話よりも、依恋と別のことを話したいんだけどね」
悠賀様はおどけるように、ははっと笑った。
「じゃあ、なんで彼は立花家との縁談を?」
「それはね、僕が頼んだから。あんな将来性のある企業、桜堂が易々逃すわけがない。僕が桜堂グループの傘下に入れる代わりに、君との縁談を演じてくれるよう頼んだんだ」
「――全部、悠賀様がしたことだったのですか……?」
「ああ。君が『立花依恋』だと確証を得てすぐ、どうにか君の心を僕に向けて欲しくて、立花家にも君を見つけて欲しくて――宣戦布告という意味でだよ――君をパーティーのパートナーに誘った。残業だと言えば、君は断らないだろうから」
悠賀様は申し訳なさそうに眉をひそめた。
「けれど、立花財閥が君を攫いに来るのが思いのほか早くてね。立花家での君の味方も見つけたし、君のことは彼女に頼んでおいたんだけれど、……それでも、依恋には怖い思いをさせてしまったね」
「晶子さん……」
晶子さんは立花家に呼ばれたと言っていたけれど、本当は悠賀様に頼まれて立花家に戻ったんだ。
そういえば、彼女に『きっと幸せは訪れる』とか、言われたような……?
「立花家を解体するのは、立花家にもいいことだと思う。あのままじゃ赤字が募って、どっちにしろ解体せざるを得なかったと思うんだ。傘下の企業は、桜堂が引き受けた。これから立花家は、元来の重工業のみに戻ってもらって――」
じっと聞いていれば、悠賀様は私だけじゃない、立花家の未来も考えてくれていることが分かる。
でも、それって――。
「どうして悠賀様は、そこまで立花家を? 確か、互いに敵視していると――」
「立花家の人たちからしたらそうかもね。けれど、桜堂は江戸からの旧家。立花は大正からの新興財閥。確かに一時は力が強かったけれど、桜堂には及ばないよ。それに――」
悠賀様は私の頭をそっと撫でた。
「立花家は、君が育った場所だ。全部を無くしたら、君が嫌がると思ったんだ」
「悠賀様……」
この人は、やっぱりとても優しい人。
温和怜悧な、御曹司様。
「まあ、僕としてはそんな話よりも、依恋と別のことを話したいんだけどね」
悠賀様はおどけるように、ははっと笑った。