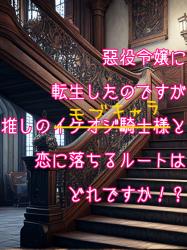お見合いはつつがなく進む。
お見合いなんていうけれど、実質この人との結婚は確定的だ。
私は道具に過ぎなくて、つまり立花家に捨てられたようなものだ。
この人の会社は、私を妻にする代わりに立花財閥の傘下に入る。
立花財閥は、この人の会社の技術や業績を独占できる。
家と会社とをつなげる婚姻。私に断るという選択肢はない。
これは、政略結婚であり、そこに恋愛など存在しない。
相手はベンチャーIT企業の社長だった。
まだ若いというけれど、もうすでに40歳。
庶民の出の苦労人で、企業を立ち上げるまでに時間がかかったという。
けれど、会話の中身は全て隣に座る叔父様に向けられていた。
私に対しては冷たく、見下すような視線を投げてくる。
居心地が悪い。
けれど私は、この人を生涯の伴侶に選ばなくてはならない。
「立花家の後ろ盾があれば、こちらとしても――」
まだゴマをする男性を見て、私は顔を伏せた。
彼はどうせこちらなど、見ていない。
私の幸せは、終わってしまったんだ。
父母の死んだ、あの日で。
悠賀様が私にかけた魔法の一夜は、そんな私を哀れんだ神様が、最後に夢を見せてくれただけだろう。
――悠賀様……。
今ごろ、彼はどうしているだろうか。
私がいないと気づいて、捜索をしてくれてはいないだろうか。
いいえ、と思い直す。
そんなはずはない。
私なんかを気にかけるほど、彼は暇じゃない。
お見合いなんていうけれど、実質この人との結婚は確定的だ。
私は道具に過ぎなくて、つまり立花家に捨てられたようなものだ。
この人の会社は、私を妻にする代わりに立花財閥の傘下に入る。
立花財閥は、この人の会社の技術や業績を独占できる。
家と会社とをつなげる婚姻。私に断るという選択肢はない。
これは、政略結婚であり、そこに恋愛など存在しない。
相手はベンチャーIT企業の社長だった。
まだ若いというけれど、もうすでに40歳。
庶民の出の苦労人で、企業を立ち上げるまでに時間がかかったという。
けれど、会話の中身は全て隣に座る叔父様に向けられていた。
私に対しては冷たく、見下すような視線を投げてくる。
居心地が悪い。
けれど私は、この人を生涯の伴侶に選ばなくてはならない。
「立花家の後ろ盾があれば、こちらとしても――」
まだゴマをする男性を見て、私は顔を伏せた。
彼はどうせこちらなど、見ていない。
私の幸せは、終わってしまったんだ。
父母の死んだ、あの日で。
悠賀様が私にかけた魔法の一夜は、そんな私を哀れんだ神様が、最後に夢を見せてくれただけだろう。
――悠賀様……。
今ごろ、彼はどうしているだろうか。
私がいないと気づいて、捜索をしてくれてはいないだろうか。
いいえ、と思い直す。
そんなはずはない。
私なんかを気にかけるほど、彼は暇じゃない。