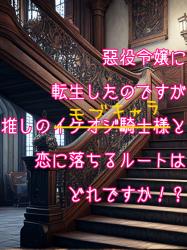着せられた振袖は、朱の地に二羽の鶴が舞っている。襟元には橘の白い花が細々と描かれ、どれも金色の糸で縁取られていた。
髪はゆるいシニヨンで纏められ、帯は金色に輝く錦織。
――ああ、ついにこの日が来てしまった。
おしろいを塗られ、真っ赤なリップを纏う。
私は今日、お見合いをする。
「ふん、馬子にも衣裳だな。まるで立花家の令嬢になったようだ」
庭へ出ると叔父様がそう言って、さっさと車に乗り込む。
顎で「私に続け」と指示され、そうするしかなかった。
立花家を出た車の中。
隣に座る叔父様は私の方など見ずに、窓の外に視線を向けている。
「いいか、絶対に粗相はするなよ。口答えもするな。お前にこの婚姻に反対する資格はない。兄と同じく、お前は裏切り者なのだからな」
低い声で言われ、「はい」と頷いた。
私はこの声に逆らえない。
自分の手で、人生を切り開いてきたと思っていた。
けれどその実、ちっぽけな逃亡に過ぎなかった。
私の居場所は、ここなのだ。
立花家の人間なのだから、仕方のないことなのだ。
それが、私に一番ふさわしい。
諦めればいい。
幸せな日々を捨て、また心を閉ざせばいい。
私はぐっとこぶしを握り締めた。
幸せな過去――悠賀様への恋心に、決別するために。
髪はゆるいシニヨンで纏められ、帯は金色に輝く錦織。
――ああ、ついにこの日が来てしまった。
おしろいを塗られ、真っ赤なリップを纏う。
私は今日、お見合いをする。
「ふん、馬子にも衣裳だな。まるで立花家の令嬢になったようだ」
庭へ出ると叔父様がそう言って、さっさと車に乗り込む。
顎で「私に続け」と指示され、そうするしかなかった。
立花家を出た車の中。
隣に座る叔父様は私の方など見ずに、窓の外に視線を向けている。
「いいか、絶対に粗相はするなよ。口答えもするな。お前にこの婚姻に反対する資格はない。兄と同じく、お前は裏切り者なのだからな」
低い声で言われ、「はい」と頷いた。
私はこの声に逆らえない。
自分の手で、人生を切り開いてきたと思っていた。
けれどその実、ちっぽけな逃亡に過ぎなかった。
私の居場所は、ここなのだ。
立花家の人間なのだから、仕方のないことなのだ。
それが、私に一番ふさわしい。
諦めればいい。
幸せな日々を捨て、また心を閉ざせばいい。
私はぐっとこぶしを握り締めた。
幸せな過去――悠賀様への恋心に、決別するために。