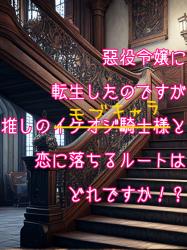「本当、何と申していいか……。立花家から旅立ちになった依恋様を、立花家に連れ戻すような形になってしまって――」
晶子さんは私の背を撫でながら、ゆっくりと話してくれる。
そんなことない。
晶子さんは何も悪くない。
それに、晶子さんには十分にしてもらった。
そう伝えたいのに、涙が止まらない。
ひっくひっくと肩を揺らすことしかできず、何も言えない。
「けれど、晶子は依恋様にはあきらめないで欲しいのです。きっと幸せは訪れます。不幸せは、永遠には続きません」
晶子さんは、私を慰めてくれるのだろう。
そんな彼女に、私は小さくこくりと頷き返すことしかできなかった。
*
それから数日。
どこへ連絡を取ることも許されず、私は部屋の中でほぼ監禁状態だった。
食事を持ってきてくれるメイドは晶子さんではない。
だから、誰も話し相手がいない。
幼いころに読んだ本たちが、まだ部屋に残っていた。
それをぱらぱら捲りながら、ただ一日をぼうっと過ごす。
諦めてしまえば簡単なこと。
何もしなければ、何も失わない。
心が動かなければ、寂しくも悲しくもない。
そうやって、心が沈まないように、平静さに努めた。
子供のころからそうやって生きてきた。
仕方のないことだ。
自分が立花家の人間である運命からは、逃れられない。
たとえそれが、自分が望んで得たものではないとしても。
頭に浮かぶ悠賀様の笑顔は、無理やりにかき消した。
心を押し殺して、無になる。
私はそれでしか、生きられない。
けれどもその日、私は無ではいられなかった。
朝から、晶子さんが部屋に飛び込んできたのだ。
「依恋様、準備をいたしますよ!」
晶子さんは私の背を撫でながら、ゆっくりと話してくれる。
そんなことない。
晶子さんは何も悪くない。
それに、晶子さんには十分にしてもらった。
そう伝えたいのに、涙が止まらない。
ひっくひっくと肩を揺らすことしかできず、何も言えない。
「けれど、晶子は依恋様にはあきらめないで欲しいのです。きっと幸せは訪れます。不幸せは、永遠には続きません」
晶子さんは、私を慰めてくれるのだろう。
そんな彼女に、私は小さくこくりと頷き返すことしかできなかった。
*
それから数日。
どこへ連絡を取ることも許されず、私は部屋の中でほぼ監禁状態だった。
食事を持ってきてくれるメイドは晶子さんではない。
だから、誰も話し相手がいない。
幼いころに読んだ本たちが、まだ部屋に残っていた。
それをぱらぱら捲りながら、ただ一日をぼうっと過ごす。
諦めてしまえば簡単なこと。
何もしなければ、何も失わない。
心が動かなければ、寂しくも悲しくもない。
そうやって、心が沈まないように、平静さに努めた。
子供のころからそうやって生きてきた。
仕方のないことだ。
自分が立花家の人間である運命からは、逃れられない。
たとえそれが、自分が望んで得たものではないとしても。
頭に浮かぶ悠賀様の笑顔は、無理やりにかき消した。
心を押し殺して、無になる。
私はそれでしか、生きられない。
けれどもその日、私は無ではいられなかった。
朝から、晶子さんが部屋に飛び込んできたのだ。
「依恋様、準備をいたしますよ!」