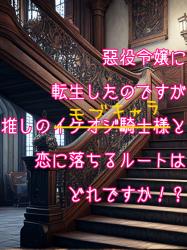信じたくないことが、現実に起こってしまった。
『Ellen Tachibana』
そう記されたメモは下に、『Gold Coast, Maryland』と続いていた。
資料のページは、私の履歴書のコピー。
『氷室』の文字が、赤い丸で囲まれている。
――悠賀様は、私のことを知っていた。それに、私の過去も。
やはり、悠賀様の専属メイドというのは建前。
私が立花家の人間だから、表に出ない仕事を言いつけられたのだ。
立花家の人間である私の顔を、お客様に顔を見られないように。
桜堂グループで立花家の人間が働くなんて、御法度だ。
なのに、それをすり抜けるように働き始めてしまった。
そんな身の程知らずな私は、立花家にとっても桜堂家にとっても恥。
悠賀様も、そう思っているに違いない。
慌てて資料を戻し、ほう、と息をつく。
けれど、まだ心臓はドクドクと嫌な音を立てている。
落ち着け落ち着けと、ダスターを握ったのと反対の手を胸にあてた。
何度か深呼吸を繰り返し、冷静さを取り戻した。
――大丈夫、クビを言い渡されたわけじゃない。
今朝だって、悠賀様は褒めてくれたばかりだ。
けれど、何のために? という疑問が浮かび、期待しては無駄だと絶望し。
一人問答を脳内で繰り広げながら支配人室を清掃していたら、いつの間にか終業時刻を過ぎてしまった。
*
一週間が過ぎた。
時折、悠賀様や執事さんがやってきて、仕事の様子を確認して帰っていく。
けれど思っていたような追及はなく、のびのびと仕事をこなすことができていた。
それでも、不安は拭えなかった。
いつ立花家の人間だと追及されるのか、震えながら悠賀様のお部屋を清掃する毎日だった。
今日も清掃業務を終え、用具室に清掃道具を返す。
扉をしめ、鍵がかかったことを確認し、エレベーターホールに向かおうとしたところで、ちょうどエレベーターが開いた。
悠賀様と、執事さんが降りてくる。
「お、お疲れ様です」
慌てて彼らの方に向き直り、頭を下げる。
すると悠賀様は「ちょうど良かった」と頭を下げたままの私の肩を叩いた。
「支配人室へ、来てくれないかな?」
『Ellen Tachibana』
そう記されたメモは下に、『Gold Coast, Maryland』と続いていた。
資料のページは、私の履歴書のコピー。
『氷室』の文字が、赤い丸で囲まれている。
――悠賀様は、私のことを知っていた。それに、私の過去も。
やはり、悠賀様の専属メイドというのは建前。
私が立花家の人間だから、表に出ない仕事を言いつけられたのだ。
立花家の人間である私の顔を、お客様に顔を見られないように。
桜堂グループで立花家の人間が働くなんて、御法度だ。
なのに、それをすり抜けるように働き始めてしまった。
そんな身の程知らずな私は、立花家にとっても桜堂家にとっても恥。
悠賀様も、そう思っているに違いない。
慌てて資料を戻し、ほう、と息をつく。
けれど、まだ心臓はドクドクと嫌な音を立てている。
落ち着け落ち着けと、ダスターを握ったのと反対の手を胸にあてた。
何度か深呼吸を繰り返し、冷静さを取り戻した。
――大丈夫、クビを言い渡されたわけじゃない。
今朝だって、悠賀様は褒めてくれたばかりだ。
けれど、何のために? という疑問が浮かび、期待しては無駄だと絶望し。
一人問答を脳内で繰り広げながら支配人室を清掃していたら、いつの間にか終業時刻を過ぎてしまった。
*
一週間が過ぎた。
時折、悠賀様や執事さんがやってきて、仕事の様子を確認して帰っていく。
けれど思っていたような追及はなく、のびのびと仕事をこなすことができていた。
それでも、不安は拭えなかった。
いつ立花家の人間だと追及されるのか、震えながら悠賀様のお部屋を清掃する毎日だった。
今日も清掃業務を終え、用具室に清掃道具を返す。
扉をしめ、鍵がかかったことを確認し、エレベーターホールに向かおうとしたところで、ちょうどエレベーターが開いた。
悠賀様と、執事さんが降りてくる。
「お、お疲れ様です」
慌てて彼らの方に向き直り、頭を下げる。
すると悠賀様は「ちょうど良かった」と頭を下げたままの私の肩を叩いた。
「支配人室へ、来てくれないかな?」