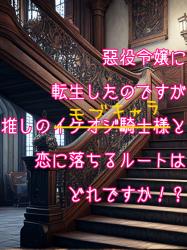悠賀様はそれから、空いた手でなぜか私の手を取った。
触れ合ってしまった。それで、また心拍数が上がってしまう。
「こんなに手が荒れてしまうほど、丁寧に清掃をしてくれているのだね」
「あ、あの、客室係は皆こんなではないでしょうか……?」
恥ずかしい。
水回り清掃と洗い立てのリネンに肌の水分を持っていかれるから、私の手はいつも酷いありさまだ。
ささくれ立っていて、カサカサで、爪もボロボロ。
けれど、見ないでと訴えることはできず、適当なことを言う。
「手荒れ用のクリームが必要か。それとも洗剤の変更を提案してみるか――」
悠賀様はそうぶつぶつ呟いて、私の手を離す。
「あ、あの――」
「ああ、邪魔をしてしまったね。すまない」
悠賀様は落としていた視線をこちらに向け、またニコリと笑った。
その顔に、また胸がドキリとする。
「そうだ、お願いがあってきたんだ。今日は、ダイニングの清掃はいいから、支配人室を掃除してもらえるかな? 僕はこれから桜堂家に戻る用事があって、君を一人にしてしまうけれど――定刻になったら、帰ってもらって構わないから」
「は、はい!」
立ち上がった彼に倣い、慌てて立ち上がる。
悠賀様は「よろしくね」と言って去っていく。
私は慌てて腰を折り、去っていく彼を見送った。
まだ、心臓がバクバクと言っている。
悠賀様に触れられた手の感触を、しっかりと覚えてしまっている。
温かい手だった。髪に触れられ、手を握られてしまった。
――どうしよう、私。こんなにも、心臓が破裂しそうになってる。
けれどこの時、その胸の高鳴りの意味が昨日と今日で変わっていることに、私はまだ気づいていなかった。
触れ合ってしまった。それで、また心拍数が上がってしまう。
「こんなに手が荒れてしまうほど、丁寧に清掃をしてくれているのだね」
「あ、あの、客室係は皆こんなではないでしょうか……?」
恥ずかしい。
水回り清掃と洗い立てのリネンに肌の水分を持っていかれるから、私の手はいつも酷いありさまだ。
ささくれ立っていて、カサカサで、爪もボロボロ。
けれど、見ないでと訴えることはできず、適当なことを言う。
「手荒れ用のクリームが必要か。それとも洗剤の変更を提案してみるか――」
悠賀様はそうぶつぶつ呟いて、私の手を離す。
「あ、あの――」
「ああ、邪魔をしてしまったね。すまない」
悠賀様は落としていた視線をこちらに向け、またニコリと笑った。
その顔に、また胸がドキリとする。
「そうだ、お願いがあってきたんだ。今日は、ダイニングの清掃はいいから、支配人室を掃除してもらえるかな? 僕はこれから桜堂家に戻る用事があって、君を一人にしてしまうけれど――定刻になったら、帰ってもらって構わないから」
「は、はい!」
立ち上がった彼に倣い、慌てて立ち上がる。
悠賀様は「よろしくね」と言って去っていく。
私は慌てて腰を折り、去っていく彼を見送った。
まだ、心臓がバクバクと言っている。
悠賀様に触れられた手の感触を、しっかりと覚えてしまっている。
温かい手だった。髪に触れられ、手を握られてしまった。
――どうしよう、私。こんなにも、心臓が破裂しそうになってる。
けれどこの時、その胸の高鳴りの意味が昨日と今日で変わっていることに、私はまだ気づいていなかった。