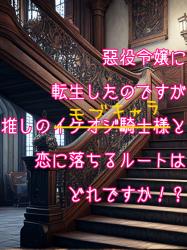彼はそのまま身を翻し、私の隣に華麗に着地する。
無論、落ちてきたのは王子様ではない。
控えめに輝くシルバーのスーツを着た、長身の男性だった。
「大変申し訳ございません!」
慌てて頭を下げた。
モップの拭きが甘かったか。水滴が残っていたのか。
いずれにせよ、私の不注意で彼は滑ったのだろう。
夕日に気を取られていた私の所為。
ダメダメな自分が不甲斐ない。
悔しさと申し訳なさがこみ上げて、視界がぼやけた。
目の前の彼の、磨かれた革靴が夕日に照らされて輝いている。
「顔を上げて」
「ですが……」
「君の顔が、見たいんだよ」
そう言われては、上げるしかない。
強張った肩のまま、意を決しゆっくりと身体を起こした。
先ほどシルバーだと思ったのは、夕日に照らされた上品なグレーのスーツ。
桜色のネクタイは、彼がこのホテルの関係者であることを表している。
さらに顔をあげると、襟元のフラワーホールにつけらえた紋章が目に入り、私は肩をぴくりと揺らした。
――桜を象った、美しい紋の襟章。
それは、桜堂家の人間のみがつけられるもの。
「大丈夫、別に君を責めたいわけじゃない」
その優しい声色に、恐れながらも顔を上げた。
西日が彼の輪郭に明暗を作る。
整った鼻筋に、切れ長の目元。
短く切りそろえられた髪は、丁寧にまとめ上げられている。
温和怜悧という言葉の似合うこの人物を、このホテルで知らない人はいない。
桜堂悠賀。
――桜堂財閥の御曹司で、桜堂ホテルグループの総支配人だ。
無論、落ちてきたのは王子様ではない。
控えめに輝くシルバーのスーツを着た、長身の男性だった。
「大変申し訳ございません!」
慌てて頭を下げた。
モップの拭きが甘かったか。水滴が残っていたのか。
いずれにせよ、私の不注意で彼は滑ったのだろう。
夕日に気を取られていた私の所為。
ダメダメな自分が不甲斐ない。
悔しさと申し訳なさがこみ上げて、視界がぼやけた。
目の前の彼の、磨かれた革靴が夕日に照らされて輝いている。
「顔を上げて」
「ですが……」
「君の顔が、見たいんだよ」
そう言われては、上げるしかない。
強張った肩のまま、意を決しゆっくりと身体を起こした。
先ほどシルバーだと思ったのは、夕日に照らされた上品なグレーのスーツ。
桜色のネクタイは、彼がこのホテルの関係者であることを表している。
さらに顔をあげると、襟元のフラワーホールにつけらえた紋章が目に入り、私は肩をぴくりと揺らした。
――桜を象った、美しい紋の襟章。
それは、桜堂家の人間のみがつけられるもの。
「大丈夫、別に君を責めたいわけじゃない」
その優しい声色に、恐れながらも顔を上げた。
西日が彼の輪郭に明暗を作る。
整った鼻筋に、切れ長の目元。
短く切りそろえられた髪は、丁寧にまとめ上げられている。
温和怜悧という言葉の似合うこの人物を、このホテルで知らない人はいない。
桜堂悠賀。
――桜堂財閥の御曹司で、桜堂ホテルグループの総支配人だ。