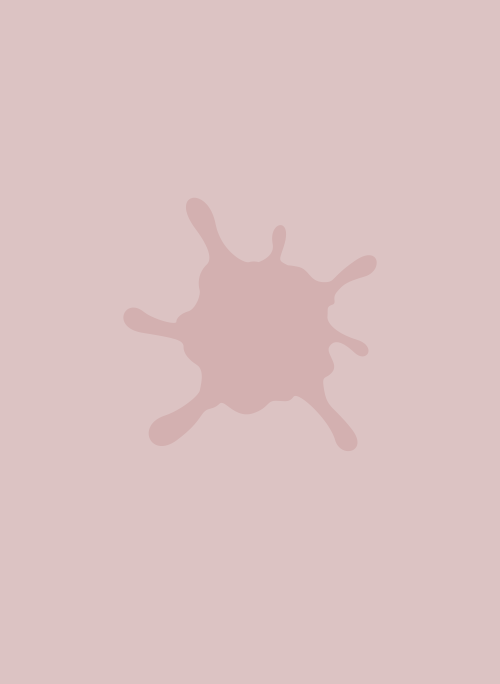そこで俺は、その日の午後、早速行動を起こした。
「ふぅ…。出来た」
如何せん、この家で「コレ」を出すのは初めてだからな。
ああでもないこうでもないと、しばらく四苦八苦、悪戦苦闘して。
何とか、今年も「コレ」を出すことが出来た。
果たして、これで寿々花さんの機嫌が直るだろうか。
…すると。
「…?悠理君、何やってるの?」
「お。来たか」
リビングで、俺がゴソゴソやってる音が聞こえたのだろう。
昼食の後、ずっと自分の部屋に引きこもっていた寿々花さんがリビングに降りてきた。
ようこそ。
「…!何?これ。何?」
気づいたようだな。
「凄いだろ?…コタツ、出したんだ」
「…!凄い!テーブルがお布団かけてる…!」
そう。冬の風物詩、コタツである。
やっぱり、冬と言えばこれを出さないとな。
「ふぅ…。出来た」
如何せん、この家で「コレ」を出すのは初めてだからな。
ああでもないこうでもないと、しばらく四苦八苦、悪戦苦闘して。
何とか、今年も「コレ」を出すことが出来た。
果たして、これで寿々花さんの機嫌が直るだろうか。
…すると。
「…?悠理君、何やってるの?」
「お。来たか」
リビングで、俺がゴソゴソやってる音が聞こえたのだろう。
昼食の後、ずっと自分の部屋に引きこもっていた寿々花さんがリビングに降りてきた。
ようこそ。
「…!何?これ。何?」
気づいたようだな。
「凄いだろ?…コタツ、出したんだ」
「…!凄い!テーブルがお布団かけてる…!」
そう。冬の風物詩、コタツである。
やっぱり、冬と言えばこれを出さないとな。
「わーい。お布団だ〜。テーブルがお布団かけてる〜」
寿々花さん、コタツに興味津々。
「コタツ、入ったことあるか?」
「…こたつ?」
こてん、と首を傾げる寿々花さん。
成程。コタツをご存知でないと。
生まれてこの方、暖房器具と言えばエアコンと床下暖房で生きてきたお嬢様だな。
一方俺の実家には、暖房器具はストーブとホットカーペット、そしてこのコタツだった。
だから、毎年冬になるとコタツを出していたのである。
コタツなんて貧乏臭い、と言われるかと思って、ずっと遠慮していたのだが…。
「これどうしたの?テーブルが寒そうだったから、お布団かけてあげたの?悠理君優しいねー」
「…ちげーよ…」
寒そうなテーブルに気を遣って、布団をかけてあげた訳じゃない。
言葉で説明するより、実際に体感してもらった方が早いな。
俺はコタツの電源コードをコンセントを差し込み、スイッチをオンにした。
「よし、出来たぞ」
「…?…?何が?」
「まぁまぁ、良いからここに座ってみろよ」
実践とばかりに、俺は真っ先にコタツに入ってみせた。
すると寿々花さんは、不思議そうに首を傾げながら、俺の横にぴったりとくっついて座った。
「…何故そこに座る?」
「え?だって悠理君が座れって」
「…」
横に座れとは言ってねぇよ。
まぁ良いや。好きにさせておこう。
「…?これでどうするの?」
「何もしなくて良いよ。このまましばらく座っておけば」
「座ってたら…何がどうなるの?」
「大丈夫だよ。今に分かる」
温かくなるまで、少し時間がかかるからな。
しばらく待っていれば、段々と…。
…すると。
「…!何だか、テーブルの中がじんわり温かくなってきた」
よしよし。気づいたようだな。
「もしかして…火事…?」
「…そういう暖房器具なんだよ…」
無知とは恐ろしいものだな。
「凄い。机の中がほっかほかだ〜」
コタツに入れている足が、じんわりぽかぽかと温まってきた。
そうそう。これだよ。
コタツで温まると、毎年、冬が来たなぁって思うよな。
いやぁ、温かい。
エアコンも床下暖房も良いけど、やっぱり俺は慣れ親しんだコタツが一番だ。
「わー、温かい。座ってるだけであったかーい」
寿々花さん、初めてのコタツに大興奮。
「どうだ?コタツ。気に入ったか?」
「うん!」
目をキラキラとさせて、生まれて初めてのコタツを堪能する寿々花お嬢さんである。
気に入ってもらえたようだな。良かった。
クリスマスツリーの代わりにはならないが、今度は冬が終わるまで、コタツを出しておくから。
これで満足してくれ。
…さて、寿々花さんがコタツを気に入ってくれたようなので。
「コタツの風物詩…。アレをやらないとな」
「…あれ?」
「まぁ、ちょっと待っててみろ」
俺は立ち上がって、キッチンに向かった。
コタツに入ってやることと言えば…決まってるよな?
寿々花さん、コタツに興味津々。
「コタツ、入ったことあるか?」
「…こたつ?」
こてん、と首を傾げる寿々花さん。
成程。コタツをご存知でないと。
生まれてこの方、暖房器具と言えばエアコンと床下暖房で生きてきたお嬢様だな。
一方俺の実家には、暖房器具はストーブとホットカーペット、そしてこのコタツだった。
だから、毎年冬になるとコタツを出していたのである。
コタツなんて貧乏臭い、と言われるかと思って、ずっと遠慮していたのだが…。
「これどうしたの?テーブルが寒そうだったから、お布団かけてあげたの?悠理君優しいねー」
「…ちげーよ…」
寒そうなテーブルに気を遣って、布団をかけてあげた訳じゃない。
言葉で説明するより、実際に体感してもらった方が早いな。
俺はコタツの電源コードをコンセントを差し込み、スイッチをオンにした。
「よし、出来たぞ」
「…?…?何が?」
「まぁまぁ、良いからここに座ってみろよ」
実践とばかりに、俺は真っ先にコタツに入ってみせた。
すると寿々花さんは、不思議そうに首を傾げながら、俺の横にぴったりとくっついて座った。
「…何故そこに座る?」
「え?だって悠理君が座れって」
「…」
横に座れとは言ってねぇよ。
まぁ良いや。好きにさせておこう。
「…?これでどうするの?」
「何もしなくて良いよ。このまましばらく座っておけば」
「座ってたら…何がどうなるの?」
「大丈夫だよ。今に分かる」
温かくなるまで、少し時間がかかるからな。
しばらく待っていれば、段々と…。
…すると。
「…!何だか、テーブルの中がじんわり温かくなってきた」
よしよし。気づいたようだな。
「もしかして…火事…?」
「…そういう暖房器具なんだよ…」
無知とは恐ろしいものだな。
「凄い。机の中がほっかほかだ〜」
コタツに入れている足が、じんわりぽかぽかと温まってきた。
そうそう。これだよ。
コタツで温まると、毎年、冬が来たなぁって思うよな。
いやぁ、温かい。
エアコンも床下暖房も良いけど、やっぱり俺は慣れ親しんだコタツが一番だ。
「わー、温かい。座ってるだけであったかーい」
寿々花さん、初めてのコタツに大興奮。
「どうだ?コタツ。気に入ったか?」
「うん!」
目をキラキラとさせて、生まれて初めてのコタツを堪能する寿々花お嬢さんである。
気に入ってもらえたようだな。良かった。
クリスマスツリーの代わりにはならないが、今度は冬が終わるまで、コタツを出しておくから。
これで満足してくれ。
…さて、寿々花さんがコタツを気に入ってくれたようなので。
「コタツの風物詩…。アレをやらないとな」
「…あれ?」
「まぁ、ちょっと待っててみろ」
俺は立ち上がって、キッチンに向かった。
コタツに入ってやることと言えば…決まってるよな?
テーブルの上には、みかんを数個と、アイスクリーム。
そして、大きな土鍋でほかほかと湯気をあげるおでん。
そう、これをやらなきゃ冬はやって来ない。
コタツでみかん、コタツでアイスクリーム、コタツでお鍋。
鉄板だな。
「ぽかぽかしながらアイスクリーム食べるの、美味しいね。幸せだねー」
「だろ?」
アイスクリーム大好きな寿々花さん、これにはクリスマスツリーを片付けて落ち込んでいたことも忘れ。
ほっこりとした笑みを浮かべて、バニラアイスをスプーンですくっていた。
見てるこっちまで、思わず口元が緩みそうになる。
じゃあ、俺も食べるかな。
「寿々花さん。おでん食べるか?取ってやろうか」
「食べるー」
と言うので、寿々花さんの取り皿におでんを取ってあげた。
おでんの具材は至ってシンプル。大根とちくわと卵と…その他諸々。
おでんに何を入れるかって、その家庭によって様々だと思うが…。
うちの実家は、里芋と木綿豆腐を入れるのが定番の味。
おでんの出汁がしみて、これが美味しいんだわ。とても。
「…美味いか?」
「はふはふ。美味しい」
「良かった」
二人してコタツに入って、はふはふ言いながらおでんを食べる。
こういうつまらないことを共有出来るのが、大きな幸福だと感じる今日この頃である。
そして、大きな土鍋でほかほかと湯気をあげるおでん。
そう、これをやらなきゃ冬はやって来ない。
コタツでみかん、コタツでアイスクリーム、コタツでお鍋。
鉄板だな。
「ぽかぽかしながらアイスクリーム食べるの、美味しいね。幸せだねー」
「だろ?」
アイスクリーム大好きな寿々花さん、これにはクリスマスツリーを片付けて落ち込んでいたことも忘れ。
ほっこりとした笑みを浮かべて、バニラアイスをスプーンですくっていた。
見てるこっちまで、思わず口元が緩みそうになる。
じゃあ、俺も食べるかな。
「寿々花さん。おでん食べるか?取ってやろうか」
「食べるー」
と言うので、寿々花さんの取り皿におでんを取ってあげた。
おでんの具材は至ってシンプル。大根とちくわと卵と…その他諸々。
おでんに何を入れるかって、その家庭によって様々だと思うが…。
うちの実家は、里芋と木綿豆腐を入れるのが定番の味。
おでんの出汁がしみて、これが美味しいんだわ。とても。
「…美味いか?」
「はふはふ。美味しい」
「良かった」
二人してコタツに入って、はふはふ言いながらおでんを食べる。
こういうつまらないことを共有出来るのが、大きな幸福だと感じる今日この頃である。
しかし、コタツを出して、ほっこりしてばかりはいられない。
というのも。
クリスマスが終わったら、いよいよ年末。
そろそろ、年越しの準備をしなくてはならないのだ。
年末と言えば、やることがたくさんあるだろう?
大掃除に始まり、餅つき、年賀状作り。
年末年始はスーパーが大変混むので、買い物に行くのも一苦労である。
学校は休みだけど、冬休みの宿題があるしな。
やることたくさん。大忙し。
まずは一番の大物、大掃除から済ませようと。
エプロンをつけて、あちこち拭いたり掃いたりしていると…。
「…じーっ」
「はっ…!」
背中に、寿々花さんの視線を感じた。
「ど、どうした…?」
俺は雑巾を片手に振り向いた。
コタツを出してからというもの、今度はコタツに夢中らしく。
毎日コタツにすっぽり収まって、今日も朝からコタツでお絵描きをしていたはずの寿々花さんが。
いつの間にか、俺の背後に立っていた。
気配なく立つのやめてくれないか。ビビるから。
「悠理君…何してるの?」
「何って…。見ての通り、掃除だけど…」
あ、そうか。
「ごめん。ゴソゴソしてうるさかったか?」
気が散るからあっちに行ってくれ、と言われるのかと思ったら。
そういう訳ではないらしく。
「悠理君、いつもお掃除してるのに、今日もお掃除するの?」
「年末だからな。大掃除してるんだよ」
「ほぇー。大掃除…」
「今年中に、何処か掃除して欲しいところあるか?」
この辺汚いからやっておいて、とか。
如何せん家が広いから、普段は隅々まで掃除出来ないんだよ。
今流行りの自動掃除機、あれ、買うべきかなぁ。
お高いんだろ?あれ。なんか勿体無いような気がして、手が出ないんだよな。
「掃除…。大掃除…」
「…寿々花さん?」
「…よし」
寿々花さんが、何かを決意した。
…何だろう。嫌な予感。
「悠理君、私もお掃除手伝う。お手伝いさせて」
出た。寿々花さんの、謎のやる気。
「いや、良いって。お嬢様のやることじゃないから。俺がやるから…」
「悠理君が頑張ってるのに、私だけボーッと座ってる訳にはいかないもん」
大変素晴らしい心掛けである。
その気持ちは有り難いんだが、でも寿々花さんの掃除って…。
…思い出す。階段で、頭からバケツいっぱいの水を被ったことを。
…あれは…嫌な事件だったな…。
あれの再来はやめて欲しいのだ。何としても。
「…出来るのか?寿々花さん…」
「うん、頑張る。悠理君みたいに、家の中ぴっかぴかにするよ」
またしても、素晴らしい心掛け。
…不安は大きく残るが。
ならば、この心掛けに応えるのが、せめて俺が寿々花さんにしてあげられることだろう。
良いじゃないか、多少失敗しても。
この寒い時期に、またしても頭から水を被るのは遠慮したかったが。
やる気を出しているうちにやらせて、褒めて伸ばす。
子育てしてるような気分だな。
「よし、分かった…。じゃあ、寿々花さんに重大な任務を与える」
「おぉっ…。何でありますか、隊長」
誰だよ。
「…風呂掃除、頼む」
びしょ濡れにされる前に、いっそびしょ濡れになっても良い場所の掃除を頼もうという腹である。
というのも。
クリスマスが終わったら、いよいよ年末。
そろそろ、年越しの準備をしなくてはならないのだ。
年末と言えば、やることがたくさんあるだろう?
大掃除に始まり、餅つき、年賀状作り。
年末年始はスーパーが大変混むので、買い物に行くのも一苦労である。
学校は休みだけど、冬休みの宿題があるしな。
やることたくさん。大忙し。
まずは一番の大物、大掃除から済ませようと。
エプロンをつけて、あちこち拭いたり掃いたりしていると…。
「…じーっ」
「はっ…!」
背中に、寿々花さんの視線を感じた。
「ど、どうした…?」
俺は雑巾を片手に振り向いた。
コタツを出してからというもの、今度はコタツに夢中らしく。
毎日コタツにすっぽり収まって、今日も朝からコタツでお絵描きをしていたはずの寿々花さんが。
いつの間にか、俺の背後に立っていた。
気配なく立つのやめてくれないか。ビビるから。
「悠理君…何してるの?」
「何って…。見ての通り、掃除だけど…」
あ、そうか。
「ごめん。ゴソゴソしてうるさかったか?」
気が散るからあっちに行ってくれ、と言われるのかと思ったら。
そういう訳ではないらしく。
「悠理君、いつもお掃除してるのに、今日もお掃除するの?」
「年末だからな。大掃除してるんだよ」
「ほぇー。大掃除…」
「今年中に、何処か掃除して欲しいところあるか?」
この辺汚いからやっておいて、とか。
如何せん家が広いから、普段は隅々まで掃除出来ないんだよ。
今流行りの自動掃除機、あれ、買うべきかなぁ。
お高いんだろ?あれ。なんか勿体無いような気がして、手が出ないんだよな。
「掃除…。大掃除…」
「…寿々花さん?」
「…よし」
寿々花さんが、何かを決意した。
…何だろう。嫌な予感。
「悠理君、私もお掃除手伝う。お手伝いさせて」
出た。寿々花さんの、謎のやる気。
「いや、良いって。お嬢様のやることじゃないから。俺がやるから…」
「悠理君が頑張ってるのに、私だけボーッと座ってる訳にはいかないもん」
大変素晴らしい心掛けである。
その気持ちは有り難いんだが、でも寿々花さんの掃除って…。
…思い出す。階段で、頭からバケツいっぱいの水を被ったことを。
…あれは…嫌な事件だったな…。
あれの再来はやめて欲しいのだ。何としても。
「…出来るのか?寿々花さん…」
「うん、頑張る。悠理君みたいに、家の中ぴっかぴかにするよ」
またしても、素晴らしい心掛け。
…不安は大きく残るが。
ならば、この心掛けに応えるのが、せめて俺が寿々花さんにしてあげられることだろう。
良いじゃないか、多少失敗しても。
この寒い時期に、またしても頭から水を被るのは遠慮したかったが。
やる気を出しているうちにやらせて、褒めて伸ばす。
子育てしてるような気分だな。
「よし、分かった…。じゃあ、寿々花さんに重大な任務を与える」
「おぉっ…。何でありますか、隊長」
誰だよ。
「…風呂掃除、頼む」
びしょ濡れにされる前に、いっそびしょ濡れになっても良い場所の掃除を頼もうという腹である。
寿々花さんに風呂掃除を頼むと。
寿々花さんは、そりゃもう嬉々として引き受けてくれた。
仮にも無月院家のお嬢様が、風呂掃除で喜ぶんじゃない。
掃除道具の使い方を軽く教えて、あとは寿々花さんにお任せした。
…任せて大丈夫だよな?多分。
滑って浴槽に転んで、溺れたりしないよな…?
「…」
任せはしたものの、やはり心配である。
別の場所を掃除しながらも、寿々花さんのことが気になって気になって。全然集中出来ない。
…やっぱり不安。
どうしても気になって、俺は寿々花さんの様子を見に行った。
すると、丁度寿々花さんは浴室の床に洗剤を撒いて、スポンジでごしごし擦っているところだった。
「ゆ〜りくんはー♪ごはんがじょうずで〜、優しいね〜♪」
謎の歌を口ずさみながら。
「ゆ〜りくんはー♪女の子のかっこうが〜、似合うよ〜♪」
やめろ。
「寿々花さん、調子はどうだ?」
随分楽しそうに掃除してるが。捗ってるか?
「あ、悠理君。うん、だいじょ、」
俺の声に振り向いた寿々花さんが、突然洗剤まみれの床に、ひょこっ、と立ち上がった。
すると、その拍子に。
「!寿々花さん!」
「へぶっ」
洗剤でツルッと足を滑らせたらしく、スポンジを持ったまま、派手な音を立てて転倒した。
あぁ…恐れていたことが。
俺は手に持っていた雑巾を投げ捨てて、急いで浴室に…寿々花さんのもとに駆け寄った。
「おい、大丈夫か!?」
「ほぇー…。びっくりしたー…」
意外と大丈夫だった。
頭、割とゴツンといった気がしたんだが…もしかしてあんた、石頭か?
いや、そんな冗談はさておき。
「どっか痛いか?骨折れたりしてないよな…!?」
年末に大怪我なんて、冗談じゃないぞ。
終わり悪ければ全て悪し、になってしまう。
しかし。
「ほぇ?うん。平気だよ?」
派手にずっこけた割には、けろっとしていらっしゃる。
…全身、洗剤まみれだけど。
洗剤撒き散らした床に転んだんだから、そりゃそうなる。
…そうか。うん。分かった。
寿々花さんに危険な風呂掃除を任せた、俺が悪かった。
もっと考えて…慎重になるべきだった。
怪我しなくて良かったよ。本当に。
「…寿々花さん。頼むからあんたはもう…コタツでお絵描きしててくれ」
やっぱり、寿々花さんに掃除は向いてない。
やる気があるのは良いことだが、しかしその溢れ出るやる気で、怪我をされたら本末転倒。
俺が怪我をするのは別に良いけど、寿々花さんを怪我させる訳にはいかないのだ。
「え?でも、悠理君のお手伝い…」
「うん、ありがとうな。大人しく座って…応援しててくれるのが、一番のお手伝いだよ」
俺の精神衛生の為にも、頼むからじっとしててくれ。頼むから。な?
寿々花さんは、そりゃもう嬉々として引き受けてくれた。
仮にも無月院家のお嬢様が、風呂掃除で喜ぶんじゃない。
掃除道具の使い方を軽く教えて、あとは寿々花さんにお任せした。
…任せて大丈夫だよな?多分。
滑って浴槽に転んで、溺れたりしないよな…?
「…」
任せはしたものの、やはり心配である。
別の場所を掃除しながらも、寿々花さんのことが気になって気になって。全然集中出来ない。
…やっぱり不安。
どうしても気になって、俺は寿々花さんの様子を見に行った。
すると、丁度寿々花さんは浴室の床に洗剤を撒いて、スポンジでごしごし擦っているところだった。
「ゆ〜りくんはー♪ごはんがじょうずで〜、優しいね〜♪」
謎の歌を口ずさみながら。
「ゆ〜りくんはー♪女の子のかっこうが〜、似合うよ〜♪」
やめろ。
「寿々花さん、調子はどうだ?」
随分楽しそうに掃除してるが。捗ってるか?
「あ、悠理君。うん、だいじょ、」
俺の声に振り向いた寿々花さんが、突然洗剤まみれの床に、ひょこっ、と立ち上がった。
すると、その拍子に。
「!寿々花さん!」
「へぶっ」
洗剤でツルッと足を滑らせたらしく、スポンジを持ったまま、派手な音を立てて転倒した。
あぁ…恐れていたことが。
俺は手に持っていた雑巾を投げ捨てて、急いで浴室に…寿々花さんのもとに駆け寄った。
「おい、大丈夫か!?」
「ほぇー…。びっくりしたー…」
意外と大丈夫だった。
頭、割とゴツンといった気がしたんだが…もしかしてあんた、石頭か?
いや、そんな冗談はさておき。
「どっか痛いか?骨折れたりしてないよな…!?」
年末に大怪我なんて、冗談じゃないぞ。
終わり悪ければ全て悪し、になってしまう。
しかし。
「ほぇ?うん。平気だよ?」
派手にずっこけた割には、けろっとしていらっしゃる。
…全身、洗剤まみれだけど。
洗剤撒き散らした床に転んだんだから、そりゃそうなる。
…そうか。うん。分かった。
寿々花さんに危険な風呂掃除を任せた、俺が悪かった。
もっと考えて…慎重になるべきだった。
怪我しなくて良かったよ。本当に。
「…寿々花さん。頼むからあんたはもう…コタツでお絵描きしててくれ」
やっぱり、寿々花さんに掃除は向いてない。
やる気があるのは良いことだが、しかしその溢れ出るやる気で、怪我をされたら本末転倒。
俺が怪我をするのは別に良いけど、寿々花さんを怪我させる訳にはいかないのだ。
「え?でも、悠理君のお手伝い…」
「うん、ありがとうな。大人しく座って…応援しててくれるのが、一番のお手伝いだよ」
俺の精神衛生の為にも、頼むからじっとしててくれ。頼むから。な?
洗剤まみれの服を着替えてもらって、念の為に転んでぶつけた頭に氷のうを乗せてから。
寿々花さんにはリビングで待機してもらって、俺はその間に家中の掃除を済ませた。
…ホッ。やっと終わった。
年末の大掃除が終わると、なんだかこう、やり遂げた感があるよな。
これで心置きなく、去る年を見送ることが出来るって言うか…。安心して年を越せるって言うか…。
とにかく、大仕事が終わってホッとした。
おでこを風呂の床とゴッツンコした寿々花さんも、全然痛くないらしくてけろっとしていたし。何よりだ。
さてはあんた、やっぱり石頭だな?
そのことに何よりホッとしたよ。
しかし、安心してばかりはいられない。
年末の大仕事は、これだけではないからである。
「悠理君、今度は何してるのー?」
大掃除の翌日。
朝からリビングで、せっせと作業しているところに。
寿々花さんが、ちょこちょこと歩み寄ってきた。
どうも。いらっしゃい。
「年賀状作りだよ」
これも、毎年年末にやらなければならない仕事の代表格だよな。
昨今では、メールで済ませる人も多くなっているようだが。
やっぱり紙の年賀状には、紙の良さがある…と、いうのは口実で。
毎年送ってるものだし、毎年送られてくるもんだから、今年も送らなきゃいけない。
そういうものだろ?年賀状って。
お互い「そろそろやめたいなぁ」と思いつつも、タイミングを逃して結局毎年送ってる。
一人二人くらい、そういう人いない?
俺もそれだよ。
小学校の時の同級生とか、中学の時の担任の先生とか。
実家にいた頃近所に住んでた人とか、親戚とか…。
あとは、今年から雛堂と乙無も追加された。
年々増えていくばっかりだよ。やれやれ。
寿々花さんにはリビングで待機してもらって、俺はその間に家中の掃除を済ませた。
…ホッ。やっと終わった。
年末の大掃除が終わると、なんだかこう、やり遂げた感があるよな。
これで心置きなく、去る年を見送ることが出来るって言うか…。安心して年を越せるって言うか…。
とにかく、大仕事が終わってホッとした。
おでこを風呂の床とゴッツンコした寿々花さんも、全然痛くないらしくてけろっとしていたし。何よりだ。
さてはあんた、やっぱり石頭だな?
そのことに何よりホッとしたよ。
しかし、安心してばかりはいられない。
年末の大仕事は、これだけではないからである。
「悠理君、今度は何してるのー?」
大掃除の翌日。
朝からリビングで、せっせと作業しているところに。
寿々花さんが、ちょこちょこと歩み寄ってきた。
どうも。いらっしゃい。
「年賀状作りだよ」
これも、毎年年末にやらなければならない仕事の代表格だよな。
昨今では、メールで済ませる人も多くなっているようだが。
やっぱり紙の年賀状には、紙の良さがある…と、いうのは口実で。
毎年送ってるものだし、毎年送られてくるもんだから、今年も送らなきゃいけない。
そういうものだろ?年賀状って。
お互い「そろそろやめたいなぁ」と思いつつも、タイミングを逃して結局毎年送ってる。
一人二人くらい、そういう人いない?
俺もそれだよ。
小学校の時の同級生とか、中学の時の担任の先生とか。
実家にいた頃近所に住んでた人とか、親戚とか…。
あとは、今年から雛堂と乙無も追加された。
年々増えていくばっかりだよ。やれやれ。
「ねんがじょ…?」
相変わらず、きょとんと首を傾げるのがお上手。
「寿々花さんも年賀状、出すだろ?もう準備したか?」
あんたは多いだろう。無月院家のご令嬢という立場上。
軽く、俺の十倍くらいは…。
「…ねんがじょ、って何?」
「…マジかよ…」
まさかの0枚。
0に何かけても0だっつーの。
つーか、年賀状の存在そのものをご存知でないとは。
嘘だろ…。毎年どうしてたんだ。これまで。
「もらわなかったのか…?年賀状…」
「ねんがじょ?」
「年賀状。毎年年が明けたら、『新年あけましておめでとうございます』って手紙が来るだろ?」
寿々花さんのことだ。俺なんかとは比べ物にならないほどたくさんの人から…。
「お手紙…。私にお手紙をくれる人は、昔からお姉様だけだよ」
「…!」
「お姉様にはいつも、たくさんのお手紙が来るけど…。私には…」
と、小声で言って俯く寿々花さん。
…そうか。
それは…悪いことを聞いてしまったな。
…年賀状くらい、送ってやれっつーの。
あるいは、送られてたかもしれないけど…椿姫お嬢様との連名だったのかもな。
あくまで寿々花さんは、椿姫お嬢様のおまけ、ってか?馬鹿馬鹿しい。
そんな失礼極まりない奴らに、年賀状を送ってやる必要はない。
「悠理君は、お手紙を出すんだね」
「そうだな…。って言っても、親戚と小・中学校の知人だけで、今はろくに付き合ってない奴らばっかりだけどな」
「それでも、お手紙を出せる相手がいるのは幸せなことだよ」
…本当にな。
寿々花さんにも、そういう相手が…。
…あ、そうだ。
「じゃあ、寿々花さん。ちょっと手伝ってくれないか?」
「ふぇ?」
「年賀状作り。一人でやるの大変なんだ。寿々花さんが手伝ってくれたら助かる」
思いつきで、そう提案してみると。
「…!…うん、やる。お手伝いする」
何でもお手伝いしたい、おませなお年頃。
やっぱり、食いついてきたな。
「住所と宛て名は俺が書くから、裏面にメッセージを書くのを手伝ってくれ」
「うん、分かったー」
年賀状には、毎年似たようなメッセージを書くのがお決まりなのだが。
別に大したことは書いてないぞ。「あけましておめでとうございます。昨年は色々とお世話になりました。今年も宜しくお願いします」みたいな。
何処でも聞くような、ありきたりな新年の挨拶だ。
毎年同じことを書いてるような気がするよ。
「何て書けば良いの?」
「…えーと…それじゃ…。『新年あけましておめでとうございます。変わらずお元気にされてますか。お互い良い一年になりますように。今年もよろしくお願いします。』…みたいな感じで」
「悠理君、何処かの会社の社長さんみたいだね」
そ、そうか?堅苦しいか?
毎年こんな感じなんだけど。
こういうのって、つい当たり障りのないフレーズになりがちだよな。
上手い言葉が思いつかないんだよ。
「じゃあ、私が悠理君の代わりに書くね。みなさーん。私は悠理君ですよー」
と言いながら、寿々花さんは俺の代わりに、年賀状に挨拶を書き始めた。
いや、あんたは寿々花さんだから。
…まぁいっか。気を良くして書いてるんだし。
しばらく任せるとしよう。
相変わらず、きょとんと首を傾げるのがお上手。
「寿々花さんも年賀状、出すだろ?もう準備したか?」
あんたは多いだろう。無月院家のご令嬢という立場上。
軽く、俺の十倍くらいは…。
「…ねんがじょ、って何?」
「…マジかよ…」
まさかの0枚。
0に何かけても0だっつーの。
つーか、年賀状の存在そのものをご存知でないとは。
嘘だろ…。毎年どうしてたんだ。これまで。
「もらわなかったのか…?年賀状…」
「ねんがじょ?」
「年賀状。毎年年が明けたら、『新年あけましておめでとうございます』って手紙が来るだろ?」
寿々花さんのことだ。俺なんかとは比べ物にならないほどたくさんの人から…。
「お手紙…。私にお手紙をくれる人は、昔からお姉様だけだよ」
「…!」
「お姉様にはいつも、たくさんのお手紙が来るけど…。私には…」
と、小声で言って俯く寿々花さん。
…そうか。
それは…悪いことを聞いてしまったな。
…年賀状くらい、送ってやれっつーの。
あるいは、送られてたかもしれないけど…椿姫お嬢様との連名だったのかもな。
あくまで寿々花さんは、椿姫お嬢様のおまけ、ってか?馬鹿馬鹿しい。
そんな失礼極まりない奴らに、年賀状を送ってやる必要はない。
「悠理君は、お手紙を出すんだね」
「そうだな…。って言っても、親戚と小・中学校の知人だけで、今はろくに付き合ってない奴らばっかりだけどな」
「それでも、お手紙を出せる相手がいるのは幸せなことだよ」
…本当にな。
寿々花さんにも、そういう相手が…。
…あ、そうだ。
「じゃあ、寿々花さん。ちょっと手伝ってくれないか?」
「ふぇ?」
「年賀状作り。一人でやるの大変なんだ。寿々花さんが手伝ってくれたら助かる」
思いつきで、そう提案してみると。
「…!…うん、やる。お手伝いする」
何でもお手伝いしたい、おませなお年頃。
やっぱり、食いついてきたな。
「住所と宛て名は俺が書くから、裏面にメッセージを書くのを手伝ってくれ」
「うん、分かったー」
年賀状には、毎年似たようなメッセージを書くのがお決まりなのだが。
別に大したことは書いてないぞ。「あけましておめでとうございます。昨年は色々とお世話になりました。今年も宜しくお願いします」みたいな。
何処でも聞くような、ありきたりな新年の挨拶だ。
毎年同じことを書いてるような気がするよ。
「何て書けば良いの?」
「…えーと…それじゃ…。『新年あけましておめでとうございます。変わらずお元気にされてますか。お互い良い一年になりますように。今年もよろしくお願いします。』…みたいな感じで」
「悠理君、何処かの会社の社長さんみたいだね」
そ、そうか?堅苦しいか?
毎年こんな感じなんだけど。
こういうのって、つい当たり障りのないフレーズになりがちだよな。
上手い言葉が思いつかないんだよ。
「じゃあ、私が悠理君の代わりに書くね。みなさーん。私は悠理君ですよー」
と言いながら、寿々花さんは俺の代わりに、年賀状に挨拶を書き始めた。
いや、あんたは寿々花さんだから。
…まぁいっか。気を良くして書いてるんだし。
しばらく任せるとしよう。
…しかし。
そのことに気づいたのは、住所と宛て名を全部書き終えてからだった。
「よし、こっちは終わり…。…寿々花さん、どうだ?進んでるか?」
「うん。書いてるよー」
寿々花さんは、さらさらとサインペンを動かしていた。
何だか、えらく流暢に筆が動いてるが…。
どれどれ、とばかりに寿々花さんの手元を覗き込んでみると。
えーと?『I wish you a happy New Year.How have you…』以下略。
…うん。
「…何で英語で書いてんのっ!?」
「えっ。駄目だった?」
寿々花さん、びっくり。
いや、俺もびっくりだよ。
既に書き終えた年賀状を見てみると、めちゃくちゃ達筆な筆記体で、全部英文で書かれていた。
マジで?ぱっと見日本語訳分からんけど、さっき俺がリクエストした挨拶、全部英訳して書いてんの?
どんだけお洒落な年賀状だよ。
住所と宛て名は、普通に下手くそな字を書いてんのに。
メッセージの部分だけが、こんなに達筆な英文とは。なんというアンバランス。
この一年の間に、俺に何かあったんじゃないかと心配されそう。
何かに目覚めたんじゃないかと。いや、何にも目覚めてないです。至って普通です。
そんな、たった一年で突然インテリ化するはずもなく。
つーか、俺を昔から知ってる人は、俺がこんなお洒落な英語を書ける訳がないってことをよくよく分かっているだろうから。
別の人に代筆を頼んだって、すぐにバレそう。
「何で英語で書いた…?」
「…えっ…。フランス語の方が良かった…?」
違う。そうじゃない。
ここ日本だから。年賀状って日本の文化だから。普通に日本語でOK。
海外にも年賀状を送り合う文化ってあるのだろうか。知らないけど。
新年よりも、クリスマスに重きを置いて祝ってるようなイメージがある。
英語でもフランス語でも、辞書も使わずにすらすら書けるなんて、相変わらず凄い頭良いな。
それなのに、年賀状の存在は知らないんだから、知識の偏りが激しい。
…さて。この年賀状をどうしたものか。
「もしかして…これ、駄目だった…?」
寿々花さんは困ったような戸惑ったような顔で、不安そうに俺の顔を覗き込んだ。
「いや…。駄目ってことはないけど…」
ただ…何だろう。うん。
物凄くお洒落な年賀状になったな。
こんな気取った年賀状を送る趣味はないので、出来れば書き直したいところだったが…。
改めて今から買ってくるのも面倒だし、お金がかかるし、書き直すのも大変だし。
…いっか。このまま送ろう。
お洒落に高校デビューしてみましたってことで。
大丈夫大丈夫。誰も俺の年賀状なんて、じろじろ見ないよ。多分。
「私、また変なことしちゃった?悠理君怒ってる?」
怒られるかもしれない、とびくびく聞いてくる寿々花さん。
「え?いや、別に…怒ってないけど…」
日本語で書いてくれ、と言わなかった俺が悪い。
…いや、まさか英語で書くとは誰も思わないだろ。ここ日本だぞ?
寿々花さんにだって悪気があった訳じゃないし、誰が悪いということも…。
「ごめんね、悠理君…」
寿々花さんは、しょぼーん、と落ち込みながら謝ってきた。
…そんな、改まって謝られると、むしろそっちの方が困るんだが?
そのことに気づいたのは、住所と宛て名を全部書き終えてからだった。
「よし、こっちは終わり…。…寿々花さん、どうだ?進んでるか?」
「うん。書いてるよー」
寿々花さんは、さらさらとサインペンを動かしていた。
何だか、えらく流暢に筆が動いてるが…。
どれどれ、とばかりに寿々花さんの手元を覗き込んでみると。
えーと?『I wish you a happy New Year.How have you…』以下略。
…うん。
「…何で英語で書いてんのっ!?」
「えっ。駄目だった?」
寿々花さん、びっくり。
いや、俺もびっくりだよ。
既に書き終えた年賀状を見てみると、めちゃくちゃ達筆な筆記体で、全部英文で書かれていた。
マジで?ぱっと見日本語訳分からんけど、さっき俺がリクエストした挨拶、全部英訳して書いてんの?
どんだけお洒落な年賀状だよ。
住所と宛て名は、普通に下手くそな字を書いてんのに。
メッセージの部分だけが、こんなに達筆な英文とは。なんというアンバランス。
この一年の間に、俺に何かあったんじゃないかと心配されそう。
何かに目覚めたんじゃないかと。いや、何にも目覚めてないです。至って普通です。
そんな、たった一年で突然インテリ化するはずもなく。
つーか、俺を昔から知ってる人は、俺がこんなお洒落な英語を書ける訳がないってことをよくよく分かっているだろうから。
別の人に代筆を頼んだって、すぐにバレそう。
「何で英語で書いた…?」
「…えっ…。フランス語の方が良かった…?」
違う。そうじゃない。
ここ日本だから。年賀状って日本の文化だから。普通に日本語でOK。
海外にも年賀状を送り合う文化ってあるのだろうか。知らないけど。
新年よりも、クリスマスに重きを置いて祝ってるようなイメージがある。
英語でもフランス語でも、辞書も使わずにすらすら書けるなんて、相変わらず凄い頭良いな。
それなのに、年賀状の存在は知らないんだから、知識の偏りが激しい。
…さて。この年賀状をどうしたものか。
「もしかして…これ、駄目だった…?」
寿々花さんは困ったような戸惑ったような顔で、不安そうに俺の顔を覗き込んだ。
「いや…。駄目ってことはないけど…」
ただ…何だろう。うん。
物凄くお洒落な年賀状になったな。
こんな気取った年賀状を送る趣味はないので、出来れば書き直したいところだったが…。
改めて今から買ってくるのも面倒だし、お金がかかるし、書き直すのも大変だし。
…いっか。このまま送ろう。
お洒落に高校デビューしてみましたってことで。
大丈夫大丈夫。誰も俺の年賀状なんて、じろじろ見ないよ。多分。
「私、また変なことしちゃった?悠理君怒ってる?」
怒られるかもしれない、とびくびく聞いてくる寿々花さん。
「え?いや、別に…怒ってないけど…」
日本語で書いてくれ、と言わなかった俺が悪い。
…いや、まさか英語で書くとは誰も思わないだろ。ここ日本だぞ?
寿々花さんにだって悪気があった訳じゃないし、誰が悪いということも…。
「ごめんね、悠理君…」
寿々花さんは、しょぼーん、と落ち込みながら謝ってきた。
…そんな、改まって謝られると、むしろそっちの方が困るんだが?
大掃除も失敗し、年賀状作りも上手く行かず(?)。
寿々花さんは、どよーんと落ち込んでいた。
「悠理君のお手伝いをしたかったのに…。私はいつも足を引っ張るだけ…」
「そ、そんなことないって…。その気持ちだけで充分助かってるよ」
「気持ちだけじゃ、お腹は膨れないんだよ」
そ、そうかもしれないけど。
「悠理君を怒らせちゃった…」
「別に…全然怒ってないけど…」
これは本当である。
俺は元々、寿々花さんに家事を手伝って欲しいなんて微塵も思ってないからな。
手伝おうとしてくれる、その気持ちだけで充分嬉しい。
…のだが、役に立てない(と、自分で思い込んでいる)寿々花さんにとっては、それだけじゃ納得出来ないのだろう。
「私はいつもそうだよ。悠理君のお手伝いをするつもりで、逆に足を引っ張って…」
「ま、まぁまぁ…別に気にしなくて良いよ、そんなこと」
むしろ、そうやって落ち込んでいる方が、俺としては反応に困る。
なんと言って慰めようか、と考えていた、その時。
我が家のインターホンが鳴った。
誰だよ。こんな時に。今お取り込み中なんだけど?
しかし、無視する訳にもいかず。
「ちょ…ちょっと出てくるよ」
「うん…」
寿々花さんに断ってから、俺は急ぎ足で玄関に向かった。
円城寺だったらぶん殴ろう、と思ってドアを開けたところ。
「こんにちは。宅配便でーす」
あ、宅配便だった…。
大晦日も近いっていうのに、今日も荷物の配達、お疲れ様です。
「あ、はい。どうも…」
「重いので、気をつけて持ってくださいねー」
「え。あ、はい。…うぉっ…」
配達員のお兄さんに、ずっしりと重い段ボール箱を渡された。
「ありがとうございましたー」
笑顔で頭を下げる配達員さんを、玄関で見送り。
俺は、段ボール箱に貼られていた配達伝票を確認。
またフランスからの荷物かと思ったら…寿々花さん宛てではなく、俺の名前が書いてあった。
俺宛ての荷物?…ってことは…。
「あ、母さんだ…」
誰あろう、俺の母親からの荷物だった。
荷物の中身、食品、って書いてある。
食品…?
…ともかく、リビングに持って入ってから開けてみよう。
「重っ…」
えっちらおっちら、へっぴり腰でよたよたしながら、荷物を玄関に持って入ろうとすると。
「悠理君、大丈夫っ?」
「うわっ、びっくりした」
いつの間にか、寿々花さんが玄関までやって来ていた。
びっくりして荷物を落とすところだったろうが。不意打ちはやめてくれ。
「荷物?それなぁに?」
「まだ分からん。かあ…えっと、俺の母親からの荷物みたいなんだが」
「悠理君のお母さん?」
この間、干し柿送ってくれたから。
またその類だろうか。
「ちょっと…リビングまで運ぶから…」
「うん。貸して」
「あ、ちょ、」
寿々花さんは俺の手から段ボール箱をもぎ取り。
ひょいっ、と軽々と持ち上げた。
すげぇ…。男顔負けの力持ち…。
「リビングに運べば良いんだよね?」
「あぁ…。頼むよ…」
「お任せー」
へっぴり腰で運んでいた自分が、情けなく思えてくる。
寿々花さんは妙に張り切って、今度こそ役に立つと意気込みながら荷物を運んでくれた。
寿々花さんは、どよーんと落ち込んでいた。
「悠理君のお手伝いをしたかったのに…。私はいつも足を引っ張るだけ…」
「そ、そんなことないって…。その気持ちだけで充分助かってるよ」
「気持ちだけじゃ、お腹は膨れないんだよ」
そ、そうかもしれないけど。
「悠理君を怒らせちゃった…」
「別に…全然怒ってないけど…」
これは本当である。
俺は元々、寿々花さんに家事を手伝って欲しいなんて微塵も思ってないからな。
手伝おうとしてくれる、その気持ちだけで充分嬉しい。
…のだが、役に立てない(と、自分で思い込んでいる)寿々花さんにとっては、それだけじゃ納得出来ないのだろう。
「私はいつもそうだよ。悠理君のお手伝いをするつもりで、逆に足を引っ張って…」
「ま、まぁまぁ…別に気にしなくて良いよ、そんなこと」
むしろ、そうやって落ち込んでいる方が、俺としては反応に困る。
なんと言って慰めようか、と考えていた、その時。
我が家のインターホンが鳴った。
誰だよ。こんな時に。今お取り込み中なんだけど?
しかし、無視する訳にもいかず。
「ちょ…ちょっと出てくるよ」
「うん…」
寿々花さんに断ってから、俺は急ぎ足で玄関に向かった。
円城寺だったらぶん殴ろう、と思ってドアを開けたところ。
「こんにちは。宅配便でーす」
あ、宅配便だった…。
大晦日も近いっていうのに、今日も荷物の配達、お疲れ様です。
「あ、はい。どうも…」
「重いので、気をつけて持ってくださいねー」
「え。あ、はい。…うぉっ…」
配達員のお兄さんに、ずっしりと重い段ボール箱を渡された。
「ありがとうございましたー」
笑顔で頭を下げる配達員さんを、玄関で見送り。
俺は、段ボール箱に貼られていた配達伝票を確認。
またフランスからの荷物かと思ったら…寿々花さん宛てではなく、俺の名前が書いてあった。
俺宛ての荷物?…ってことは…。
「あ、母さんだ…」
誰あろう、俺の母親からの荷物だった。
荷物の中身、食品、って書いてある。
食品…?
…ともかく、リビングに持って入ってから開けてみよう。
「重っ…」
えっちらおっちら、へっぴり腰でよたよたしながら、荷物を玄関に持って入ろうとすると。
「悠理君、大丈夫っ?」
「うわっ、びっくりした」
いつの間にか、寿々花さんが玄関までやって来ていた。
びっくりして荷物を落とすところだったろうが。不意打ちはやめてくれ。
「荷物?それなぁに?」
「まだ分からん。かあ…えっと、俺の母親からの荷物みたいなんだが」
「悠理君のお母さん?」
この間、干し柿送ってくれたから。
またその類だろうか。
「ちょっと…リビングまで運ぶから…」
「うん。貸して」
「あ、ちょ、」
寿々花さんは俺の手から段ボール箱をもぎ取り。
ひょいっ、と軽々と持ち上げた。
すげぇ…。男顔負けの力持ち…。
「リビングに運べば良いんだよね?」
「あぁ…。頼むよ…」
「お任せー」
へっぴり腰で運んでいた自分が、情けなく思えてくる。
寿々花さんは妙に張り切って、今度こそ役に立つと意気込みながら荷物を運んでくれた。
この作家の他の作品
表紙を見る
彼らは夢を見る。毎晩、バケモノに襲われる悪夢を。
彼らは生贄。罪を犯した人間達が生み出したバケモノを、その手で殺すことを宿命付けられた生贄。
彼らは選ばれた。「普通」であることに選ばれなかった彼ら。
裁定者たる天使が振った賽に、選ばれてしまった彼らが辿る運命は。
そして、生贄に選ばれた彼らの抱える、辛く、苦しみに満ちた過去の記憶とは…。
表紙を見る
2019年に作者が携帯小説モバスペbookに投稿した作品を移植しました。
彼らの迎えた夜明けに、祝福の歌を。
表紙を見る
2021年にモバスペbookに投稿した作品を移植しました。
エロマフィア、記念すべき第5弾。
最果てにあるレゾンデートルを、お楽しみください。
※この作品に登場する宗教、教義、宗教組織は全てフィクションです。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…