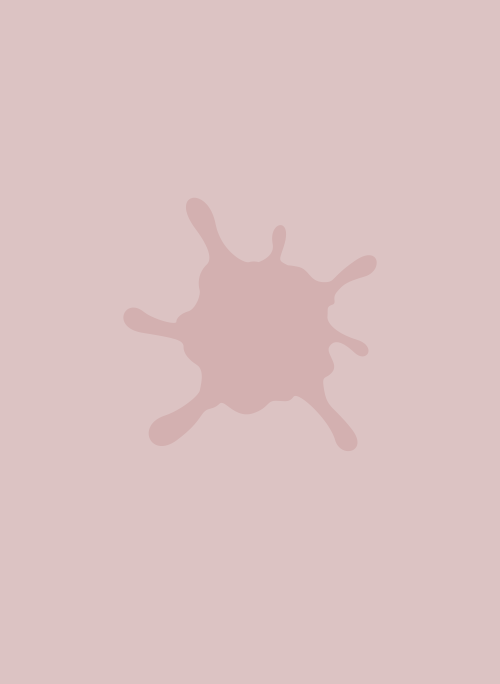幸か不幸か、そんな俺の悩みを解決してくれる人物が、意外なところから訪れた。
その日は偶然水曜日で、水曜日と言えば俺の園芸委員の活動日である。
雛堂の文化祭実行委員を手伝っているからといって、園芸委員の仕事はなくならない。
いつも通りである。当然だが。
それはそれ、これはこれということだな。
文化祭の準備の為に、毎日忙しく働いてるんだからさ。
ちょっとくらい楽させてもらえねーかな。…無理だよなぁ。
「…はー…」
無意識に、さすがに疲れが溜まっていたのか。
花壇に水やりをしながら、思わず溜め息をついていた。
その溜め息を、一緒にいた小花衣先輩は聞き逃さなかった。
「あら、悠理さん。何だかお疲れのようね」
「あ…済みません…」
つい。口をついて溜め息が。
別に、花の水やりにうんざりしてる訳じゃなくて…。
「大丈夫?休めてないのかしら」
「あぁ、えぇと、そうじゃなくて…その…。最近文化祭の準備で忙しくて…」
「そうだったのね。私も文化祭のステージ発表があるから、毎日練習で大変だわ」
…ステージ発表?
「小花衣先輩も、ステージに立つんですね」
「えぇ。私、管弦楽部でバイオリンを担当しているの」
バイオリンだってさ。
実に優雅な趣味だなぁ…。いかにもお嬢様って感じだ。
バイオリンを習ってる、って聞くと、途端にお嬢様度が上がる気がする。
一方我が家のお嬢様、寿々花さんは、音楽の流れる絵本で喜んでいる。
同じお嬢様なのに、この差よ。
まぁ、寿々花さんが突然バイオリンなんか始めたら、俺は寿々花さんの影武者を疑うけどな。
「悠理さんも、何か音楽をやっているのかしら?」
「えっ?…いや、俺は何も…」
音楽なんて、まともに人前で演奏したのは小学校の時の鍵盤ハーモニカが最後…。
…だったのだが。
「でも、さっき悠理さんもステージに立つって」
俺は、ステージに立つなんて一言も…。
…思い出した。
俺、さっき迂闊に…小花衣先輩「も」ステージに立つんですね、って言った。
小花衣先輩「も」ってことは、自分もステージに上がる予定があるってことじゃん。
とんでもない失言。
確かに俺も、ステージに立つ予定はあるけども。
それは断じて、小花衣先輩のように優雅なバイオリンなどではなく…。
「え、え、えーと…。いや、その、俺は別に…」
「男性で音楽を習っているなんて、この学校では珍しいのね。何かしら?チェロ?コントラバス?それともトロンボーンとか?」
何?そのお洒落な楽器。
寿々花さんじゃないけど、何それ美味しいの状態。
そんないかにも優雅な楽器、弾けるどころか、まともに見たこともないっての。
「え、えっと、楽器じゃなくて…」
「あら、じゃあ声楽?」
とんでもない。俺がまともに歌える歌なんて、国家と校歌とハッピーバースデートゥーユーくらいだろ。
どうする?言うべきか?小花衣先輩に。
「実は女装・男装コンテストの出場者に選ばれたんですよー」なんて、口が裂けても言えない。
…と、思ったけど。
もし小花衣先輩がステージを見ていたら、どうせ女装したことはバレる訳で。
隠しても無駄、って奴だ。
…むしろ、覚悟を決めて早めにカミングアウトするべきなのでは?
「…実は…」
俺は内心泣きそうになりながら、小花衣先輩に全てを打ち明けた。
その日は偶然水曜日で、水曜日と言えば俺の園芸委員の活動日である。
雛堂の文化祭実行委員を手伝っているからといって、園芸委員の仕事はなくならない。
いつも通りである。当然だが。
それはそれ、これはこれということだな。
文化祭の準備の為に、毎日忙しく働いてるんだからさ。
ちょっとくらい楽させてもらえねーかな。…無理だよなぁ。
「…はー…」
無意識に、さすがに疲れが溜まっていたのか。
花壇に水やりをしながら、思わず溜め息をついていた。
その溜め息を、一緒にいた小花衣先輩は聞き逃さなかった。
「あら、悠理さん。何だかお疲れのようね」
「あ…済みません…」
つい。口をついて溜め息が。
別に、花の水やりにうんざりしてる訳じゃなくて…。
「大丈夫?休めてないのかしら」
「あぁ、えぇと、そうじゃなくて…その…。最近文化祭の準備で忙しくて…」
「そうだったのね。私も文化祭のステージ発表があるから、毎日練習で大変だわ」
…ステージ発表?
「小花衣先輩も、ステージに立つんですね」
「えぇ。私、管弦楽部でバイオリンを担当しているの」
バイオリンだってさ。
実に優雅な趣味だなぁ…。いかにもお嬢様って感じだ。
バイオリンを習ってる、って聞くと、途端にお嬢様度が上がる気がする。
一方我が家のお嬢様、寿々花さんは、音楽の流れる絵本で喜んでいる。
同じお嬢様なのに、この差よ。
まぁ、寿々花さんが突然バイオリンなんか始めたら、俺は寿々花さんの影武者を疑うけどな。
「悠理さんも、何か音楽をやっているのかしら?」
「えっ?…いや、俺は何も…」
音楽なんて、まともに人前で演奏したのは小学校の時の鍵盤ハーモニカが最後…。
…だったのだが。
「でも、さっき悠理さんもステージに立つって」
俺は、ステージに立つなんて一言も…。
…思い出した。
俺、さっき迂闊に…小花衣先輩「も」ステージに立つんですね、って言った。
小花衣先輩「も」ってことは、自分もステージに上がる予定があるってことじゃん。
とんでもない失言。
確かに俺も、ステージに立つ予定はあるけども。
それは断じて、小花衣先輩のように優雅なバイオリンなどではなく…。
「え、え、えーと…。いや、その、俺は別に…」
「男性で音楽を習っているなんて、この学校では珍しいのね。何かしら?チェロ?コントラバス?それともトロンボーンとか?」
何?そのお洒落な楽器。
寿々花さんじゃないけど、何それ美味しいの状態。
そんないかにも優雅な楽器、弾けるどころか、まともに見たこともないっての。
「え、えっと、楽器じゃなくて…」
「あら、じゃあ声楽?」
とんでもない。俺がまともに歌える歌なんて、国家と校歌とハッピーバースデートゥーユーくらいだろ。
どうする?言うべきか?小花衣先輩に。
「実は女装・男装コンテストの出場者に選ばれたんですよー」なんて、口が裂けても言えない。
…と、思ったけど。
もし小花衣先輩がステージを見ていたら、どうせ女装したことはバレる訳で。
隠しても無駄、って奴だ。
…むしろ、覚悟を決めて早めにカミングアウトするべきなのでは?
「…実は…」
俺は内心泣きそうになりながら、小花衣先輩に全てを打ち明けた。
話したよ。包み隠さず。
女装・男装コンテストの出場者が決まらず、仕方なくあみだくじで決めることになり。
厳正なるあみだくじの結果、俺の意志とは関係なく、俺の意志とは関係なく(←ここ重要)、女装コンテストの出場者に決まってしまったこと。
俺の意志とは関係ないので、何ならまだ女装用の衣装すら用意してなくて、それが憂鬱で溜め息をついていたこと。
ついでに、俺のクラスで予定されているカレー食堂の話もしたよ。
お陰で超忙しいんだってこともな。
カミングアウトと言うより、途中からもう、ただの愚痴みたいになってしまったが。
親切な小花衣先輩は、同情するように頷きながら聞いてくれた。
「…って、感じです」
全てを話し終えると、小花衣先輩は憐れな俺に向かって、
「そうだったの。本意ではなかったとはいえ…またとない経験が出来そうね」
と、非常に前向きなお言葉を賜った。
ポジティブだなぁ…。俺はそんな経験、人生で一度も体験したくなかったけどな。
「それに悠理さん、綺麗なお顔だから、きっと何を着ても似合うと思うわ」
これほど嬉しくない褒め言葉が、他にあるだろうか。
「…そりゃどうも…」
「悠理さんのクラスのカレーショップ、是非行ってみたいわ」
「…御口に合えば良いんですけどね…」
如何せん、手抜き貧乏カレーなんでね。
小花衣先輩みたいな、生粋のお嬢様の口に合うかどうか。
「ねぇ、悠理さん」
「何ですか…?」
「女装・男装コンテストで着る衣装のことだけれど、まだ決まっていないと言っていたでしょう?こんな衣装を着たい、という希望はあるの?」
希望など、一片たりともあるはずがない。
「全く無いですけど…」
「余計なお世話かもしれないけれど、もしこだわりがないようだったら、あなたに貸してあげられそうな衣装があるわ」
何だって?
「去年高校を卒業した従姉妹の制服があるの。背格好が丁度悠理さんと同じくらいだから、ぴったり合うんじゃないかと思って」
これは予想外の、思ってもみない有り難い申し出だった。
女装の為に女モノの服を新着するなんて、そんな無駄遣いは死んでも御免だと思っていた。
誰かから古着を借りることが出来るなら、それに越したことはない。
「そうしてもらえると、物凄く有り難いですけど…。でも、良いんですか?」
一応、従姉妹に許可を取ってからの方が…。
いくら卒業して、もう着ないとはいえ…自分の制服を、何処ぞの馬の骨とも知らない男に貸すなんて。
普通、嫌だと思うのでは?
「おおらかな性格だから、頼めば快く貸してくれると思うわ。良かったら、本人に尋ねてみましょうか」
「お願いします。貸してもらえるなら、是非」
厚かましいお願いだということは、百も承知。
しかし、現状、他に衣装を手に入れられそうなアテもないし。
ここは、是非とも小花衣先輩と従姉妹さんのご厚意に甘えさせてもらいなかった。
女装・男装コンテストの出場者が決まらず、仕方なくあみだくじで決めることになり。
厳正なるあみだくじの結果、俺の意志とは関係なく、俺の意志とは関係なく(←ここ重要)、女装コンテストの出場者に決まってしまったこと。
俺の意志とは関係ないので、何ならまだ女装用の衣装すら用意してなくて、それが憂鬱で溜め息をついていたこと。
ついでに、俺のクラスで予定されているカレー食堂の話もしたよ。
お陰で超忙しいんだってこともな。
カミングアウトと言うより、途中からもう、ただの愚痴みたいになってしまったが。
親切な小花衣先輩は、同情するように頷きながら聞いてくれた。
「…って、感じです」
全てを話し終えると、小花衣先輩は憐れな俺に向かって、
「そうだったの。本意ではなかったとはいえ…またとない経験が出来そうね」
と、非常に前向きなお言葉を賜った。
ポジティブだなぁ…。俺はそんな経験、人生で一度も体験したくなかったけどな。
「それに悠理さん、綺麗なお顔だから、きっと何を着ても似合うと思うわ」
これほど嬉しくない褒め言葉が、他にあるだろうか。
「…そりゃどうも…」
「悠理さんのクラスのカレーショップ、是非行ってみたいわ」
「…御口に合えば良いんですけどね…」
如何せん、手抜き貧乏カレーなんでね。
小花衣先輩みたいな、生粋のお嬢様の口に合うかどうか。
「ねぇ、悠理さん」
「何ですか…?」
「女装・男装コンテストで着る衣装のことだけれど、まだ決まっていないと言っていたでしょう?こんな衣装を着たい、という希望はあるの?」
希望など、一片たりともあるはずがない。
「全く無いですけど…」
「余計なお世話かもしれないけれど、もしこだわりがないようだったら、あなたに貸してあげられそうな衣装があるわ」
何だって?
「去年高校を卒業した従姉妹の制服があるの。背格好が丁度悠理さんと同じくらいだから、ぴったり合うんじゃないかと思って」
これは予想外の、思ってもみない有り難い申し出だった。
女装の為に女モノの服を新着するなんて、そんな無駄遣いは死んでも御免だと思っていた。
誰かから古着を借りることが出来るなら、それに越したことはない。
「そうしてもらえると、物凄く有り難いですけど…。でも、良いんですか?」
一応、従姉妹に許可を取ってからの方が…。
いくら卒業して、もう着ないとはいえ…自分の制服を、何処ぞの馬の骨とも知らない男に貸すなんて。
普通、嫌だと思うのでは?
「おおらかな性格だから、頼めば快く貸してくれると思うわ。良かったら、本人に尋ねてみましょうか」
「お願いします。貸してもらえるなら、是非」
厚かましいお願いだということは、百も承知。
しかし、現状、他に衣装を手に入れられそうなアテもないし。
ここは、是非とも小花衣先輩と従姉妹さんのご厚意に甘えさせてもらいなかった。
翌日。
小花衣先輩は早速、従姉妹のお姉さんに話をつけてくれたらしく。
快く、制服を貸してもらえることになった。
有り難い。大変有り難い。
いや、全然嬉しくはないけど、有り難いのは確かである。
小花衣先輩も先輩の従姉妹さんも、すぐに動いてくれたお陰で。
小花衣先輩に相談を持ちかけた翌々日の放課後には、俺の手元に制服が届いていた。
3年間着た制服だから、よれよれでヘタっているかと思ったが、開けてみたらまだまだ新品みたいで。
保存状態も良好で、文句のつけようがなかった。
さすが小花衣先輩の従姉妹だけあって、こちらもお嬢様って感じだ。
ともあれ、それで衣装は手元に届いた。
小花衣先輩と先輩の従姉妹さんに、感謝。
メイド服は回避したぞ。
これで、あとは文化祭当日を待つだけ…になったが。
…気になるのは、寿々花さんの方である。
「…なぁ、寿々花さんは衣装、どうするんだ?」
「ほぇ?」
男装コンテストでの衣装について尋ねたら、相変わらずこの反応である。
おいおい。自分から立候補したんだろ?
だったら、準備くらいちゃんとしておけよ。
…って、俺も人のこと言えないけど。
小花衣先輩は早速、従姉妹のお姉さんに話をつけてくれたらしく。
快く、制服を貸してもらえることになった。
有り難い。大変有り難い。
いや、全然嬉しくはないけど、有り難いのは確かである。
小花衣先輩も先輩の従姉妹さんも、すぐに動いてくれたお陰で。
小花衣先輩に相談を持ちかけた翌々日の放課後には、俺の手元に制服が届いていた。
3年間着た制服だから、よれよれでヘタっているかと思ったが、開けてみたらまだまだ新品みたいで。
保存状態も良好で、文句のつけようがなかった。
さすが小花衣先輩の従姉妹だけあって、こちらもお嬢様って感じだ。
ともあれ、それで衣装は手元に届いた。
小花衣先輩と先輩の従姉妹さんに、感謝。
メイド服は回避したぞ。
これで、あとは文化祭当日を待つだけ…になったが。
…気になるのは、寿々花さんの方である。
「…なぁ、寿々花さんは衣装、どうするんだ?」
「ほぇ?」
男装コンテストでの衣装について尋ねたら、相変わらずこの反応である。
おいおい。自分から立候補したんだろ?
だったら、準備くらいちゃんとしておけよ。
…って、俺も人のこと言えないけど。
「コンテストの衣装。もう決めてるのか?」
「うーん。まだー」
おいおい。悠長だな。
「何を着るつもりなのか知らないけど…早いところ用意しておけよ。前日になったらバタバタして…」
「私ね、着てみたい服があるんだー」
とのこと。
着てみたい服…?それは珍しいな。
着るものに全く頓着しない寿々花さんが、自ら「着たい」と希望するなんて。
一体どんな衣装なんだろう。
「何?着てみたい服って」
「鎧と鉄かぶと」
…何処の戦国武将?
「小道具に太刀と刀を持って、格好良く抜刀術とか披露したい」
うきうきと夢を語ってくれてありがとう。
でも、それは無理だから。
現実を見ような。現実を。
「無理だろ。何処に売ってるんだよ。鎧なんか…」
「ないかな?悠理君、鎧持ってない?」
「持ってる訳がない」
どんな衣装持ちでも、鎧と鉄かぶとがクローゼットの中に入っている一般人はいねーよ。
コスプレじゃん。
「そっかー。…残念だなー」
残念なのかよ。
一体何に触発されたのか…。戦国武将にでも憧れてるのか?
まぁ、あれだよ。男の子なら人生で一度は、格好良く鎧を着て、猛然と戦う戦国武将に憧れたりするもんだろ?
それと同じだと思えば…。
…俺はなかったけどな。戦国武将への憧れは。
「それなら仕方ない…。…悠理君、悠理君の服貸してくれる?」
「え?」
「悠理君の持ってる男の子の服、着たい」
と、寿々花さんが頼んできた。
俺の服?
「別に良いけど…。そんな立派なもんじゃないぞ?」
それこそ、春に一緒に服を買いに行った、例のファッションセンターイマムラで買ったような安物ばっかり。
それに、もう何年も着てるから、大抵の服はくたびれてきてるし…。
「悠理君の服なら何でも良いよ」
とのこと。
何でも良いって言われてもな…。寿々花さんほどじゃないけど、俺も、それほど衣装持ちという訳でもなく…。
まぁ、良いか。服を貸すくらい、どうということはない。
「じゃあ、俺のタンスから好きなのを選んでくれ。どれでも良いぞ」
「わーい。タンス漁りだ〜」
漁るな。
「うーん。まだー」
おいおい。悠長だな。
「何を着るつもりなのか知らないけど…早いところ用意しておけよ。前日になったらバタバタして…」
「私ね、着てみたい服があるんだー」
とのこと。
着てみたい服…?それは珍しいな。
着るものに全く頓着しない寿々花さんが、自ら「着たい」と希望するなんて。
一体どんな衣装なんだろう。
「何?着てみたい服って」
「鎧と鉄かぶと」
…何処の戦国武将?
「小道具に太刀と刀を持って、格好良く抜刀術とか披露したい」
うきうきと夢を語ってくれてありがとう。
でも、それは無理だから。
現実を見ような。現実を。
「無理だろ。何処に売ってるんだよ。鎧なんか…」
「ないかな?悠理君、鎧持ってない?」
「持ってる訳がない」
どんな衣装持ちでも、鎧と鉄かぶとがクローゼットの中に入っている一般人はいねーよ。
コスプレじゃん。
「そっかー。…残念だなー」
残念なのかよ。
一体何に触発されたのか…。戦国武将にでも憧れてるのか?
まぁ、あれだよ。男の子なら人生で一度は、格好良く鎧を着て、猛然と戦う戦国武将に憧れたりするもんだろ?
それと同じだと思えば…。
…俺はなかったけどな。戦国武将への憧れは。
「それなら仕方ない…。…悠理君、悠理君の服貸してくれる?」
「え?」
「悠理君の持ってる男の子の服、着たい」
と、寿々花さんが頼んできた。
俺の服?
「別に良いけど…。そんな立派なもんじゃないぞ?」
それこそ、春に一緒に服を買いに行った、例のファッションセンターイマムラで買ったような安物ばっかり。
それに、もう何年も着てるから、大抵の服はくたびれてきてるし…。
「悠理君の服なら何でも良いよ」
とのこと。
何でも良いって言われてもな…。寿々花さんほどじゃないけど、俺も、それほど衣装持ちという訳でもなく…。
まぁ、良いか。服を貸すくらい、どうということはない。
「じゃあ、俺のタンスから好きなのを選んでくれ。どれでも良いぞ」
「わーい。タンス漁りだ〜」
漁るな。
早速、俺の部屋にやって来た寿々花さんは。
しばし吟味するように、俺のタンスの中を物色し始めた。
…何の躊躇いもなく。
あんたな…。いくら一緒に暮らしてるとはいえ、よくもまぁ、男のタンスをそんな…。
何の躊躇いもなく開けて、平気で中を物色出来るもんだよ。
もうちょっと躊躇わないか?普通。女子なら。
…まぁ、逆にこれで良かったのかもしれない。
いちいち恥ずかしがられたら、こっちまで恥ずかしくなってくるだろうから。
そもそも恥ずかしいと思ってるなら、わざわざ俺の服を貸してくれ、と頼んだりはしないだろう。
「どれなら良い?どれだったら私が着ても良いかな」
「あ?別に良いぞ、どれでも」
どうぞ、遠慮なく。俺の服で良かったらどれでも。
俺は別に、自分の服にそんなにこだわりないし。
「そっかー。どれにしよっかなー」
とか言いながら、寿々花さんは一枚一枚、服を手にとっては眺めていた。
…今時の高校生にしてはダサい…とか思われてんのかな。
自慢じゃないけど、俺は服のセンスなんて皆無だからな。
流行に釣られるタイプでもないから、時代遅れのデザインもたくさん混ざっている。
良いじゃん、別に。普段着くらい何でも。
ファッションモデルでもあるまいに。
いちいち、シーズンごとに流行の最先端を追ってたら、キリがないっての。
「どうだ?お眼鏡に叶う衣装はあったか?」
「このタンスの中の服、どれも悠理君の匂いがするー」
「…それって、俺、もしかして悪口言われてる?」
タンス用の脱臭剤、買って入れておこう。
「…よし、決めた」
「…何だよ…?」
「これにする。これ貸してー」
と言って、寿々花さんが選んだ一着は。
「そ、それは…」
タンスの一番隅っこに入れていたはずの、制服だった。
俺が中学校の時に着ていた、学ラン。
奇しくも、寿々花さんも俺と同じく、学校の制服をコンテストの衣装に選んだらしい。
いや、でも。それはちょっと…。…どうなの?
「…駄目?」
「いや、駄目ってことはないけど…」
どれでも好きなのを、って言った手前…それはやめておけ、とは言えないけど。
俺のタンスの中にあるダサい服のラインナップから、敢えて一番ダサいであろうその学ランを選ぶとは。
しかも、3年間着古してるから、よれよれだし。
…汗臭くね?それ。大丈夫か?
汗臭いより、カビ臭いんじゃね?
「このお洋服、悠理君が着てるの見たことないね。お気に入りなの?」
「お気に入りじゃなくて…それ、中学の時の制服だから」
「中学?悠理君が中学生の時の制服、これだったの?」
「あ、うん…」
昔懐かしの、ダサい学ランだよ。
…それが何か?
しばし吟味するように、俺のタンスの中を物色し始めた。
…何の躊躇いもなく。
あんたな…。いくら一緒に暮らしてるとはいえ、よくもまぁ、男のタンスをそんな…。
何の躊躇いもなく開けて、平気で中を物色出来るもんだよ。
もうちょっと躊躇わないか?普通。女子なら。
…まぁ、逆にこれで良かったのかもしれない。
いちいち恥ずかしがられたら、こっちまで恥ずかしくなってくるだろうから。
そもそも恥ずかしいと思ってるなら、わざわざ俺の服を貸してくれ、と頼んだりはしないだろう。
「どれなら良い?どれだったら私が着ても良いかな」
「あ?別に良いぞ、どれでも」
どうぞ、遠慮なく。俺の服で良かったらどれでも。
俺は別に、自分の服にそんなにこだわりないし。
「そっかー。どれにしよっかなー」
とか言いながら、寿々花さんは一枚一枚、服を手にとっては眺めていた。
…今時の高校生にしてはダサい…とか思われてんのかな。
自慢じゃないけど、俺は服のセンスなんて皆無だからな。
流行に釣られるタイプでもないから、時代遅れのデザインもたくさん混ざっている。
良いじゃん、別に。普段着くらい何でも。
ファッションモデルでもあるまいに。
いちいち、シーズンごとに流行の最先端を追ってたら、キリがないっての。
「どうだ?お眼鏡に叶う衣装はあったか?」
「このタンスの中の服、どれも悠理君の匂いがするー」
「…それって、俺、もしかして悪口言われてる?」
タンス用の脱臭剤、買って入れておこう。
「…よし、決めた」
「…何だよ…?」
「これにする。これ貸してー」
と言って、寿々花さんが選んだ一着は。
「そ、それは…」
タンスの一番隅っこに入れていたはずの、制服だった。
俺が中学校の時に着ていた、学ラン。
奇しくも、寿々花さんも俺と同じく、学校の制服をコンテストの衣装に選んだらしい。
いや、でも。それはちょっと…。…どうなの?
「…駄目?」
「いや、駄目ってことはないけど…」
どれでも好きなのを、って言った手前…それはやめておけ、とは言えないけど。
俺のタンスの中にあるダサい服のラインナップから、敢えて一番ダサいであろうその学ランを選ぶとは。
しかも、3年間着古してるから、よれよれだし。
…汗臭くね?それ。大丈夫か?
汗臭いより、カビ臭いんじゃね?
「このお洋服、悠理君が着てるの見たことないね。お気に入りなの?」
「お気に入りじゃなくて…それ、中学の時の制服だから」
「中学?悠理君が中学生の時の制服、これだったの?」
「あ、うん…」
昔懐かしの、ダサい学ランだよ。
…それが何か?
「そっかー。悠理君、去年まで毎日これ着てたんだー…」
しみじみ、と学ランを眺める寿々花さん。
…そんなまじまじと見るようなもんじゃねーだろ。
学ランなんて。非常にありふれた制服だからな。
「そう、去年まで毎日着てたからさ…。結構よれよれだし、匂いも…」
「匂い?…くんくん」
「ちょ、嗅ぐなって、馬鹿」
あろうことか寿々花さんは、俺の学ランの首元に顔をくっつけて、匂いを嗅いでいた。
アホなのか。勇者か?
「臭いだろ。ずっとしまってたから…。着るつもりなら、一度洗濯するよ」
「ううん、大丈夫。何だか…染み付いた悠理君の匂いがする」
「そうか。急いで洗濯しよう」
可及的速やかに洗濯しよう。
何ならもう、タンスごと丸洗いしたい気分。
自分の匂いって、自分ではなかなか分からないもんだからなぁ…。
知らない間にめちゃくちゃ臭くなってるとか、あるある。
「これ着たい。悠理君の制服〜」
何故嬉しそうなのか。
別に良いけど…。好きなようにすれば。
「私、これ似合うかな?」
「さぁ…。あんたは顔が良いから、学ランだろうと鎧だろうと、何でも似合うんじゃね?」
「ありがとう。悠理君も格好良いから、きっと何を着ても似合うよ。ワンピースとかスカートを穿いても似合うと思う」
それは褒め言葉だと思って良いんだよな?
全然嬉しくはないけど。
…ともあれ、これでお互い、コンテストで着る衣装が決まった。
やれやれ。衣装だけで大騒ぎだよ。全く。
しみじみ、と学ランを眺める寿々花さん。
…そんなまじまじと見るようなもんじゃねーだろ。
学ランなんて。非常にありふれた制服だからな。
「そう、去年まで毎日着てたからさ…。結構よれよれだし、匂いも…」
「匂い?…くんくん」
「ちょ、嗅ぐなって、馬鹿」
あろうことか寿々花さんは、俺の学ランの首元に顔をくっつけて、匂いを嗅いでいた。
アホなのか。勇者か?
「臭いだろ。ずっとしまってたから…。着るつもりなら、一度洗濯するよ」
「ううん、大丈夫。何だか…染み付いた悠理君の匂いがする」
「そうか。急いで洗濯しよう」
可及的速やかに洗濯しよう。
何ならもう、タンスごと丸洗いしたい気分。
自分の匂いって、自分ではなかなか分からないもんだからなぁ…。
知らない間にめちゃくちゃ臭くなってるとか、あるある。
「これ着たい。悠理君の制服〜」
何故嬉しそうなのか。
別に良いけど…。好きなようにすれば。
「私、これ似合うかな?」
「さぁ…。あんたは顔が良いから、学ランだろうと鎧だろうと、何でも似合うんじゃね?」
「ありがとう。悠理君も格好良いから、きっと何を着ても似合うよ。ワンピースとかスカートを穿いても似合うと思う」
それは褒め言葉だと思って良いんだよな?
全然嬉しくはないけど。
…ともあれ、これでお互い、コンテストで着る衣装が決まった。
やれやれ。衣装だけで大騒ぎだよ。全く。
その後の数日も、毎日文化祭の準備に追われ。
いよいよ、聖青薔薇学園文化祭の当日を迎えた。
いよいよ、聖青薔薇学園文化祭の当日を迎えた。
さぁ、いよいよ始まった文化祭。
昨日までに、雛堂達と協力しながら、準備万端整えてきたからな。
特にこの数日と来たら、あまりの忙しさに、雛堂がまたしても白目を剝いていたくらいだから。
今日は、その成果を遺憾なく発揮したい。
…ところだったが。
問題は、苦労して開店した『HoShi壱番屋』に、ちゃんとお客さんが来てくれるのか、という点だ。
こればかりは、俺にはどうしようもない。
教室の真ん前には、立派な看板を立ててある。
クラスメイトと協力して、ペンキを塗って作った力作である。
とは言っても、某カレーショップのロゴマークをモチーフにした、パクリ看板だけど。
クラスメイトに頼んで、手書きのメニュー表をたくさんコピーして、ビラにして新校舎で配ってもらうことにはなっているが。
果たして、あの白黒印刷の安っぽいビラに、どれほど効果があるものだろうか…。
カレーの準備も、糠漬けの準備も既に出来ている。
教室の中も、テーブルと椅子を並べ、テーブルクロスを敷いて、ばっちりセッティングしてある。
こちらの準備は完璧。
あとは、カレーを食べにやって来るお客さんを待つだけである。
…しかし。
「…人、来ねぇな…」
「あぁ…来ねぇなぁ…」
「見事に閑古鳥ですね」
恐れていたことが起きてしまった。
開店したのに、お客さんが一人も来ない。
これには、シェフ(俺)も涙目である。
昨日までに、雛堂達と協力しながら、準備万端整えてきたからな。
特にこの数日と来たら、あまりの忙しさに、雛堂がまたしても白目を剝いていたくらいだから。
今日は、その成果を遺憾なく発揮したい。
…ところだったが。
問題は、苦労して開店した『HoShi壱番屋』に、ちゃんとお客さんが来てくれるのか、という点だ。
こればかりは、俺にはどうしようもない。
教室の真ん前には、立派な看板を立ててある。
クラスメイトと協力して、ペンキを塗って作った力作である。
とは言っても、某カレーショップのロゴマークをモチーフにした、パクリ看板だけど。
クラスメイトに頼んで、手書きのメニュー表をたくさんコピーして、ビラにして新校舎で配ってもらうことにはなっているが。
果たして、あの白黒印刷の安っぽいビラに、どれほど効果があるものだろうか…。
カレーの準備も、糠漬けの準備も既に出来ている。
教室の中も、テーブルと椅子を並べ、テーブルクロスを敷いて、ばっちりセッティングしてある。
こちらの準備は完璧。
あとは、カレーを食べにやって来るお客さんを待つだけである。
…しかし。
「…人、来ねぇな…」
「あぁ…来ねぇなぁ…」
「見事に閑古鳥ですね」
恐れていたことが起きてしまった。
開店したのに、お客さんが一人も来ない。
これには、シェフ(俺)も涙目である。
幸先が悪いにも程があるだろ。
これだけ準備万端整えたのに、食べに来る人が誰もいないとは。
どうする?早速、クラスメイトの為に賄いでも作る?
すげー惨めなんだけど?
「まぁ、まだ開いたばっかりですから。お昼時になったら、少しは人、来てくれるんじゃないですか?」
と、乙無が切ないフォロー。
そうだと良いんだけど。
そもそも、文化祭がようやく始まったというのに。
旧校舎全体に、全然活気がないんだよな。
多分うちのクラスだけじゃなくて、男子部のクラスは何処もこんな感じだと思う。
無理もない。
文化祭始まったばかりなのに、わざわざ小汚い旧校舎に先に足を運ぶ物好きがいるかよ。
きっと今頃、新校舎の方は、活気に満ち溢れていることだろう。
…寿々花さん、どうしてんのかな…。
メイドカフェだって言ってたけど…。変な男に絡まれたりしてないよな…?
「まぁ、良いや。真珠兄さんの言う通りだ。昼時になったら、人も来るだろ」
と、雛堂は努めて楽観視を装った。
「それまで、トランプでもやって遊んでようぜ」
暇過ぎて、客が来るまで厨房でトランプ遊びをする店主と従業員。
大問題だろ、これ。
でも仕方ないじゃないか。誰もお客さんが来ないんだから。
まぁ、いっか。
そうこうしてたら来るだろう、お客さん。一人二人くらいは。
「じゃ、ババ抜きでもするかー」
「おぉ…」
「一枚のジョーカーを他人に押し付け合う…。まるで社会の縮図のようなゲームですね」
ろくでもないことを言うんじゃない、乙無。
自慢じゃないけど、俺、こう見えてトランプ遊びには慣れてるんだよ。
何せ、寿々花さんに何度も付き合わされてるからな。
だから、トランプにはちょっと自信があった…はずなのだが。
これだけ準備万端整えたのに、食べに来る人が誰もいないとは。
どうする?早速、クラスメイトの為に賄いでも作る?
すげー惨めなんだけど?
「まぁ、まだ開いたばっかりですから。お昼時になったら、少しは人、来てくれるんじゃないですか?」
と、乙無が切ないフォロー。
そうだと良いんだけど。
そもそも、文化祭がようやく始まったというのに。
旧校舎全体に、全然活気がないんだよな。
多分うちのクラスだけじゃなくて、男子部のクラスは何処もこんな感じだと思う。
無理もない。
文化祭始まったばかりなのに、わざわざ小汚い旧校舎に先に足を運ぶ物好きがいるかよ。
きっと今頃、新校舎の方は、活気に満ち溢れていることだろう。
…寿々花さん、どうしてんのかな…。
メイドカフェだって言ってたけど…。変な男に絡まれたりしてないよな…?
「まぁ、良いや。真珠兄さんの言う通りだ。昼時になったら、人も来るだろ」
と、雛堂は努めて楽観視を装った。
「それまで、トランプでもやって遊んでようぜ」
暇過ぎて、客が来るまで厨房でトランプ遊びをする店主と従業員。
大問題だろ、これ。
でも仕方ないじゃないか。誰もお客さんが来ないんだから。
まぁ、いっか。
そうこうしてたら来るだろう、お客さん。一人二人くらいは。
「じゃ、ババ抜きでもするかー」
「おぉ…」
「一枚のジョーカーを他人に押し付け合う…。まるで社会の縮図のようなゲームですね」
ろくでもないことを言うんじゃない、乙無。
自慢じゃないけど、俺、こう見えてトランプ遊びには慣れてるんだよ。
何せ、寿々花さんに何度も付き合わされてるからな。
だから、トランプにはちょっと自信があった…はずなのだが。
この作家の他の作品
表紙を見る
彼らは夢を見る。毎晩、バケモノに襲われる悪夢を。
彼らは生贄。罪を犯した人間達が生み出したバケモノを、その手で殺すことを宿命付けられた生贄。
彼らは選ばれた。「普通」であることに選ばれなかった彼ら。
裁定者たる天使が振った賽に、選ばれてしまった彼らが辿る運命は。
そして、生贄に選ばれた彼らの抱える、辛く、苦しみに満ちた過去の記憶とは…。
表紙を見る
2019年に作者が携帯小説モバスペbookに投稿した作品を移植しました。
彼らの迎えた夜明けに、祝福の歌を。
表紙を見る
2021年にモバスペbookに投稿した作品を移植しました。
エロマフィア、記念すべき第5弾。
最果てにあるレゾンデートルを、お楽しみください。
※この作品に登場する宗教、教義、宗教組織は全てフィクションです。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…