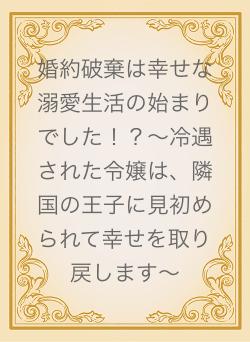「すごいでしょ? これがボクの好きなもの」
「そっか。ナノはヴァイオリンが得意なんだね」
「うん! ボクは音楽が好きなんだ。友達の印に、君の思い出の曲を奏でてあげるよ!」
ナノはひれを羽のように広げて、足元の水面を弾いた。舞い上がった水飛沫は、くるくると空へ昇ってやがて楽譜に形を変えると、ひらひらと海鈴たちのもとに落ちてくる。
「息を吹きかけてみて」
海鈴がふぅ、とバースデーキャンドルを吹き消すように息を吐くと、それらは小さな旋風となり、やがて人の形を成し始めた。あっという間に小さな精霊たちが現れる。ナノがヴァイオリンの弓を指揮棒代わりに持ち直し、パッと振る。風の精霊たちが揃えて発した声は、オーケストラの盛大な音楽だった。
モーツァルトやショパン、ラヴェルやクライスラー。耳に馴染みの深い名曲たちが、精霊たちの声であって声ではない声に優しく繊細に紡がれていく。
海鈴の中で、なにかがカタンと音を立てたような気がした。しかし、海鈴はそのことに気付かないまま、ナノの生み出す音楽に耳を傾けた。
演奏を終えると、ナノが言った。
「そうだ! ボク、今からステラと会うんだけど、君も来ない? ステラはボクの親友なんだ!」
なんだか美味しそうな名前だ。どの道、ここでこのままぼんやりしていてもどうにもならないし、元の世界に戻るには、やはりもう少しこの世界のことを知らなければならない。
「ステラか……うん。会ってみたいかも」
「やったー! それじゃあ、善は急げ! 行こう、ミレイ」
ふよふよと空中を泳ぐように飛ぶナノの後ろをついて歩きながら、海鈴は目の前の世界をあらためて見つめた。
「ねぇ、ナノ。この世界はさ、どこかの世界と繋がってたりする?」
たとえば、海鈴が住んでいる世界とか。
「うーん。どうかなぁ。でもね、この世界、最近少し不安定になってるみたいなんだ」
「不安定?」
「うん。なんかよく分からないけど、最近ちょっと殺伐としている気がするんだ。みんななにかに焦ってるみたい。この前もナイトメアたちがなにか物騒なものを作ってるって噂を聞いた」
「ナイトメア? なあにそれ」
首を傾げてナノを見るが、ナノも海鈴に合わせて首を傾げた。
「ボクもよく分かんないんだ」
「そっか……あ、そういえばさっき、ナノは音楽が好きって言ってたけど」
「うん! ボクは音楽そのものから生まれたんだ」
「音楽そのもの?」
海鈴は瞳をぱちくりと瞬かせた。
「そう! ボクは、あの子の音楽が好きって気持ちから生まれたの。でも、ボクだけじゃないよ。この世界はあの子が作ってくれたんだ」
「あの子? この世界を作った……?」
「ボクはね、生まれてからずっとこの世界の音を生み出してるんだ。いつか、広いドームでコンサートをするのがボクの夢なんだ。ボクの楽しいって気持ちは、あの子の楽しいって気持ちなの。だから、分かるんだ。あの子は今、暗闇の中にいる。でも、きっとあの子は自分で自分の道を見つけるから。ボクはそれを信じてるんだ」
前へ踏み出す足が重くなり、歩みが止まる。ナノは心からその子を信じているようだった。
「……ナノはその子のこと、大好きなんだね」
海鈴も音楽は好きだ。ナノの背負うヴァイオリンケースを見る。メタリックの入ったバーガンディー色。海鈴は懐かしさに目を細めた。
幼少期、海鈴もヴァイオリンを習っていた。びんと響く音も、弦を押さえたときに指にできる痕も、すべてが懐かしい。けれど、たった一度コンクールの舞台で弓が切れ、失敗してしまったことがトラウマになって、それきりやめてしまったのだった。
「君も弾いてみる? ヴァイオリン、とっても気持ちいいんだよ」
ヴァイオリンの音色を聴くのは、今でも大好きだ。けれど、きっともう弾くことはないだろうと思っていた。
海鈴の胸にじんわりと苦い痛みが広がっていく。
「なにか、大切なことを思い出せるかもしれないよ」
ナノの声は、意味深に海鈴の心を打った。ナノは海鈴の横顔をじっと見つめている。
「……じゃあ、ちょっとだけ、やってみようかな」
ナノのヴァイオリンは、しっかり手入れされていた。触れると、その感触にあの頃の懐かしさがじんわりと広がっていく。持った途端に手の中に伝わる重さと感触。それは、海鈴の過去へ続く扉を小さくノックした。
「聞かせて、君の音楽」
顎で挟み、右手を添え、弓を構える。
心臓がどくどくと脈を打つ。ちゃんと弾けるだろうか。上手く弾けなかったらどうしよう。怖い。でも、弾きたい。様々な感情がざわざわと胸に締め付ける。
びぃん……。
弓がかすかにしなる。
心が震えた。胸がいっぱいになって、苦しくて、でもその苦しさがなぜだか心地よかった。海鈴の奏でる音楽に合わせて、ナノが指揮を始める。すると、精霊たちも海鈴の周りを取り囲み、新たな音楽団が生まれた。
これは夢だ。なんでもあって、なんでもない夢。海鈴が好きなものを好きと言って、好きなことを自由にできる夢。
演奏が終わり、ヴァイオリンを拭きながら、海鈴は思い出した。
コンテストなんて出なくてもいい。ただ自由に弾くだけでいい。それだけで、こんなにも心は満たされるのだ。
「良かった! 君が笑顔になって」
「ナノ、貸してくれてありがとう。すごく楽しかった」
ナノはにこっと笑うと、再びふよふよと泳ぎ出した。
水面に映る自分自身を打ち消しながら、海鈴はナノとともにステラというナノの友達の元へ向かっていた。
「……ねぇ、ナノ。私は何者なのかな?」
先を行くナノの背中に、ふと疑問に思ったことを訊ねてみる。
「何者?」
ナノは丸々とした瞳をぱちくりと瞬いた。
「私は、ナノみたいになんの特技もないし、好きなものもないから……」
すると、ナノはころころと笑う。
「ミレイ。ここは自由な場所なんだよ。なんでもあってなんにもない。みんな自由に暮らしてる。みんな何者にもなれるし、何者でもないのさ。君は好きなものがないんじゃなくて、ただ忘れてるだけ。きっとそのうち思い出せるよ」
つぎはぎの空を見上げる。
なんのしがらみにも拘束されず、好きなことをしている自由なナノ。たかだか高校卒業後の進路のことで悩んでいる自分が不甲斐(ふがい)なく思えてきた。
立ち止まった海鈴を振り返って、ナノが言った。
「だって、好きなものがないなんて嘘だもん。誰だって好きって気持ちはあるんだ。この世界はね、嫌いな気持ちを育てるより、好きな気持ちをちょこっと大切にしてるだけ。不安に思うことなんてないよ」
ナノの丸い口からぽんと出た言葉は、まるで世界の始まりに吹くラッパのように、海鈴の胸にじんと響いた。
「……ありがとう、ナノって優しいね」
えへへと照れくさそうに笑うナノの吐息から、ぽろろと音符が零れ、また新たな譜面が完成していく。
「……この世界は不思議だね」
まるで、解き放たれたような感覚を覚えた。自身の手を開いてみたり閉じてみたりしながら、海鈴は言った。
「不思議? そう?」
この世界は不思議だ。海鈴は目を伏せた。
「まるでおもちゃ箱みたい。夢とか好きなものが溢れてて、制限するものはなにもなくて輝いてる……」
海鈴は目を閉じ、音楽に耳を傾けた。
チクタクチクタク……。
「……あれ?」
ナノの音楽に混じって、別の機械的な音が聞こえる。しかもそれは、段々と大きくなっていた。
「なに、この音?」
「え?」
ナノはきょとんとしている。
「聞こえない? ほら、なんか……」
「いや……ボクにはなにも?」
チクタクチクタクチクタクチクタク。
いや、やはり聞こえる。
「時計の音……」
「とけい? なあに、それ」
それは、この世界へ来たときからたしかに鳴っていた時計の秒針の音だった。しかし、目が覚めたときよりも確実に大きくなっている。
「ボクにはなんにも聞こえないよ?」
ナノが振り向いた瞬間、背中のヴァイオリンケースがきらりと光った。その中に閉じ込められた自分自身と、パッと目が合う。海鈴は意識を手放した。
「そっか。ナノはヴァイオリンが得意なんだね」
「うん! ボクは音楽が好きなんだ。友達の印に、君の思い出の曲を奏でてあげるよ!」
ナノはひれを羽のように広げて、足元の水面を弾いた。舞い上がった水飛沫は、くるくると空へ昇ってやがて楽譜に形を変えると、ひらひらと海鈴たちのもとに落ちてくる。
「息を吹きかけてみて」
海鈴がふぅ、とバースデーキャンドルを吹き消すように息を吐くと、それらは小さな旋風となり、やがて人の形を成し始めた。あっという間に小さな精霊たちが現れる。ナノがヴァイオリンの弓を指揮棒代わりに持ち直し、パッと振る。風の精霊たちが揃えて発した声は、オーケストラの盛大な音楽だった。
モーツァルトやショパン、ラヴェルやクライスラー。耳に馴染みの深い名曲たちが、精霊たちの声であって声ではない声に優しく繊細に紡がれていく。
海鈴の中で、なにかがカタンと音を立てたような気がした。しかし、海鈴はそのことに気付かないまま、ナノの生み出す音楽に耳を傾けた。
演奏を終えると、ナノが言った。
「そうだ! ボク、今からステラと会うんだけど、君も来ない? ステラはボクの親友なんだ!」
なんだか美味しそうな名前だ。どの道、ここでこのままぼんやりしていてもどうにもならないし、元の世界に戻るには、やはりもう少しこの世界のことを知らなければならない。
「ステラか……うん。会ってみたいかも」
「やったー! それじゃあ、善は急げ! 行こう、ミレイ」
ふよふよと空中を泳ぐように飛ぶナノの後ろをついて歩きながら、海鈴は目の前の世界をあらためて見つめた。
「ねぇ、ナノ。この世界はさ、どこかの世界と繋がってたりする?」
たとえば、海鈴が住んでいる世界とか。
「うーん。どうかなぁ。でもね、この世界、最近少し不安定になってるみたいなんだ」
「不安定?」
「うん。なんかよく分からないけど、最近ちょっと殺伐としている気がするんだ。みんななにかに焦ってるみたい。この前もナイトメアたちがなにか物騒なものを作ってるって噂を聞いた」
「ナイトメア? なあにそれ」
首を傾げてナノを見るが、ナノも海鈴に合わせて首を傾げた。
「ボクもよく分かんないんだ」
「そっか……あ、そういえばさっき、ナノは音楽が好きって言ってたけど」
「うん! ボクは音楽そのものから生まれたんだ」
「音楽そのもの?」
海鈴は瞳をぱちくりと瞬かせた。
「そう! ボクは、あの子の音楽が好きって気持ちから生まれたの。でも、ボクだけじゃないよ。この世界はあの子が作ってくれたんだ」
「あの子? この世界を作った……?」
「ボクはね、生まれてからずっとこの世界の音を生み出してるんだ。いつか、広いドームでコンサートをするのがボクの夢なんだ。ボクの楽しいって気持ちは、あの子の楽しいって気持ちなの。だから、分かるんだ。あの子は今、暗闇の中にいる。でも、きっとあの子は自分で自分の道を見つけるから。ボクはそれを信じてるんだ」
前へ踏み出す足が重くなり、歩みが止まる。ナノは心からその子を信じているようだった。
「……ナノはその子のこと、大好きなんだね」
海鈴も音楽は好きだ。ナノの背負うヴァイオリンケースを見る。メタリックの入ったバーガンディー色。海鈴は懐かしさに目を細めた。
幼少期、海鈴もヴァイオリンを習っていた。びんと響く音も、弦を押さえたときに指にできる痕も、すべてが懐かしい。けれど、たった一度コンクールの舞台で弓が切れ、失敗してしまったことがトラウマになって、それきりやめてしまったのだった。
「君も弾いてみる? ヴァイオリン、とっても気持ちいいんだよ」
ヴァイオリンの音色を聴くのは、今でも大好きだ。けれど、きっともう弾くことはないだろうと思っていた。
海鈴の胸にじんわりと苦い痛みが広がっていく。
「なにか、大切なことを思い出せるかもしれないよ」
ナノの声は、意味深に海鈴の心を打った。ナノは海鈴の横顔をじっと見つめている。
「……じゃあ、ちょっとだけ、やってみようかな」
ナノのヴァイオリンは、しっかり手入れされていた。触れると、その感触にあの頃の懐かしさがじんわりと広がっていく。持った途端に手の中に伝わる重さと感触。それは、海鈴の過去へ続く扉を小さくノックした。
「聞かせて、君の音楽」
顎で挟み、右手を添え、弓を構える。
心臓がどくどくと脈を打つ。ちゃんと弾けるだろうか。上手く弾けなかったらどうしよう。怖い。でも、弾きたい。様々な感情がざわざわと胸に締め付ける。
びぃん……。
弓がかすかにしなる。
心が震えた。胸がいっぱいになって、苦しくて、でもその苦しさがなぜだか心地よかった。海鈴の奏でる音楽に合わせて、ナノが指揮を始める。すると、精霊たちも海鈴の周りを取り囲み、新たな音楽団が生まれた。
これは夢だ。なんでもあって、なんでもない夢。海鈴が好きなものを好きと言って、好きなことを自由にできる夢。
演奏が終わり、ヴァイオリンを拭きながら、海鈴は思い出した。
コンテストなんて出なくてもいい。ただ自由に弾くだけでいい。それだけで、こんなにも心は満たされるのだ。
「良かった! 君が笑顔になって」
「ナノ、貸してくれてありがとう。すごく楽しかった」
ナノはにこっと笑うと、再びふよふよと泳ぎ出した。
水面に映る自分自身を打ち消しながら、海鈴はナノとともにステラというナノの友達の元へ向かっていた。
「……ねぇ、ナノ。私は何者なのかな?」
先を行くナノの背中に、ふと疑問に思ったことを訊ねてみる。
「何者?」
ナノは丸々とした瞳をぱちくりと瞬いた。
「私は、ナノみたいになんの特技もないし、好きなものもないから……」
すると、ナノはころころと笑う。
「ミレイ。ここは自由な場所なんだよ。なんでもあってなんにもない。みんな自由に暮らしてる。みんな何者にもなれるし、何者でもないのさ。君は好きなものがないんじゃなくて、ただ忘れてるだけ。きっとそのうち思い出せるよ」
つぎはぎの空を見上げる。
なんのしがらみにも拘束されず、好きなことをしている自由なナノ。たかだか高校卒業後の進路のことで悩んでいる自分が不甲斐(ふがい)なく思えてきた。
立ち止まった海鈴を振り返って、ナノが言った。
「だって、好きなものがないなんて嘘だもん。誰だって好きって気持ちはあるんだ。この世界はね、嫌いな気持ちを育てるより、好きな気持ちをちょこっと大切にしてるだけ。不安に思うことなんてないよ」
ナノの丸い口からぽんと出た言葉は、まるで世界の始まりに吹くラッパのように、海鈴の胸にじんと響いた。
「……ありがとう、ナノって優しいね」
えへへと照れくさそうに笑うナノの吐息から、ぽろろと音符が零れ、また新たな譜面が完成していく。
「……この世界は不思議だね」
まるで、解き放たれたような感覚を覚えた。自身の手を開いてみたり閉じてみたりしながら、海鈴は言った。
「不思議? そう?」
この世界は不思議だ。海鈴は目を伏せた。
「まるでおもちゃ箱みたい。夢とか好きなものが溢れてて、制限するものはなにもなくて輝いてる……」
海鈴は目を閉じ、音楽に耳を傾けた。
チクタクチクタク……。
「……あれ?」
ナノの音楽に混じって、別の機械的な音が聞こえる。しかもそれは、段々と大きくなっていた。
「なに、この音?」
「え?」
ナノはきょとんとしている。
「聞こえない? ほら、なんか……」
「いや……ボクにはなにも?」
チクタクチクタクチクタクチクタク。
いや、やはり聞こえる。
「時計の音……」
「とけい? なあに、それ」
それは、この世界へ来たときからたしかに鳴っていた時計の秒針の音だった。しかし、目が覚めたときよりも確実に大きくなっている。
「ボクにはなんにも聞こえないよ?」
ナノが振り向いた瞬間、背中のヴァイオリンケースがきらりと光った。その中に閉じ込められた自分自身と、パッと目が合う。海鈴は意識を手放した。