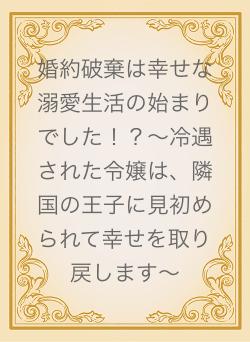その日の昼過ぎ、海鈴は町で唯一のスーパーにいた。くすんだガラスのかつて自動ドアであったそれは、数年前に壊れたまま。古ぼけた看板には、『スーパーキューブ』とある。
海鈴は母に頼まれた牛乳とマヨネーズ、それからちゃっかり自分用のメロンパンと板チョコが入ったビニール袋を手に、手動ドアを開けて外に出る。途端にむわんとした空気が一気に海鈴の肌に張り付き、汗を誘った。
「あっつぅ……」
太陽の燦々とした眩しさに目が眩み、空へ手をかざす。指の隙間から差し込む光が、海鈴の顔に斑な影を落とした。
帰り道、海鈴は無人の神社に立ち寄った。賽銭箱の隣に腰を下ろし、スーパーの前に立ち寄った図書館で借りてきた本を手に、青々とした竹が生い茂った神社の空気を味わう。
風が葉を優しく撫で、吹き抜けていく。遠くで鷹が空を旋回しながら鳴いていた。耳にかけていた前髪が、さらりと落ちた。
『ねぇ』
葉が騒ぐ音に交じって、かすかに声がした。顔を上げ、辺りを見る。人気はない。海鈴は気のせいだと聞き流した。小さな音を立てて、柄杓の中に一滴の雫が落ちた。
『ねぇってば』
ハッとした。聞こえてきたのは、紛れもなく自分の声だった。本を閉じ、顔を上げる。どこから聞こえるだろう。林の中ではないし、手水舎にも人の影はない。
すぐに今朝の鏡の中の彼女……ではなく、自分だと思い至り、鏡なんて持っていない海鈴は、もう一度きょろきょろと辺りを見回した。
『ここよ、ここ』
柄杓の中の水がぴちゃんと弾けた。それは凪いでいた水面に波紋を作り、やがて静寂を取り戻す。
『やっと会えたわ、海鈴』
柄杓の水面に映った自分が言う。海鈴はいよいよ言葉を失った。一日に二度までもこんな不思議な目眩を起こすなんて、とうとう自分が心配になってきた。
「なんなの……あなた?」
そもそも水面に映った自分に問いかけている時点でどうかしているが、聞かずにはいられなかった。
『私はあなた。もう一人のあなたよ』
おかしい。なぜ自分と会話が成立しているのだろう。
『海鈴? なににでも意味を求めるのは良くないと思うわよ。だって、この世は意味があるものだけじゃないんだから』
呆れ気味の自分に諭され、眉を寄せる。
「……どういうこと?」
『知りたい?』
水の中の自分がにやりと笑う。それは、子どもがいたずらを思いついたときのような無邪気な笑みで。
『ねぇ、海鈴。私と入れ替わってみない?』
胸が弾む。とても有り得ない、これは現実ではないと思いながら、心のどこかでわくわくしている自分がいる。
『この中には、あなただけの物語があるのよ。ねぇ、知りたくない?』
水面が揺れる。中とは、この柄杓の中という意味なのだろうか。どちらにせよ、海鈴は思った。
「知りたい……」
どうやら、海鈴はまだ大人にはなりたくないらしい。水面の自分が、手を伸ばす。海鈴の膝にあった本がパタンと落ちた。
この世には、理論も物理も不可能なんて言葉だって存在しない。いつだってちぐはぐで、願えばユニコーンでも神様でも悪魔でも、運命の人だって現れる無限の世界なのだ。
海鈴の手が水の中に沈む。しかし、感じるのはひんやりとした水の感触ではなく、人の手のぬくもりだった。
『さぁ、世界を交換しよう』
その日、海鈴の世界がぐにゃりと歪んだ。
世界は不思議で満ち満ちている。
たとえば、今目の前にあるこのすべて。布地にビーズやボタンを散りばめたような明るい星空。
どこからか、時計の音が心地よく流れる不思議な空間。海鈴はまるで、絵本の中に入り込んでしまったかと思った。空にはつぎはぎの半透明のレールが流れ、そこを立派な銀色の汽車が星屑を散らしながら走っていく。
煌めく宝石の瞳を埋め込まれた回転木馬や大きな角のユニコーン、偉大な翼を従えたペガサスたちは、ぐるぐると回るそこを飛び出し、いななきながら自由に空を駆けていく。
足元には一面透明な水が張り、覗くと縫い目のある空やビルや海鈴を映し出していた。指揮棒を振れば、どこからか現れた楽器たちが自由気ままに音楽を奏で出す。
お菓子の家やチョコレートの滝、ビスケットの車やバウムクーヘンの切り株が立ち並ぶ甘い町並み。大きな白い袋を持って歩く花は居心地のいい場所を求めて旅をして、服を着た動物たちは楽しそうに人の言葉を話しながら、お茶をしたり煙草を咥えていたり。
海鈴よりもずっと大きな体をした虫はたくさんの脚を器用に使ってとんとんかんかん日曜大工。手のひらサイズの月は空中にたゆたい、気持ち良さそうに寝息を立てていた。
「なに……ここ……」
海鈴はその場に立ち尽くした。夢を見ているのかと頬をつねってみたりしたが、痛みだけたしかに感じるだけで、一向に夢から醒める気配はない。
一歩足を踏み出すと、海鈴から波紋が広がっていく。ぴちゃん、と軽やかな音がする。水の中の海鈴の影が一瞬消え、揺らぎ、また現れる。
「……ん?」
海鈴はしゃがみ込んだ。水の中の自分は、見慣れない赤いワンピースを着ていた。裾や袖には幾層にもなったラメ入りの黒いフリルとレース。
腰に絡みついた漆黒のリボンは海鈴の細い腰をより強調している。バルーンのようにふんわりと広がったスカートから覗く二本の足を彩るのは、赤いハイヒール。
自分なのに自分ではないような感じがした。こんな派手な服は着たことがない。海鈴は少しだけ恥ずかしくなった。
「あの……ちょっと?」
おずおずと声をかけてみる。しかし、見慣れたその顔は自分の意思に反して瞬きをすることも笑うことも、ましてや喋り出す気配もなかった。
「ねぇ……ここはどこ?」
いくら呼びかけても、答えは返ってこない。
「あのー……もしもし? もしもーし……」
いよいよ困り果てた海鈴は、そのときふと思い出した。
『この世は意味があるものだけじゃない』
手でさっと水を弾く。その瞬間、ぱしゃんと飛沫が上がり、自分の姿がかき消された。弾けた飛沫はやがて大きな泡になって、空中を漂い出す。
まるでマジックのようだ。泡になった水飛沫たちは、様々な色に輝きながら割れることなく空へ昇っていく。
光の泡がぽわんぽわんと薄紫色の空を彩り始めれば、光の泡が踊り出す。光に合わせて、どこかから鳴り出す軽快なリズム。
思わず後退ると、タップシューズを履いているわけでもないのに高らかな音を奏でる踵。
「なにこれ……すごい!」
なんだか楽しくなってきた。こんなにも胸が弾むのはいつぶりだろう。
もう一度水を弾けば、今度は白いレースが生まれた。ひらひらと蝶のように舞うそれは、空を飛ぶカササギの体に巻きついて美しいドレスに変化する。
進路も夢も、つまらない現実も。海鈴は、すべてを忘れてはしゃいだ。
海鈴は母に頼まれた牛乳とマヨネーズ、それからちゃっかり自分用のメロンパンと板チョコが入ったビニール袋を手に、手動ドアを開けて外に出る。途端にむわんとした空気が一気に海鈴の肌に張り付き、汗を誘った。
「あっつぅ……」
太陽の燦々とした眩しさに目が眩み、空へ手をかざす。指の隙間から差し込む光が、海鈴の顔に斑な影を落とした。
帰り道、海鈴は無人の神社に立ち寄った。賽銭箱の隣に腰を下ろし、スーパーの前に立ち寄った図書館で借りてきた本を手に、青々とした竹が生い茂った神社の空気を味わう。
風が葉を優しく撫で、吹き抜けていく。遠くで鷹が空を旋回しながら鳴いていた。耳にかけていた前髪が、さらりと落ちた。
『ねぇ』
葉が騒ぐ音に交じって、かすかに声がした。顔を上げ、辺りを見る。人気はない。海鈴は気のせいだと聞き流した。小さな音を立てて、柄杓の中に一滴の雫が落ちた。
『ねぇってば』
ハッとした。聞こえてきたのは、紛れもなく自分の声だった。本を閉じ、顔を上げる。どこから聞こえるだろう。林の中ではないし、手水舎にも人の影はない。
すぐに今朝の鏡の中の彼女……ではなく、自分だと思い至り、鏡なんて持っていない海鈴は、もう一度きょろきょろと辺りを見回した。
『ここよ、ここ』
柄杓の中の水がぴちゃんと弾けた。それは凪いでいた水面に波紋を作り、やがて静寂を取り戻す。
『やっと会えたわ、海鈴』
柄杓の水面に映った自分が言う。海鈴はいよいよ言葉を失った。一日に二度までもこんな不思議な目眩を起こすなんて、とうとう自分が心配になってきた。
「なんなの……あなた?」
そもそも水面に映った自分に問いかけている時点でどうかしているが、聞かずにはいられなかった。
『私はあなた。もう一人のあなたよ』
おかしい。なぜ自分と会話が成立しているのだろう。
『海鈴? なににでも意味を求めるのは良くないと思うわよ。だって、この世は意味があるものだけじゃないんだから』
呆れ気味の自分に諭され、眉を寄せる。
「……どういうこと?」
『知りたい?』
水の中の自分がにやりと笑う。それは、子どもがいたずらを思いついたときのような無邪気な笑みで。
『ねぇ、海鈴。私と入れ替わってみない?』
胸が弾む。とても有り得ない、これは現実ではないと思いながら、心のどこかでわくわくしている自分がいる。
『この中には、あなただけの物語があるのよ。ねぇ、知りたくない?』
水面が揺れる。中とは、この柄杓の中という意味なのだろうか。どちらにせよ、海鈴は思った。
「知りたい……」
どうやら、海鈴はまだ大人にはなりたくないらしい。水面の自分が、手を伸ばす。海鈴の膝にあった本がパタンと落ちた。
この世には、理論も物理も不可能なんて言葉だって存在しない。いつだってちぐはぐで、願えばユニコーンでも神様でも悪魔でも、運命の人だって現れる無限の世界なのだ。
海鈴の手が水の中に沈む。しかし、感じるのはひんやりとした水の感触ではなく、人の手のぬくもりだった。
『さぁ、世界を交換しよう』
その日、海鈴の世界がぐにゃりと歪んだ。
世界は不思議で満ち満ちている。
たとえば、今目の前にあるこのすべて。布地にビーズやボタンを散りばめたような明るい星空。
どこからか、時計の音が心地よく流れる不思議な空間。海鈴はまるで、絵本の中に入り込んでしまったかと思った。空にはつぎはぎの半透明のレールが流れ、そこを立派な銀色の汽車が星屑を散らしながら走っていく。
煌めく宝石の瞳を埋め込まれた回転木馬や大きな角のユニコーン、偉大な翼を従えたペガサスたちは、ぐるぐると回るそこを飛び出し、いななきながら自由に空を駆けていく。
足元には一面透明な水が張り、覗くと縫い目のある空やビルや海鈴を映し出していた。指揮棒を振れば、どこからか現れた楽器たちが自由気ままに音楽を奏で出す。
お菓子の家やチョコレートの滝、ビスケットの車やバウムクーヘンの切り株が立ち並ぶ甘い町並み。大きな白い袋を持って歩く花は居心地のいい場所を求めて旅をして、服を着た動物たちは楽しそうに人の言葉を話しながら、お茶をしたり煙草を咥えていたり。
海鈴よりもずっと大きな体をした虫はたくさんの脚を器用に使ってとんとんかんかん日曜大工。手のひらサイズの月は空中にたゆたい、気持ち良さそうに寝息を立てていた。
「なに……ここ……」
海鈴はその場に立ち尽くした。夢を見ているのかと頬をつねってみたりしたが、痛みだけたしかに感じるだけで、一向に夢から醒める気配はない。
一歩足を踏み出すと、海鈴から波紋が広がっていく。ぴちゃん、と軽やかな音がする。水の中の海鈴の影が一瞬消え、揺らぎ、また現れる。
「……ん?」
海鈴はしゃがみ込んだ。水の中の自分は、見慣れない赤いワンピースを着ていた。裾や袖には幾層にもなったラメ入りの黒いフリルとレース。
腰に絡みついた漆黒のリボンは海鈴の細い腰をより強調している。バルーンのようにふんわりと広がったスカートから覗く二本の足を彩るのは、赤いハイヒール。
自分なのに自分ではないような感じがした。こんな派手な服は着たことがない。海鈴は少しだけ恥ずかしくなった。
「あの……ちょっと?」
おずおずと声をかけてみる。しかし、見慣れたその顔は自分の意思に反して瞬きをすることも笑うことも、ましてや喋り出す気配もなかった。
「ねぇ……ここはどこ?」
いくら呼びかけても、答えは返ってこない。
「あのー……もしもし? もしもーし……」
いよいよ困り果てた海鈴は、そのときふと思い出した。
『この世は意味があるものだけじゃない』
手でさっと水を弾く。その瞬間、ぱしゃんと飛沫が上がり、自分の姿がかき消された。弾けた飛沫はやがて大きな泡になって、空中を漂い出す。
まるでマジックのようだ。泡になった水飛沫たちは、様々な色に輝きながら割れることなく空へ昇っていく。
光の泡がぽわんぽわんと薄紫色の空を彩り始めれば、光の泡が踊り出す。光に合わせて、どこかから鳴り出す軽快なリズム。
思わず後退ると、タップシューズを履いているわけでもないのに高らかな音を奏でる踵。
「なにこれ……すごい!」
なんだか楽しくなってきた。こんなにも胸が弾むのはいつぶりだろう。
もう一度水を弾けば、今度は白いレースが生まれた。ひらひらと蝶のように舞うそれは、空を飛ぶカササギの体に巻きついて美しいドレスに変化する。
進路も夢も、つまらない現実も。海鈴は、すべてを忘れてはしゃいだ。