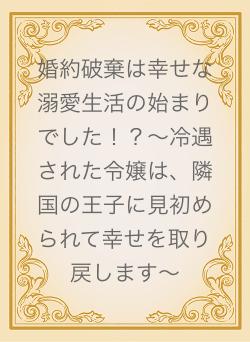それから五年後、海鈴はホテルの会議室にいた。入口には、『第十回小説大賞授賞式』という立て看板。
「それでは皆さんお待ちかね! 第十回小説大賞にて大賞を受賞された飛鳥ミレイさんのご登壇です!」
拍手喝采とフラッシュの前に現れたのは、照れ笑いを浮かべたスーツ姿の海鈴だった。
悪戦苦闘して描き上げた『ミレイと不思議な鏡の国』が、小説大賞で大賞をとったのだ。
司会が海鈴へマイクを向ける。
「今回大賞をとられた作品は、どのように完成したのですか?」
「このお話の主人公は私です。高校生の頃、私は、迷いや不安に囚われて、身動きが取れなくなっていました。周りはどんどん大人になっていくのに、自分だけ何者にもなれない焦りと、変わることへの恐怖でいっぱいいっぱいで……。そんなとき、助けてくれた人がいました。その人は私に大切なことを教えてくれました。そして、誰よりも自分が一番に自分を信じてあげなきゃダメだって、気付いたんです。この作品は、私自身の体験をもとに描き上げました」
海鈴の表情は晴れやかだった。
「この作品は、自分自身がまた道に迷うことがないようにと思って描きました。でも、その結果こうしてたくさんの方に届いていると思うと、とても嬉しいです」
「最後に一言、伝えたいことはありますか」
「変わっていくことは怖いし、大切な人との別れも寂しいです。でも、別れがあるからこそ出会いがあります。新しい場所に飛び込まなかったら、知らなかった感情があります。だから、変わることを恐れないで。この作品を通して、皆さんだけの物語を見つけてください」
空は未来への祝福を謳う。風は青葉の香りとともに、あの頃の面影を連れて、海鈴のすぐ横をすり抜けていく。
「海鈴!」
大好きな人たちが、大好きな声が海鈴を呼ぶ。あの頃からいろんな経験をした海鈴の周りには、懐かしい顔ぶれも、新しい顔もいる。
「海鈴、久しぶりだな」
翠は相変わらず、あの頃となにも変わらない穏やかな声で海鈴を呼んだ。翠は教師になった。普段は素っ気ないが、面倒見がよく頼りになる教師だと評判らしい。隣には、三条女史もいる。
「おう、飛鳥! まさかお前が賞とるとはなー」
五年ぶりの三条女史も相変わらずだ。少しだけ、ほんの少しだけ皺が増えただろうか。
「海鈴、やったじゃん!」
ゆっこが大きく手を振って海鈴を呼ぶ。あれからゆっこは随分落ち着いて、さらに大人っぽくなった。今は国際線の客室乗務員目指して国内を飛んでいるという。
そして、
「海鈴」
涼やかな声で海鈴を呼んだのは、穏やかな笑みを浮かべた湊だった。
「湊さん!」
「挨拶、すごく良かったよ」
二人は顔を見合わせて微笑み合う。
「相変わらずラブラブだねぇ」
「バカップルだな」
「幸せそうでなによりだ」
和やかな雰囲気で、海鈴たちは並んで歩く。
「ねぇ、これからどこ行く?」
「どこでもいいよ。みんなと一緒なら」
「まったく、飛鳥は変わんないな」
「そうですか? 結構変わった気がしてたんだけどな」
「みんな変わってるよ。でも、いつまでも変わらないものだってあったっていいだろ。ほら、俺たちの関係とか」
翠の言葉に、海鈴はふっと笑った。その通りだ。海鈴たちはとても変わった。それぞれ別々の仕事をして、別々の場所で生きている。
でも、変わらないものもある。みんなのことを大好きな気持ちはこれからもずっと変わらないし、かつて不思議な世界で出会った友人たちを忘れることもない。
「海鈴ちゃん」
「海鈴」
大学で知り合った友達が海鈴を呼んだ。音楽科の友人・二宮雪斗と、油絵科の星宮ツグミだ。雪斗は色白で華奢な男の子だ。黒々とした大きな瞳がどこかナノに似ていて、とても懐っこくて、しかもマヨラーだというから驚きだ。
雪斗はピアノがとても上手く、海外でのコンクールでも賞を取るほどの腕前を持っている。ツグミはのんびりした女の子で、いつもベレー帽を被っている女の子だ。ツグミ曰く、画家と言えばベレー帽らしい。
「海鈴。これ、あげる」
ツグミはおっとりとした声で海鈴を呼び、その頭に自身とお揃いのベレー帽をぽんと乗せた。深緑色のシックな帽子だ。
「おめでとう、海鈴」
にっこりと笑ったその顔は、ステラにそっくりだ。
「ありがとう。ツグミ、ニノ」
変わることは、決して恐ろしいことなんかではない。そのときどんなに悲しくて辛い経験をしたとしても、その先にきっとなにかが待っている。
この世界は、まるであの子のおもちゃ箱。ひっくり返したら、ガラス玉やぬいぐるみや、誰かの夢や希望が床の上を転がり出す。
それらはこてんと転がると、意志を持って動き出し、好き勝手に音楽を奏でたり踊り出したり、自由で気ままなサーカスが始まる。
ナノが胸を張って指揮棒を振れば、おもちゃの楽器や精霊たちはならって歌い出し、ちぐはぐな空には白黒の譜面が現れる。譜面はいずれバラバラになって、銀河鉄道を運ぶ線路に変わっていく。
布地をチクチクと縫い合わせたような空の中、自分の体よりも大きな筆に乗ったステラがのんびりと欠伸をしながら飛んでいたり、煌めく星屑を散らしながら銀色の列車がガタンゴトンと走り抜けていったり。
紺色の空をキラリと流れた星は彼方の誰かの夢を叶えて、どこからか吹く風は、誰かのころころとした楽しげな笑い声を連れてくる。
レインは今日も、星の河床を進む列車で旅をしているのだろう。迷子の乗客を導くお手伝いをしながら。レインのステッキが瞬いて、現れた傘が大きく開けば、迷子はちゃんと自分の世界に戻って目を覚ますのだ。
そして、自分だけの物語を見つけて、たった一人で歩き出す。暗いトンネルを抜けて、明るい日の下を歩いていくのだ。
もうなににも臆することなく、誰かを疑うこともなく、自分が信じた道を進む。自分自身が変わっていくことにわくわくと胸を弾ませながら、少しだけ開いた飴色の扉をくぐるのだ。