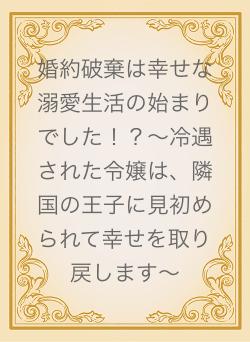バサリと音を立てて、本棚から本が落ちた。海鈴はその音に驚いて、ハッと目を覚ました。
そこは、すっかり見慣れた自分の部屋。壁にはこれまでの思い出が詰まったコルクボード。
勉強机にはまだ途中の課題が開かれたままで、その隣の本棚の下には、今落ちた本がある。深い緑色の布と黄金色の糸、そして表紙の枠を囲う唐草模様と、中央には真っ赤なりんご。
海鈴はベッドから降り、本を手に取った。題名は、こうつづられている。
『君だけの物語』
その表紙には、見覚えがあった。これは、レインが持っていた本だ。震える手でページを開く。
しかし、そこには白紙のページが続くばかりだった。本自体の厚みはあるのに、最後の一ページまでまっさらなまま。但し、一番最後のページにだけ、メッセージが綴られていた。
『拝啓、海鈴へ。
私よ、ミレイ。今この本を読んでいるということは、無事元の世界に戻れたようで安心したわ。
まったくあなたってば、期限ギリギリまで夢を見つけてくれないから、ヒヤヒヤしちゃった。
ねぇ、海鈴。大人になるのは寂しいし、変わるのはとっても怖いこと。でも、大人になるというのは、決して好きなものを捨てるということじゃない。
好きなものは、大人になったって好きだと言っていいの。
大人だって遊んでいいの。
大人は子どもなんかよりもっともっと自由よ。
好きなものを買えるし、恋愛だって自由にできる。たとえばほら、あの彼ととか。
私の役目はもうおしまい。
だから、私はもう眠りにつくけど、忘れないで。
たとえこの世界が眠りについたとしても、どんなところにいても、私は海鈴を信じてる。ずっとずっと応援してる。あなたの世界が煌めき続けますように。
私もナノも、ステラもレインもずっと祈ってるわ。それじゃあね。またいつか、どこかで――ミレイ』
海鈴は、不思議な世界の余韻を味わうように目を閉じる。
「ありがとう……」
あっという間の夏休み。いろんなことがあった。
三条女史にこっぴどく叱られて、絵画教室に通うことになって、不思議な世界に迷い込んで。夏休みが始まった頃は、なにも分からなかった。でも、今ならはっきりと分かる。
「私だけの物語か……」
海鈴はふっと息を吐いた。海鈴の瞳には、星屑のような煌めきが灯っていた。
――夏休み最後の月曜日、海鈴は少し早めに美術室に向かった。
誰もいない美術室。絵の具と黴と、ちょっとだけ生臭い匂いが鼻につく。教室の中には、受講生たちの完成された絵たちが並んでいた。布がかけられた絵画の中に、湊の絵がある。
「……あれ、飛鳥さん?」
耳の中に、すっとしなやかに入ってくる声。振り向くと、そこには驚いた顔をして海鈴を見る湊がいた。その背後には、同じような顔をした三条女史もいる。
「飛鳥!」
三条女史が駆け寄ってくる。
「あ……湊先生と、三条先生」
「お前ー! ずっとサボりやがって! 待ってたんだぞー」
湊も嬉しそうに海鈴のもとへ来ると、「もう来てくれないと思ってたよ」と嬉しそうに笑った。
「すみません。ちょっと眠っていたというか、冒険していたというか」
三条女史と湊は訝しげに顔を見合せた。海鈴は構わず湊が描いた『仮面』の前に立った。
「先生、私……この絵が大好きです」
その声はまるで、愛の告白のように滑らかで、柔らかい響きを持って湊の耳へ入っていった。
「湊先生が描いた、この『仮面』っていう絵。ずっと題名の意味がわからなかったけど……今ならなんとなく分かります」
海鈴は湊の絵を見つめた。そして、三条女史へ視線を移す。
「私、大学に行きます。文学部。言葉を学びたい。それでいつか、私だけの物語を描きたいです」
三条女史は一瞬きょとんとした顔をしたものの、すぐに歯を見せて笑った。
「……いいと思う。応援するよ」
「飛鳥さん。俺も応援してる」
「じゃあ、受験する大学を決めなくちゃな」
「あ、それはもう決めてあります。湊先生と同じ大学に行きたいんです」
二人は驚いたように顔を見合わせた。
「たしかに、俺の大学には文学部があるけど、君ならもっとレベルの高いとこ行けるのに、どうして?」
「音楽学部と美術学部があるから。同じキャンパスみたいだし、自分とはまったく違う感性の友達が欲しいんです」
「へぇ、それはまた……」
「私、湊先生と知り合って感じたんです。こんな素敵な絵を描ける人と友達になって話がしてみたいって」
三条女史は小さく、「そうか」と言って微笑んだ。
「てか、それならコイツと友達になればいいじゃん」
三条女史が、湊を海鈴の前に突き出して言った。
「えっ?」
海鈴が声を上げると、湊がパッと手を取った。
「うん、そうだよ。俺はもう今日で講師じゃなくなるし、飛鳥さん、友達になろう?」
「友達? 湊……先生と?」
「一応僕も美術学部なんだけど……俺じゃダメかな?」
湊は困ったように笑っている。その艶っぽい表情に、海鈴の心臓が早鐘を打ち出した。
「ダ、ダメでは……ないですけど」
寧ろ、とっても嬉しいですけど、と、海鈴の心臓が勝手に頷く。しどろもどろとし出した海鈴を、三条女史はにやつきながら見物している。
「よ……よろしくお願いします」
海鈴は、りんごのように染まった頬が見られないように俯きながら、小さくそう返したのだった。
――世界は光に満ち満ちている。
海鈴は、指の隙間から差し込む太陽の眩しさに目を細めた。ふわりと桜の花びらが風に舞い、髪につく。それを指で掴み取り、海鈴は頬を緩めた。
「きれい……」
顔を上げた先には、新入生の門出を祝う桜の巨木がある。光に透け、桃色のはずのそれはどことなく白く煌めいていた。
「飛鳥さん!」
まだ着慣れないスーツに身を包んだ海鈴に手を振っているのは、大学四年生になった湊だった。入学式のためスーツを着ている海鈴に合わせて、湊もわざわざスーツを着て出迎えてくれたのだ。相変わらず細やかな湊の気配りに、海鈴はさらに彼を好きになる。
「湊先生!」
海鈴が駆け寄っていくと、湊は恥ずかしそうに笑う。
「先生はやめて。俺はもう講師じゃないから。俺のことは湊でいいよ。飛鳥さん」
「いや、さすがに呼び捨ては……あ、じゃあ、湊先輩で」
先輩と呼ぶと、彼はやはり恥ずかしそうに笑っていた。少しだけ湊に近づけた気がして、海鈴はなんだか嬉しかった。
「入学おめでとう」
「ありがとうございます」
海鈴は無事、湊と同じ大学へ入学した。今日は入学祝いに食事にでも行こうと誘ってくれた湊と、初めてのデート記念日。
できれば可愛い服を着て並びたかったけれど、一人暮らしだからあまり無駄使いはできない。海鈴はもう子どもではないのだ。ちゃんと自分で考えて生活しなければならない。
二人並んで歩き出す。目の前には桃色に鮮やかな桜並木。まるでステラの家に向かう途中のあの道みたい、と海鈴は思った。スーツのポケットに触れると、細長いものが入っている。その柔らかな感触に、海鈴はホッとした。
「その本はなに?」
海鈴の手の中にある立派な装丁の本を見て、湊は首を傾げた。
「君だけの物語……?」
「これは、私の道しるべなんです」
海鈴は本を抱き締めながら言う。この本だけじゃない。
一人暮らしを始めた家に置いてある子供の頃のヴァイオリンも、ステラから貰った小さな筆も大切な道しるべ。
「そっか」
湊は優しい眼差しで海鈴を見つめた。海鈴は、深緑色の表紙をなぞりながら、言った。
「湊先輩。私、今、お話を描いているんです」
湊が驚いた顔をする。
「もし……このお話を完成させることができたら、読んでもらえませんか? その、ご迷惑じゃなければ……」
湊は眩しさに目を細めるようにして、海鈴を見つめた。
「ぜひ。一番に読みたいな」
「ありがとうございます! 頑張れます」
胸がきゅっとなる。言葉に言い表せない、苦しいけれどとても心地いい痛みだった。
「ねぇ、飛鳥さん。俺……君のお話の、一番の登場人物になりたい」
湊の声が甘く響く。海鈴の大きな瞳がガラス玉のようにきらりと光り、湊を映した。
湊がパッと海鈴の手を取って、桜の花びらの絨毯の上を歩き出す。つむじ風が花びらを巻き上げ、二人の未来を祝福するように包み込んだ。