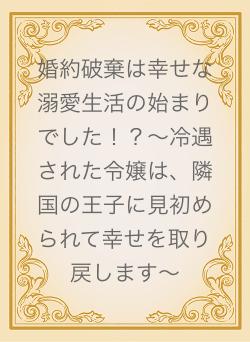飛鳥海鈴は、机の上に置かれた進路希望調査表とにらめっこをしていた。
くすんだ紙の小さな黒枠に囲まれた白い空間。それは、見る度に残酷にも海鈴に現実を突きつけてくる。
海鈴は今、暗闇の中にいる。
目の前に道があるのか、歩いてきた道がどんな道だったか、振り返っても足跡すら見えない闇の中に。
黄ばんだカーテンが風と踊る。机の上には読みかけの文庫本が二冊と、それから白紙の進路希望調査表。学校独特の木机のニスの匂いを嗅ぎながら、海鈴は深いため息を漏らした。
「まーたため息ついてんのか、海鈴」
「海鈴、面談お疲れー。結果は聞くまでもないね」
クラスメイトで幼馴染のゆっここと藤木結子と、木崎翠が顔を見合わせて苦笑している。
「惨敗です」
「三条女史、怒ると怖いからなぁ」
三条女史とは、海鈴たちの担任教師で本名を三条さとみという。
きっぱりとした性格で、ベテランというほどの経験もまだ大してないはずなのに、どこか迫力のある美人教師である。
「今回は怒られたというより、呆れられたというか」
「三条女史もちゃんとクラス全員の進路を決めて卒業させたいんだよ」
「どうせ三条女史には分かんないよ、私の気持ちなんて」
海鈴はまるで子どものように口を尖らせた。
「おい、三条先生を悪く言うなよ。この時期になっても進路を決めてない海鈴が悪い。もう三年の夏だぞ」
「翠ってば相変わらず真面目だねぇ」
「そんなことより、気になる大学のオーキャンでも行けばいいじゃん」
「それはそうなんだけどさ……」
そう、そんな言葉を言い返したところで海鈴の問題は解決しない。むしろ、増える。そもそも翠やゆっことでは、立場が違うのだ。
二人は進路が明確に決まっている。この黒枠に強大なるあの敵と向き合うだけの武器を仕込んであるからそう言えるのだ。
一方海鈴は、剣も盾も持たない丸腰。持っているのは白いフラッグくらいだ。結果は火を見るより明らかだろう。
「敵、強し……」
「敵じゃねぇけど、たしかに三条先生って隙がないよな。でもま、そこがいいっていうか。俺としては、そういう強いところを見られる海鈴の方がよっぽど羨ましいっつーの」
ゆっこ同様幼馴染の翠は、パックの野菜ジュースを飲みながら言った。海鈴はちらりと翠を横目で見る。
「そういえば、翠は三条女史と働きたいから教師目指してるんだもんね」
にやっと笑いながら言ってやると、翠の頬がぼっと赤く染まった。
「べ、べつにそんなの勝手だろ」
「翠のタイプはああいう強い感じの……」
「うるさいうるさい。ったく、お前らは小バエか」
翠は手でパッパッと海鈴たちの冷やかしを払う。翠曰く、その人を好きになると、その人の好きなものまで好きになるそうだ。
その人が好きな音楽、食べ物、服装、その人が青が好きだと言えば、青がどんな極彩にも劣らない色に思えてしまうのだと。
「恋ねぇ……」
興味がないわけではないけれど、海鈴にはまだ、愛だの恋だのという気持ちはよく分からない。
「まったく不純な決め方だよねー。海鈴は見習っちゃダメだよ」
「なんだよ、いいだろべつに」
図星を突かれて真っ赤に茹で上がった翠を見て、ゆっこはけらけらと笑っている。翠は恋をして、進む道を決めた。
「恋は盲目とは、よく言ったもんだ」
ゆっこに言われ、翠はムッと口を尖らせた。
「盲目だとしても、前に進めるならいいと思う……」
恋をしたとしても、海鈴自身が二人のような武器を持てるとは思えないけれど。ぽつりと呟いた海鈴を、翠はなにも言わずに見つめた。
「あら。庇ってもらえて良かったね、翠」
尚もにやついた顔を向けるゆっこに、翠も負けじと言った。
「なんだよ、お前だって、パイロット引っ掛けたいから客室乗務員になりたいとか言ってたじゃんか」
「そうよ。私はこんな田舎で燻ったりしない。世界へ飛び立って、目指すは国際結婚よー!」
机で進路希望調査表とにらめっこを続ける海鈴を置いてけぼりにして、翠とゆっこは楽しそうに話している。
「……いいなぁ、二人は夢があって」
「夢ってほどでもないけどな。でもま、いつまでも子どものままじゃいられないだろ?」
海鈴は床の木目をぼんやりと見つめながら、曖昧に頷く。
「三条先生になんて言われたんだ?」
「……さっきの面談で私だけ別の課題出されたの」
「えっ! なにそれ!」
ゆっこが声を上げる。
「毎週月曜日は呼び出し確定だって。もう最悪だよ……」
ため息をつきながら机に突っ伏すと、正面に向かい合うように座っていたゆっこが優しく頭を撫でてくれる。
「海鈴って、先生にはなんにも言わないよね。いつも私たちに自由な物言いをしてくる割にはさ」
「どういう意味ですか」
「三条女史、本当の海鈴のことなんも知らないんじゃない? この前話してたよくわかんない戯曲だとか、深海魚とか好きってこと。海鈴のああいう知識がどこから来るのかは私たちも疑問だけど?」
「いや。常識でしょ?」
「いやいや。サスペンダーとか、アロマントリスとか、常識ではないよ?」
「シェイクスピアとアノマロカリスね。戯曲家と古代生物」
「そう、それ。てか何語?」
「どっちも人類の大先輩じゃん……」
「だって知らないものは知らないもん」
「まぁ……たしかに、普通は知らねぇかもな」
呆れた。県内トップの進学校で、しかも特進クラスにいるくせに、そんなことも知らないとは。
だが、ゆっこの言う通りでもある。海鈴はいつだって、大人の前では本当の自分をさらけ出すことができないのだ。
窓の外、校庭で部活に励む下級生の青春の一コマを見つめながら、海鈴はつい数分前の面談室での出来事を思い返す。