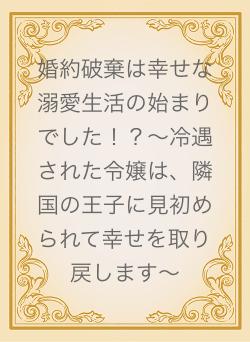レインは戸惑う海鈴の手を取って立ち上がり、列車を降りた。戸惑いながら瞳を瞬くと、景色はまた変わっていた。目の前は、本の海。
「ここ……もしかして、図書館?」
自分は今、一体どこにいるのだろうと海鈴は考えた。ついさっきはナノと出会った場所に、そしてステラの家に向かったはずが、気が付けばレインと共に列車に乗っていた。そして今、海鈴はなぜか図書館らしき場所にいる。
「ここは、君の原点だよ。この本もここから拝借したんだ」
「私の……?」
いよいよ夢を見ているのかもしれない。そう思った瞬間、瞼が重くなってくる。
眠くなってきた。すると、レインが言った。
「これは現実。君だけの現実だよ。絶対に自分を見失っちゃダメだ」
どきりとして、慌てて頬を張る。と、同時に、とあることに気付く。
「ねぇ、この世界の人は、みんな私のことを知ってるの?」
「もちろん。この世界のもう一人の自分、ミレイが君を助けようと必死だったから僕たちは協力したまでだ」
「私が夢を見つけられるように?」
「さぁ、急ごう。この世界に閉じ込められてしまう前に」
「……閉じ込められたらどうなるの?」
「この世界とともに、眠る。君は何者にもなれないまま、大人とも言えない大人になってしまう」
「何者にもなれない……」
海鈴は目を伏せた。大人になるというのは、どうやらとても大きな代償を支払うものらしい。
海鈴の手を引きながら、レインは本の海を駆けていく。ほどなくして、海鈴の目の前に大きな鉄の扉が現れた。海鈴とレインは立ち止まる。
きっと、この扉の先には未来が待つ。海鈴が進むべき道に繋がっている。しかし、海鈴はその扉をくぐるのが怖いと思った。
扉の前で立ち尽くす海鈴。気が付けば、海鈴の手には先程レインが読み聞かせてくれた深緑色の本が握られていた。
「これ……」
ぱらりとページをめくる。
小学一年生のとき、ピアノをやっていたゆっこの演奏を聴いて感動した。そして、自分も音楽をやりたいと母親にせがんで、ヴァイオリンを始めた。自らの手が音を奏でる快感。
「私が本当になりたいもの……」
あの頃は、ただ奏でることが楽しかった。多少不格好でも、音が外れても、それすら楽しくて夢中になった。いつから失敗するのが怖くなったのだろうか。
少し埃っぽい表紙を、海鈴は優しくなぞった。
「君は、寂しいんだ」
海鈴は静かにレインを見上げた。
「寂しい?」
「いずれ大人になって、大切に守ってもらっていた親から離れて、仲の良かった友達とも離れて、ひとりになる」
「……そう。だって、もし大学に行くなら、あの町を出なくちゃいけないから。両親は放任主義だから、きっと私がこの家を出ていきたいって言ったら止めたりしない」
「でも、それは君を信じてるから。君は気付いたはずだろう?」
ハッとする。そうだ。
「あの家は、この十七年間の君を作り上げた。君のすべてだ。手放すのが怖いのは当然だ」
海鈴の不安を掬うように、レインは柔らかい声音で言った。
「……でも、それだけじゃないの。ゆっこも翠もこの町を出たら、次はいつ帰って来るか分からないって。もしかしたら、もうずっと会えなくなっちゃうかもしれない。仕方ないって分かってる。でも、寂しいの」
「二人だって、簡単に決めたわけじゃない」
レインが咳払いをすると、その手の中に二冊の本が抱えられていた。橙色の本と、深海のように深い藍色の本だ。レインが優しい声で語り出す。
「ゆっこはずっと、海の向こう側に憧れていた。外の世界はどんな景色が広がっているのだろう。どんな人がいるのだろう。人と話すことが大好きな活発な女の子は、初めて乗った飛行機で、隣の席の外国人の親子に声をかけられた。英語なんて話せなかったゆっこは困惑した。そこへ、搭乗していたスタッフが声をかけてきた」
そのときの客室乗務員の対応にゆっこは感動し、憧れた。初めて顔を合わせたはずの異国の人と笑顔でコミュニケーションをとる女性。ゆっこは、いつか自分も彼女のようになりたいと思った。
「外国人の親子は、彼女が折っていた折り紙に感動した。そうして文化の違いを知り、外国に興味を持った」
レインは橙色の本を閉じると、藍色の本を開いた。
「少年は恋をした。幼い頃から面倒見が良かった少年は、周りの子より淡白で大人びていた。そんな彼が恋に落ちたのは、担任の女性教師。彼女に出会ったその瞬間、彼の時間は動き出した。つまらなかった毎日がパッと色づき始めて、彼女の声はやけにクリアに彼の耳に響いた。結ばれなくてもいいから、彼女と一緒にいたい。教師と生徒というアンフェアな立ち位置ではなく、彼女と対等に話をしてみたい。そして、彼は教師になることを選んだ」
「そうだったんだ……」
「結局、人を突き動かすのは感情なんだよ」
レインは藍色の本を閉じて言った。ケロリとした顔で都会の大学に行くと話していた二人。ゆっこも翠も、ちゃんと考えていた。誰よりも真剣に、将来のことを。
「変わるのは怖い。でも、不安なのは彼らだって同じだ。家を出れば守ってくれる人はいなくなるし、生活も全部自己責任。友達がいない場所に一人で飛び込むんだから」
ゆっこも、翠も同じように怖いのだ。だけど、進もうとしている。自分の思い描く未来のために、恐怖とともに。
「君は、音楽が好きだ。絵にも空にも興味がある。読書が好きで、なにかを表現することも好き」
海鈴は胸に手を当てた。どくん、と心臓が脈を打つ。
「君はこの世界で、好きなものともう一度出会った」
レインの手から、柔らかなぬくもりが伝わってくる。海鈴はぎゅっと目を瞑った。すると、遠くで微かに汽笛の音がした。列車がきたらしい。
「行こうか。ここもじき門を閉じてしまうから」
「ここ……もしかして、図書館?」
自分は今、一体どこにいるのだろうと海鈴は考えた。ついさっきはナノと出会った場所に、そしてステラの家に向かったはずが、気が付けばレインと共に列車に乗っていた。そして今、海鈴はなぜか図書館らしき場所にいる。
「ここは、君の原点だよ。この本もここから拝借したんだ」
「私の……?」
いよいよ夢を見ているのかもしれない。そう思った瞬間、瞼が重くなってくる。
眠くなってきた。すると、レインが言った。
「これは現実。君だけの現実だよ。絶対に自分を見失っちゃダメだ」
どきりとして、慌てて頬を張る。と、同時に、とあることに気付く。
「ねぇ、この世界の人は、みんな私のことを知ってるの?」
「もちろん。この世界のもう一人の自分、ミレイが君を助けようと必死だったから僕たちは協力したまでだ」
「私が夢を見つけられるように?」
「さぁ、急ごう。この世界に閉じ込められてしまう前に」
「……閉じ込められたらどうなるの?」
「この世界とともに、眠る。君は何者にもなれないまま、大人とも言えない大人になってしまう」
「何者にもなれない……」
海鈴は目を伏せた。大人になるというのは、どうやらとても大きな代償を支払うものらしい。
海鈴の手を引きながら、レインは本の海を駆けていく。ほどなくして、海鈴の目の前に大きな鉄の扉が現れた。海鈴とレインは立ち止まる。
きっと、この扉の先には未来が待つ。海鈴が進むべき道に繋がっている。しかし、海鈴はその扉をくぐるのが怖いと思った。
扉の前で立ち尽くす海鈴。気が付けば、海鈴の手には先程レインが読み聞かせてくれた深緑色の本が握られていた。
「これ……」
ぱらりとページをめくる。
小学一年生のとき、ピアノをやっていたゆっこの演奏を聴いて感動した。そして、自分も音楽をやりたいと母親にせがんで、ヴァイオリンを始めた。自らの手が音を奏でる快感。
「私が本当になりたいもの……」
あの頃は、ただ奏でることが楽しかった。多少不格好でも、音が外れても、それすら楽しくて夢中になった。いつから失敗するのが怖くなったのだろうか。
少し埃っぽい表紙を、海鈴は優しくなぞった。
「君は、寂しいんだ」
海鈴は静かにレインを見上げた。
「寂しい?」
「いずれ大人になって、大切に守ってもらっていた親から離れて、仲の良かった友達とも離れて、ひとりになる」
「……そう。だって、もし大学に行くなら、あの町を出なくちゃいけないから。両親は放任主義だから、きっと私がこの家を出ていきたいって言ったら止めたりしない」
「でも、それは君を信じてるから。君は気付いたはずだろう?」
ハッとする。そうだ。
「あの家は、この十七年間の君を作り上げた。君のすべてだ。手放すのが怖いのは当然だ」
海鈴の不安を掬うように、レインは柔らかい声音で言った。
「……でも、それだけじゃないの。ゆっこも翠もこの町を出たら、次はいつ帰って来るか分からないって。もしかしたら、もうずっと会えなくなっちゃうかもしれない。仕方ないって分かってる。でも、寂しいの」
「二人だって、簡単に決めたわけじゃない」
レインが咳払いをすると、その手の中に二冊の本が抱えられていた。橙色の本と、深海のように深い藍色の本だ。レインが優しい声で語り出す。
「ゆっこはずっと、海の向こう側に憧れていた。外の世界はどんな景色が広がっているのだろう。どんな人がいるのだろう。人と話すことが大好きな活発な女の子は、初めて乗った飛行機で、隣の席の外国人の親子に声をかけられた。英語なんて話せなかったゆっこは困惑した。そこへ、搭乗していたスタッフが声をかけてきた」
そのときの客室乗務員の対応にゆっこは感動し、憧れた。初めて顔を合わせたはずの異国の人と笑顔でコミュニケーションをとる女性。ゆっこは、いつか自分も彼女のようになりたいと思った。
「外国人の親子は、彼女が折っていた折り紙に感動した。そうして文化の違いを知り、外国に興味を持った」
レインは橙色の本を閉じると、藍色の本を開いた。
「少年は恋をした。幼い頃から面倒見が良かった少年は、周りの子より淡白で大人びていた。そんな彼が恋に落ちたのは、担任の女性教師。彼女に出会ったその瞬間、彼の時間は動き出した。つまらなかった毎日がパッと色づき始めて、彼女の声はやけにクリアに彼の耳に響いた。結ばれなくてもいいから、彼女と一緒にいたい。教師と生徒というアンフェアな立ち位置ではなく、彼女と対等に話をしてみたい。そして、彼は教師になることを選んだ」
「そうだったんだ……」
「結局、人を突き動かすのは感情なんだよ」
レインは藍色の本を閉じて言った。ケロリとした顔で都会の大学に行くと話していた二人。ゆっこも翠も、ちゃんと考えていた。誰よりも真剣に、将来のことを。
「変わるのは怖い。でも、不安なのは彼らだって同じだ。家を出れば守ってくれる人はいなくなるし、生活も全部自己責任。友達がいない場所に一人で飛び込むんだから」
ゆっこも、翠も同じように怖いのだ。だけど、進もうとしている。自分の思い描く未来のために、恐怖とともに。
「君は、音楽が好きだ。絵にも空にも興味がある。読書が好きで、なにかを表現することも好き」
海鈴は胸に手を当てた。どくん、と心臓が脈を打つ。
「君はこの世界で、好きなものともう一度出会った」
レインの手から、柔らかなぬくもりが伝わってくる。海鈴はぎゅっと目を瞑った。すると、遠くで微かに汽笛の音がした。列車がきたらしい。
「行こうか。ここもじき門を閉じてしまうから」