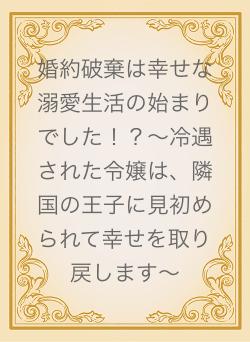窓の外には、列車が吐き出した無数の泡と星屑たち。
「僕はそれを見届ける星の案内人」
どうやらレインは、海鈴の問いを誤魔化す気なんてないらしく、一つ一つ丁寧に答えてくれるらしかった。
「私だけの星を見つけたら、この世界は消えるんだね」
海鈴が呟く。レインはなにも言わなかった。
「……あなたはそれでいいの?」
すると、ようやくレインは海鈴に顔を向け、首を傾げた。
「私が夢を見つけたら、あなたたちは眠らなくちゃいけないんでしょ?」
「変わっていくのは、成長するということ。そのために僕たちは生まれ、眠る。君が大人にならなければ、僕たちが生まれてきた意味がない」
泡が水の中をくるくると昇っていく音と、列車の車輪の音がやけに大きく聞こえた。
「それは……そうかもしれないけど……」
「少し退屈だね。ちょうどいい。君の物語を読み聞かせてあげよう」
レインが長い足を組み、隣にかけておいたステッキを手に取ると、おもむろにゆらりと振った。随分と重そうに見えたステッキは、レインの手にかかれば軽く見えてしまうから不思議だ。
振れたステッキがキラキラと輝き出したかと思えば、視界を真っ白にするほど眩く光り、海鈴は目を瞑った。
瞼の裏の光が消えた頃、おずおずと目を開けると、いつの間にかステッキは消え、レインの手には本物の本が握られていた。
それは、電子書籍が流行する近頃には珍しいくらい、丁寧に装丁された本だった。深い緑色の布と黄金色の糸、そして表紙の枠を囲う唐草模様。
中央には真っ赤なりんごの絵。
レインは腰掛けに座り直し、上品な仕草で本を開いた。
「それは、今から十四年前のこと。人見知りで臆病な性格の君は、幼稚園でもいつもひとりぼっちだった。そんな君に声をかけてきたのは、活発なおさげの女の子と、面倒見の良い男の子」
ハッとした。
ゆっこと翠だ。海鈴が二人と出会ったのは、幼稚園の頃だった。大人しく、気弱でいつも先生の陰に隠れていた海鈴。
海鈴はいつも部屋の隅で絵本を読んだり一人でお絵描きをして遊んでいた。そこにゆっこが来て、いつの間にか翠も隣にいて。いつしか、三人でいることが多くなった。
レインは目を伏せ、開いてあるページを優しく撫でる。
「新しい場所に行くのは、いつだって怖いことだ。でも、新しい場所に行かなければ、出会えない人がいる。出会えない感情がある。君はそれをいらないというの?」
「え……?」
「君がもし幼稚園に行かなかったら、両親と別れて寂しいという気持ちには出会わなかっただろう。立派な感情だ。そうして初めて両親への愛を知る。そして、ゆっこや翠、友達という存在に巡り会うこともなかった」
レインの言う通りだ。これまでずっとそうだった。新しい環境に慣れるのが苦手で、海鈴はいつも一人殻に閉じこもって、一人で楽しめるものばかり好きになった。
「でも、別れがなければ出会いはないんだよ。新しい場所に行くっていうのは、そういうことだ」
レインの言葉は、海鈴の心の奥深くにさらりと落ちた。
「この世界だって、新しい場所だったはずだ。なのに君は、なぜ怖いと思わなかった?」
「そういえば……なんでだろう」
「それは、この世界が君のためにあるから。ナノは、君の音楽が好きという気持ちから生まれた。ナノのひとつのことに夢中になる性格は君の一面だし、ゼロからなにかを生み出したいという思いから生まれたステラもそう。ステラののんびりとしたところも間違いなく君の一部なんだよ。それから、僕も……」
レインがしなやかに片目を瞑る。鷹色の瞳がかすかに濡れた。
「え……レインも?」
海鈴は驚いてレインを見つめた。
「僕は、君の愛から生まれた」
「あ、あい!?」
海鈴の頬がカッと染まる。予想だにしない答えに、海鈴の心臓が驚きに跳ねた。
「そう。君、誰かに恋をしただろう」
「こ、恋なんて……」
否定しながらも、脳裏には湊の笑顔が浮かんでいた。
「恋……ってことは、あなたは私の好きな人なの?」
「いいや。僕はあくまで星の案内人。君は彼に出会って少し変わった。僕も彼と同じ……君を正しい道に導くという役目があるんだ」
レインは、パタンと本を閉じる。海鈴は、車窓の外に目を向けた。列車はいつの間にか停止していた。
「だから、早くここから帰るんだ。君はもう、夢を見つけたんだから」
「え、夢? 待って、私、そんなの……」
「僕はそれを見届ける星の案内人」
どうやらレインは、海鈴の問いを誤魔化す気なんてないらしく、一つ一つ丁寧に答えてくれるらしかった。
「私だけの星を見つけたら、この世界は消えるんだね」
海鈴が呟く。レインはなにも言わなかった。
「……あなたはそれでいいの?」
すると、ようやくレインは海鈴に顔を向け、首を傾げた。
「私が夢を見つけたら、あなたたちは眠らなくちゃいけないんでしょ?」
「変わっていくのは、成長するということ。そのために僕たちは生まれ、眠る。君が大人にならなければ、僕たちが生まれてきた意味がない」
泡が水の中をくるくると昇っていく音と、列車の車輪の音がやけに大きく聞こえた。
「それは……そうかもしれないけど……」
「少し退屈だね。ちょうどいい。君の物語を読み聞かせてあげよう」
レインが長い足を組み、隣にかけておいたステッキを手に取ると、おもむろにゆらりと振った。随分と重そうに見えたステッキは、レインの手にかかれば軽く見えてしまうから不思議だ。
振れたステッキがキラキラと輝き出したかと思えば、視界を真っ白にするほど眩く光り、海鈴は目を瞑った。
瞼の裏の光が消えた頃、おずおずと目を開けると、いつの間にかステッキは消え、レインの手には本物の本が握られていた。
それは、電子書籍が流行する近頃には珍しいくらい、丁寧に装丁された本だった。深い緑色の布と黄金色の糸、そして表紙の枠を囲う唐草模様。
中央には真っ赤なりんごの絵。
レインは腰掛けに座り直し、上品な仕草で本を開いた。
「それは、今から十四年前のこと。人見知りで臆病な性格の君は、幼稚園でもいつもひとりぼっちだった。そんな君に声をかけてきたのは、活発なおさげの女の子と、面倒見の良い男の子」
ハッとした。
ゆっこと翠だ。海鈴が二人と出会ったのは、幼稚園の頃だった。大人しく、気弱でいつも先生の陰に隠れていた海鈴。
海鈴はいつも部屋の隅で絵本を読んだり一人でお絵描きをして遊んでいた。そこにゆっこが来て、いつの間にか翠も隣にいて。いつしか、三人でいることが多くなった。
レインは目を伏せ、開いてあるページを優しく撫でる。
「新しい場所に行くのは、いつだって怖いことだ。でも、新しい場所に行かなければ、出会えない人がいる。出会えない感情がある。君はそれをいらないというの?」
「え……?」
「君がもし幼稚園に行かなかったら、両親と別れて寂しいという気持ちには出会わなかっただろう。立派な感情だ。そうして初めて両親への愛を知る。そして、ゆっこや翠、友達という存在に巡り会うこともなかった」
レインの言う通りだ。これまでずっとそうだった。新しい環境に慣れるのが苦手で、海鈴はいつも一人殻に閉じこもって、一人で楽しめるものばかり好きになった。
「でも、別れがなければ出会いはないんだよ。新しい場所に行くっていうのは、そういうことだ」
レインの言葉は、海鈴の心の奥深くにさらりと落ちた。
「この世界だって、新しい場所だったはずだ。なのに君は、なぜ怖いと思わなかった?」
「そういえば……なんでだろう」
「それは、この世界が君のためにあるから。ナノは、君の音楽が好きという気持ちから生まれた。ナノのひとつのことに夢中になる性格は君の一面だし、ゼロからなにかを生み出したいという思いから生まれたステラもそう。ステラののんびりとしたところも間違いなく君の一部なんだよ。それから、僕も……」
レインがしなやかに片目を瞑る。鷹色の瞳がかすかに濡れた。
「え……レインも?」
海鈴は驚いてレインを見つめた。
「僕は、君の愛から生まれた」
「あ、あい!?」
海鈴の頬がカッと染まる。予想だにしない答えに、海鈴の心臓が驚きに跳ねた。
「そう。君、誰かに恋をしただろう」
「こ、恋なんて……」
否定しながらも、脳裏には湊の笑顔が浮かんでいた。
「恋……ってことは、あなたは私の好きな人なの?」
「いいや。僕はあくまで星の案内人。君は彼に出会って少し変わった。僕も彼と同じ……君を正しい道に導くという役目があるんだ」
レインは、パタンと本を閉じる。海鈴は、車窓の外に目を向けた。列車はいつの間にか停止していた。
「だから、早くここから帰るんだ。君はもう、夢を見つけたんだから」
「え、夢? 待って、私、そんなの……」