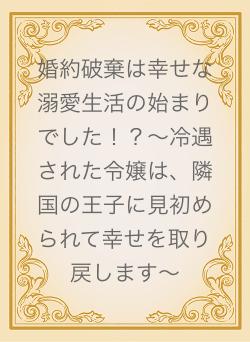天窓の先に続くのは、無限の宇宙。宝物のような星たちはあの頃から変わらない煌めきで、海鈴を見下ろしている。
三条女史と面談をして、少しだけ未来が見えた気がした。海鈴はこれまで、なりたいものになるために大学を選択するものと思っていた。しかし、三条女史は好きなことを勉強しろと言った。それでいいのだと。
海鈴は今、分岐点にいる。目の前にはいくつかに別れた線路が続く。透明な線路。まるで、あの不思議な世界の銀河鉄道が進むような星屑の線路だ。
もう少しでひとつに絞れそうな気がするのに、まだなにかがひっかかっている。
しんとした世界で、海鈴は鏡界のことを思った。ナノとステラは今どこにいるだろう。会いたい。二人に会って、あの笑顔が見たい。
海鈴は部屋の姿見の前に立った。ミレイと入れ替わるようになって、海鈴は初めて自分と向き合えた気がしていた。
「ミレイ、いる?」
鏡の中の自分は紛れもない海鈴自身で、ミレイではなかった。
「やっぱりダメか……」
もしかしたら、ミレイが出てきてくれるかもしれないと思ったけれど。海鈴が落胆のため息を漏らしていると、突然目の前の鏡が歪んだ。
「えっ……!?」
海鈴は目を瞠る。水滴が落ちるように波紋を広げ始め、徐々に激しくなっていく。海鈴の姿を打ち消した鏡は波打ち、そして海鈴を呑み込んだ。
チクタクチクタク。
これまで規則正しく鳴っていたその音は、どこか濁ってどろりとしていた。微睡みの中から目覚め、目を開いた海鈴は言葉を失った。
空に流れていた半透明のレールは、水流にゆらゆらと心もとなげに揺れている。宝石の瞳を持つ回転木馬や、立派な角のユニコーン、大きな翼を持ったペガサスたちは、低く響くような音の中、錆び付いたように止まっていた。
海鈴や空を映していたビルは水の中に沈み、もうなにも映していない。
そして、海鈴も水の中にいた。不思議と息はできるものの、水の中で響く時計の音はひどく奇妙で、不気味な感じがした。
水の中には、壊れたお菓子の家や眠った住人たちが浮遊している。月は光を失い、真っ赤なりんごの群れは水の流れに抗うことなく、従順に流されていた。
あんなに華やかだった世界は、音と色を失くしていた。
「ナノ? ステラ?」
ゴボゴボと、開いた唇から泡が生まれて昇っていく。海鈴の小さな声は泡となって消え、静かな世界でも響くことはなかった。
不安がどんどん膨らんでいく。海鈴は急いでステラの家に向かった。振り向いても、海鈴の歩いてきた道に光はない。桃色だった並木道も、水の中では色を失い、灰色だ。木々たちはじっと目を閉じ、微動だにしない。
鏡界は、深い眠りについているようだった。パッと視界が開け、ステラの小さな可愛い家が現れる。
ホッとしながら中に入った。扉を開けると、鈍くがらんと音がした。少し濁っているけれど、間違いなくステラのベルの音だ。
「ステラー! いる?」
ステラの部屋の匂いに安心しながら、声をかける。しかし、反応はなかった。どろりと重い水が動く。ハッとして振り向くと、白黒の鍵盤のような板が浮いていた。
「ステラ!」
思わず涙が出そうになった。しかし、駆け寄ってもその板が動く気配はない。板を叩くと、微かにぽろんと音がした。
「なぜ、ここにいる」
静かな空間を切り裂くように、しなやかな声が聞こえた。
「あなたは……」
銀河鉄道で見た仮面の車掌だった。仮面は変わらず付けていたが、しかし、この前見たときとは衣服が違った。
車掌服から、重々しい法衣のような服になっていた。手には、切符を切る改札鋏ではなく、車掌の背より高いステッキ。まるで、聖職者のようだと思った。
「僕はレイン」
海鈴は眉を寄せる。相変わらず神出鬼没でよく分からない人だ。
「ここは君の住む世界ではない。早く帰らないと、取り返しのつかないことになる」
「友達を探してるの。ナノとステラって言うんだけど、居場所を知らな……」
言い終わらぬうちに、レインは海鈴の手をパッと取った。
「えっ!? ちょっと……」
レインは海鈴の手を無理やり引き、ステラの壺の欠片に触れさせた。コンコンコンというノックの音。
ほどなくして、カタカタと動き出した板が壺の形になる。中を覗くと、すやすやと眠るステラがいた。
「ステラ!」
いつものように声をかけても、ステラは眠ったまま目を開けなかった。
「ステラはもう起きることはない」
ひんやりとした声だった。
「もう期限切れなんだ。この世界は」
仮面の穴から覗く鷹色の瞳は、窓の外の閑散とした世界を見ていた。
「夢は終わり。みんな、眠りに着く時間」
「意味がわからないんだけど……そうだ。ナノはどこ?」
「会ってどうする。眠っているのに」
「そんなの信じられない! ナノのところに案内して!」
負けじと強い口調で言うと、レインは小さくため息をついて歩き出した。海鈴は眉をしかめたまま、レインの後を追った。
ほどなくして行き着いたのは、拓けた公園のような場所。広い敷地を覆うのは、幽霊のような大きな葉をした木々たち。それらは、なにかを覆うようにしなだれかかっていた。
「ここは?」
初めて来た場所だ。
木々が覆い隠すようにしてできた空洞に、大きなスノードームのような建物があった。海鈴は訝しげにドームの中を見つめる。そして、息を呑んだ。
「ナノ!?」
幻想的な雪が舞う大きな大きなスノードームの中には、演奏中のナノがいた。ちゃっかり黒いスーツなんて着て、蝶ネクタイまで締めている。ヴァイオリン奏でるその姿は、とても楽しそうに見えた。周りには様々な姿をした観客たち。みんなナノの演奏に聴き入っていた。
「なにこれ!? どうしちゃったの!? ナノ!」
スノードームに駆け寄り、ナノに声をかけるが、ガラス一枚隔てた海鈴には、まったく気付いていないようだった。
「このスノードームの中の生き物たちは、まだ眠ってはいない。けれど、じき眠りにつく」
「じきに……でも、よかった。とりあえず、無事で」
「でも、このガラス一枚隔てた世界に、君の声は届かない」
「そんな……あなたでも、なんとかならないの?」
「ならない」
海鈴はナノを見つめる。
「ナノもステラも、もう君とはいられないんだ。君の声はもう届かない。この世界は、君の希望や夢で構築された世界。だから、君が大人になれば消える。門を固く閉じて、僕らは眠りにつくんだ」
海鈴は呆然とナノを見つめた。
「私が……大人になったら……?」
ふと、面談室での三条女史との会話が蘇る。
「もしかして……私が進路を考えてたから? だから、ステラは眠っちゃったの? ナノに声が届かないの? 私のせいで、この世界は水の中に沈んじゃったの?」
「驚かなくていい。これが正常なんだから」
レインは飄々と言って、手に持っていた巨大なステッキで地面を叩いた。
「これが正常? そんなのおかしいよ! だって、町全体が水の中に沈んじゃってるのに……」
「それでも正常なんだ。だって、僕たちは君の夢を見つけるために生まれたのだから」
夢。では、それを見つけられなかったら、どうなるの。海鈴はそれを、怖くて言葉にはできなかった。
ふと気がつくと、海鈴は銀河鉄道に乗っていた。ビロードの腰掛けに、海鈴の赤いワンピースのレースが花びらのように広がっている。向かいには、レインが座っていた。腰掛けの端には、座ったレインよりも長いステッキが立てかけられている。
「これは、僕のステッキだ」
海鈴の視線に気付いたレインが言った。重そうだし、持ち歩きにも不便そうなそのステッキを、海鈴はじっと見つめた。
「あなたは何者? 車掌さんじゃないの? 聖職者? それとも……」
「どれでもない。僕は、星の案内人」
それは、本気で言っているのか、それとも返答が面倒で適当に流したのか。海鈴は後者だと考え、車窓に目を向けた。
「ねぇ、この列車はどこに行くの?」
レインは黙ったまま、海鈴の向かいに座っている。
銀河鉄道は海鈴の心身を揺らしながら、どんどん進んでいく。
「……列車の進む先は、君が決めるんだ」
レインがぽつりと言った。
「私が?」
「そう。ここは君だけの世界だから。この列車は君の旅路。迷い、揺らいで、苦しみながら、星の海の中を進んでいく。そして、この山ほどの星屑の中から君だけの星を見つけるんだ」
三条女史と面談をして、少しだけ未来が見えた気がした。海鈴はこれまで、なりたいものになるために大学を選択するものと思っていた。しかし、三条女史は好きなことを勉強しろと言った。それでいいのだと。
海鈴は今、分岐点にいる。目の前にはいくつかに別れた線路が続く。透明な線路。まるで、あの不思議な世界の銀河鉄道が進むような星屑の線路だ。
もう少しでひとつに絞れそうな気がするのに、まだなにかがひっかかっている。
しんとした世界で、海鈴は鏡界のことを思った。ナノとステラは今どこにいるだろう。会いたい。二人に会って、あの笑顔が見たい。
海鈴は部屋の姿見の前に立った。ミレイと入れ替わるようになって、海鈴は初めて自分と向き合えた気がしていた。
「ミレイ、いる?」
鏡の中の自分は紛れもない海鈴自身で、ミレイではなかった。
「やっぱりダメか……」
もしかしたら、ミレイが出てきてくれるかもしれないと思ったけれど。海鈴が落胆のため息を漏らしていると、突然目の前の鏡が歪んだ。
「えっ……!?」
海鈴は目を瞠る。水滴が落ちるように波紋を広げ始め、徐々に激しくなっていく。海鈴の姿を打ち消した鏡は波打ち、そして海鈴を呑み込んだ。
チクタクチクタク。
これまで規則正しく鳴っていたその音は、どこか濁ってどろりとしていた。微睡みの中から目覚め、目を開いた海鈴は言葉を失った。
空に流れていた半透明のレールは、水流にゆらゆらと心もとなげに揺れている。宝石の瞳を持つ回転木馬や、立派な角のユニコーン、大きな翼を持ったペガサスたちは、低く響くような音の中、錆び付いたように止まっていた。
海鈴や空を映していたビルは水の中に沈み、もうなにも映していない。
そして、海鈴も水の中にいた。不思議と息はできるものの、水の中で響く時計の音はひどく奇妙で、不気味な感じがした。
水の中には、壊れたお菓子の家や眠った住人たちが浮遊している。月は光を失い、真っ赤なりんごの群れは水の流れに抗うことなく、従順に流されていた。
あんなに華やかだった世界は、音と色を失くしていた。
「ナノ? ステラ?」
ゴボゴボと、開いた唇から泡が生まれて昇っていく。海鈴の小さな声は泡となって消え、静かな世界でも響くことはなかった。
不安がどんどん膨らんでいく。海鈴は急いでステラの家に向かった。振り向いても、海鈴の歩いてきた道に光はない。桃色だった並木道も、水の中では色を失い、灰色だ。木々たちはじっと目を閉じ、微動だにしない。
鏡界は、深い眠りについているようだった。パッと視界が開け、ステラの小さな可愛い家が現れる。
ホッとしながら中に入った。扉を開けると、鈍くがらんと音がした。少し濁っているけれど、間違いなくステラのベルの音だ。
「ステラー! いる?」
ステラの部屋の匂いに安心しながら、声をかける。しかし、反応はなかった。どろりと重い水が動く。ハッとして振り向くと、白黒の鍵盤のような板が浮いていた。
「ステラ!」
思わず涙が出そうになった。しかし、駆け寄ってもその板が動く気配はない。板を叩くと、微かにぽろんと音がした。
「なぜ、ここにいる」
静かな空間を切り裂くように、しなやかな声が聞こえた。
「あなたは……」
銀河鉄道で見た仮面の車掌だった。仮面は変わらず付けていたが、しかし、この前見たときとは衣服が違った。
車掌服から、重々しい法衣のような服になっていた。手には、切符を切る改札鋏ではなく、車掌の背より高いステッキ。まるで、聖職者のようだと思った。
「僕はレイン」
海鈴は眉を寄せる。相変わらず神出鬼没でよく分からない人だ。
「ここは君の住む世界ではない。早く帰らないと、取り返しのつかないことになる」
「友達を探してるの。ナノとステラって言うんだけど、居場所を知らな……」
言い終わらぬうちに、レインは海鈴の手をパッと取った。
「えっ!? ちょっと……」
レインは海鈴の手を無理やり引き、ステラの壺の欠片に触れさせた。コンコンコンというノックの音。
ほどなくして、カタカタと動き出した板が壺の形になる。中を覗くと、すやすやと眠るステラがいた。
「ステラ!」
いつものように声をかけても、ステラは眠ったまま目を開けなかった。
「ステラはもう起きることはない」
ひんやりとした声だった。
「もう期限切れなんだ。この世界は」
仮面の穴から覗く鷹色の瞳は、窓の外の閑散とした世界を見ていた。
「夢は終わり。みんな、眠りに着く時間」
「意味がわからないんだけど……そうだ。ナノはどこ?」
「会ってどうする。眠っているのに」
「そんなの信じられない! ナノのところに案内して!」
負けじと強い口調で言うと、レインは小さくため息をついて歩き出した。海鈴は眉をしかめたまま、レインの後を追った。
ほどなくして行き着いたのは、拓けた公園のような場所。広い敷地を覆うのは、幽霊のような大きな葉をした木々たち。それらは、なにかを覆うようにしなだれかかっていた。
「ここは?」
初めて来た場所だ。
木々が覆い隠すようにしてできた空洞に、大きなスノードームのような建物があった。海鈴は訝しげにドームの中を見つめる。そして、息を呑んだ。
「ナノ!?」
幻想的な雪が舞う大きな大きなスノードームの中には、演奏中のナノがいた。ちゃっかり黒いスーツなんて着て、蝶ネクタイまで締めている。ヴァイオリン奏でるその姿は、とても楽しそうに見えた。周りには様々な姿をした観客たち。みんなナノの演奏に聴き入っていた。
「なにこれ!? どうしちゃったの!? ナノ!」
スノードームに駆け寄り、ナノに声をかけるが、ガラス一枚隔てた海鈴には、まったく気付いていないようだった。
「このスノードームの中の生き物たちは、まだ眠ってはいない。けれど、じき眠りにつく」
「じきに……でも、よかった。とりあえず、無事で」
「でも、このガラス一枚隔てた世界に、君の声は届かない」
「そんな……あなたでも、なんとかならないの?」
「ならない」
海鈴はナノを見つめる。
「ナノもステラも、もう君とはいられないんだ。君の声はもう届かない。この世界は、君の希望や夢で構築された世界。だから、君が大人になれば消える。門を固く閉じて、僕らは眠りにつくんだ」
海鈴は呆然とナノを見つめた。
「私が……大人になったら……?」
ふと、面談室での三条女史との会話が蘇る。
「もしかして……私が進路を考えてたから? だから、ステラは眠っちゃったの? ナノに声が届かないの? 私のせいで、この世界は水の中に沈んじゃったの?」
「驚かなくていい。これが正常なんだから」
レインは飄々と言って、手に持っていた巨大なステッキで地面を叩いた。
「これが正常? そんなのおかしいよ! だって、町全体が水の中に沈んじゃってるのに……」
「それでも正常なんだ。だって、僕たちは君の夢を見つけるために生まれたのだから」
夢。では、それを見つけられなかったら、どうなるの。海鈴はそれを、怖くて言葉にはできなかった。
ふと気がつくと、海鈴は銀河鉄道に乗っていた。ビロードの腰掛けに、海鈴の赤いワンピースのレースが花びらのように広がっている。向かいには、レインが座っていた。腰掛けの端には、座ったレインよりも長いステッキが立てかけられている。
「これは、僕のステッキだ」
海鈴の視線に気付いたレインが言った。重そうだし、持ち歩きにも不便そうなそのステッキを、海鈴はじっと見つめた。
「あなたは何者? 車掌さんじゃないの? 聖職者? それとも……」
「どれでもない。僕は、星の案内人」
それは、本気で言っているのか、それとも返答が面倒で適当に流したのか。海鈴は後者だと考え、車窓に目を向けた。
「ねぇ、この列車はどこに行くの?」
レインは黙ったまま、海鈴の向かいに座っている。
銀河鉄道は海鈴の心身を揺らしながら、どんどん進んでいく。
「……列車の進む先は、君が決めるんだ」
レインがぽつりと言った。
「私が?」
「そう。ここは君だけの世界だから。この列車は君の旅路。迷い、揺らいで、苦しみながら、星の海の中を進んでいく。そして、この山ほどの星屑の中から君だけの星を見つけるんだ」