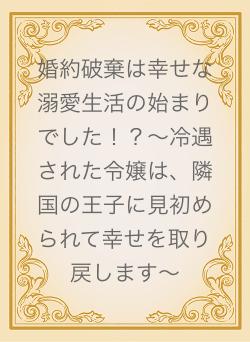それから、数日はぼんやりと過ごした。そして訪れた絵画教室の月曜日、海鈴は初めてサボってしまった。
なにがあったというわけではないのだ。ただ、やっぱり美大に行きたいわけでもないのに絵を描いていたって時間の無駄だと思っただけだ。
ベッドに寝転がりながら、机の上にあるスケッチブックを見る。そこにはステラを思い浮かべて落とした色があった。ふと、スマホが振動した。
『サボりやがったな』
三条女史から、ひとことだけのメッセージ。そのあとすぐ、電話がかかってきた。出るか迷ったが、さすがに居留守はできなかった。
「……なんですか」
機嫌を隠すのも億劫で、低い声のまま通話ボタンをタップした。
『お前……あからさまにいじけてんな』
「……べつに、いじけてません」
三条女史のため息が聞こえる。
『とにかく、面談。今日午後一時、学校に来い』
時計を見る。
「一時って、もう三十分もないじゃないですか!」
三条女史は『問答無用』とぶっきらぼうに告げると、一方的に通話を切った。
なんて乱暴な教師だ。心の中で呟いても、当然のごとく返事は返ってこなかった。
海鈴は重い足取りで階段を下りる。しんとした家の中。両親はお盆のため帰省中で、今この大きな箱の中にいるのは海鈴一人だけだった。相変わらず本人主義な両親だ。
制服に着替え、歯を磨く。爽やかなミントの味が口の中に広がり、水で軽くゆすぐと、頭の中までさっぱりした気がした。
鋭い陽射しの中、海鈴は黒く焼け焦げている自分の影を見る。夏の暑さに文句一つ言うことなく、ゆったりと立つ木々たち。その代わりに主張する、木に張り付いた油蝉の声。それらを横目に、海鈴は学校へ向かう。
「来たな、学年トップの劣等生」
四畳ほどの面談室で、海鈴は再び三条女史と向かい合った。
「進路なら、まだ決まってません」
「先回りすんなよ」三条女史が苦笑する。
「それを聞きに呼び出したんじゃないんですか」
「まぁそうだけど。絵画教室はつまんなかったか?」
三条女史の声に棘はなく、柔らかかった。海鈴は三条女史から目を逸らした。
「天城が落ち込んでたぞ。飛鳥が来なかったって」
海鈴は目を逸らした。三条女史の口から飛び出た湊の名前に、海鈴は奥歯を噛む。
「……べつに私、美大受けるつもりないですし。参加しても意味ないじゃないですか」
不貞腐れた答えしか出てこない自分自身に、海鈴はさらに嫌な気分になった。ため息が頭の上から降ってくる。
「……天城はな、お前と同じだったんだよ」
顔を上げると、三条女史の少し困ったような笑顔があった。
「あいつも高校三年のこの時期まで、全然進路を決められなくてさ」
「え……そうなんですか?」
「私立の美大は金がかかるし、かといって国立はとんでもない倍率だ。好きなことを貫いて美大を挑戦するか、諦めて無難な大学を出て就職するか」
海鈴は顔を上げ、三条女史を見つめた。
「……私はさぁ、口を開けばガミガミ説教臭くなっちゃうんだよな。悪い癖だって分かってんだけど、ついつい口を出しちゃうんだ。大人の理屈なんか言ったところで、悩んでる本人の心には全然響かないのにさ」
そう言って、三条女史は自嘲気味に笑い、頬杖をついた。
「湊先生って、三条先生の教え子だったんですか」
知らなかった。湊は、三条女史が初めて担任として送り出した卒業生だったという。
「私はさ、悩んでるあいつに頑張れなんて無責任な言葉は言えなかったし、かといって夢を諦めさせて普通の大学を進めることも怖くてできなかった。あいつは結局、自分で進路を切り開いたんだ。私は最後まで力になれなかった。何年経っても、ずっとそれが胸の中にあってさ。あいつは私のトラウマなんだ。だからか、今もちょっと気を使っちゃうんだよな」
頭を掻きながら、自嘲気味に笑う三条女史。
「トラウマ? ……え、恋人じゃなくて?」
「恋人? ないない。歳の差考えろ。どんな誤解だ」
海鈴の素っ頓狂な勘違いに、三条女史はキョトンとした顔をした後、けらけらと涙を流して笑った。恥ずかしさに、頬に熱が集まっていくのが自分でも分かった。
「いや……だって……」
「夜飯ついでに飲みに行っただけだ。お互い自炊なんかしないし、わざわざ夏休みのこの時期に呼び出したのは私だから、礼もかねてな」
「なんだ……もう、紛らわしいな」
海鈴は口を尖らせた。とんだ勘違いをしてしまった。
「……でも、どうして絵画教室だったんですか?」
「あーそれな。私が美術部顧問だったから」
「……は? それだけ?」海鈴は唖然とする。
「本当はさ、なんでもよかったんだ。飛鳥にはただ、まったく関係のない大人と話してほしかっただけなんだよ」
「知らない大人と……? なんのために?」
「飛鳥は私の前だと、いつも自分を抑えていい子でいようとする。でも、藤木たちといるときは違うだろ? 本当は自分の意見をしっかり持ってるし、それを言葉にできる頭もある。飛鳥は周りに置いていかれてるように感じていたかもしれないが、全然そんなことはないんだよ。飛鳥はちゃんと大人になってるよ。私はただ、それに気付いてほしかったんだ」
海鈴の大きな瞳から、涙が溢れ出す。ぽろぽろと、心の中に溜まっていた不安が吐き出されていくようにとめどなく流れていった。
「私は応援することくらいしかできないけどさ。お前は一人じゃないよ。お前の親御さんはすごいよ。娘を信じて放っておけるんだからな」
海鈴は目を瞠る。母は、ずっと興味がないのだと思っていた。心配されていないのだと思っていた。でも、違った。本当は全然そんなことなくて、なにも言わず、海鈴を信じてずっと見守ってくれていたのだ。
胸がぎゅっと苦しくなる。長い間心の中で燻っていた黒い靄が、陽光が射したようにすっと消えていく。
海鈴はぎゅっと両手を握り込む。
「でも、私は……みんなと違ってなりたいものなんてないし」
そんな海鈴に、三条女史は柔らかな笑顔で笑いかける。
「なりたいものを学ぼうと考えて進路を探すから見つからないんだよ。だったら、好きなものを学べばいい。飛鳥の好きな物はなんだ?」
「私の好きなものは……ヴァイオリン」
海鈴は音楽の自由さを、ナノとヴァイオリンを奏でて思い出した。弾む音符と、ナノの楽しそうな笑顔。精霊たちの歌声。口にできない思いは、音楽にして伝えればいいと気付いた。
「ヴァイオリンか……音楽が好きなんだな」
「星も好きです。宇宙を想像するのが好き。神話の登場人物たちが空で生きている想像をするのが好き」
「いいじゃないか。物語。飛鳥は本も好きだもんな」
「はい」
「音楽を学びたいなら音大か、天文に関して科学的に研究したいなら理学部か、天文考古学っていう文学的に天文を研究する学科もあるぞ」
「え……天文は理系かと思ってました」
「音大を出れば、音楽家や学校の音楽の先生を目指せる。天文なら研究者として、宇宙航空研究開発機構とかの専門機関に就職したり、あとはプラネタリウムや天文台で、解説者として人に星の魅力を伝えるなんて仕事もあるぞ。あぁ、あとは、読書が好きなら図書館司書とか、出版社に勤めるとかそういう道もあるな」
三条女史の話は目から鱗だった。
「……ちょっと自分で調べてみます」
その日、海鈴は初めて未来に興味を覚えた。
なにがあったというわけではないのだ。ただ、やっぱり美大に行きたいわけでもないのに絵を描いていたって時間の無駄だと思っただけだ。
ベッドに寝転がりながら、机の上にあるスケッチブックを見る。そこにはステラを思い浮かべて落とした色があった。ふと、スマホが振動した。
『サボりやがったな』
三条女史から、ひとことだけのメッセージ。そのあとすぐ、電話がかかってきた。出るか迷ったが、さすがに居留守はできなかった。
「……なんですか」
機嫌を隠すのも億劫で、低い声のまま通話ボタンをタップした。
『お前……あからさまにいじけてんな』
「……べつに、いじけてません」
三条女史のため息が聞こえる。
『とにかく、面談。今日午後一時、学校に来い』
時計を見る。
「一時って、もう三十分もないじゃないですか!」
三条女史は『問答無用』とぶっきらぼうに告げると、一方的に通話を切った。
なんて乱暴な教師だ。心の中で呟いても、当然のごとく返事は返ってこなかった。
海鈴は重い足取りで階段を下りる。しんとした家の中。両親はお盆のため帰省中で、今この大きな箱の中にいるのは海鈴一人だけだった。相変わらず本人主義な両親だ。
制服に着替え、歯を磨く。爽やかなミントの味が口の中に広がり、水で軽くゆすぐと、頭の中までさっぱりした気がした。
鋭い陽射しの中、海鈴は黒く焼け焦げている自分の影を見る。夏の暑さに文句一つ言うことなく、ゆったりと立つ木々たち。その代わりに主張する、木に張り付いた油蝉の声。それらを横目に、海鈴は学校へ向かう。
「来たな、学年トップの劣等生」
四畳ほどの面談室で、海鈴は再び三条女史と向かい合った。
「進路なら、まだ決まってません」
「先回りすんなよ」三条女史が苦笑する。
「それを聞きに呼び出したんじゃないんですか」
「まぁそうだけど。絵画教室はつまんなかったか?」
三条女史の声に棘はなく、柔らかかった。海鈴は三条女史から目を逸らした。
「天城が落ち込んでたぞ。飛鳥が来なかったって」
海鈴は目を逸らした。三条女史の口から飛び出た湊の名前に、海鈴は奥歯を噛む。
「……べつに私、美大受けるつもりないですし。参加しても意味ないじゃないですか」
不貞腐れた答えしか出てこない自分自身に、海鈴はさらに嫌な気分になった。ため息が頭の上から降ってくる。
「……天城はな、お前と同じだったんだよ」
顔を上げると、三条女史の少し困ったような笑顔があった。
「あいつも高校三年のこの時期まで、全然進路を決められなくてさ」
「え……そうなんですか?」
「私立の美大は金がかかるし、かといって国立はとんでもない倍率だ。好きなことを貫いて美大を挑戦するか、諦めて無難な大学を出て就職するか」
海鈴は顔を上げ、三条女史を見つめた。
「……私はさぁ、口を開けばガミガミ説教臭くなっちゃうんだよな。悪い癖だって分かってんだけど、ついつい口を出しちゃうんだ。大人の理屈なんか言ったところで、悩んでる本人の心には全然響かないのにさ」
そう言って、三条女史は自嘲気味に笑い、頬杖をついた。
「湊先生って、三条先生の教え子だったんですか」
知らなかった。湊は、三条女史が初めて担任として送り出した卒業生だったという。
「私はさ、悩んでるあいつに頑張れなんて無責任な言葉は言えなかったし、かといって夢を諦めさせて普通の大学を進めることも怖くてできなかった。あいつは結局、自分で進路を切り開いたんだ。私は最後まで力になれなかった。何年経っても、ずっとそれが胸の中にあってさ。あいつは私のトラウマなんだ。だからか、今もちょっと気を使っちゃうんだよな」
頭を掻きながら、自嘲気味に笑う三条女史。
「トラウマ? ……え、恋人じゃなくて?」
「恋人? ないない。歳の差考えろ。どんな誤解だ」
海鈴の素っ頓狂な勘違いに、三条女史はキョトンとした顔をした後、けらけらと涙を流して笑った。恥ずかしさに、頬に熱が集まっていくのが自分でも分かった。
「いや……だって……」
「夜飯ついでに飲みに行っただけだ。お互い自炊なんかしないし、わざわざ夏休みのこの時期に呼び出したのは私だから、礼もかねてな」
「なんだ……もう、紛らわしいな」
海鈴は口を尖らせた。とんだ勘違いをしてしまった。
「……でも、どうして絵画教室だったんですか?」
「あーそれな。私が美術部顧問だったから」
「……は? それだけ?」海鈴は唖然とする。
「本当はさ、なんでもよかったんだ。飛鳥にはただ、まったく関係のない大人と話してほしかっただけなんだよ」
「知らない大人と……? なんのために?」
「飛鳥は私の前だと、いつも自分を抑えていい子でいようとする。でも、藤木たちといるときは違うだろ? 本当は自分の意見をしっかり持ってるし、それを言葉にできる頭もある。飛鳥は周りに置いていかれてるように感じていたかもしれないが、全然そんなことはないんだよ。飛鳥はちゃんと大人になってるよ。私はただ、それに気付いてほしかったんだ」
海鈴の大きな瞳から、涙が溢れ出す。ぽろぽろと、心の中に溜まっていた不安が吐き出されていくようにとめどなく流れていった。
「私は応援することくらいしかできないけどさ。お前は一人じゃないよ。お前の親御さんはすごいよ。娘を信じて放っておけるんだからな」
海鈴は目を瞠る。母は、ずっと興味がないのだと思っていた。心配されていないのだと思っていた。でも、違った。本当は全然そんなことなくて、なにも言わず、海鈴を信じてずっと見守ってくれていたのだ。
胸がぎゅっと苦しくなる。長い間心の中で燻っていた黒い靄が、陽光が射したようにすっと消えていく。
海鈴はぎゅっと両手を握り込む。
「でも、私は……みんなと違ってなりたいものなんてないし」
そんな海鈴に、三条女史は柔らかな笑顔で笑いかける。
「なりたいものを学ぼうと考えて進路を探すから見つからないんだよ。だったら、好きなものを学べばいい。飛鳥の好きな物はなんだ?」
「私の好きなものは……ヴァイオリン」
海鈴は音楽の自由さを、ナノとヴァイオリンを奏でて思い出した。弾む音符と、ナノの楽しそうな笑顔。精霊たちの歌声。口にできない思いは、音楽にして伝えればいいと気付いた。
「ヴァイオリンか……音楽が好きなんだな」
「星も好きです。宇宙を想像するのが好き。神話の登場人物たちが空で生きている想像をするのが好き」
「いいじゃないか。物語。飛鳥は本も好きだもんな」
「はい」
「音楽を学びたいなら音大か、天文に関して科学的に研究したいなら理学部か、天文考古学っていう文学的に天文を研究する学科もあるぞ」
「え……天文は理系かと思ってました」
「音大を出れば、音楽家や学校の音楽の先生を目指せる。天文なら研究者として、宇宙航空研究開発機構とかの専門機関に就職したり、あとはプラネタリウムや天文台で、解説者として人に星の魅力を伝えるなんて仕事もあるぞ。あぁ、あとは、読書が好きなら図書館司書とか、出版社に勤めるとかそういう道もあるな」
三条女史の話は目から鱗だった。
「……ちょっと自分で調べてみます」
その日、海鈴は初めて未来に興味を覚えた。