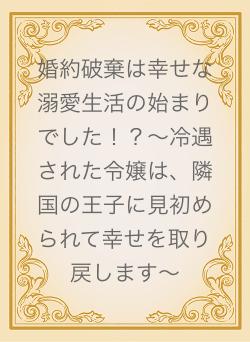夏休みが始まって三週間経った夜のこと。いつものように鏡の国でティータイムをしていると、
「海鈴。今日はお出かけするの……」
「お出かけ?」
「お隣のコルコットさんの姪っ子の知り合いから頼まれごと……」
ステラにしては珍しく早口で、聞き取れなかった。
「お、お隣のコルコットさんの姪っ……え、なに?」
近いのか遠いのか。いや、もはや他人ではないだろうか。大きな欠伸をするステラの代わりに、ナノが説明をしてくれる。
「お隣のコルコットさんの、姪っ子の知り合いの魔道具屋さんを営むケインさんの奥さんのロッタさんっていう人からの頼まれごとらしいよ」
おっと、名前が増えたような。
「……まぁ、いいや。その頼まれごとってなんなの?」
「最近……息子さんの元気がなくなっちゃったから……新しい花壇と太陽を作ってほしいって……」
なぜ息子の元気がなくなったからといって、花壇と太陽を作ってほしいということになるのだろう。謎だ。首を傾げていると、ナノが気付いて言葉を付け足した。
「ロッタさんの息子さんは、太陽が大好きなひまわりなんだよ。だから、太陽がないと死活問題なんだ」
もう考えるのはよそう。
「とりあえずお出かけするんだね」
「うん……ロッタさんのおうちは……ここから五百マイル行ったとこ……」
「遠くない!?」
思わず声を上げると、ナノがのんびりとした調子で言う。
「銀河鉄道に乗っていけばすぐだよ」
こうして海鈴とナノとステラは、この小屋のお隣の、コルコットさんの姪っ子の知り合いの魔道具屋さんを営むケインさんの奥さんのロッタさんだかいう人に会いに行くことになった。
ナノはヴァイオリンケースを背負い、ステラは魔女らしくとんがり帽子をきちんと被って筆に乗った。三人で身支度を整えて、小屋を出る。
小屋のすぐ横には、以前ステラが生み出した大きな白銀の大樹がある。あれからさらに成長し、今では空も突き破るのではと思うほどの大きさにまでなっていた。
銀河鉄道は、この世界の者ならば乗り降りが自由で、勝手に目的地に連れて行ってくれるという。銀色の大きな車体は、鏡のように反射して、海鈴の姿を写していた。
三人は後方の座席に着いた。汽笛を鳴らし、車体がガタンと揺れる。車窓から一望できるのは、空の上に広がる青紫色の花畑だった。前方の煙突から、カラフルな星屑が吐き出される。それらは線路を囲うように咲き乱れる花たちに、雨のように降り注いでいた。
「銀河鉄道は……星を燃料にして進むの……」
「星かぁ。まるで童話の夢の旅のようだね」
「……でも、最近星が少なくなって……燃料不足なんだって……車掌さんが嘆いてた……」
言いながら、ステラの瞼がゆっくりと落ちていく。どうやら睡魔に負けつつあるようだ。
「ステラ、着くまで寝てていいよ。私は起きてるから」
優しく諭すと、ステラは柔らかい笑みを浮かべ、すぐに寝息を立て始めた。
「着くまで、ボクも寝ようかなぁ」
海鈴の隣に座っていたナノまでが、目の縁に涙を溜めて欠伸をしている。
二人の規則正しい寝息が聞こえ始めると、海鈴は一人、車窓から見える景色を楽しんだ。
星屑が舞う。儚く、淡く、きらきらと。それはまるで、誰かの夢のように。列車は進む。透明な線路の上を。迷わずに、まっすぐと。まるで見えないなにかに導かれるように。
自分もこうしてどこまでも行けたら、なんて、海鈴は車窓に切り取られた景色を眺めながら、心の中で呟いた。
さわさわという不思議な音に、海鈴は瞳を開く。いつの間にか寝入っていたようだ。窓の外は、雨が降っていた。この世界に来て、初めての雨だった。
「この世界も、雨って降るんだ……」
ぼんやりと窓の外を見ながら、ハッとした。
「あれ……そういえば、もう目的地?」
呟きながら瞳を瞬いた海鈴は固まった。同じボックス席に座っていたはずのナノとステラがいなくなっていた。
弾かれたように立ち上がる。もしかして、寝過ごしてしまったのだろうか。いやしかし、着いたらさすがに起こしてくれるだろう。
「ナノ? ステラ? どこ?」
車内には、ナノとステラの姿はない。車内を見渡しても、見知らぬ乗客しか乗っていなかった。
「ナノ! ステラ!」
海鈴の声は、ガタガタと揺れる車窓にぶつかって消えていく。そのとき、ガラリと貫通扉が開く音がした。どきん、と、心臓が跳ねた。もしやと思い振り向くが、そこにいたのは車掌の格好をした背の高い男だった。
「切符を拝見致します」
車掌は、乗客たちが差し出す切符を順番に確認し、切っていく。
海鈴は途方に暮れた。どうしよう。切符なんて持っていない。そもそも乗り降り自由なのではなかったか。
「切符を拝見致します」
目の前で、車掌が止まった。二人の間を満たすのは、激しい夕立の後のような、奇妙な静寂。
男がじっと海鈴を見下ろす。冷や汗が背中をつたう。
不思議な格好をした男だった。純白のシャツに黄金色のネクタイを締め、裾の長いダークネイビーのジャケットとおそろいのズボンを上品に着こなしている。さらに、顔には猫の耳らしき飾りが着いた漆黒の仮面をつけ、長く絹のように美しい銀髪は後ろでひとつにまとめられていた。
向き合う二人。沈黙に耐えられなくなった海鈴は、おずおずと口を開く。
「あの……ごめんなさい。私、切符持ってないんです」
しかし、仮面の車掌は無言のままだった。
「あの、ナノとステラという子を知りませんか。ジュゴンと魔女の子なんですけど。一緒にいたのに、いつの間にかいなくなっちゃって……」
正直に謝ったあと、縋る思いで訊ねながら、海鈴は仮面の奥の瞳を覗いた。その瞳は、鷹色をしていた。凛としていて、涼しげで。顔なんてほとんど見えていないのに、海鈴は仮面の車掌のことを、なぜだか美しい人だと思った。
「……帰りなさい」
高いような低いような、艶のある声で仮面の車掌が言う。誰かに似ていると思って考えていると、ふと一人の男の顔が浮かんだ。湊だ。この仮面の車掌は、どことなく湊に似ているのだ。
「あなたはもう、彼らに会うことはできない」
しかし、違うのは声の柔らかさだった。仮面の車掌の声は、甘さを一切封印したコーヒーゼリーのように、苦い後味だけを海鈴の耳の奥に残した。
「ここは、あなたのいるべき世界じゃない。手遅れになる前に、早く帰りなさい」
ドキリとした。彼の言葉は、ミレイに対しての言葉ではない。海鈴に対して言っているのだとすぐに分かった。
海鈴の中で小さな不安が生まれ、瞬く間にむくむくとふくらんでいく。
「私のこと、知ってるの? あなたは誰?」
警戒しながら仮面の穴を覗く。そこには闇が続くばかりで、仮面の車掌の真意は読み取れない。再び沈黙が落ちたとき、時間を知らせる鐘が鳴った。ハッとして、海鈴はすぐ真横の車窓に反射する自分に気が付いた。
「鏡……」
窓の中に、自分――いや、ミレイがいた。ミレイはなにかを伝えようと口を開く。しかし、ミレイの言葉はどれだけ耳をすませても聞こえない。
聞きたいことがある。ナノとステラはどこにいってしまったのか。この仮面の車掌は誰なのか。しかし、鐘の音は、海鈴の中で渦巻く疑問を残したまま勝手に終わりを告げようとしている。
二人の手が重なる。ぐにゃりと視界が歪み、その瞬間、海鈴は意識を手放した。