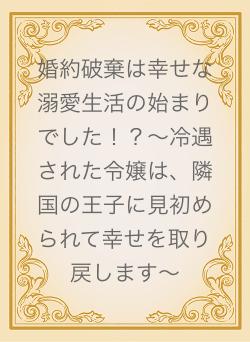海鈴は鏡の中の世界――鏡界にいた。つぎはぎの空の下、水面とガラスの境が消えた世界。ちくちくと縫い込まれた空。月は小さく、太陽は眠っている。天使のような光の精霊や歩く植物、着物を着た動物たち。歩いた後には星の川が、息を吐けば色がつく不思議な空間。
もう何度この世界に足をつけただろうか。これは、現実の夢。現実だけど、夢なのだ。
進路がどうとか、嫌なことを言う人はいない。だってこんな楽しい現実があるのだ。この現実を前に、そんな言葉が説得力を持つわけもない。
ここ数日は、ステラの小屋の隣にある白い巨木の樹洞の中で、ナノとステラのティータイムをするのが日課になっていた。
昼間は学校の課題や読書、なんとなく申し込んだ名前も知らない大学のオープンキャンパスに行って、夜になったらミレイと入れ替わって鏡界で息抜きをする。
「はぁぁ……」
海鈴は落ち込んでいた。今日は月曜日。例の絵画教室の日だった。しかし一週間考えても、なにを描きたいかもなにを描けばいのかも分からず、今回もまた時間を無駄にしてしまった。
「はぁ……」
海鈴以外の美術部員たちは、神話に出てくるような半裸の人間を描いていたり、鏡を見た自画像だったり。
どれも下書きの時点で完成されているのではと思うほど綺麗だった。美術部員にならって自分も自画像にしようかとも考えたが、結局自信がない海鈴には、自分を描くことはできなかった。
「ミレイ、最近ため息ばっかり……」
眠そうに目を細めたまま、ステラが嘆く。
「あ、ごめん……ちょっと悩んでてさ」
「悩みって、なに?」ナノが訊ねる。
海鈴は思い切って、絵画教室でのことを話してみることにした。
「……ねぇ。二人だったら、絵を描くとしたら、なにを描く?」
「うーん……なんでもいいって言われたら、ボクならマヨネーズかな! それか、楽譜!」
海鈴は苦笑する。ナノらしい。どちらもナノが大好きなものだ。
そういえば、湊もべつに絵にこだわらなくていいと言っていた。
「ステラは?」
「私は……好きな色を落とす……かな」
「色? それだけ?」予想外の答えだった。
「うん……。水に滲む色を見るの……好きだから……」
これまたステラらしい。
「ミレイは描きたいもの……ないの?」
「うん……なにも浮かばないの。好きに描いていいって言われても、迷っちゃって」
「迷う? 羨ましいなぁ」
ナノが言う。海鈴は瞳をぱちくりと瞬いた。
「え、どうして? 結局なんにも描けてないのに」
「だって、ミレイは……それだけたくさん描きたいものがあるってこと……でしょ……?」
ステラがふわりと欠伸をする。海鈴は空を見上げる。
「……そうなのかなぁ」
どうなのだろう。上手く答えられない。
「ミレイ……これ……あげる」
ステラは海鈴に向かって漆黒の衣装に隠れた小さな手を突き出した。
「え、これって……」
ステラがくれたのは、彼女が愛用している筆と似たものだった。大きさはシャーペンほどだが、ステラのものとおそろいだ。
「これ……くれるの?」
これは、魔法の筆だ。描いたものに命を吹き込むことができる不思議な筆。
「うん……私とおそろい……これでミレイの好きなものを描けばいいと思う……ここでなら、なんでも生み出せる……やってみせて」
マヨネーズの容器をイメージし、手を動かした。すると描いた軌道がきらりと光り、瞬きを繰り返し、巨大なマヨネーズが現れた。
「きぃゃぁあああ! マヨネーズ! 夢のようなマヨネーズだぁっ!」
ナノは現れたマヨネーズを見て発狂し、飛びついた。
「すごいわ、ミレイ……。描けるじゃない……これならきっと、課題だってすぐに終わっちゃうよ……」
ステラは目尻を下げ、微笑んだ。つられるように、海鈴の頬も緩む。
「……ありがとう、ステラ」
手の中の筆が、夢のようにきらりと輝いた。
白いスケッチブックと、海鈴はにらめっこをしていた。少し毛羽立った画用紙。まっさらで、まだ何色にも染まっていない。
それから一週間後の月曜日、海鈴は美術室にいた。部員たちの下絵は完成し、それぞれ色つけに入っている。いつもなら焦って適当になにかしら描き始めるところだが、今日の海鈴は少し気分が違った。
海鈴の手には、ステラからもらった筆が握られている。
「その筆、可愛いね」
海鈴の手元を見て、湊が言う。
「あ……湊先生」
海鈴は顔を上げ湊を見た後、すぐに筆に視線を戻した。
「友達からもらったんです。悩んでたら、絵が好きな子がこれで描くといいよって」
「素敵な友達だね」
「はい……でも、私、下絵もなしにいきなり筆で絵を描くなんて……」
湊が海鈴のすぐ顔の横にかがみ、スケッチブックに手をついた。
「大丈夫。上手く描こうとしないで。正解なんてないんだよ」
湊の優しい声に、どきんと胸が跳ねる。湊は絵のことになると我を忘れるのか、たまに距離が近いことがある。その度に耳に触れる吐息が海鈴の心を掻き乱した。
「……あ、あの」
「このスケッチブックは、君みたいだ」
「え?」
海鈴は驚いて顔を上げた。
「まっさらで、綺麗な白。この四角い枠は無限だよ。君の可能性は無限にあるんだ」
鷹色の瞳が海鈴を映す。
「この筆をくれた子は、君のことをよく分かっているね」
耳の奥に湊の吐息がたまっていく。甘く優しく、海鈴の脳みそを溶かしていく。眩暈がする。
これまで異性に興味なんてなかった。テレビでかっこいい人を見ても、かっこいいなぁと思うだけだった。
クラスの違う同級生に告白されたときも、嬉しいなぁと思うだけで、その先を想像したりなんてしなかった。
それなのに今、海鈴の身体中の神経は、湊たった一人に集中している。
「飛鳥さん?」
黙り込んだ海鈴を、湊が呼ぶ。
名前を呼ばれるだけで、胸が騒いだ。頬が熱い。いったいどうしちゃったのだろうと、海鈴は自分自身がよくわからなくなった。
どうやらこれが、恋というものらしい。
視界が淡く輝く。まるで海鈴の双方のレンズにフィルターがかかってしまったかのように、湊が輝いて見えた。
じっと見上げていると、湊がくすりと笑う。
「……あ、す、すみません」慌てて俯く。
「君、本が好きなんだろ? 本を描いてみるのはどう?」
「本を……描く?」
「そう」
「本は描くものじゃなくて、読むものじゃ……?」
言いながら、なんてつまらなくて可愛げのない回答だろう、と思った。しかし湊は嫌な顔ひとつせず、穏やかに微笑んだまま続けた。
「でも、そうしたら、本はただの文字の羅列になってしまうよ。それじゃあ読み手は感動しない」
海鈴は首を傾げる。湊の伝えようとしていることが分からなかった。
「どういうことですか?」
「物語は、いつだって描くものだよ」
「描く……?」
「そう。どんなものも、すべては点で始まる。そこに線がついて、色がついて、影や動きがついて、初めて物語になるんだよ。文字に命を吹き込んで、物語になって初めて人に届く。本はそうやってできてる」
湊の声は、海鈴以外の深く柔らかいところに落ちていく。
海鈴は絵の具をパレットに絞り出した。桃色の絵の具を筆につけ、水の中に落とす。透明な水の中に、どろりと桃色の絵の具が落ちると、少しずつ滲み出した。
塊がほつれ、水が染まり、桃色が薄くなる。
「綺麗……」
隣で、湊が頷く。
「うん。綺麗だ」
かすかに色のついた水を、スケッチブックに落としてみる。しかし、違う。ステラの桃色はもっともっと淡い。
消えそうなくらいに儚い桃色。柔らかくて、ひらひらしていて、可愛らしい。絵の知識が海鈴に、上手く表現できるか分からないけれど。
「表現してみたくなっただろ?」
「はい」
海鈴の声が弾む。海鈴は笑顔で湊を見上げた。湊は一瞬僅かに目を瞠り、すぐに細めた。
表現してみたい。あの世界を。
無心でスケッチブックに色を付け出した海鈴を、湊は優しい顔で見守っている。
もう何度この世界に足をつけただろうか。これは、現実の夢。現実だけど、夢なのだ。
進路がどうとか、嫌なことを言う人はいない。だってこんな楽しい現実があるのだ。この現実を前に、そんな言葉が説得力を持つわけもない。
ここ数日は、ステラの小屋の隣にある白い巨木の樹洞の中で、ナノとステラのティータイムをするのが日課になっていた。
昼間は学校の課題や読書、なんとなく申し込んだ名前も知らない大学のオープンキャンパスに行って、夜になったらミレイと入れ替わって鏡界で息抜きをする。
「はぁぁ……」
海鈴は落ち込んでいた。今日は月曜日。例の絵画教室の日だった。しかし一週間考えても、なにを描きたいかもなにを描けばいのかも分からず、今回もまた時間を無駄にしてしまった。
「はぁ……」
海鈴以外の美術部員たちは、神話に出てくるような半裸の人間を描いていたり、鏡を見た自画像だったり。
どれも下書きの時点で完成されているのではと思うほど綺麗だった。美術部員にならって自分も自画像にしようかとも考えたが、結局自信がない海鈴には、自分を描くことはできなかった。
「ミレイ、最近ため息ばっかり……」
眠そうに目を細めたまま、ステラが嘆く。
「あ、ごめん……ちょっと悩んでてさ」
「悩みって、なに?」ナノが訊ねる。
海鈴は思い切って、絵画教室でのことを話してみることにした。
「……ねぇ。二人だったら、絵を描くとしたら、なにを描く?」
「うーん……なんでもいいって言われたら、ボクならマヨネーズかな! それか、楽譜!」
海鈴は苦笑する。ナノらしい。どちらもナノが大好きなものだ。
そういえば、湊もべつに絵にこだわらなくていいと言っていた。
「ステラは?」
「私は……好きな色を落とす……かな」
「色? それだけ?」予想外の答えだった。
「うん……。水に滲む色を見るの……好きだから……」
これまたステラらしい。
「ミレイは描きたいもの……ないの?」
「うん……なにも浮かばないの。好きに描いていいって言われても、迷っちゃって」
「迷う? 羨ましいなぁ」
ナノが言う。海鈴は瞳をぱちくりと瞬いた。
「え、どうして? 結局なんにも描けてないのに」
「だって、ミレイは……それだけたくさん描きたいものがあるってこと……でしょ……?」
ステラがふわりと欠伸をする。海鈴は空を見上げる。
「……そうなのかなぁ」
どうなのだろう。上手く答えられない。
「ミレイ……これ……あげる」
ステラは海鈴に向かって漆黒の衣装に隠れた小さな手を突き出した。
「え、これって……」
ステラがくれたのは、彼女が愛用している筆と似たものだった。大きさはシャーペンほどだが、ステラのものとおそろいだ。
「これ……くれるの?」
これは、魔法の筆だ。描いたものに命を吹き込むことができる不思議な筆。
「うん……私とおそろい……これでミレイの好きなものを描けばいいと思う……ここでなら、なんでも生み出せる……やってみせて」
マヨネーズの容器をイメージし、手を動かした。すると描いた軌道がきらりと光り、瞬きを繰り返し、巨大なマヨネーズが現れた。
「きぃゃぁあああ! マヨネーズ! 夢のようなマヨネーズだぁっ!」
ナノは現れたマヨネーズを見て発狂し、飛びついた。
「すごいわ、ミレイ……。描けるじゃない……これならきっと、課題だってすぐに終わっちゃうよ……」
ステラは目尻を下げ、微笑んだ。つられるように、海鈴の頬も緩む。
「……ありがとう、ステラ」
手の中の筆が、夢のようにきらりと輝いた。
白いスケッチブックと、海鈴はにらめっこをしていた。少し毛羽立った画用紙。まっさらで、まだ何色にも染まっていない。
それから一週間後の月曜日、海鈴は美術室にいた。部員たちの下絵は完成し、それぞれ色つけに入っている。いつもなら焦って適当になにかしら描き始めるところだが、今日の海鈴は少し気分が違った。
海鈴の手には、ステラからもらった筆が握られている。
「その筆、可愛いね」
海鈴の手元を見て、湊が言う。
「あ……湊先生」
海鈴は顔を上げ湊を見た後、すぐに筆に視線を戻した。
「友達からもらったんです。悩んでたら、絵が好きな子がこれで描くといいよって」
「素敵な友達だね」
「はい……でも、私、下絵もなしにいきなり筆で絵を描くなんて……」
湊が海鈴のすぐ顔の横にかがみ、スケッチブックに手をついた。
「大丈夫。上手く描こうとしないで。正解なんてないんだよ」
湊の優しい声に、どきんと胸が跳ねる。湊は絵のことになると我を忘れるのか、たまに距離が近いことがある。その度に耳に触れる吐息が海鈴の心を掻き乱した。
「……あ、あの」
「このスケッチブックは、君みたいだ」
「え?」
海鈴は驚いて顔を上げた。
「まっさらで、綺麗な白。この四角い枠は無限だよ。君の可能性は無限にあるんだ」
鷹色の瞳が海鈴を映す。
「この筆をくれた子は、君のことをよく分かっているね」
耳の奥に湊の吐息がたまっていく。甘く優しく、海鈴の脳みそを溶かしていく。眩暈がする。
これまで異性に興味なんてなかった。テレビでかっこいい人を見ても、かっこいいなぁと思うだけだった。
クラスの違う同級生に告白されたときも、嬉しいなぁと思うだけで、その先を想像したりなんてしなかった。
それなのに今、海鈴の身体中の神経は、湊たった一人に集中している。
「飛鳥さん?」
黙り込んだ海鈴を、湊が呼ぶ。
名前を呼ばれるだけで、胸が騒いだ。頬が熱い。いったいどうしちゃったのだろうと、海鈴は自分自身がよくわからなくなった。
どうやらこれが、恋というものらしい。
視界が淡く輝く。まるで海鈴の双方のレンズにフィルターがかかってしまったかのように、湊が輝いて見えた。
じっと見上げていると、湊がくすりと笑う。
「……あ、す、すみません」慌てて俯く。
「君、本が好きなんだろ? 本を描いてみるのはどう?」
「本を……描く?」
「そう」
「本は描くものじゃなくて、読むものじゃ……?」
言いながら、なんてつまらなくて可愛げのない回答だろう、と思った。しかし湊は嫌な顔ひとつせず、穏やかに微笑んだまま続けた。
「でも、そうしたら、本はただの文字の羅列になってしまうよ。それじゃあ読み手は感動しない」
海鈴は首を傾げる。湊の伝えようとしていることが分からなかった。
「どういうことですか?」
「物語は、いつだって描くものだよ」
「描く……?」
「そう。どんなものも、すべては点で始まる。そこに線がついて、色がついて、影や動きがついて、初めて物語になるんだよ。文字に命を吹き込んで、物語になって初めて人に届く。本はそうやってできてる」
湊の声は、海鈴以外の深く柔らかいところに落ちていく。
海鈴は絵の具をパレットに絞り出した。桃色の絵の具を筆につけ、水の中に落とす。透明な水の中に、どろりと桃色の絵の具が落ちると、少しずつ滲み出した。
塊がほつれ、水が染まり、桃色が薄くなる。
「綺麗……」
隣で、湊が頷く。
「うん。綺麗だ」
かすかに色のついた水を、スケッチブックに落としてみる。しかし、違う。ステラの桃色はもっともっと淡い。
消えそうなくらいに儚い桃色。柔らかくて、ひらひらしていて、可愛らしい。絵の知識が海鈴に、上手く表現できるか分からないけれど。
「表現してみたくなっただろ?」
「はい」
海鈴の声が弾む。海鈴は笑顔で湊を見上げた。湊は一瞬僅かに目を瞠り、すぐに細めた。
表現してみたい。あの世界を。
無心でスケッチブックに色を付け出した海鈴を、湊は優しい顔で見守っている。