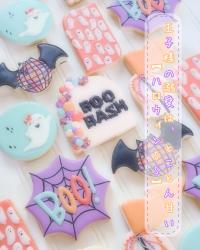「そっ……それ、は……」
ドックンドックン、心臓が大暴れ。
なるちゃんの瞳をじっと見上げると、いつになく真剣な表情とぶつかった。
いつもいつも私を気にかけてくれて、優しくしてくれる幼なじみ。
……そう、最近まで思っていたのに。
やっぱり、口ではあれこれ言っても心は誤魔化せないんだ。
…だってね?なるちゃんに見られていると思うとね、馬鹿みたいにドキドキしちゃって、変になるの。
二人っきりになると、息が詰まりそうなくらい緊張するし。
笑った顔も怒った顔も、キラキラ輝いて見えて。
「なるちゃんとは、もう……」
息を、吸う。
「…幼なじみに、戻れない」
それを吐いた時にはもう、熱でおかしくなりそうだった。
「それは…どういう意味?」
なるちゃんの不安そうな顔。
伝わっていないのが非常にもどかしい。
「だ、だからっ…〜〜っなるちゃんのバカ!!」
気づけば、なるちゃんの胸板を叩いていた。
「っは…?いや、どうした急に…」
「どうもこうもないよ!!」
もうやだっ…!!これ、私の口から言わないといけないの…!?