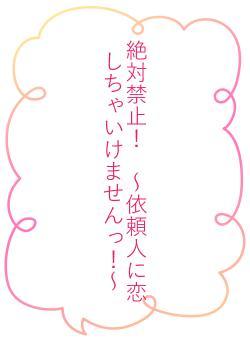朱里の五歳の誕生日の夜。
僕の部屋の真ん中で二人で笑いあったあと、しばらくの間もじもじしていた朱里が、「あのね、南くん」って、遠慮がちに僕に呼びかけた。
「うん? なあに?」
「あのね……」
なんだかすごく言いにくそうにしている。
あ、ひょっとして——。
「朱里、僕の血がほしいの?」
僕がそう尋ねると、朱里はぶんぶんと全力で首を横に振った。
「じゃあ、なあに? ちゃんと言って?」
「あ、あのね……南くんとずーっと一緒にいられるおまじない、してもいい?」
「ずーっと一緒にいられるおまじない?」
僕が首をかしげながら聞き返すと、朱里がこくりと小さくうなずく。
「あのね、朱里のお父さんとお母さんもしたんだって。だからね……」
『ずーっと一緒にいられるおまじない』っていうのは、今思うとちょっと違ったかなって思う。
だけど、朱里はそう願ってくれていたってことなのかな。
僕とずっと一緒にいたいって。