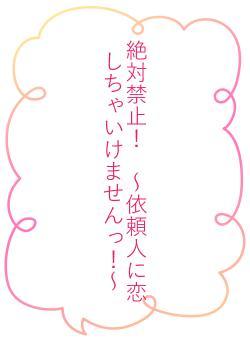「もう二度と会えないと思ってた」
「ごめん。なにも言わずにいなくなって。……あの日、俺、泣かずに『さよなら』を言う自信がどうしてもなくてさ。って、そんなとこで5歳のガキがカッコつけてどーすんだって話だけど」
それって、南くんも、離れたくないって思ってくれてたってことだよね?
わたしだけじゃなかったってことだよね?
そのことが、なによりもうれしい。
「けど、これがあれば、いつかきっと会えるって。それだけが、ずっと俺の心の支えだった」
そう言いながら、首筋の『契約の証』をもう一度わたしに見せてくれた。
そういえば、わたし、いったいなんて言って南くんに契約をお願いしたんだろう?
思い出したいような……恥ずかしすぎて思い出したくないような。
……いやこれ絶対間違いなく恥ずかしいやつだ!
わたしがかぁっと熱を持った頬を両手で覆うと、「隠さないで、ちゃんと見せてよ」なんて言いながら、南くんがわたしの顔を覗き込んでくる。
「みっ、見ないで」
「やーだ。『契約』のことを思い出して恥ずかしがってるんでしょ? だったら、俺にも見る権利あると思うんだけど?」
み、南くん、さっきまでと雰囲気がちがう気がするんですけど?
「ずっと我慢してたんだからな。朱里の『南くん』だって名乗るの。だって、さすがにカッコ悪すぎだろ? 本気で俺のこと忘れられてたら」
「そんなこと! 絶対に忘れるわけないよ!」
「うん、ならよかった」
わたしがぶんぶんと首を横に振りながらそう言うと、南くんがふふっと笑う。
「ごめん。なにも言わずにいなくなって。……あの日、俺、泣かずに『さよなら』を言う自信がどうしてもなくてさ。って、そんなとこで5歳のガキがカッコつけてどーすんだって話だけど」
それって、南くんも、離れたくないって思ってくれてたってことだよね?
わたしだけじゃなかったってことだよね?
そのことが、なによりもうれしい。
「けど、これがあれば、いつかきっと会えるって。それだけが、ずっと俺の心の支えだった」
そう言いながら、首筋の『契約の証』をもう一度わたしに見せてくれた。
そういえば、わたし、いったいなんて言って南くんに契約をお願いしたんだろう?
思い出したいような……恥ずかしすぎて思い出したくないような。
……いやこれ絶対間違いなく恥ずかしいやつだ!
わたしがかぁっと熱を持った頬を両手で覆うと、「隠さないで、ちゃんと見せてよ」なんて言いながら、南くんがわたしの顔を覗き込んでくる。
「みっ、見ないで」
「やーだ。『契約』のことを思い出して恥ずかしがってるんでしょ? だったら、俺にも見る権利あると思うんだけど?」
み、南くん、さっきまでと雰囲気がちがう気がするんですけど?
「ずっと我慢してたんだからな。朱里の『南くん』だって名乗るの。だって、さすがにカッコ悪すぎだろ? 本気で俺のこと忘れられてたら」
「そんなこと! 絶対に忘れるわけないよ!」
「うん、ならよかった」
わたしがぶんぶんと首を横に振りながらそう言うと、南くんがふふっと笑う。