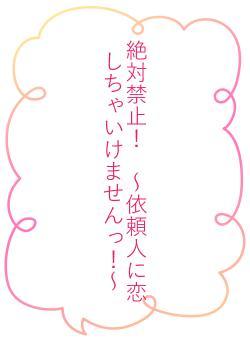坂の下にある駅までの道を、黙ったまま早足で下っていく。
「あのっ……東条くん」
「なに?」
返事をしながらも東条くんは速度を緩めず、前を向いたままずんずん進んでいく。
「ごめんなさい。東条くんがせっかく止めてくれたのに、わたし、言うことを聞かなくて」
「別に。そのことについては、しょうがないって思ってるから。……だいたい、ここまでのことは、さすがに俺だって想定してなかったし」
ぶっきらぼうな言い方だけど、わたしの手を握る東条くんの手に、ぎゅっと力がこもる。
わたしのことをすごく心配してくれていたっていうのが、手から伝わってくるみたい。
でも、どうしてそこまでわたしのことを心配してくれるんだろう。
あの朝、木陰でうずくまるわたしを助けてくれた、ただそれだけの関係のはずなのに。
「あのっ……東条くん」
「なに?」
返事をしながらも東条くんは速度を緩めず、前を向いたままずんずん進んでいく。
「ごめんなさい。東条くんがせっかく止めてくれたのに、わたし、言うことを聞かなくて」
「別に。そのことについては、しょうがないって思ってるから。……だいたい、ここまでのことは、さすがに俺だって想定してなかったし」
ぶっきらぼうな言い方だけど、わたしの手を握る東条くんの手に、ぎゅっと力がこもる。
わたしのことをすごく心配してくれていたっていうのが、手から伝わってくるみたい。
でも、どうしてそこまでわたしのことを心配してくれるんだろう。
あの朝、木陰でうずくまるわたしを助けてくれた、ただそれだけの関係のはずなのに。