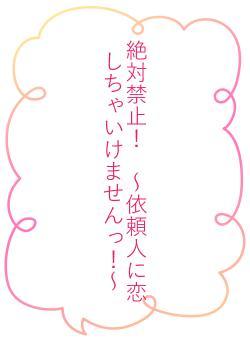東条くんが、心配してくれていたのに……あのとき忠告を聞かなかったわたしが全部悪いんだ。
わたしもヴァンパイアだから大丈夫って、どこかで油断してた。
「お願い白都くん、ここから出して」
震える声で白都くんに懇願すると、白都くんが冷たい笑みを浮かべた。
「ひょっとして、ハーフヴァンパイアのクセに、純血の僕に逆らうの? ちょっとは自分の立場をわきまえなよ。君は、ヴァンパイアでも人間でもないんだよ。そんな君のことを、僕が愛してあげるって言ってるのに。さあ、こっちへおいで」
ゆっくりと白都くんの手が近づいてきて、わたしの手を取ろうとしたその瞬間——。
ガッシャーン‼
勢いよくリビングの窓ガラスが割れ、サッカーボールが飛び込んできた。
「あー悪い悪い。つい足が滑って」
東条くんが、ヘラヘラ笑いながら割れた窓のところから顔を覗かせた。
「は? これはなんの冗談? 朱里との愛しい時間を邪魔しないでくれるかなあ?」
怒りを押し殺したような口調で言い返す白都くんの髪が、ぶわっと逆立つ。
こ、これ、絶対めちゃくちゃ怒ってるよね⁉
だけど、東条くんはそんな白都くんにもまったく怯むことなくヘラヘラ笑ったまま。
「でも、朱里は怯えてるみたいだけど? 朱里は? どうしたいの?」
東条くんに下の名前で呼ばれた瞬間——ドクンッ。
まただ。
体中の血がまるで暴れているみたいで、自分の欲求が抑えられなくなりそう。
わたしもヴァンパイアだから大丈夫って、どこかで油断してた。
「お願い白都くん、ここから出して」
震える声で白都くんに懇願すると、白都くんが冷たい笑みを浮かべた。
「ひょっとして、ハーフヴァンパイアのクセに、純血の僕に逆らうの? ちょっとは自分の立場をわきまえなよ。君は、ヴァンパイアでも人間でもないんだよ。そんな君のことを、僕が愛してあげるって言ってるのに。さあ、こっちへおいで」
ゆっくりと白都くんの手が近づいてきて、わたしの手を取ろうとしたその瞬間——。
ガッシャーン‼
勢いよくリビングの窓ガラスが割れ、サッカーボールが飛び込んできた。
「あー悪い悪い。つい足が滑って」
東条くんが、ヘラヘラ笑いながら割れた窓のところから顔を覗かせた。
「は? これはなんの冗談? 朱里との愛しい時間を邪魔しないでくれるかなあ?」
怒りを押し殺したような口調で言い返す白都くんの髪が、ぶわっと逆立つ。
こ、これ、絶対めちゃくちゃ怒ってるよね⁉
だけど、東条くんはそんな白都くんにもまったく怯むことなくヘラヘラ笑ったまま。
「でも、朱里は怯えてるみたいだけど? 朱里は? どうしたいの?」
東条くんに下の名前で呼ばれた瞬間——ドクンッ。
まただ。
体中の血がまるで暴れているみたいで、自分の欲求が抑えられなくなりそう。