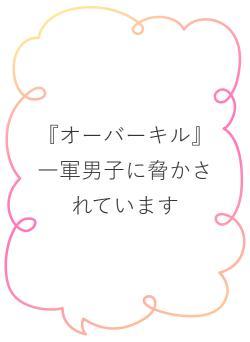「デートに誘ってくれたってことは、俺ら付き合ってるんすよね?」
「へ?」
「違うんすか?」
「……」
「じゃあ、なんで俺の物が欲しいとか言うんすか」
「……」
私は狡くてせこい。
彼からの好意は嬉しく思うのに、明確な関係性を求められたら一歩後ずさる。
高校生になったら、誰でも恋をするのだと思ってた。
高校受験があるように、高校生にあるような日常が、入学と同時に幕を切るとばかり思っていたけれど。
現実は違った。
『女の子』としての努力もせず、『恋愛』の何たるやも知りもしないのに、『彼氏』ができると思っていた自分に上段回し蹴りを喰らわせたくらいだ。
だから、すっかり諦めきっていた夢のような世界が、今さら『ようこそ』とばかりに手を広げられても。
自信もなければ、勇気だってない。
「ごめんねっ、自分勝手なのは重々承知してるんだけど……。彼氏だとか恋愛だとか、よく分からなくて」
「俺のことは嫌いじゃないんすよね?」
「……うん」
「じゃあ、もう彼氏でいいじゃないっすか」
「え」
「受験控えてて気持ち的にどうしてもって言うんなら、『先輩の彼氏』という枠の推薦入試?みたいなもんで」
「……」
「先輩の受験が無事に終わったら、晴れて『彼氏』昇格ってことで」
「っ……」
「俺、一歩も引く気ないんで」
「へ」
「先輩のことがめちゃくちゃ好きなんすよ」
「っっ」
「寝ても覚めても先輩のこと、ずっと考えてるんで」
握られた手にぎゅっと力が込められる。
『俺の気持ち、伝わってますよね?』的な想いが伝わって来る。