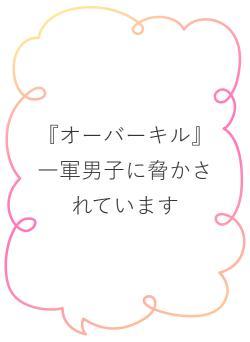十一月下旬の日暮れは早い。
あっという間に辺りが暗くなって来た。
「寒くないっすか?」
「……大丈夫」
左側に津田くんがいるというだけで、左半身が異常に熱い。
ううん、体全体が熱を持っているみたいに熱くて、寒さなんて感じないほど。
手を繋いでいるわけでも、腕を組んでいるわけでもないのに。
彼が隣りを歩いているというだけで。
完全に彼を意識している自分がいる。
だって、時折ピューッと吹く北風を壁になって遮ってくれるんだもん。
意識せずにはいられない。
「本当にそれでよかったんすか?もっと見栄えのあるものでも、買えばよかったっすね」
「ううん、これがいい。ありがとね」
彼の自宅に寄って、普段使っている道着袋に着けているレザーのネームタグを貰った。
おうちの人と居合わせたらなんてご挨拶しようか悩んだけど、ご両親も弟さんもちょうど不在だった。
父親の車で出掛ける時に『津田空手道場』の前はよく通るけど、初めて中に入らせて貰った。
多くの賞状やトロフィー、盾やメダルが飾ってあったが、やはり一番目に付いたのはオリンピックの金メダルだった。
「本当に一人で帰れるよ?」
「俺が送りたいんで」
「っ…」
こういう優しさに慣れていない。
女の子同士なら『バイバイ』で済むのに。
「手、繋いでもいいっすか?」
「へ?」
「俺の手、あったかいっすよ」
「……別に、私の手も温かいけど」
胸の前で手を擦り合わせ、自分の体温を再確認してると、大きな手にがしっと掴まれた。
「家に着くまで」
絡まる指先。
温かいと思っていたのに、彼の体温は私より遥かに高かった。
「ホントだね。すっごくあったかい」