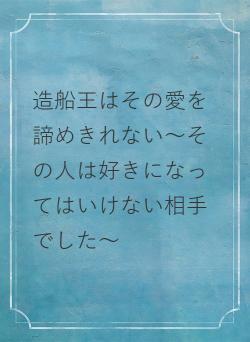「その子の年齢は」
父親は誰だ、などという質問は愚問だった。
誰であろうと、昴の子供のではないという結果は変わらない。
昴と花蓮との間には、原因になるような出来事が何もなかったからだ。
手を繋ぐのがやっとで、キスなどたった一度、掠めるようなものしかしたことがない。
昴は、いつから自分を偽っていたのかと聞きたいのだ。
「一歳半です……」
昴と別れざるを得なくなったのと同じ期間。
ようするに、ふたりが付き合っていた時に、妊娠していたと言っているのも当然であった。
「なんだって? どういうことだ」
昴の声に非難が混じる。
当たり前だ。わざと誤解を招くように言った。
怒った姿を見たのは初めてで、自分でそう仕向けていながら悲しくなった。
嫌われたくない。
同時に、もっと嫌ってくれればいいとも思っている。
そうじゃないと、いつまでも引きずってしまうから。
「花蓮!」
昴の、腕を掴む力が強くなった。
口調には険が含まれている。
「い、いたっ……」
骨が軋み、思わず悲鳴を上げる。
昴ははっとし、すぐに手を離した。
宙に浮いた手は彷徨い、それから気まずそうにこぶしを握る。
「すまない」
「いえ……」
昴が謝ることなんてない。悪いのは、何も相談もせずに姿を消した花蓮だ。
連絡を絶ち居場所は誰にも知らせていないのに、なぜここがわかったのだろう。
父親は誰だ、などという質問は愚問だった。
誰であろうと、昴の子供のではないという結果は変わらない。
昴と花蓮との間には、原因になるような出来事が何もなかったからだ。
手を繋ぐのがやっとで、キスなどたった一度、掠めるようなものしかしたことがない。
昴は、いつから自分を偽っていたのかと聞きたいのだ。
「一歳半です……」
昴と別れざるを得なくなったのと同じ期間。
ようするに、ふたりが付き合っていた時に、妊娠していたと言っているのも当然であった。
「なんだって? どういうことだ」
昴の声に非難が混じる。
当たり前だ。わざと誤解を招くように言った。
怒った姿を見たのは初めてで、自分でそう仕向けていながら悲しくなった。
嫌われたくない。
同時に、もっと嫌ってくれればいいとも思っている。
そうじゃないと、いつまでも引きずってしまうから。
「花蓮!」
昴の、腕を掴む力が強くなった。
口調には険が含まれている。
「い、いたっ……」
骨が軋み、思わず悲鳴を上げる。
昴ははっとし、すぐに手を離した。
宙に浮いた手は彷徨い、それから気まずそうにこぶしを握る。
「すまない」
「いえ……」
昴が謝ることなんてない。悪いのは、何も相談もせずに姿を消した花蓮だ。
連絡を絶ち居場所は誰にも知らせていないのに、なぜここがわかったのだろう。