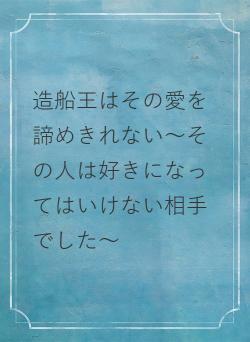味気ないデートばかりになってしまったのは、花蓮を愛しすぎるがゆえ欲望をぶつけないようにするのが大変だったという理由もある。
ベッドに押し倒し、桜色の唇に貪り付きたいと何度妄想したことか。
(花蓮が俺を裏切っただって……?)
清い関係を貫いてきたとはいえ、何年も付き合っていれば性格くらいわかる。
しかし、居なくなる前の何カ月かは、彼女の行動を疑い不安になることがあった。
100パーセント信じることが出来ず疑心暗鬼になっていたのは否めない。
(花蓮に隠し事があった?)
デート中に誰かと連絡をとっていたり、自分の知らない予定が増えた。
詳しく聞こうとしても視線を逸らし、話しを濁すのはそういえば花蓮らしくなかった。
信頼していたから問い詰めることもしなかったが、実は、他に男を作っていたということか?
(自分を愛してくれていると思っていたのに)
他の男と逃げたと聞かされたときの悔しさと絶望を思いだして、拳を握りしめた。
「なにかの……間違いなんだ……」
仕事ばかりで会えなかったのも、すべてはふたりの未来の為。それがすべて無駄になったとわかって恨んだ時期もあったが、やはりなにかの間違いだと思い直した。
せめて、本人の口から説明をうけるべきだ。
思いに耽っていたとき、刺すように見つめていた花蓮の部屋の玄関ドアが動いた。
四階建てのアパートの、一階の真ん中の部屋だ。
「せめて最上階の角部屋にするべきなのに、なんだってあんなところを選んだんだ……」
自分ではない男と暮らす家とはいえ、とうとう会えるのかもと思うと気持が逸る。
長年大切にしてきた花蓮を奪った男はどんな奴なのだろうか。
どんなに自分より長けた男であっても、憎しみで殴ってしまいそうだった。
鈍色のドアが軋むように動き、スニーカーが顔を出す。
(花蓮……!)
会えた嬉しさと緊張で心臓が跳ねた次の瞬間、彼女の腕に抱かれた物に目が釘付けになった。
ベッドに押し倒し、桜色の唇に貪り付きたいと何度妄想したことか。
(花蓮が俺を裏切っただって……?)
清い関係を貫いてきたとはいえ、何年も付き合っていれば性格くらいわかる。
しかし、居なくなる前の何カ月かは、彼女の行動を疑い不安になることがあった。
100パーセント信じることが出来ず疑心暗鬼になっていたのは否めない。
(花蓮に隠し事があった?)
デート中に誰かと連絡をとっていたり、自分の知らない予定が増えた。
詳しく聞こうとしても視線を逸らし、話しを濁すのはそういえば花蓮らしくなかった。
信頼していたから問い詰めることもしなかったが、実は、他に男を作っていたということか?
(自分を愛してくれていると思っていたのに)
他の男と逃げたと聞かされたときの悔しさと絶望を思いだして、拳を握りしめた。
「なにかの……間違いなんだ……」
仕事ばかりで会えなかったのも、すべてはふたりの未来の為。それがすべて無駄になったとわかって恨んだ時期もあったが、やはりなにかの間違いだと思い直した。
せめて、本人の口から説明をうけるべきだ。
思いに耽っていたとき、刺すように見つめていた花蓮の部屋の玄関ドアが動いた。
四階建てのアパートの、一階の真ん中の部屋だ。
「せめて最上階の角部屋にするべきなのに、なんだってあんなところを選んだんだ……」
自分ではない男と暮らす家とはいえ、とうとう会えるのかもと思うと気持が逸る。
長年大切にしてきた花蓮を奪った男はどんな奴なのだろうか。
どんなに自分より長けた男であっても、憎しみで殴ってしまいそうだった。
鈍色のドアが軋むように動き、スニーカーが顔を出す。
(花蓮……!)
会えた嬉しさと緊張で心臓が跳ねた次の瞬間、彼女の腕に抱かれた物に目が釘付けになった。