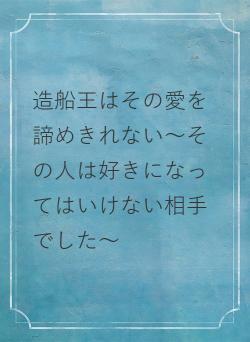転ばないようにスニーカーを履き、動きやすいように毎日パンツスタイルだ。洋服は古着。顔はノーメイク。
最近は、日焼け止めさえ塗るのを忘れる日もある。手入れをする暇のないパサついた髪はひとつにまとめただけで、なんの飾り気もない。
与えられたハイブランドのワンピースを、なにも考えずに日替わりで着ていたあのころとは違う。
食事も、掃除も洗濯も、家で雇っているお手伝いさんがやってくれ、親のお金で美容や遊びを楽しめていたころとは雲泥の差であった。
見た目を取り繕えないことを恥ずかしく思ったが、すぐにそうじゃないと思い直した。
―――今の暮らしを誇っている。
そして歩那との生活は幸せだ。精一杯やっている今を、恥じることなんてない。
昴の話し方から推測すると、花蓮は家を捨てて駆け落ちしたとでもなっているのだろう。香ならば、ないことまで尾ひれをつけて悪く伝えるに違いない。
歩那は駆け落ちし、できた子供。
それもまた真実だ。
「仕事ばかりにかまけていて、俺がふがいなかったことも承知している。けれどまさか、正式な婚約を目前に逃げられるとは思っていなかったけど」
昴ははっと空気を漏らし口元を歪めた。
こんな顔をさせたかったわけじゃない。
迷惑をかけたいわけでもない。
胸がずくんと疼く。
真実をぶちまけてしまいたい。
夢にまで見た愛しい人を目前に、決意が揺らぎそうになる。
(違うの。本当は、わたしはずっとあなたを愛していて別れたくなどなかった。でも、どうしても……)
花蓮は一度乾いた唇を舐め、気持ちを落ち着かせてから答えた。
最近は、日焼け止めさえ塗るのを忘れる日もある。手入れをする暇のないパサついた髪はひとつにまとめただけで、なんの飾り気もない。
与えられたハイブランドのワンピースを、なにも考えずに日替わりで着ていたあのころとは違う。
食事も、掃除も洗濯も、家で雇っているお手伝いさんがやってくれ、親のお金で美容や遊びを楽しめていたころとは雲泥の差であった。
見た目を取り繕えないことを恥ずかしく思ったが、すぐにそうじゃないと思い直した。
―――今の暮らしを誇っている。
そして歩那との生活は幸せだ。精一杯やっている今を、恥じることなんてない。
昴の話し方から推測すると、花蓮は家を捨てて駆け落ちしたとでもなっているのだろう。香ならば、ないことまで尾ひれをつけて悪く伝えるに違いない。
歩那は駆け落ちし、できた子供。
それもまた真実だ。
「仕事ばかりにかまけていて、俺がふがいなかったことも承知している。けれどまさか、正式な婚約を目前に逃げられるとは思っていなかったけど」
昴ははっと空気を漏らし口元を歪めた。
こんな顔をさせたかったわけじゃない。
迷惑をかけたいわけでもない。
胸がずくんと疼く。
真実をぶちまけてしまいたい。
夢にまで見た愛しい人を目前に、決意が揺らぎそうになる。
(違うの。本当は、わたしはずっとあなたを愛していて別れたくなどなかった。でも、どうしても……)
花蓮は一度乾いた唇を舐め、気持ちを落ち着かせてから答えた。