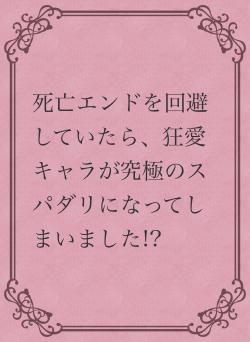最近、学園では不穏な噂が飛び交っている。
「婚約者を差し置いて、カイル殿下の隣にはいつも幼馴染の公爵令嬢がいる。ノエル様のことはどうされる気なのだろうか」
幼馴染の公爵令嬢とは、王妃陛下の生家であるローレンツ公爵家の令嬢、ドロテア様のことだ。
王太子殿下を含め、幼い頃から交流があるカイル殿下とドロテア様は、お互い気心が知れているからか学内でもよく一緒にいる。
ドロテア様はふた月前まで隣国に留学していたこともあり、学園での生活に慣れていない。王妃陛下からしばらく面倒を見てほしいと頼まれたそうなので、彼女と親しいカイル殿下が親切心からいつも一緒にいてもそこまで不思議な話ではなかった。
ところで――私、ノエル・ヴォルガノスは、現在学園の裏手に造られた庭園に足を運んでいる。
学徒の憩いの場としても利用されている庭園の隅……小川のせせらぎを耳にしながら視線を向けると、木陰に二つの人影があった。
後ろ姿でもすぐに分かる。
あの場に立っているのはカイル殿下。そしてカイル殿下のシルエットと重なるようにいるのは――ドロテア様だ。
「あ、あの……ノエル様……」
隣に立つ友人のミーナ様が青ざめた顔をしている。
無理もない。おそらくミーナ様の目には、二人が顔を近づけてキスをしているように映っているだろうから。もちろん私だけ景色が違うということはなく、同じものが見えている。
「ミーナ様、行きましょう」
「へっ!? で、でもノエル様!」
小声で慌てるミーナ様の手首を掴んで私は来た道を引き返す。
あんな場面を目撃して、どう行動をとるのが正解なのか分からないけれど。二人の間に割って入る勇気が私にはなかった。
(ああ、不甲斐ない……崇高な精神を掲げるヴォルガノスの者が、逃げるしかできないなんて)
あれは、いわゆる……横恋慕というものなのだろうか。浮気……とは違う。婚約はしていても結婚はしていないし。
(そもそもお二人が互いに想い合っているのなら、横恋慕という言葉も少し違う気がするけれど)
なんだか、胸の奥がつきんと痛くなる。
息苦しさもほんのりと感じて、私は学内に入ったところで歩みをとめた。
「ミーナ様、強引に手首を掴んでしまい申し訳ございません」
「いえ、それは全く構わないというか、むしろ光栄といいますか」
「それと、先ほど見たことは忘れてくれませんか?」
「えっ」
「むやみに話が広がって、騒ぎを大きくしたくはないので……」
「で、でも。そもそも、おかしいです! 殿下とドロテア様があんなことっ」
「ただ、学園を案内していただけかもしれないですから」
「案内といっても、ドロテア様が学園に入ってからもうすぐでひと月です! 今さらどこを案内すると……いえ、まずなにかの間違いですよ!」
気遣ってくれているのか、ミーナ様は見たものは勘違いかもしれないと言ってくれる。でも、握りしめた両手は震えていて、同様の色を隠すことはできていない。
私はくしゃりと泣きそうな顔のミーナ様の肩に手を置き、安堵させたくて笑顔を浮かべた。
「では、落ち着いたら……殿下に聞いてみます」
「はい! 絶対に、絶対に目にゴミが入って見てもらっているの図だったに違いありませんから!!」
私の友人ミーナ様は、そう強く意気込んだ。
彼女は王都に構える大きな商会長の一人娘であり、在学中も商業を手広く学んでいる影響か、少し気の強いところがある。そんなところも魅力なのだけど。
今回は、そんな彼女の性格にすごく救われた気がする。
……しかし、それから三週間が経ってもカイル殿下を問いただすことができなかった。
***
「ノエル、お前……どうかしたのか?」
ヴォルガノス侯爵邸敷地内に建設された騎士団訓練場。
我が家門は建国より王国の剣として名を馳せる騎士の一族であり、私も幼少から剣を手にしていた。
並行して貴族の子女としての嗜みを一通り学んでいるものの、頭をすっきりさせたいときは無我夢中で素振りをしている。
今日も学園から帰宅したあと、個人の訓練場で剣を振っていた。
その最中に一番上の兄、エリック兄様に背後から声をかけられた。
「エリック兄様、おかえりなさい。いつからそちらに?」
「5分ほど前からだな。珍しいな、ノエルが気配の察知に遅れるとは……って、なんだよその手は」
「手?」
私はようやく気がついた。剣を握る両手から、血が滲み出ていることに。
エリック兄様は私の手を取ると、眉を顰める。
すぐに訓練場の外に控えていた騎士の一人に救護箱を持ってくるように指示を出し、救護箱を受け取るとエリック兄様は処置を始めた。
「一日や二日でできたものじゃないな。一体いつから無茶な振り方をしていた?」
「それは……えへへ」
「その顔、言う気ないだろ」
三週間前、学園でカイル殿下とドロテア様の逢瀬を目撃してからだと、素直に言うことができない。
しかし、いつまでも一人で悶々としていたところで仕方がないので、それとなくエリック兄様の意見を聞いてみることにした。
「エリック兄様、例えばの話としてご意見をお聞きしたいのですが……カイル殿下と婚約解消をするというのは、現実的に可能でしょうか」
すると、エリック兄様は鳩が豆鉄砲を食ったような顔をする。
声を荒らげそうになっていたが、すんでのところでぐっと堪えていた。そして額に手を当てると、それは深い息を吐いた。
「………………あの意気地無し」
「兄様?」
「ああ、いや。なんでもない。それよりノエルは婚約解消をしたいということか?」
「そのほうが、カイル殿下のためになるかと思ったんです」
「やっぱり、何かあったんだな?」
「…………い、いいえ?」
「誤魔化しが下手すぎる」
無意識に視線を逸らすと、軽く指で額を突かれた。
その後、両手の手当てが終わりエリック兄様に再び尋ねられる。
「何があったんだ。兄様に言ってみろ」
「誰とは言いませんが……カイル殿下には、慕っている女性がいるかもしれなくてですね」
「な……は!? 女性って、誰のことだ!?」
「誰とは言いませんと先に伝えたじゃないですか」
「いや、まず、そんなことがあるはず……あり得ないだろう? カイル殿下だぞ」
そう言われても、あの場を見たあとではあり得ない話ではない。
どうしてエリック兄様がこんなにも取り乱しているのか私には分からなかった。
「エリック兄様は、最近カイル殿下とお会いしました?」
「……ああ。変わりない様子だったが」
「そうですか」
「そもそも、何がきっかけでカイル殿下に慕っている女性がいると、そう思ったんだ」
いくら兄とはいえ、カイル殿下の沽券に関わることなので、軽々しく打ち明けることができない。
私室で話すならまだしも、ここは屋外。誰が聞き耳を立てているのか分からないのだ。
「うーん、そうですね。色々と思うところがありまして」
笑って言葉を濁す。
正直に胸の内で抱いていた気持ちを言うのなら、私はカイル殿下の婚約者としてふさわしいのかと、考えることが多々あった。
家門を考慮して定められた婚約に本人同士の意思はなく、貴族に生まれたからには当然の義務だった。
婚約者になってからというもの、カイル殿下との交流の場を設けられる機会が増えたが、私をどう思っているのか本人から聞いたことはない。
(最初はもう少し、和気あいあいと話していた気がするのに。いつの間にかカイル殿下は私の前で常に張り詰めた顔をされるようになった)
思わずため息をついてしまう。
目を落とすと、包帯で巻かれた自分の手が見える。
「こんなに手をぼろぼろにしてしまって、淑女としてみっともないですね。カイル殿下も……」
今さらという気もするけれど、カイル殿下は剣を扱うような女を好まないのかもしれない。女性らしさという面では、私はきっとドロテア様に敵わないだろう。
「こら、ノエル」
私がこぼした弱音を、エリック兄様は許さなかった。
「お前の我慢強さ、忍耐強さは騎士道においては美徳だ。だけどな、今は少し悪い方面に出てしまっている。相手の意見を聞かないうちに自己完結してはいけない」
「ごめんなさい」
「謝る必要はない。ただ、そうだな……一度殿下と話してみてはどうだ」
「カイル殿下と……」
「ああ。ちょうど明後日は殿下との約束の日だろ。ゆっくりティータイムでもしながら、御心をたずねるんだ」
「ま、真正面からですか」
たしかに思い悩んでいたところで現状が変わるわけではない。
ここは当たって砕けろの勢いで胸の内を聞いてみよう。
(カイル殿下は、いつも私に誠実に接してくださっていた。恐縮してしまうほど沢山届く贈り物の数々、口数は少なく淡白だけれど二人きりの茶会は毎回出席してくれて、真摯に向き合ってくれる)
今まで蔑ろにされたことなど一度もなく、向き合えばきっと答えてくださると信じている。
それが、どんな理由だったとしても。
たとえば「好きな女性がいる」と言われたとしても。カイル殿下から直接打ち明けられる気持ちであれば、私は潔く受け入れたい。
(潔く、ヴォルガノスらしく)
ちなみに、当初の質問である婚約解消は可能なのかという話だが、できなくはないらしい。
自分で聞いたのに、いざカイル殿下と婚約解消することになったら……と想像したら、心臓がぎゅっと掴まれたように苦しくなった。
***
昨日はエリック兄様と話せたおかげで決心がついた。
そして、明日はカイル殿下とのお茶会。婚約者同士の交流を図ることを目的としたものなので、二人きりでゆっくり話すことができる。
「ノエル」
明日のことを考えるとどうしても落ち着かない。
気分を変えるため、昼休憩の時間を利用して学園内をあてもなく歩いていたら、中庭に出たところでカイル殿下に声をかけられてしまった。……隣には、当たり前のようにドロテア様がいる。
なんだかんだこの三週間、顔を合わせづらくて接触を避けていたのに、どうしてこうもタイミング悪く鉢合わせてしまうのだろう。
「カイル、殿下。ドロテア様、こんにちは」
「ごきげんよう、ノエル様」
会釈すると、ドロテア様はふんわりと微笑んだ。
「君の顔を見るのは、久しぶりな気がする」
「そうですね。ええと、お元気ですか?」
「ああ。……君は?」
「はい、私も特に変わりなく」
「そうか。その手は――」
「まあ、ノエル様! どうなさったの、この手!」
突然、ドロテア様に手首を掴まれ、手のひらを上向きにされる。
包帯が巻かれた手を大袈裟に晒され、私は驚いて言葉を失っていた。
「女性の手がこんなに傷だらけなんて、一体どうしたのですか?」
「これは、剣を振っていてできたものです」
「剣? ヴォルガノス侯爵家は、女性が剣を取らねばならないほど人材が不足しているの?」
「……、そんなことはありません」
すべての発言に敵意が含まれているように感じた。
ドロテア様が不憫そうに私を見るたび、周囲を歩いていた学徒たちに「なんだなんだ?」と注目を浴びてしまう。
「どちらにせよ淑女の手がこんなに汚れていては、社交界の場で婚約者であるカイル様に恥を欠かせ――」
「やめてくれないか、ドロテア嬢」
「えっ、カイル様?」
「ノエルが俺の婚約者だと分かっていての発言なのだとしたら、不愉快極まりない。この手も、今すぐに離せ」
私の手首を押さえ込んでいたドロテア様の腕を、カイル殿下は冷ややかな目をして掴む。
そんなことを言われるとは思っていなかった、と言いたげな顔で瞠目するドロテア様は、取り繕うように発言する。
「ど、どうしてなのカイル様。あなたは彼女をよく思っていないのでしょう。だからわたくしは、」
「――は? 誰がそんな馬鹿げたことを言った?」
「それはっ」
「君はノエルの手を汚れていると言ったが、俺は気高く美しいと常日頃から思っている。恥だと感じたことも一度だってあるものか」
驚いた。まさかカイル殿下の口から乱暴な「は?」を聞くことになるとは。そしてこんなに饒舌に語る姿も。ドロテア様もびっくりして後ずさってしまっている。
私と話すときのカイル殿下は、いつも気性を荒らげることはなく、何をするにもクールな人だったから。
そんな人が目をカッと開いて表情を崩しているので、まじまじと見てしまう。
その視線に気がついたカイル殿下は、我に返ったようにバツの悪い顔をしていた。
「あの、カイル殿下……」
言いかけたとき、私たちの頭上から悲鳴があがった。
見上げて、鉢植えが目に入る。
「殿下!」
「ノエル!」
その瞬間、同時に声があがった。
私はカイル殿下をその場から退けようと体を押し、カイル殿下は私を落ちてくる鉢植えから守るように腕を引く。
結果、二人分の重心が後ろに傾き、私たちは揃って中庭の芝生に倒れ込んでしまう。
ドサッという衝撃音のあと、私は急いで上体を起こした。
カイル殿下に怪我はないか確認したかったから。
「痛っ!」
カイル殿下の体を避けるように地面に両手をついたけれど、昨日の今日で癒えていない手のひらの傷が悲鳴をあげる。
ゆえに再び、カイル殿下の体に覆い被さるような形で密着してしまった。
「カイル殿下、お怪我はありませんか!?」
「………………ダメだ、心臓がもたない」
「心臓!?!?」
ひゅっと背筋が冷えていく。背中から倒れ込んでそのまま強く打ち付けてしまったのだろう。
しっかり呼吸はできているのか、今度こそカイル殿下の体から退いて確かめる。
「で、殿下、顔が」
「頼む、見るな」
「いえ見ます。ダメです、顔が赤いです。どんな症状なのか私には判断がつきません、すぐ医務室に」
「待てっ……!」
立ち上がろうとすると、カイル殿下は私の手首を掴んで行動を制止してくる。
一体どうしてとカイル殿下に目を向ければ、顔がさらにブワワッと赤く染まった。
「ノエル、ひとまず離れて差しあげなさい」
「ハルト兄様……?」
戸惑っていると、学園在学中の二番目の兄、ハルト兄様がやって来てカイル殿下から距離を取らせた。
「ハルト兄様! カイル殿下のお体を診てください、どこか強く打ってしまったようで」
「まあまあ、落ち着きなさい」
ハルト兄様は学園の備品室を私物化し、研究に没頭するためよく引きこもっているが、王室医療班顔負けの知識と腕を持っていた。ちなみに今年で二度目の留年となっている。
ハルト兄様は「まず落ち着きなさい、ほら飴だよ」と包装された飴玉をくれる。このとおりマイペースな性格なのだが、怪我人や病人に対しては真摯に向き合うことのできる立派な人だ。
それなのにいまだ天を仰いでいるカイル殿下の容態を確かめることはなく、ちらりと視線を投げるだけだった。
「殿下、ご無事ですよね?」
「……大丈夫だ」
ハルト兄様の声掛けで、のっそりと起き上がったカイル殿下。顔を片手で隠しているのでどんな表情をしているのか分からないが、やっぱり耳まで真っ赤になっている。
不意に覆った指の隙間から目が合う。ああ、首までも真っ赤に。
カイル殿下は挙動不審な動きを見せ、この世の後悔をすべて煮詰めたような深いため息をついた。
***
回想 (カイル)
俺には、目に入れても痛くないと本気で思っているくらい大切な女性がいる。
その女性こそ、ノエル・ヴォルガノス侯爵令嬢。
7歳の誕生日に婚約した由緒ある騎士家系の令嬢だ。
初対面のときは「控えめだが笑顔が可愛い子だな」という印象が強く、好感は持っていても異性としての意識はまるでなかった。
当人同士の意思がない婚約だったが、物心ついた時から王侯貴族の婚約とはそういうものだと学んでいたので特に支障もなく、ノエルと出会ってあっという間に一年が過ぎた。
交流も深まってきた頃、俺は初めて城下町に出向くことなった。平民に偽って王都の様子を見聞きし、それを文書にして陛下に提出する。王子としての課題のようなものだ。
そこでばったりノエルに会った。
平民の姿をしている自分に一目で気づく洞察力は、さすがヴォルガノス侯爵家の人間だと思った。
せっかくなので「どこかおすすめの場所はあるか」と聞いてみると、迷った末にノエルが案内したのは武器屋だった。
ノエルは生き生きしながら店頭にある剣を見て回っていた。店主の男はまるで孫を見るような目をしており、彼女が頻繁にここに通っていることが容易に窺えた。
「まだ体がちいさいのでどれも扱えないのですが、おおきくなったらお父様やお兄様たちのようにブンブン振りまわすのです」
「ブンブン振り回すのか」
王城で会うときと違って、慣れ親しんだ場所だからか、いつもより硬さがとれた話し方。ノエルの素を知れたような気がして嬉しくなった。
しかし案内先に選んだ場所が武器屋とは、またしてもさすがヴォルガノス侯爵令嬢……と思ったが、店の反対側に位置したドール人形やぬいぐるみが置かれる可愛らしい雑貨店に羨望の眼差しを注ぐノエルを見て、また印象が変わった。
幼い貴族の女子なら特に欲しがるような物で、ノエルも隠してはいるが気になっていたのだろう。
しかし、ノエルがそういった類のものを所持しているところを見たことがなかった。
欲しいのかと聞いてみると、ノエルは珍しくもじもじと恥ずかしそうにして首をふるふると横に動かした。誤魔化すのはあまり上手くない子のようだ。
「わたしには、にあいません。この前も、からかわれました。女が剣をならうなんてって。怪力女って」
「怪力女……」
「だから、いいのです。かわいいものは、かわいい女の子が持つべきです。絵本のお姫様みたいな」
ヴォルガノス侯爵家は、威厳のある騎士家系。母親の亡きあと、父親や兄たちから可愛がられていると聞いていたが、ノエルは家門の雰囲気を察して遠慮していたみたいだった。
もちろん武器に目を輝かせるのも本心なのだろうが、可愛い品物を羨ましく思うのも同じく本心なのだ。
だから俺は「今の自分に一番価値のあるものを買ってきなさい」という陛下の課題の一つとして預かっていた資金で、何かノエルに贈り物をしようと考えた。
ノエルが気になっていたのは白うさぎのぬいぐるみだった。
すぐに買って店先で渡すと、ノエルは大きな瞳をさらに広げて何度もまばたきを繰り返していた。
可愛い。胸が熱くなって、その顔が見られて本当に良かったと心から思った。
そうこうしてるうちに有意義な散策も終わりに差し掛かる。
そんな時、宝石店で盗みを働いた男が広場まで逃げてきて、俺の方に走ってきた。
「邪魔だどけ!!」
男はナイフを俺に振り下ろした。
少し離れたところから見守っていた騎士たちが、こちらに駆けてくるのが分かった。
しかしそれよりも早く動いたのは、ノエルだ。
「殿下っ」
ノエルは俺の肩をグイッと引いて抱き寄せると、体のどこかに仕込んでいた短剣で男のナイフを受け止めた。
男は武器もろくに扱えない素人のようで、ノエルは器用にナイフの持ち手を弾くと、それを遠くに蹴飛ばしてみせた。
その後、すぐに騎士によって捕らえられた男は連行され、事なきを得たのだが。
「カイル殿下、おケガはありませんか……っ」
「大、丈夫」
ありがとう、と言いたかったのに口が動かなかった。
頭から足の指先に雷が落ちたような感覚に身動きが取れなかったのだ。
自分よりも幼く、か弱く見えていた少女。
それが一瞬で顔つきが変わった。
凛々しく、勇ましい身のこなしと横顔を目にしたとき、あんな状況だったにも関わらず俺はノエルに見惚れていた。
ゴーン、ゴーンと、夕刻を知らせる時計塔の音が響く。
そして同じくらいの激しい音が俺の心臓から鳴っていたことに気づいた。
俺がノエルを本格的に意識しだしたのはその時からだった。
このまま話が終わるなら、初恋を知らない少年が初恋を知った可愛らしい思い出話である。
だが、予想外の事態が俺に中で起こっていた。
「カイル殿下、お顔が赤いです。熱があるのかも……」
異変に気づいたのは、町でノエルに救われた日から一週間後のこと。定期的に開かれるノエルとの茶会の席である。
「熱なんて、ないはずだが」
「でも……」
むしろ絶好調だった。
その日はノエルに会えるということで、茶会を楽しみに剣技の訓練でも浮かれていたくらいには。
だが、ノエルに指摘されて鏡を確認した俺は驚愕した。
(本当に顔が真っ赤じゃないか! それになんだ、この締りのない表情はっ……)
まさかこんなにも自分が腑抜け面をしているとは思わず、それをノエルに晒していたかと思うと羞恥心で倒れそうだった。
(戻れ戻れ! 目、口、頬、にやけるな! …………戻らないだとっ!?)
こんな格好のつかない婚約者をノエルに見られるわけにはいかない。俺は体調不良を理由にこの日の茶会をすぐに切り上げることにした。
ノエルは俺のことを心配して不安そうにしていたが、また次の茶会を約束して屋敷に帰らせた。
そしてノエルがいなくなったあと、俺はその場で意識を失った。
大至急、王室医療班が招集されたが、体に問題はなく、むしろ健康優良児だという。
(動悸が治まらない、胸が苦しい……体が熱い。もしやこれは何かの病なのでは)
原因がわからず寝室で何度も寝返りを打ちながら苦しんでいると、兄のレイナードが見舞いにやってきた。
隣には、ノエルの兄であるエリックとハルトがいた。どうやら三人で遊んでいたらしい。
三人の兄たちは、ここ数日の俺の様子と、一週間前に起こった町での出来事、そして俺の状態を考慮してある診断を下した。
「カイル、それは恋の病だよ。しかも重症だ」
なるほど、恋の病。
どうりで王室医療班が突き止められないわけである。病は病でも、これは何たる病違い。
「うちのノエルは可愛いから、仕方がない」
「そうですね。むしろ重症で済んでよかったです」
「君たち本当に兄バカだね」
弟の初恋を知ってめでたいことだと頷く兄、そしてさすがは妹だと賞賛するエリックとハルト。
まさかこの三人も、ここから10年も俺が拗らせるとは思っていなかっただろう。俺も思わなかった。
***
明後日は待ちに待ったノエルとの茶会だ。
ここ最近は、ドロテア嬢が学園生活に慣れるまで手助けしてやって欲しいと母に頼まれた手前、案内などで二人きりになることが多かった。
(ノエルは元気にしているだろうか。タイミングが合わないのか、学園で見かける機会もなかった)
学年が一つ違っているからというのもそうだが、ドロテア嬢と行動を共にするようになってめっきり減ってしまった。
もういい加減、学園に慣れてきた頃だろうし、いつまでも俺の隣にいては友人も作れないのではないだろうか。
ドロテア嬢は昔から自己中心的なところがある。母からも扱いには気をつけろと言われていたが、まさか婚約者がいる身の男にここまでくっ付いてくるとは思わなかった。
これ以上、一緒にいてノエルに変な誤解をされたら立ち直れない。明日にでも「もう俺を頼るな」とはっきり告げてしまおうと、考えていた。
「ところでカイル殿下、慕っている女性がいるというのは本当か?」
「は?」
その日の晩、急に兄とエリックが部屋に訪ねてきた。久しぶりに夜酒でもどうかと言われ、しばらく付き合っていたのだが。
エリックからおかしな質問が飛んできて、しばらく思考が止まった。
「…………ノ、ノエルの話か?」
「やはりこれは白だな」
「私もそうだと思うな。いまだにノエル嬢と手も繋げないような子が、不貞疑惑だなんてね」
「一体それは、どういうことです兄上」
情報源がどこかは教えてくれなかったが、なんでもエリックが小耳に挟んだという話を元に兄が諜報班を使って調べさせたところ――どうやら学園では今、俺とドロテア嬢の仲が疑われているらしい。
(いや待て、ドロテア嬢が学園に慣れるために行動を共にしていただけで、どうしてそうなるんだ。誤解されないようそれとなく友人に協力を仰ぎ"あくまでも案内と説明"であると分かりやすく声を大に話させて周囲に知らせたはずだろう!)
なにかの間違いだと思いたかったが、諜報班の情報はよっぽどの事がない限り正確である。
「どうやら思った以上にドロテア嬢はしたたかな女性に成長したね。周囲に誤解を生む際どいラインでお前とのことを吹聴していたようだ。これに関しては後でちょっとした厳罰を受けてもらおうかな」
「まさかノエルの耳にも……」
「入っているだろうね。学園の生徒が噂しているのだから、婚約者であるノエル嬢が知らないわけない。困ったことだね」
「その割に、なぜ楽しそうなんですか兄上……」
「楽しいというか、自業自得じゃないか。初めは激しい動悸が続くあまり失神してしまうからお前のペースで進めるように見守っていたのに、もう10年になる。時間はたっぷりあった、だがお前は一定の距離から分かりづらく愛でるばかり。ノエル嬢もいい加減、愛想を尽かしているんじゃないか」
兄の容赦ない言葉が重くのしかかってくる。
間違いない。すべてその通りなのだ。
ノエルに対する想いを自覚してからというもの、彼女を前にすると自分が自分ではないみたいに言うことを利かなくなる。
この歳になってようやく平静さを保てるようにはなったが、気を抜くと表情は緩むし、目が合えば頬が熱くなる。エスコートをしたくともこんな状態ではノエルに不信感を抱かせてしまう。
ノエルは可愛い。すべてが可愛い。総じて可愛い。
普段は騎士然として周囲を惚れ惚れとさせる美しい立ち居振る舞いをしながらも、実は同性同士の友人との距離感に掴めず日々試行錯誤しながら接しているところとか。
崇高な精神を掲げるヴォルガノス侯爵家の一人として、今も剣の修練を欠かさず、たまに豆ができると気にして隠そうとしているところとか。
身内相手で素の状態だと少し言動が抜けていたり、兄たちの前で見せる妹特有の幼さを全面に発揮したり(羨ましい羨ましい)、かと思えばヴォルガノスとしてしっかりしなければと気を張って努力する姿とか。挙げたらキリがない。
「こんな、こんな……婚約者の一挙一動に内心可愛いと悶え、異性として意識しまくっている男なんて気持ちが悪すぎるッ!!」
「今更すぎるよね」
「本当にな」
兄とエリックは呆れた目をしている。
ああそうだ。これはすべて俺の削り削られ極限に小さくなったなけなしのプライドだ。
こんな自分を見せてノエルに失望されたくない、嫌われたくない、ガッカリさせたくない。そんな思いから10年も分厚い仮面を被って彼女と過ごしている。
もうこの病は手遅れなのだ。うまく付き合っていくしかないことも理解している。だが、いつも躊躇ってしまう。
「しょうがないな。婚約者愛が凄まじくも情けない可愛い弟に、一つ兄がアドバイスしよう」
「アドバイスとは」
「お前がいくらノエル嬢を想っていようとも、相手に伝わらない愛情なんぞに何の価値もない」
「ぐ、」
「いいかい、お前がこの先もノエル嬢を手離したくないと願うなら、心臓が止まってでも好意を伝えるんだよ」
兄は本当に心臓が止まるとは思っていないのだろうが、それぐらいの意気でノエルと向き合えと言っているのだ。
そして俺は、覚悟を決めた。
そんな矢先に学園で起こった事態により、言い出す前にノエルに恥を晒してしまう。
鉢植えが落ちてきたときは守ることに必死で腕を掴んでいたが、そのまま体勢を崩してノエルに押し倒される形で芝に転がった。
直視できないが、慌てている気配と声を聞き、怪我をしていないようで安堵する。
ノエルに触れて心臓が止まることはなかったものの、呼吸をするので精一杯だった。
***
次の日、私はカイル殿下と城内の東屋で向き合っていた。
いつものように二人分のティーセットが用意されており、紅茶を注がれてからしばらく経ったカップはすっかり冷めきっている。
緊張からお互い何も喉が通らず、私は席に座ってからずっとカイル殿下の話を聞いていた。
(カイル殿下に、そんな体質が)
私の顔を見ると動悸が激しくなる、だなんて。
朧気に覚えている。子供の頃、出先で平民を装うカイル殿下と出くわして、しばらくお店を見回ったあとに、盗みを働いた男からナイフを振り下ろされそうになったことがある。
その時からカイル殿下は体に異常を感じるようになったのだそうだ。
(それは、つまり)
「トラウマが……当時の記憶を思い出すことによって、心身的に負担がかかっているということですね」
「……うん?」
「私を見て顔が熱くなったり、心拍が早くなるのも、症状の一種ということなんですよね?」
なんだか申し訳ない。私という存在が、カイル殿下の状態異常を引き起こしてしまう。
納得がいった。カイル殿下が私の前でいつも気を張り詰めているのも、目を合わせないようにしているのも、そのせいだったのだ。
だとしたら私は、今のカイル殿下にとってとんでもない毒なのではないだろうか。
そう思うと、膝の上で握っていた手の温度がすっと失われていく。
「……では、やはり。私は、カイル殿下のそばにいては、いけないということなのでしょうか」
「いや、違う。違うんだ。そういうことではなくて」
「……?」
「すまない。ノエルがそう考えてしまうのも俺のせいだ。これは君に問題があるのではなく、俺の心情の問題というか……いや、症状の原因に君が関わっているのは間違ってないんだが」
煮えきれない反応を見せていたカイル殿下は、自分を落ち着かせているのが一度息を吐く。
そして、決意に満ちた目をこちらに向けてくる。
「ノエルのことが、好きなんだ。好きだからこうなっている。10年前から、変わらずに」
「……え?」
「君を失望させるのを恐れて黙っていた。でも、本当なんだ」
私が好きで、起こってしまう症状。まだピンとはきていない。
固まっていればカイル殿下が小声でボソッと「兄いわく恋の病とも言うらしい」と言った。恥ずかしさから半分ほど背けられた顔が赤くなっている。
「あの、では……ドロテア様は」
「……やはり君の耳にも入っていたんだな。ドロテア嬢はあくまで母からの頼みで短期間共に過ごしただけで、本当に何もない」
「三週間前の、キスも、見間違いですか?」
「……なん、だって?」
訳が分からない顔をしているカイル殿下に、私は見たままの説明をした。
カイル殿下はがくりと項垂れ、そして教えてくれた。
「あの日は、ドロテア嬢が小川付近で落し物をしたと言うので付き合ったんだ。結局見つからず、帰り際に片目を痛めたようで、ゴミが入っていないかと確認を求められた。おそらく、それだと思う」
本当にミーナ様の言った通りだった。
懸命に弁明するカイル殿下の姿に偽りはなく、本当にただそれだけのことだったのだろう。
ああ、なんだ、そうだったんだ。
「……ノエル?」
その時、テーブルを挟んだ先にいるカイル殿下が、がたりと音を立てた椅子から立ち上がった。
動揺の色を浮かべる様子に、どうしたのかと思えば。
「泣いて、いるのか?」
「泣いて……?」
意表を突かれて瞬きをすれば、目から涙がこぼれるように落ちる。
ぽちゃん、とカップの中に吸い込まれて弾かれた水滴に目を向けると、また涙がぽろぽろと出てきた。
「すみ、ません。まさか涙が出るとは、思っていなくて。きっと、安心したのだと思います。もしもカイル殿下がドロテア様をお慕いしているのなら、婚約解消も視野にと――」
「婚約解消……っ!?」
次の瞬間、カイル殿下は余裕のない面持ちのまま目の前にやってきた。
私の座る椅子の背もたれに右手を置き、左手は頼りなく宙をさ迷っている。
もしかすると、涙を拭おうとしてくれているのかもしれない。
「婚約解消だなんて、俺は生涯ノエルだけだ。ああ……すまない、ノエル。本当にすまない。君をこんなに泣かせてしまうなんて最低だ。気持ち悪いと思われても素直に話すべきだった」
「私がカイル殿下を気持ち悪いだなんて、思うわけないです」
「…………。それは、どうだろう」
カイル殿下の顔が引きつっている。
本当の彼はこんなにも表情豊かな人だったのだ。いや、最初の頃は確かにそうだった。いつの間にかクールな人だと思い込んでいたけれど、実際の彼はこんなにも。
「……殿下」
私は未だに宙をさ迷っていたカイル殿下の左手に触れる。
びくりと肌が震えるのを感じて、けれどゆっくり両手で包み込んだ。
「私の手を、気高く美しいと言ってくれ、ありがとうございます」
触れた左手が熱を持ちはじめる。
目が見開かれ、口元があわあわと動き、頬が紅潮していく。
本当だ、顔がまるで染められた花のように色づいている。
「……言っただろう。ダメなんだ、君を見れば見るほど、触れれば触れるほど、格好がつかなくなってしまう」
だけど、カイル殿下は私の手を振りほどくことはなかった。
なんて可愛くて、愛おしい姿なんだろう。
「カイル殿下、これからリハビリしませんか?」
「リハビリ?」
「こうして、少しずつ目を合わせる時間を長くしていって、手を繋いで、私に慣れてください」
「……慣れるかな」
始める前から自信がなさそうなカイル殿下に、私は笑みを浮かべる。
「慣れてくださると、嬉しいです。私もこの先、ずっとあなたと一緒にいたいから」