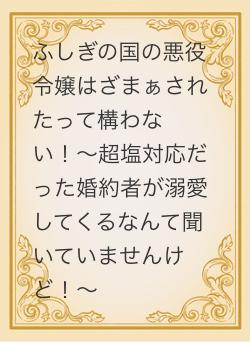マティルダはベンジャミンの言葉に首を横に振った。
「いいえ、違うのです……!わたくしがいなくなり二人は…皆は幸せになると思っていたので、予想と違っていて驚いていただけですから」
『マティルダにあんなことをして、幸せになれるはずないだろう?本当なら僕がこの手で跡形もなく消し炭にしてやりたいのに……』
ドス黒いオーラが漏れ出ているベンジャミンを諌めるようにしながらもマティルダは苦笑いを浮かべた。
それにベンジャミンは心配していたが、マティルダはこの話を聞いてもガルボルグ公爵邸に戻ろうとは思わなかった。
貴族として窮屈な日々を送るよりも、ベンジャミンとのびのびと過ごす方が自分にはあっているとわかっていたからだ。
それによくよく考えてみると、マティルダが娘として可愛いからではなくて、まだまだ使えるから失うのは惜しいという解釈ができると思った。
(心配しているのは公爵家の未来とわたくしがどう利用できるか……とかなのよね)
マティルダが一番、恐れていることはベンジャミンが王家の思惑に巻き込まれて利用されてしまうことだ。
無茶な条件でもベンジャミンはマティルダのためなら飲んでしまうことだろう。
そうなることだけは避けなければならない。
「いいえ、違うのです……!わたくしがいなくなり二人は…皆は幸せになると思っていたので、予想と違っていて驚いていただけですから」
『マティルダにあんなことをして、幸せになれるはずないだろう?本当なら僕がこの手で跡形もなく消し炭にしてやりたいのに……』
ドス黒いオーラが漏れ出ているベンジャミンを諌めるようにしながらもマティルダは苦笑いを浮かべた。
それにベンジャミンは心配していたが、マティルダはこの話を聞いてもガルボルグ公爵邸に戻ろうとは思わなかった。
貴族として窮屈な日々を送るよりも、ベンジャミンとのびのびと過ごす方が自分にはあっているとわかっていたからだ。
それによくよく考えてみると、マティルダが娘として可愛いからではなくて、まだまだ使えるから失うのは惜しいという解釈ができると思った。
(心配しているのは公爵家の未来とわたくしがどう利用できるか……とかなのよね)
マティルダが一番、恐れていることはベンジャミンが王家の思惑に巻き込まれて利用されてしまうことだ。
無茶な条件でもベンジャミンはマティルダのためなら飲んでしまうことだろう。
そうなることだけは避けなければならない。