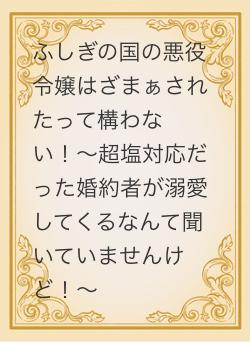「陳腐な理由ならば陛下から伺いましたが、マティルダが光魔法を使う令嬢を虐げた証拠はないどころか……周りの令息と令嬢達がマティルダを庇ってくれていますが、どう説明するおつもりですかな?」
「……っ」
「正当な理由がない限り、我々は今回のことを許すわけにはいかない。よってこれからは王家に協力するつもりはない」
「ガ、ガルボルグ公爵……!これは義務ですぞ」
「義務だろうがなんだろうが関係ないっ!娘を理由もなく国から追放しておいて国に尽くせだと?ならば我々はマティルダ同様にこの国から出ていきましょうぞ」
「ぐっ……!」
「他の雷魔法の使い手では精々、城の灯りをつけるくらいでしょうな。魔導具が使えなくなり魔石が流通しなくなれば民からの反発は免れないでしょうな」
父が顔を歪めてガルボルグ公爵を見た。
(も、もしそんなことになれば……国は!)
なんとしてもマティルダを悪にしなければならないとローリーは切り札を出す。
「し、しかしマティルダは魔法講師としてガルボルグ邸に来ていたベンジャミンという男と不貞行為を……っ」
「ありえませんな」
「なっ……!」
そう言い切ったガルボルグ公爵は顔色ひとつ変えることはなかった。
父は「やはりか」と呟いて額を押さえている。
「……っ」
「正当な理由がない限り、我々は今回のことを許すわけにはいかない。よってこれからは王家に協力するつもりはない」
「ガ、ガルボルグ公爵……!これは義務ですぞ」
「義務だろうがなんだろうが関係ないっ!娘を理由もなく国から追放しておいて国に尽くせだと?ならば我々はマティルダ同様にこの国から出ていきましょうぞ」
「ぐっ……!」
「他の雷魔法の使い手では精々、城の灯りをつけるくらいでしょうな。魔導具が使えなくなり魔石が流通しなくなれば民からの反発は免れないでしょうな」
父が顔を歪めてガルボルグ公爵を見た。
(も、もしそんなことになれば……国は!)
なんとしてもマティルダを悪にしなければならないとローリーは切り札を出す。
「し、しかしマティルダは魔法講師としてガルボルグ邸に来ていたベンジャミンという男と不貞行為を……っ」
「ありえませんな」
「なっ……!」
そう言い切ったガルボルグ公爵は顔色ひとつ変えることはなかった。
父は「やはりか」と呟いて額を押さえている。