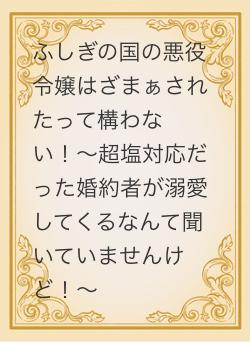しかし一向に町の明かりがつかないことにローリーは疑問に思い、ライボルトに問いかけようとしたところ、彼の額に玉のような汗が滲んでいることに気づく。
そして肩を荒く動かして金色の玉から手を離してしまった。
「お、おい!まだ町に明かりは戻っていないぞ!?もっと魔力を……」
「──わかっている!」
「ライボルト……?」
感情を荒げたライボルトの顔が歪んでいる。
そして崩れ落ちるようにその場に座り込んで何度も何度も床を叩いた。
その手は大きく震えている。
そんなタイミングで扉が開き、ガルボルグ公爵と父が入ってくる。
ガルボルグ公爵の冷めた視線がライボルトに突き刺さる。
「やはりお前の実力などその程度か」
「──違いますっ!今日はたまたま調子が悪くてっ」
「ふん!皆から報告は受けている。魔石に魔力を込めることなく、この仕事も忙しいからなどと言い訳してマティルダに任せきりだったそうだな……!こうなることは目に見えてわかっていた」
「……っ」
「なのにお前は現実から目を背け、マティルダを妬み学園に入り浸っていた。お前が仕事をしない分、ガルボルグ公爵家に舞い込む仕事を誰が代わりこなしていたと思う?」
「そ、れは……」
そして肩を荒く動かして金色の玉から手を離してしまった。
「お、おい!まだ町に明かりは戻っていないぞ!?もっと魔力を……」
「──わかっている!」
「ライボルト……?」
感情を荒げたライボルトの顔が歪んでいる。
そして崩れ落ちるようにその場に座り込んで何度も何度も床を叩いた。
その手は大きく震えている。
そんなタイミングで扉が開き、ガルボルグ公爵と父が入ってくる。
ガルボルグ公爵の冷めた視線がライボルトに突き刺さる。
「やはりお前の実力などその程度か」
「──違いますっ!今日はたまたま調子が悪くてっ」
「ふん!皆から報告は受けている。魔石に魔力を込めることなく、この仕事も忙しいからなどと言い訳してマティルダに任せきりだったそうだな……!こうなることは目に見えてわかっていた」
「……っ」
「なのにお前は現実から目を背け、マティルダを妬み学園に入り浸っていた。お前が仕事をしない分、ガルボルグ公爵家に舞い込む仕事を誰が代わりこなしていたと思う?」
「そ、れは……」